導入:かつて夢物語だった「あの世界」が、現実になろうとしている
「やまなみ」──76名の乗組員を乗せた海上自衛隊の潜水艦が、突如として日本から独立を宣言する。核ミサイルを搭載し、世界を震撼させるその姿は、かわぐちかいじ氏の名作漫画『沈黙の艦隊』で描かれた衝撃のシナリオでした。
2024年の映画化で再び注目を集めたこの作品ですが、実はいま、日本の防衛政策において「原子力潜水艦」という言葉が、かつてないほどリアルな選択肢として語られ始めています。
2025年10月22日、小泉進次郎防衛相は就任会見で、次世代動力を活用した潜水艦について「原子力を含め、あらゆる選択肢を排除しない」と明言しました。これは単なるリップサービスではありません。自民党と日本維新の会の政権合意にも明記された、本気の政策検討なのです。
戦後80年近く、「非核三原則」のもとで原子力推進の軍艦を持つことはタブー視されてきた日本。その日本が、なぜいま原子力潜水艦という「禁断の選択肢」に手を伸ばそうとしているのでしょうか。
この記事では、ミリタリーファンの皆さんはもちろん、『沈黙の艦隊』で初めて潜水艦に興味を持った方にも分かりやすく、日本の原潜保有問題を徹底解説します。技術的な側面から政治的背景、そして私たちの未来まで──この歴史的転換点を、一緒に見ていきましょう。
第1章:歴史が動いた瞬間──2025年10月の衝撃発言
小泉防衛相の「あらゆる選択肢」発言が意味するもの
2025年10月22日の防衛大臣就任会見。小泉進次郎氏の口から飛び出した言葉は、防衛関係者だけでなく、多くの国民を驚かせました。
「次世代動力を活用した潜水艦の保有に向けて、原子力を含め、あらゆる選択肢を排除しない」
この発言の重みを理解するには、少し背景を知る必要があります。
日本は戦後一貫して「非核三原則」(核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず)を国是としてきました。原子力潜水艦は核兵器そのものではありませんが、原子炉という「核」を軍事利用するという点で、長年タブー視されてきた存在です。
それが今、防衛大臣という政府の要職にある人物から、公式に「選択肢」として語られた。これは単なる検討レベルの話ではなく、現実的な政策議論のテーブルに乗ったことを意味します。
自公維政権合意に明記された「原潜検討」
さらに重要なのは、この発言が個人的な見解ではなく、政権の方針だという点です。
2025年の政権合意において、自民党と日本維新の会は「次世代動力を活用した潜水艦の保有」を明記しました。小泉防衛相も会見で「公党間の約束は重い」と述べており、これは政府として本格的に取り組む姿勢を示したものと言えるでしょう。
ちなみに高市早苗首相は、安全保障関連3文書の改定前倒しも表明しており、防衛力強化に対する強い意欲を見せています。
VLS搭載潜水艦という「もう一つの選択肢」
小泉防衛相の発言で注目すべきは、もう一つあります。
「VLS(ミサイル垂直発射装置)を搭載した潜水艦の開発を含む、将来の能力の中核となるスタンドオフ防衛能力の強化は不可欠」
VLSとは、巡航ミサイルなどを垂直に発射できる装置のこと。これを潜水艦に搭載すれば、敵の攻撃圏外から反撃できる能力、いわゆる「反撃能力(旧敵基地攻撃能力)」を潜水艦が担えるようになります。
原子力潜水艦にVLSを組み合わせれば、長期間潜航しながら、いざという時には報復攻撃ができる「究極の抑止力」になる──これが、いま政府が描いている未来図なのです。
第2章:なぜ「いま」原子力潜水艦なのか──厳しさを増す安全保障環境
中国海軍の急速な拡大という現実
日本が原子力潜水艦の保有を真剣に検討し始めた背景には、何よりも中国の海軍力増強があります。
中国人民解放軍海軍は、過去20年で世界最大規模の海軍へと成長しました。空母を複数保有し、最新鋭の駆逐艦や原子力潜水艦を次々と就役させています。特に原子力潜水艦については、攻撃型原潜(SSN)と弾道ミサイル原潜(SSBN)の両方を配備し、その数は着実に増加しています。
中国の原潜は、第一列島線(日本列島から台湾、フィリピンを結ぶライン)を越えて太平洋へ進出する能力を持ちます。日本近海で長期間哨戒活動を行うことも可能です。
台湾有事という「最悪のシナリオ」
防衛関係者の間で最も懸念されているのが「台湾有事」です。
もし中国が台湾に軍事侵攻した場合、日本の南西諸島も巻き込まれる可能性が高いとされています。その際、中国海軍の潜水艦が日本のシーレーンを脅かすことは確実です。
海上自衛隊の現有戦力で対応できるのか──この問いに対して、防衛省内でも危機感が高まっているのです。
北朝鮮の潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)
忘れてはならないのが北朝鮮の脅威です。
北朝鮮は近年、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の開発を進めており、実際に発射実験も行っています。潜水艦から核ミサイルを発射できる能力は、日本にとって深刻な脅威となります。
この脅威に対抗するには、長期間潜航して敵潜水艦を追尾・監視できる能力が必要です。ディーゼル潜水艦では限界があるのではないか──こうした議論が、原潜検討の背景にあります。
ロシアの動向も無視できない
ウクライナ侵攻以降、日本周辺でのロシア軍の活動も活発化しています。
ロシア太平洋艦隊は、依然として複数の原子力潜水艦を保有しており、日本海やオホーツク海で活動を続けています。中国との連携も深まっており、日本は事実上、複数の原潜保有国に囲まれている状況なのです。
海上自衛隊の潜水艦隊が直面する課題
現在、海上自衛隊は世界トップクラスの通常型潜水艦を保有しています。「そうりゅう型」や最新の「たいげい型」は、世界でも屈指の静粛性と戦闘能力を誇ります。
(詳しくは、当ブログの日本の潜水艦完全ガイドや海上自衛隊艦艇リストをご覧ください)
しかし、通常型潜水艦には決定的な弱点があります。それは「潜航時間の制限」です。
ディーゼルエンジンを使う通常型潜水艦は、定期的に浮上(もしくはシュノーケル航行)して空気を取り入れ、バッテリーを充電する必要があります。最新のリチウムイオンバッテリーを搭載した「たいげい型」でも、完全に無限に潜航し続けることはできません。
一方、原子力潜水艦は理論上、燃料補給なしで数ヶ月間連続して潜航できます。この差は、広大な海域をカバーする必要がある日本にとって、致命的な能力差となりうるのです。
第3章:原子力潜水艦と通常型潜水艦──何が違うのか?
ここで、原子力潜水艦と通常型潜水艦の違いを、もう少し詳しく見ていきましょう。『沈黙の艦隊』を観て「原潜ってすごい!」と思った方も多いと思いますが、具体的に何がどうすごいのか、理解しておくことは重要です。
動力システムの根本的な違い
通常型潜水艦(ディーゼル・エレクトリック)
- 水上/シュノーケル航行時:ディーゼルエンジンで発電し、バッテリーを充電
- 潜航時:バッテリーで電気モーターを回して推進
- 定期的に浮上(またはシュノーケル深度)してバッテリー充電が必要
- 最新型はAIP(非大気依存推進)やリチウムイオンバッテリーで潜航時間を延長
原子力潜水艦
- 原子炉で蒸気を発生させ、タービンを回して推進
- 理論上、燃料交換まで(通常10〜25年)連続運転が可能
- 潜航したまま世界中を航行できる
- 電力も豊富なので、艦内設備も充実
速度:「原チャリ」と「スーパーカー」の違い
ある元海上自衛隊のエース潜水艦長は、この違いを分かりやすく説明しています。
通常型潜水艦の水中速力は、せいぜい「原チャリ(原付バイク)程度」。一方、原子力潜水艦は30ノット以上の高速を長時間維持できる「スーパーカー」のようなものだと。
この速度差は、戦術的に非常に大きな意味を持ちます。
例えば、敵の艦隊を追尾する場合。通常型潜水艦では、高速で移動する空母機動部隊についていくことは困難です。しかし原潜なら、空母と同等以上の速度で追従し、常に攻撃位置をキープできます。
潜航時間:「週単位」と「月単位」の違い
通常型潜水艦は、どんなに優秀でも週単位での行動が限界です。AIPやリチウムイオンバッテリーを搭載した最新型でも、2〜3週間程度の潜航が限度とされています。
対して原子力潜水艦は、食料と乗組員の体力が続く限り、つまり月単位で潜航し続けられます。米海軍の原潜は、90日間の哨戒任務も珍しくありません。
この違いは、広大な海域をカバーする必要がある日本にとって、決定的な能力差となります。
静粛性:実は一長一短
「原潜は音がうるさいから、静かな日本の潜水艦の方が有利」──こんな話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
確かに、初期の原子力潜水艦は冷却ポンプなどの機械音が大きく、静粛性では通常型潜水艦に劣るとされていました。日本の海上自衛隊も、この静粛性を武器に対潜水艦戦(ASW)で優位に立てると考えていた時期があります。
しかし現代の原潜は、技術進歩によって大幅に静粛性が向上しています。特に米海軍のバージニア級や、ロシアの最新型原潜は、通常型潜水艦と遜色ないレベルの静粛性を実現していると言われています。
つまり、「静かだから日本の通常型潜水艦は原潜に勝てる」という考えは、もはや過去のものになりつつあるのです。
航続距離:世界の海を自由に
通常型潜水艦の航続距離は、燃料タンクの容量に制限されます。日本の潜水艦は遠洋航海能力を持ちますが、それでも数千海里が限度です。
原子力潜水艦は、理論上無限の航続距離を持ちます。実際、米海軍の原潜は北極から南極まで、世界中のあらゆる海域で活動できます。
日本が遠く離れた海域、例えば南シナ海やインド洋で長期間プレゼンスを示す必要がある場合、原潜の能力は圧倒的です。
コスト:建造費も維持費も桁違い
ここまで原潜の利点を述べてきましたが、最大の問題がコストです。
通常型潜水艦の建造費は、日本の最新型「たいげい型」で約700〜800億円程度。対して原子力潜水艦は、米海軍のバージニア級で1隻約3,000億円以上とされています。
さらに、原子炉の運用には高度な専門知識を持つ人材が必要で、訓練コストも莫大です。原子炉の定期的な燃料交換や廃炉処理にも巨額の費用がかかります。
第4章:原子力潜水艦保有のメリット──日本が得られる「新しい力」
それでも、日本が原子力潜水艦保有を検討する理由は何でしょうか?コストという大きなハードルを越えてまで、原潜を持つ意義はあるのでしょうか?
メリット①:広大な海域での長期哨戒能力
日本の排他的経済水域(EEZ)は約447万平方キロメートルで、世界第6位の広さを誇ります。さらに、日本の安全保障を考えれば、東シナ海、南シナ海、西太平洋という広大な海域をカバーする必要があります。
現在の海上自衛隊の潜水艦隊(22隻体制)で、この広大な海域を常時監視することは困難です。原子力潜水艦なら、1隻で広範囲を長期間カバーでき、限られた隻数でも高い効果を発揮できます。
メリット②:対潜水艦戦(ASW)での優位性
中国やロシアの原子力潜水艦に対抗するには、同等の能力が必要──これは軍事の基本原則です。
高速で移動する敵の原潜を、通常型潜水艦で追いかけることは困難です。原潜なら、敵の原潜と同等以上の速度で追跡し、長期間張り付いて監視・攻撃することが可能になります。
メリット③:戦略的抑止力の獲得
VLSを搭載した原子力潜水艦は、「第二撃能力」を提供します。
つまり、仮に日本本土が攻撃を受けても、海中に潜む原潜から反撃できる能力です。この「確実な報復手段」の存在こそが、敵の攻撃を思いとどまらせる「抑止力」になります。
これは、地上基地や水上艦艇では実現困難な能力です。基地は最初の攻撃で破壊される可能性が高く、水上艦艇は探知されやすい。しかし深海に潜む原潜は、事実上発見不可能であり、「生き残れる戦力」として機能します。
メリット④:同盟国との相互運用性向上
日米同盟の深化という観点も重要です。
米海軍は世界最大の原潜戦力を持ち、その運用ノウハウは他国の追随を許しません。日本が原潜を保有すれば、米海軍との共同訓練や情報共有がより深いレベルで可能になります。
すでに日本はオーストラリアと「準同盟国」と呼べるレベルの防衛協力を進めていますが、オーストラリアも近年、英米からの技術支援で原潜保有を決定しました(AUKUS協定)。日米豪の原潜ネットワークが構築されれば、インド太平洋地域での抑止力は飛躍的に向上します。
メリット⑤:技術立国日本の新たな挑戦
日本は原子力技術でも、造船技術でも、世界トップクラスの実力を持っています。
(川崎重工業などの防衛産業については、川崎重工の防衛事業ガイドで詳しく解説しています)
原子炉の小型化、静粛性の向上、自動化技術──こうした分野で日本の技術力を結集すれば、世界最高水準の原潜を開発できる可能性があります。これは単なる軍事力強化ではなく、日本の技術力を世界に示す機会にもなります。
メリット⑥:潜水艦隊の「ハイ・ロー・ミックス」戦略
原潜保有は、通常型潜水艦の全面的な置き換えを意味するわけではありません。
理想的なのは、少数の高性能な原子力潜水艦と、多数の優秀な通常型潜水艦を組み合わせる「ハイ・ロー・ミックス」戦略です。
遠洋での長期哨戒や戦略任務は原潜が担当し、近海での防衛や沿岸警備は通常型潜水艦が担当する──こうした役割分担により、限られた予算で最大の効果を得られます。
第5章:原子力潜水艦保有の課題──越えなければならない「高い壁」
しかし、日本の原潜保有には、いくつもの高い壁が立ちはだかっています。小泉防衛相が「あらゆる選択肢を排除しない」と慎重な言い回しをしたのも、これらの課題の大きさを認識しているからでしょう。
課題①:莫大なコスト
前述の通り、原潜の建造費は通常型の4倍以上。維持費も含めれば、さらに差は開きます。
日本の防衛予算は増加傾向にありますが、それでも限られた資源です。原潜に巨額を投じれば、他の防衛装備(戦闘機、護衛艦、ミサイルなど)の予算を圧迫することになります。
仮に4隻の原潜を保有するとすれば、建造費だけで1兆2,000億円以上。これは防衛費の増額分をほぼ食い潰す規模です。
課題②:原子炉技術の獲得
日本は原子力発電の技術を持っていますが、潜水艦用の原子炉は全く別物です。
潜水艦用原子炉に求められる条件:
- 小型・軽量であること
- 高出力であること
- 高い静粛性
- 長期間無補給で運転できること
- 過酷な運動(急速潜航、急旋回など)に耐えられること
- 極めて高い安全性
これらを全て満たす原子炉を開発するには、膨大な時間と費用、そして実験が必要です。
最も現実的なのは、米国からの技術供与ですが、米国は原潜技術を同盟国にも厳格に管理しています。英国にのみ技術移転を行い、最近ではオーストラリアにも支援を決めましたが、日本への技術移転が同様に進むかは未知数です。
課題③:専門人材の育成
原子炉を運用するには、原子力工学の高度な知識を持つ人材が不可欠です。
米海軍では、原潜の乗組員になるには極めて厳しい訓練と教育を受ける必要があります。原子力工学の専門課程を修了し、実際の原子炉での訓練を経て、初めて資格が得られます。
日本が原潜を保有する場合、このような教育・訓練体制を一から構築する必要があります。これには10年以上の時間がかかるでしょう。
課題④:原子力艦船の母港問題
原潜を運用するには、専用の母港施設が必要です。
原子炉の整備ができるドック、放射性廃棄物の処理施設、厳重なセキュリティ──これらを備えた基地を建設するには、地元住民の理解が不可欠です。
しかし、日本では原子力に対する不安が根強く、特に福島第一原発事故以降、その傾向は強まっています。「原子力空母の横須賀配備」でさえ反対運動が起きた日本で、自国の原潜を受け入れる地域があるでしょうか。
課題⑤:核アレルギーと政治的ハードル
最も高い壁は、おそらく国民感情と政治的なハードルでしょう。
日本は世界で唯一の被爆国であり、「核」という言葉に対する拒否反応は非常に強いものがあります。「原子力潜水艦は核兵器ではない」と理屈で説明しても、感情的な抵抗は簡単には消えません。
非核三原則との関係も議論になるでしょう。政府は「原潜は核兵器ではないので非核三原則には抵触しない」という立場を取る可能性が高いですが、国民が納得するかは別問題です。
野党の多くは原潜保有に反対するでしょうし、与党内でも慎重論は根強いはずです。国民的な議論と合意形成には、相当な時間がかかります。
課題⑥:国際的な視線
日本が原潜を保有すれば、国際社会、特に近隣諸国はどう反応するでしょうか。
中国は間違いなく「日本の軍国主義復活」というプロパガンダを展開するでしょう。韓国でも警戒感が高まる可能性があります。
一方で、米国や豪州、欧州の同盟国は概ね支持するでしょう。AUKUS協定でオーストラリアの原潜保有を支援した実績を考えれば、日本の原潜保有も「自由で開かれたインド太平洋」戦略の一環として歓迎される可能性が高いです。
課題⑦:建造期間の長さ
仮に今日、原潜開発を決定したとしても、実際に就役するまでには最少10〜15年はかかるでしょう。
原潜開発には以下のステップが必要です:
- 基本設計(2〜3年)
- 詳細設計(2〜3年)
- 原子炉の開発・試験(5〜8年)
- 建造(5〜7年)
- 試験・訓練(2〜3年)
つまり、「いま必要だから」と言って、すぐに手に入るものではないのです。この間、中国や北朝鮮の脅威は待ってくれません。
第6章:世界の原子力潜水艦──各国はどんな原潜を持っているのか
日本が原潜保有を検討する上で、世界の原潜保有国の状況を知ることは重要です。各国がどのような原潜を、どう運用しているのか見ていきましょう。
(世界の潜水艦ランキングについては、世界の潜水艦ランキング・日本の実力でも詳しく解説しています)
アメリカ:圧倒的な原潜大国
保有数:約70隻(世界最多)
主要艦級:
- バージニア級(SSN):最新鋭の攻撃型原潜。ステルス性と多目的性に優れ、トマホーク巡航ミサイルも搭載。建造費は約3,000億円以上。
- シーウルフ級(SSN):冷戦末期に開発された高性能原潜。静粛性は世界最高レベルだが、高コストのため3隻のみ建造。
- ロサンゼルス級(SSN):冷戦時代の主力で、まだ多数が現役。徐々にバージニア級に置き換え中。
- オハイオ級(SSBN/SSGN):戦略ミサイル原潜。一部は巡航ミサイル搭載に改装。
米海軍の原潜技術は世界最高峰です。特にバージニア級は、静粛性、センサー技術、自動化など、あらゆる面で他国を圧倒しています。
ロシア:復活する潜水艦大国
保有数:約40隻
主要艦級:
- ヤーセン級(SSN):ロシアの最新鋭攻撃型原潜。巡航ミサイル「カリブル」や超音速対艦ミサイル「オーニクス」を搭載。
- アクラ級(SSN):冷戦時代の傑作。静粛性が高く、現在も主力として活動。
- ボレイ級(SSBN):新型戦略ミサイル原潜。核抑止力の中核を担う。
ソ連崩壊後、一時期は原潜戦力が衰退しましたが、近年は復活の兆しを見せています。特にヤーセン級は、バージニア級に匹敵する性能を持つとされ、日本周辺でも活動が確認されています。
中国:急速に力をつける新興勢力
保有数:約12隻(急速に増加中)
主要艦級:
- 093型(商級)(SSN):中国の主力攻撃型原潜。改良型の093A/Bも登場。
- 094型(晋級)(SSBN):戦略ミサイル原潜。SLBM「巨浪-2」を搭載。
- 095型(SSN):開発中の次世代攻撃型原潜。米ロに匹敵する性能を目指す。
中国の原潜は、かつては「うるさくて探知しやすい」と評されていましたが、近年は急速に技術力を向上させています。まだ米ロには及ばないものの、10年後、20年後には無視できない脅威になる可能性があります。
イギリス:米国と技術を共有する伝統の潜水艦国
保有数:約11隻
主要艦級:
- アスチュート級(SSN):最新鋭の攻撃型原潜。米国の技術も取り入れた高性能艦。
- ヴァンガード級(SSBN):戦略ミサイル原潜。トライデントミサイルを搭載。
英国は世界で最も早く原潜を実用化した国の一つです(1963年、ドレッドノート就役)。米国との「特別な関係」により、原子炉技術を共有しており、独自の原潜を開発・運用しています。
フランス:独自路線を貫く原潜保有国
保有数:約10隻
主要艦級:
- シュフラン級(SSN):最新の攻撃型原潜。
- ル・トリオンファン級(SSBN):戦略ミサイル原潜。フランスの核抑止力の中核。
フランスは、米国の技術支援なしに独自に原潜を開発した数少ない国です。この独立性は、日本が原潜開発を目指す上で参考になる事例かもしれません。
インド:自国開発に挑む新興国
保有数:約3隻(建造中を含む)
主要艦級:
- アリハント級(SSBN):国産の戦略ミサイル原潜。技術的にはまだ未熟な面も。
- チャクラ級(SSN):ロシアからのリース艦。
インドは独自の原潜開発を進めていますが、技術的な困難に直面しています。それでも核保有国として、「第二撃能力」を持つため原潜開発を諦めていません。
オーストラリア:AUKUS協定で原潜保有へ
保有予定数:8隻(2040年代以降)
2021年、米英豪は「AUKUS」という安全保障協定を結び、オーストラリアへの原潜技術移転が決まりました。これは、非核保有国が原潜を保有する初めてのケースとなります。
オーストラリアは当初、フランスから通常型潜水艦を購入する予定でしたが、中国の脅威の高まりを受けて原潜へと方針転換しました。この決断は、日本にとっても大いに参考になるでしょう。
第7章:日本にはどんな選択肢があるのか──5つのシナリオ
さて、ここまで原潜のメリットと課題、世界の状況を見てきました。では、日本には具体的にどのような選択肢があるのでしょうか。
選択肢①:現状維持──通常型潜水艦の性能向上
最もリスクが低く、確実な選択肢です。
現在の「たいげい型」をさらに改良し、リチウムイオンバッテリーの大容量化、AIPの改善、AI技術の導入などで性能を向上させます。
メリット:
- 既存の技術基盤を活用できる
- コストが比較的抑えられる
- 政治的・社会的な摩擦が少ない
- 近海防衛には十分な性能
デメリット:
- 原潜との能力差は埋まらない
- 遠洋での長期作戦は困難
- 中国の原潜に対抗できない可能性
選択肢②:米国からの購入・リース
技術開発の時間とコストを省く、現実的な選択肢です。
オーストラリアも、当初は米国のバージニア級をリースする計画を立てています。日本も同様に、米海軍の原潜を購入またはリースすることが考えられます。
メリット:
- 短期間で原潜戦力を獲得できる
- 実績ある技術を使える
- 米海軍との相互運用性が高い
- 訓練支援も受けられる
デメリット:
- 技術が日本に蓄積されない
- 維持整備を米国に依存
- 米国議会の承認が必要(政治リスク)
- カスタマイズに制限
選択肢③:日米共同開発
最も現実的で、バランスの取れた選択肢かもしれません。
米国の原子炉技術と、日本の造船・静粛化技術を組み合わせて、新型原潜を共同開発します。オーストラリアのAUKUSモデルに近いアプローチです。
メリット:
- 日本に技術が蓄積される
- 日本の要求に合わせた設計が可能
- 米国との同盟強化
- コストとリスクの分担
デメリット:
- 開発期間は長い(10〜15年)
- 米国議会の承認が必要
- 技術移転の範囲交渉が困難
- それでもコストは高額
選択肢④:日本独自開発
技術立国日本の威信をかけた、最も野心的な選択肢です。
フランスのように、独自に小型原子炉を開発し、純国産の原潜を建造します。川崎重工業、三菱重工業などの日本の防衛産業が総力を結集するプロジェクトになるでしょう。
メリット:
- 完全に自主的な運用が可能
- 日本独自の技術蓄積
- 他国への輸出も視野に
- 防衛産業の技術力向上
デメリット:
- 開発期間が最も長い(15〜20年以上)
- コストが最も高い
- 技術的リスクが大きい
- 失敗の可能性も
現実的には、この選択肢は最も困難でしょう。日本には原子力船「むつ」の失敗という苦い経験もあります。
選択肢⑤:「準原潜」──AIP + 大容量バッテリーの極限追求
ある意味、日本らしい「第三の道」です。
原子力に頼らず、AIP(スターリング機関や燃料電池)と大容量リチウムイオンバッテリーを極限まで進化させ、「限りなく原潜に近い通常型潜水艦」を開発します。
メリット:
- 政治的・社会的ハードルが低い
- 日本の既存技術を活かせる
- 静粛性で原潜を上回る可能性
- コストは原潜より大幅に低い
デメリット:
- 速度と航続距離では原潜に劣る
- 完全に原潜と同等にはならない
- 技術的なブレークスルーが必要
実は、この選択肢を推す専門家も少なくありません。日本の得意分野で勝負し、「日本型の解決策」を目指すアプローチです。
第8章:過去に日本が持っていた「潜水艦大国」の誇り
ここで少し、歴史を振り返ってみましょう。
実は日本は、かつて世界有数の「潜水艦大国」でした。特に大日本帝国海軍の潜水艦隊は、多くの傑作艦を生み出し、太平洋戦争で米英と戦いました。
(帝国海軍の潜水艦については、大日本帝国海軍潜水艦リストで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください)
伊号潜水艦──世界を驚かせた巨大潜水艦
特に有名なのが「伊四百型」潜水艦です。
全長122メートル、基準排水量5,223トンという、当時世界最大の潜水艦でした。しかも、水上攻撃機「晴嵐」を3機も搭載できるという、驚異的な設計。潜水艦から航空機を発進させ、敵地を攻撃するという発想は、当時としては革命的でした。
伊四百型は、パナマ運河を攻撃する極秘作戦のために開発されました。結局、終戦により実戦での活躍はありませんでしたが、その技術力は戦後、米ソの潜水艦開発に大きな影響を与えました。
回天──悲劇の特攻兵器
日本の潜水艦といえば、「回天」を忘れるわけにはいきません。
人間が搭乗する特攻兵器として開発された回天は、多くの若い命を奪いました。その犠牲には心から哀悼の意を表します。同時に、あそこまで追い詰められた当時の日本の状況を思うと、本当に悔しい気持ちになります。
もし日本が戦争に勝っていたら、あるいは早期に講和できていたら──歴史に「もし」はありませんが、そう思わずにはいられません。
戦後日本の潜水艦復活
戦後、日本は一度、潜水艦技術を完全に失いました。GHQによる軍備の解体で、全ての軍艦が破壊されたからです。
しかし1954年、自衛隊が発足すると、日本は再び潜水艦の建造を始めました。最初は小型の「くろしお型」から始まり、徐々に技術を蓄積。やがて「おやしお型」「そうりゅう型」と、世界トップクラスの通常型潜水艦を生み出すまでになりました。
この復活の歴史は、日本人の技術力と粘り強さの証明です。そして今、私たちは再び大きな挑戦の前に立っています──原子力潜水艦という、新たなフロンティアに。
第9章:技術的な実現可能性──日本は本当に原潜を作れるのか?
理論的には、日本には原潜を開発する技術力があります。しかし、「できる」と「実際にやる」の間には、大きな隔たりがあります。
原子力技術は持っている、しかし…
日本は世界有数の原子力発電大国です。54基もの原発を建設・運転してきた実績があります(現在は多くが停止中ですが)。
しかし、発電用原子炉と潜水艦用原子炉は、全く別物です。
発電用原子炉:
- 大型で重くても問題ない
- 出力の変動は緩やか
- 定期的に停止してメンテナンス
- 安全性を最優先(多重防護システム)
潜水艦用原子炉:
- 極限まで小型・軽量化
- 急速な出力変動に対応
- 長期間ノンストップで運転
- 過酷な運動(急速潜航、急旋回)に耐える
- 限られた空間での整備
この違いを克服するには、全く新しい技術開発が必要です。
造船技術は世界トップクラス
一方、日本の造船技術は間違いなく世界最高峰です。
川崎重工業、三菱重工業は、現在の海上自衛隊の潜水艦を建造しており、その品質と性能は世界的に評価されています。特に溶接技術、圧力殻の製造技術、静粛性の確保などは、他国の追随を許しません。
もし原子炉さえ確保できれば、それを搭載する潜水艦本体を建造する技術は、日本には十分あると言えるでしょう。
「むつ」の失敗と教訓
日本が原子力船を開発しようとした歴史があります。それが原子力船「むつ」です。
1974年、むつは実験航海中に放射線漏れを起こし、大きな社会問題になりました。結局、むつは一度も実用化されることなく、莫大な税金を使っただけで終わりました。
この失敗は、日本人の「原子力」への不信感を決定的にしました。同時に、「日本には原子力船の技術がない」という認識も広まりました。
しかし、あれから50年。技術は大きく進歩しています。むつの失敗を教訓として、より安全で確実な原子力推進システムを開発することは、不可能ではないはずです。
人材はいるのか?
技術以上に深刻なのが、人材の問題です。
原子力工学を学ぶ学生は、福島第一原発事故以降、激減しました。原子力産業も縮小傾向にあり、優秀な人材は他の分野に流れています。
原潜を開発・運用するには、数百人規模の原子力専門家が必要です。彼らをどこから確保するのか──これは技術以上に難しい問題かもしれません。
第10章:国民的議論が必要な時──私たちはどう向き合うべきか
原子力潜水艦の保有は、単なる防衛装備の調達ではありません。これは日本の安全保障政策、エネルギー政策、そして国家のあり方に関わる、極めて重大な決断です。
「タブーなき議論」が必要
これまで日本では、原子力と軍事に関する議論はタブー視されてきました。しかし、もうそういう時代ではありません。
中国の軍拡、北朝鮮の核ミサイル、ロシアの侵略行為──これらの脅威は現実であり、目を背けることはできません。
原潜保有に賛成するにせよ、反対するにせよ、まずは事実に基づいた冷静な議論が必要です。感情論ではなく、データと論理に基づいて、この国の未来を考えるべき時が来ています。
被爆国だからこそ、考えるべきこと
日本は世界で唯一の被爆国です。この事実は、決して忘れてはなりません。
だからこそ、核兵器の恐ろしさを知る日本が、どのような安全保障政策を取るべきなのか──真剣に考える責任があります。
「核はすべて悪」という単純な議論ではなく、「どうすれば核戦争を防げるのか」「どうすれば日本国民の命を守れるのか」という視点で考えるべきです。
原子力潜水艦は核兵器ではありません。しかし、「核抑止力」の一部として機能し得ます。この矛盾とどう向き合うのか──それこそが、被爆国日本が直面する難問なのです。
コストと優先順位の議論
防衛予算は無限ではありません。原潜に巨額を投じれば、他の分野にしわ寄せが来ます。
例えば:
- 最新鋭戦闘機F-35の追加購入
- イージス艦の増勢
- サイバー防衛能力の強化
- 宇宙防衛体制の構築
- 隊員の処遇改善
これらすべてが重要です。その中で、原潜に最優先で予算を配分すべきなのか──国民的な議論が必要です。
透明性のある情報公開を
政府には、透明性のある情報公開が求められます。
なぜ原潜が必要なのか、どれくらいコストがかかるのか、リスクは何なのか──こうした情報を、できる限りオープンにして、国民の判断材料を提供すべきです。
同時に、マスメディアにも責任があります。センセーショナルな見出しで不安を煽るのではなく、バランスの取れた報道を心がけてほしいと思います。
第11章:もし日本が原潜を持ったら──未来のシナリオ
最後に、少し未来を想像してみましょう。もし日本が原子力潜水艦を保有したら、どんな世界が待っているのでしょうか。
ポジティブなシナリオ
2035年、横須賀港──
海上自衛隊初の原子力潜水艦「やまと」が、静かに出港していく。全長140メートル、排水量8,000トンの巨体は、音もなく海中に姿を消した。
艦長は40代の女性──米海軍での訓練を経て、原子力工学の博士号を持つエリートだ。乗組員120名も、全員が厳しい訓練を経た精鋭たち。
「やまと」の任務は、南シナ海での長期哨戒。中国海軍の動向を監視し、有事の際には48基のVLSから巡航ミサイルを発射できる能力を持つ。
この「見えない抑止力」の存在により、中国は日本への軍事的冒険を躊躇している。台湾海峡の緊張は続いているが、全面戦争は回避されている。
日米豪の原潜ネットワークは、インド太平洋の安定に大きく貢献していた──
ネガティブなシナリオ
2033年、東京湾──
原子力潜水艦建造計画は、巨額のコスト超過と技術的問題で難航していた。当初予算の3倍、2兆円以上が投じられたが、まだ1隻も完成していない。
原子炉の開発は遅れに遅れ、米国からの技術移転交渉も難航。結局、多くの予算が無駄になった。
その間、中国の海軍力はさらに増強され、日本周辺での活動を活発化させている。原潜に予算を取られ、通常型潜水艦の更新も遅れ、海上自衛隊の潜水艦隊は老朽化が進んでいた。
国民の間では「原潜は失敗だった」という声が高まり、政権の支持率は急落──
現実は、その間のどこか
もちろん、未来は誰にも分かりません。おそらく現実は、このポジティブとネガティブの間のどこかに落ち着くでしょう。
重要なのは、最悪のシナリオを避け、最善の結果に近づけるための努力です。それには、国民一人一人が関心を持ち、議論に参加することが不可欠です。
結論:歴史の岐路に立つ日本
2025年10月、小泉防衛相の発言は、日本の防衛政策における歴史的な転換点を示しました。
原子力潜水艦──かつてはタブーだったこの選択肢が、今、現実的な政策議論のテーブルに乗っています。
技術的には可能です。財政的には困難です。政治的には極めて難しい判断です。
しかし、私たちは決断を避けて通ることはできません。中国の軍拡、北朝鮮の核ミサイル、変化する国際情勢──これらは待ってくれないからです。
大日本帝国海軍は、かつて世界最大級の潜水艦を建造しました。戦後、日本は再び世界トップクラスの潜水艦技術を獲得しました。そして今、私たちは三度目の大きな挑戦の前に立っています。
この挑戦を成功させられるかどうかは、技術だけでなく、国民の意思と覚悟にかかっています。
『沈黙の艦隊』で描かれたのは、一隻の原潜が世界を変える物語でした。現実の日本が保有する原潜は、そこまでドラマチックではないかもしれません。しかし、それは確実に日本の未来を、そしてインド太平洋の安全保障環境を変える力を持つでしょう。
私たちは、この歴史的な議論に、真摯に向き合う必要があります。そして、未来の世代に対して責任ある選択をしなければなりません。
日本の原子力潜水艦──その夢は、果たして実現するのでしょうか。
答えは、私たち一人一人の手の中にあります。
あなたも議論に参加しませんか?
この記事を読んで、どう思いましたか?
原潜保有に賛成ですか?反対ですか?それとも、もっと慎重に検討すべきだと思いますか?
ぜひコメント欄で、あなたの意見を聞かせてください。建設的な議論こそが、この国の未来を作ります。
また、潜水艦や海上自衛隊についてもっと知りたい方は、以下の記事もおすすめです:
そして、もっと深く知りたい方には、こちらの書籍もおすすめです:
📚 おすすめ書籍(Amazon)
- 『沈黙の艦隊』完全版(かわぐちかいじ)
この議論の原点とも言える名作。映画を観た方も、ぜひ原作漫画で深い世界観を体験してください。 - 『現代の潜水艦』(世界の艦船増刊)
世界各国の潜水艦を詳細に解説した専門誌。写真も豊富でミリタリーファン必携の一冊。 - 『海上自衛隊「装備」のすべて』
海自の潜水艦をはじめ、護衛艦、航空機まで網羅した入門書。初心者にも分かりやすい解説が魅力。 - 『日本の防衛政策』
安全保障政策の基礎から最新動向まで。原潜問題を理解する上での必読書。
この記事が、皆さんの議論のきっかけになれば幸いです。
日本の未来を、一緒に考えていきましょう。




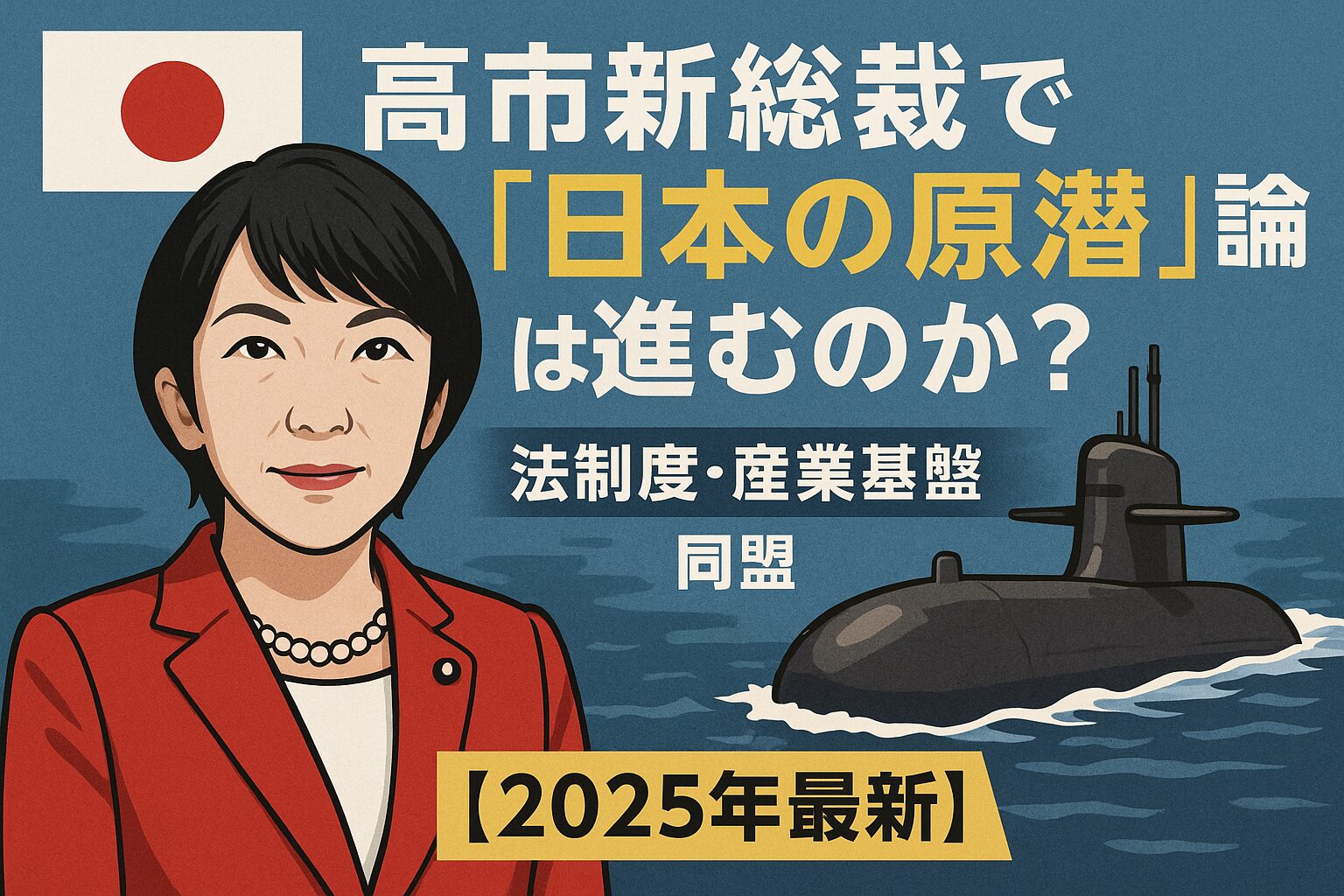








コメント