2025年11月現在、空の戦いは根本から変わった。
かつて、戦闘機パイロットの腕前や機体の運動性能が勝敗を分けた時代があった。大日本帝国海軍の零戦が、卓越した格闘戦能力で連合軍を震撼させたあの時代だ。だが21世紀の今、空戦の本質は「誰が先に相手を発見し、撃墜し、そして逃げ切るか」という情報優位戦へと完全に移行している。
レーダーに映らないステルス性、複数のセンサーを統合して戦況を瞬時に把握するセンサー融合、そして広域ネットワークで味方全体と情報を共有する能力――これらが現代戦闘機の真の強さを決める。さらに、無人僚機(ドローン)との協働、長射程対空ミサイル、AI支援、極超音速兵器まで加わり、もはや「戦闘機単体の性能」だけでは戦えない時代に突入した。
この記事では、2025年最新のステルス戦闘機TOP10を徹底比較する。 各機の強みと弱点、そして未来の空戦がどこへ向かうのかを、わかりやすく解説していく。
僕たちの先祖が命を懸けて守ろうとした空――その支配権を巡る現代の戦いを、一緒に見ていこう。
ステルス戦闘機ランキングの評価基準
このランキングでは、以下の6つの基準で各機体を評価する。
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| ステルス性 | レーダー反射断面積(RCS)の小ささ、赤外線(熱源)の低減技術 |
| センサー融合 | 複数のセンサー(レーダー、光学、電子戦装置など)を統合し、リアルタイムで戦況を把握する能力 |
| 火力・兵装 | 搭載可能なミサイル・爆弾の種類と数、空対空・空対地・空対艦の多用途性 |
| 航続距離・機動力 | 作戦半径の長さ、空中給油なしでの行動範囲、超機動性(スーパーマニューバビリティ) |
| 実戦経験・配備状況 | 実戦での使用実績、配備数、同盟国への展開状況 |
| 将来性 | アップデート可能性、AI・無人機との協働対応、第6世代への発展余地 |
単なるスペック比較ではなく、「実戦でどれだけ使えるか」「将来どこまで進化できるか」という実践的視点を重視した。
【一覧表】2025年版 世界最強ステルス戦闘機TOP10

まずは全体像を一気に見てみよう。
| 順位 | 機体名 | 国 | 最大の強み | 最大の弱点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | F-35 Lightning II | 🇺🇸 米+同盟国 | 世界最大の配備数、圧倒的センサー融合とネットワーク能力 | 高コスト、機動性は第4世代機以下 |
| 2位 | F-22 Raptor | 🇺🇸 米国 | 空対空戦闘最強、超機動性とステルス性の完璧な融合 | 生産終了済み、情報共有能力はF-35に劣る |
| 3位 | J-20 Mighty Dragon | 🇨🇳 中国 | 長大な航続距離、大推力エンジン、量産体制確立 | ステルス性に疑問、エンジン技術で西側に劣る |
| 4位 | Su-57 Felon | 🇷🇺 ロシア | 極限の超機動性、多用途性、独自の設計思想 | ステルス性不足、配備数極少、資金難 |
| 5位 | B-21 Raider | 🇺🇸 米国 | 第6世代志向のステルス爆撃機、戦略打撃の要 | 制空戦闘には不向き、配備はこれから |
| 6位 | KF-21 Boramae | 🇰🇷 韓国 | コスパ最強、段階的アップグレードで将来性大 | 現時点では完全な第5世代ではない |
| 7位 | FC-31/J-35 | 🇨🇳 中国 | 艦載型ステルス戦闘機、中国空母の切り札 | 実戦配備はまだ限定的 |
| 8位 | Tempest / GCAP | 🇯🇵🇬🇧🇮🇹 日英伊 | 第6世代機、AI+無人僚機協働の先駆者 | 完成は2035年、現時点では構想段階 |
| 9位 | FCAS | 🇩🇪🇫🇷🇪🇸 独仏西 | 欧州統合の次世代システム、有人+無人のチーム戦術 | 完成は2040年、多国間調整に課題 |
| 10位 | Su-75 Checkmate | 🇷🇺 ロシア | 低コスト志向の単発ステルス機 | 試作機すら未完成、資金不足で実現性低い |
この表を見るだけで、いくつかの重要な事実が浮かび上がる。
- アメリカの圧倒的優位:TOP10のうち3機(F-35、F-22、B-21)がアメリカ製
- 中国の急成長:J-20とJ-35で量産体制を確立、米国に次ぐステルス大国へ
- ロシアの苦戦:技術力はあるが資金難と制裁で配備数が伸びず
- 次世代の胎動:日英伊GCAP、独仏西FCASなど、第6世代機開発が本格化
それでは、各機体を詳しく見ていこう。
第10位:Su-75 “Checkmate”(ロシア)――低コストステルス機の夢と現実
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | ロシア(スホーイ設計局) |
| タイプ | 単発ステルス戦闘機(中型・輸出志向) |
| 初公開 | 2021年MAKS航空ショー |
| 現状 | 試作機段階(初飛行未実施) |
何が凄いのか?
Su-75 “Checkmate”――このネーミングからして挑発的だ。ロシアは「F-35より安く、途上国でも買える第5世代機」を目指してこの機体を発表した。
強みはこうだ。
- 低コスト志向:F-35の半額程度で提供することを目標としており、予算が限られる国々への輸出を狙う
- 単発機の軽量性:Su-57よりも小型で運用コストを抑制、機動性も確保
- 最新技術の統合:AESAレーダー、光学照準システム、多様な兵装統合を計画
だが、問題はこれがまだ「コンセプト機」でしかないという点だ。
致命的な弱点
2025年11月現在、Su-75は試作機すら完成していない。初飛行の予定は何度も延期され、実現の目処が立っていない。
原因は明白だ――資金不足と経済制裁。ウクライナ戦争後の制裁で、先端電子部品や航空機エンジン技術の調達が困難になった。さらに、ロシア国内の軍事予算は既存のSu-57やSu-35の維持に優先的に回されており、Su-75への投資は後回しにされている。
輸出市場も不透明だ。 F-35を買えない国は、既に中国のJ-10CやJ-35を選択肢に入れている。ロシア機の信頼性は、ウクライナ戦争での損失の多さで疑問視されるようになった。
総合評価:夢のまま終わる可能性大
Su-75は魅力的なコンセプトだが、2025年時点では「絵に描いた餅」だ。もし完成すれば途上国市場で一定の需要はあるだろうが、その「もし」が実現するかどうかが最大の問題である。
ランキング第10位としたが、正直なところ「ランク外」でもおかしくない状況だ。
関連記事:ロシアの航空機技術については、第二次世界大戦時のドイツとの技術交流の歴史も興味深い。詳しくはドイツ空軍最強戦闘機ランキングを参照。
第9位:FCAS(独仏西共同開発)――欧州が描く「第6世代」の理想郷
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | ドイツ・フランス・スペイン共同 |
| 正式名称 | Future Combat Air System(未来戦闘航空システム) |
| 構成 | 次世代有人戦闘機(NGF) + 複数の無人僚機 + 戦場クラウドネットワーク |
| 配備目標 | 2040年前後 |
「システム・オブ・システムズ」という革命
FCASは単なる「新型戦闘機」ではない。それは戦闘機を中心とした統合戦闘システム全体を指す。
有人戦闘機が「司令塔」となり、複数の無人僚機(リモートキャリアー)を操って戦う。各機はクラウドベースのネットワークで情報を共有し、AI支援によって最適な戦術を瞬時に判断する。レーザー兵器、電子戦装置、極超音速ミサイルなど、未来技術をフル装備する計画だ。
これこそが「第6世代戦闘機」の理想形――F-35やJ-20といった第5世代機を一気に旧式化させる可能性を秘めている。
欧州の誇りと現実の壁
欧州は長年、アメリカ製戦闘機に依存してきた。F-16、F-35、F/A-18――NATO空軍の主力はすべて米国製だ。FCAS は「欧州独自の空の主権」を取り戻すための象徴的プロジェクトでもある。
だが、多国間共同開発の難しさは誰もが知るところだ。
- ドイツとフランスの利害対立(主導権争い、技術輸出規制の違い)
- 開発コストの分担を巡る各国の綱引き
- スケジュールの遅延リスク
2025年現在、FCASはまだ構想段階であり、実機の姿すら見えていない。完成は早くても2040年以降と見られている。
総合評価:期待値は最高、だが実現は遠い
FCASが完成すれば、間違いなく世界最強クラスのステルス戦闘システムとなるだろう。だが、それは「もし完成すれば」の話だ。
2025年時点では、将来への投資案件として第9位にランクインさせた。
第8位:Tempest / GCAP(日英伊)――日本が挑む「第6世代」への野心
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | 日本・イギリス・イタリア |
| 正式名称 | GCAP(Global Combat Air Programme) |
| タイプ | 第6世代戦闘機(有人機+無人僚機協働) |
| 配備目標 | 2035年 |
日本の技術力が世界に挑む
GCAP――このプロジェクトは、日本の航空技術史における最大の挑戦だ。
第二次世界大戦で、日本は零戦や紫電改といった名機を生み出した。だが敗戦後、日本の航空産業は長く制約を受けてきた。F-2支援戦闘機の開発で一定の技術を取り戻したものの、純国産戦闘機の開発は夢のまた夢だった。
GCAPは、その夢を現実にする可能性を秘めている。
三カ国の技術融合
| 国 | 得意分野 |
|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 先進レーダー技術、複合材料、高効率エンジン(XF9-1) |
| 🇬🇧 イギリス | BAEシステムズの戦闘機設計、ステルス技術 |
| 🇮🇹 イタリア | 電子戦装置、センサー統合 |
この組み合わせは理想的だ。日本の精密加工技術、英国の設計ノウハウ、イタリアの電子戦技術――それぞれの強みを結集すれば、F-35を超える戦闘機が生まれる可能性がある。
有人機+無人僚機の協働戦術
GCAPの最大の特徴は、「Loyal Wingman(忠実な僚機)」コンセプトだ。
有人戦闘機が「母機」となり、複数の無人機(UAV)を指揮する。無人機は偵察、電子戦妨害、ミサイル運搬、囮など多様な役割を担う。これにより、有人機パイロットの負担を減らしつつ、戦闘力を飛躍的に高める。
AI支援による戦術判断も標準装備される予定だ。パイロットがAIと対話しながら、最適な戦術を瞬時に選択できる。
最大の課題:国際共同開発のリスク
だが、国際共同開発には常にリスクが伴う。
- 利害調整の難しさ:主導権を巡る各国の綱引き
- 技術流出の懸念:機密情報の管理体制
- コスト増大:開発費が予算を超過する可能性
さらに、2035年という配備目標が守られるかどうかも不透明だ。過去の共同開発プロジェクト(例:ユーロファイター・タイフーン)は、多くがスケジュール遅延とコスト超過に苦しんだ。
総合評価:日本の未来を賭けた勝負
GCAPは、2025年時点ではまだ構想と初期開発の段階だ。だが、2030年代半ばに配備が始まれば、間違いなく世界の空戦地図を塗り替える。
僕たちの先祖が零戦で成し遂げた「技術立国日本」の誇りを、現代に蘇らせる可能性を秘めている。
期待を込めて、第8位にランクインさせた。
関連記事:日本の戦闘機開発の歴史については、日本の戦闘機一覧で詳しく解説している。零戦から最新のF-35まで、技術の系譜を辿ってほしい。
第7位:FC-31/J-35(中国)――空母の切り札、艦載ステルス機の実力
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | 中国(瀋陽航空機公司) |
| タイプ | 中型双発ステルス戦闘機 |
| 名称 | 試作:FC-31 / 艦載型:J-35 |
| 現状 | 量産前、艦載機として採用進行中 |
中国海軍の野望――空母艦載ステルス機
中国は現在、3隻の空母を運用している。
- 遼寧(旧ソ連製空母を改修)
- 山東(国産通常動力空母)
- 福建(最新の電磁カタパルト搭載空母)
だが、これらの空母に搭載されている艦載機は、旧式のJ-15(Su-33のコピー)だった。ステルス性能はゼロ、米海軍のF-35Cに対抗できない。
J-35は、この弱点を一気に解消する切り札だ。
「中国版F-35C」の実力
J-35の外見は、米国のF-35に酷似している。双発エンジン、内部兵器庫、ステルス形状――設計思想は明らかにF-35を参考にしている(技術流出の疑惑もあるが)。
強みはこうだ。
- 艦載ステルス機の実現:米国以外でステルス艦載機を実戦配備できる唯一の国に
- 低コスト志向:F-35Cより安価に量産可能(推定)
- AESAレーダーと長射程ミサイル:PL-15空対空ミサイル(射程約200km)との組み合わせで、地域制空権確保に有利
だが、本当に「強い」のか?
問題は、J-35の実際の性能が不透明だという点だ。
- ステルス性能:外見は似ているが、レーダー吸収材や内部構造の質は西側に劣ると見られる
- エンジン技術:中国製エンジン(WS-13/19)は信頼性に課題あり
- センサー融合:F-35の最大の強みであるセンサー融合能力で、どこまで追いついているかは不明
実戦配備もまだ限定的だ。2025年時点では、試験飛行と評価が続いており、本格的な量産・配備はこれからとなる。
総合評価:中国海軍の未来を担う存在
J-35は、中国が「ステルス空母航空団」を実現するための鍵だ。米海軍に対抗できる唯一のカードとも言える。
ただし、性能と成熟度ではF-35Cに及ばない。将来性を評価して第7位とした。
第6位:KF-21 Boramae(韓国)――コスパ最強の「準ステルス機」
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | 韓国(KAI:韓国航空宇宙産業) |
| タイプ | 第4.5〜第5世代多用途戦闘機 |
| 初飛行 | 2022年7月 |
| 配備予定 | Block I(2026年〜)、Block II(2030年代) |
「中価格帯ステルス機」という新市場
KF-21 Boramae(ボラメ、韓国語で「若鷹」の意)は、韓国が初めて開発した国産戦闘機だ。
その最大の特徴は、「F-35より安く、第4世代機より強い」という絶妙なポジショニングにある。
| 機体 | 価格(推定) | ステルス性 |
|---|---|---|
| F-35A | 約8,000万ドル | 完全ステルス |
| KF-21 Block I | 約6,500万ドル | 準ステルス |
| F-16V | 約7,000万ドル | 非ステルス |
F-35は高すぎる、でも旧式機では不安――そんな国にとって、KF-21は理想的な選択肢となる。
段階的アップグレード戦略
KF-21の賢いところは、段階的に進化させる計画を最初から組み込んでいる点だ。
| バージョン | 特徴 |
|---|---|
| Block I | 空対空戦闘中心、外部兵装搭載(ステルス性は限定的) |
| Block II | 内部兵器庫追加、ステルス性強化、空対地能力拡充 |
| Block III以降 | AI協働、無人僚機連携など第6世代要素の追加 |
この戦略により、早期配備と将来拡張性の両立を実現している。
輸出市場での期待
KF-21は既にインドネシアが共同開発国として参加している(開発費の一部を負担)。さらに、東南アジア諸国(フィリピン、マレーシア、タイなど)や中東諸国(サウジアラビア、UAE)への輸出も視野に入れている。
「F-35は高すぎるが、中国製は信用できない」という国々にとって、韓国製は魅力的な第三の選択肢だ。
弱点:まだ「完全な第5世代機」ではない
だが、KF-21にも弱点はある。
- Block Iはステルス性が限定的:外部兵装を搭載するため、RCS(レーダー反射断面積)が大きい
- センサー融合能力:F-35のような高度なセンサー統合はまだ実現していない
- 実戦経験ゼロ:配備が始まったばかりで、運用ノウハウの蓄積はこれから
総合評価:未来性とコスパで高評価
KF-21は現時点では「準ステルス機」だが、Block II以降の進化で真の第5世代機に到達する可能性が高い。
コストパフォーマンスと将来性を評価して、第6位とした。
第5位:B-21 Raider(アメリカ)――第6世代志向のステルス爆撃機
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | アメリカ(ノースロップ・グラマン) |
| タイプ | 戦略ステルス爆撃機 |
| 初飛行 | 2023年11月 |
| 配備予定 | 2020年代後半〜 |
「戦闘機」ではないが、ランクインさせた理由
B-21 Raiderは厳密には「戦闘機」ではなく、「戦略爆撃機」だ。だが、このランキングに含めた理由がある。
B-21は、単なる爆撃機ではない。それは「第6世代戦闘システムの核」となる存在だからだ。
「見えない戦略打撃」の恐怖
B-21の最大の特徴は、極限のステルス性能だ。
B-2スピリット(先代のステルス爆撃機)をさらに進化させ、以下の技術を投入している。
- 次世代レーダー吸収材:従来より広い周波数帯でステルス性を維持
- 赤外線低減技術:エンジン排熱を拡散し、赤外線センサーでの探知を困難に
- 電子戦装置:敵レーダー網を無力化しながら進入
敵の防空網を突破し、核兵器や精密誘導爆弾を投下できる――これが B-21の真価だ。
有人・無人両対応の「第6世代設計」
B-21はさらに、有人・無人の両方で運用可能な設計となっている。
- 有人運用:長距離戦略爆撃、核抑止任務
- 無人運用(将来):危険な敵防空網への突入、長時間偵察任務
さらに、無人僚機(CCA:Collaborative Combat Aircraft)との協働も想定されている。B-21が「母艦」となり、複数の無人攻撃機を指揮して目標を叩く――第6世代戦闘機に求められる能力を、既に実装しようとしているのだ。
弱点:制空戦闘には不向き
ただし、B-21には明確な弱点がある。
空対空戦闘能力がほぼゼロだ。
B-21は爆撃に特化しており、敵戦闘機との交戦を想定していない。制空権が確保されていない空域では、F-22やF-35の護衛が必須となる。
総合評価:戦略打撃の要として第5位
B-21は「戦闘機」ではないが、現代戦における戦略的重要性は極めて高い。
米国の核抑止力の中核を担い、将来的には有人・無人協働の先駆者となる。その意味で、第5位にランクインさせた。
第4位:Su-57 Felon(ロシア)――超機動性とステルス性の狭間で
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | ロシア(スホーイ設計局) |
| タイプ | 第5世代多用途戦闘機 |
| 初飛行 | 2010年 |
| 配備状況 | 2020年〜(配備数は極少) |
ロシアの「独自路線」――西側とは違うステルス思想
Su-57を語る前に、まず理解すべきことがある。
ロシアは、西側とは異なる「ステルス思想」を持っているということだ。
F-22やF-35は、「完全にレーダーから消える」ことを目指した。そのために、機動性や兵装搭載量を一部犠牲にした。
だがSu-57は、「ステルス性と機動性の両立」を目指した。完璧なステルス性は追求せず、その代わりに圧倒的な運動性能を確保する――これがロシアの選択だ。
「スーパーマニューバビリティ」の圧倒的優位
Su-57の最大の強みは、極限の超機動性(スーパーマニューバビリティ)だ。
- 推力偏向ノズル:エンジン噴射方向を3次元で変更可能
- 前縁延長(LEVCON):翼の前縁部分が可動し、空力制御を最適化
- 高推力エンジン:AL-41F1Sエンジン(将来的にはProduct 30エンジンに換装予定)
これらの技術により、Su-57は以下のような「あり得ない機動」が可能だ。
| 機動名 | 説明 |
|---|---|
| プガチョフのコブラ | 機首を急激に上げて一瞬停止、後方の敵をやり過ごす |
| クルビット | 宙返りしながら180度反転 |
| ベルマン | 超低速で急旋回 |
近距離ドッグファイトになれば、Su-57は圧倒的に有利だ。
致命的な弱点:ステルス性の不足と配備数の少なさ
だが、Su-57には重大な弱点がある。
1. ステルス性が不十分
Su-57のレーダー反射断面積(RCS)は、F-22やF-35と比べて10〜100倍大きいと推定されている。
原因はこうだ。
- エンジンの露出:吸気口から見えるエンジンブレードがレーダー波を反射
- 外部兵装:一部のミサイルを外付けするため、RCSが増大
- 表面仕上げの粗さ:製造精度が西側機に劣る
つまり、Su-57は「ステルス機」とは言えない――少なくとも、F-22やF-35と同じ意味では。
2. 配備数が極端に少ない
2025年11月時点で、Su-57の配備数はわずか20機程度と推定される。
理由は明白だ――資金不足と製造能力の限界。
ウクライナ戦争で既存機の損失と修理が優先され、Su-57の量産は後回しにされている。さらに、経済制裁で先端部品の調達が困難になり、生産ペースは大幅に低下した。
実戦での評価:シリア・ウクライナでの運用
Su-57は、シリア内戦とウクライナ戦争で実戦運用されている。
だが、その使われ方は「限定的」だ。
- 防空網の外から長射程ミサイルを発射(スタンドオフ攻撃)
- 敵ステルス機との直接交戦は回避
つまり、Su-57は「完全な制空権下でしか使えない」機体だということだ。F-22やF-35が待ち構える空域には、おそらく投入できない。
総合評価:技術力は高いが、戦力化に失敗
Su-57は、技術的には優れた戦闘機だ。超機動性、多用途性、独自の設計思想――ロシア航空技術の結晶と言える。
だが、ステルス性の不足と配備数の少なさが致命的だ。実戦で西側第5世代機と渡り合えるかは疑問が残る。
技術力を評価しつつも、実戦性能の限界を考慮して第4位とした。
関連記事:ロシアの航空技術の系譜は、第二次世界大戦時のドイツとの技術交流に遡る。詳しくは第二次世界大戦ドイツ空軍最強戦闘機ランキングを参照。
第3位:J-20 Mighty Dragon(中国)――アジアの空を支配する巨龍
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | 中国(成都航空機工業集団) |
| タイプ | 第5世代重戦闘機 |
| 初飛行 | 2011年 |
| 配備状況 | 2017年〜(推定300機以上配備) |
中国の野望――「ステルス大国」への急成長
2011年、中国がJ-20の初飛行映像を公開したとき、西側諸国は衝撃を受けた。
「中国がステルス戦闘機を? まさか、そんなはずは……」
だが、それは現実だった。中国は、米国に次ぐ「第二のステルス戦闘機大国」となったのだ。
J-20の圧倒的強み
1. 長大な航続距離
J-20の全長は約21メートル――F-22(約19m)やF-35(約15m)よりも大型だ。
この大きさは、長大な航続距離を実現する。
| 機体 | 戦闘行動半径(推定) |
|---|---|
| J-20 | 約2,000km |
| F-22 | 約850km |
| F-35A | 約1,000km |
J-20は、空中給油なしでも広大な太平洋上空を作戦行動できる。これは、米空母打撃群への対抗手段として極めて有効だ。
2. 大推力エンジン
当初、J-20はロシア製エンジン(AL-31F)を使用していたが、現在は国産WS-10Cエンジンに換装が進んでいる。さらに将来的には、WS-15エンジン(推力約18トン)への換装が予定されている。
WS-15が実用化されれば、J-20はF-22に匹敵する超音速巡航能力を獲得する。
3. 量産体制の確立
2025年時点で、J-20の配備数は推定300機以上とされる。これは、F-22の総生産数(187機)を既に上回っている。
中国は、ステルス戦闘機を「量産できる」唯一の国(米国を除く)だ。
致命的な弱点:ステルス性とエンジン技術
だが、J-20にも重大な弱点がある。
1. ステルス性能の疑問
J-20の形状は、一見ステルスに見える。だが、専門家は以下の点を指摘している。
- カナード翼(前翼):機動性向上のために装備されているが、レーダー波を反射しやすい
- エンジンノズルの設計:F-22のような推力偏向ノズルではなく、通常の円形ノズルのため、赤外線シグネチャーが大きい
- 表面処理の質:レーダー吸収材の質が西側機に劣る可能性
実際のRCS値は公表されていないが、F-22やF-35ほどのステルス性はないと見られている。
2. エンジン技術の遅れ
中国の航空エンジン技術は、長年の弱点だった。
WS-15エンジンは開発中だが、信頼性と寿命で西側エンジンに劣るとされる。エンジン故障のリスクは、実戦運用で致命的な問題となる。
実戦での評価:台湾海峡・南シナ海での威圧
J-20は、台湾海峡と南シナ海で頻繁に威圧飛行を行っている。
2023年以降、台湾の防空識別圏(ADIZ)への侵入回数は急増しており、その中にJ-20が含まれることも増えている。
ただし、実際の戦闘経験はゼロだ。F-22やF-35との直接対決がどうなるかは、誰にもわからない。
総合評価:量産と配備で米国に次ぐ存在
J-20は、ステルス性やエンジン技術で西側機に劣る。だが、量産体制と配備数で圧倒的優位を築いている。
数は力――この原則は、現代戦でも変わらない。
技術的限界を認識しつつも、戦略的重要性を評価して第3位とした。
第2位:F-22 Raptor(アメリカ)――「史上最強の制空戦闘機」の光と影
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | アメリカ(ロッキード・マーチン) |
| タイプ | 第5世代制空戦闘機 |
| 初飛行 | 1997年 |
| 配備状況 | 2005年〜(総生産数187機) |
「ラプター」が体現する”完璧”
F-22 Raptor――その名は「猛禽類」を意味する。
そして、その名の通り、F-22は空対空戦闘において”完璧”に近い戦闘機だ。
F-22の圧倒的強み
1. 極限のステルス性
F-22のレーダー反射断面積(RCS)は、約0.0001平方メートルと推定される。これは、ビー玉程度の大きさだ。
通常の戦闘機(F-15やSu-27など)のRCSが約10〜15平方メートルであることを考えると、その差は10万倍以上だ。
敵レーダーは、F-22を「鳥」か「気象ノイズ」と判断してしまう。
2. 超音速巡航能力(スーパークルーズ)
F-22は、アフターバーナーなしで超音速飛行が可能だ。
| 機体 | スーパークルーズ速度 |
|---|---|
| F-22 | マッハ1.8 |
| F-35 | 不可 |
| Su-57 | マッハ1.6(推定) |
スーパークルーズの利点は、以下の通りだ。
- 燃料消費が少ない:作戦時間が延びる
- 赤外線シグネチャーが小さい:ミサイルに狙われにくい
- 迅速な戦域離脱:危険を察知したら即座に逃げられる
3. 圧倒的な機動性
F-22は、推力偏向ノズル(エンジンの噴射方向を変更できる)を装備している。これにより、以下の機動が可能だ。
- 高迎角機動:機首を急激に上げても失速しない
- 超低速域での機動:通常なら墜落する速度でも操縦可能
- 瞬間的な方向転換:ドッグファイトで圧倒的優位
近距離戦闘になれば、F-22に勝てる戦闘機は存在しない――これが専門家の一致した見解だ。
致命的な弱点:生産終了とネットワーク能力の不足
だが、F-22にも重大な弱点がある。
1. 生産終了――もう増やせない
F-22の生産は、2011年に終了した。
当初計画では750機を生産する予定だったが、予算削減によりわずか187機で打ち切られた。
つまり、F-22は「絶滅危惧種」だ。戦闘で失われれば、二度と補充できない。
2. 情報共有能力の不足
F-22の設計は1990年代に完成した。当時はまだ、「ネットワーク中心戦」の概念が確立していなかった。
そのため、F-22は他の戦闘機や地上部隊との情報共有能力が限定的だ。
| 機体 | データリンク能力 |
|---|---|
| F-35 | 全軍統合ネットワーク対応 |
| F-22 | 限定的(近年の改修で改善中) |
F-35が「空飛ぶ司令部」なら、F-22は「孤高の暗殺者」――そんな違いがある。
3. 整備コストの高さ
F-22の1飛行時間あたりの整備コストは、約5万ドルと推定される。これは、F-35の約2倍だ。
さらに、特殊なステルス塗装の維持には莫大な手間がかかる。飛行後、毎回丁寧に再塗装する必要がある。
実戦での評価:「キルレシオ144:0」の伝説
F-22は、実戦経験が豊富だ。
- シリア内戦:ISIS拠点への空爆作戦
- アラスカ上空:ロシア軍機への迎撃・警告
- 演習での圧倒的戦果:レッドフラッグ演習で「144機撃墜、被撃墜ゼロ」を記録
F-22に撃墜された敵は、「何が起きたのかわからないまま死ぬ」――これが実戦の現実だ。
総合評価:制空戦闘では最強、だが時代遅れの側面も
F-22は、空対空戦闘においては間違いなく世界最強だ。
だが、ネットワーク戦の時代には、F-35のほうが「使いやすい」という現実もある。
最強の個体能力を評価して第2位としたが、総合的な戦力としてはF-35に軍配が上がる。
関連記事:F-22とF-35の違いについては、現役限定・世界最強戦闘機ランキングで詳しく解説している。
第1位:F-35 Lightning II(アメリカ+同盟国)――数とネットワークが変えた空戦の未来
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国 | アメリカ(ロッキード・マーチン) |
| タイプ | 第5世代多用途戦闘機 |
| バリエーション | F-35A(空軍型)、F-35B(STOVL型)、F-35C(艦載型) |
| 初飛行 | 2006年 |
| 配備状況 | 2015年〜(2025年時点で1,000機以上配備) |
なぜF-35が「最強」なのか?
F-22のほうが速く、機動性も上だ。J-20のほうが航続距離が長い。Su-57のほうが超機動が得意だ。
それなのに、なぜF-35が第1位なのか?
答えは単純だ――「戦闘機単体の性能」では、もはや勝敗は決まらないからだ。
現代の空戦は、ネットワーク、情報共有、システム統合が勝敗を分ける。そして、この分野でF-35は圧倒的に優れている。
F-35の真の強み
1. 世界最大の配備数――「数は力」
2025年11月時点で、F-35の配備数は1,000機を超えた。
さらに、以下の国々がF-35を運用している。
| 国 | 配備・発注数 |
|---|---|
| 🇺🇸 アメリカ | 約600機 |
| 🇯🇵 日本 | 約140機(予定) |
| 🇬🇧 イギリス | 約70機 |
| 🇮🇹 イタリア | 約90機 |
| 🇦🇺 オーストラリア | 約70機 |
| その他(韓国、ノルウェー、オランダ、イスラエルなど) | 約300機 |
F-35は、同盟国全体で共有される「共通戦力」だ。これは、他のどの戦闘機も実現していない。
2. センサー融合――「空飛ぶ司令部」
F-35の最大の特徴は、センサー融合(Sensor Fusion)だ。
F-35は、以下のセンサーを搭載している。
- AN/APG-81 AESAレーダー:360度全方位監視
- AN/AAQ-40 EOTS:光学照準・追尾システム
- AN/AAQ-37 DAS:赤外線センサー(全周6台のカメラ)
- AN/ASQ-239電子戦システム:敵レーダー・ミサイルの探知と妨害
これらのセンサー情報を、AIが統合してパイロットに提示する。
パイロットは、コックピットのディスプレイで「戦場全体の状況」を一目で把握できる。敵機、味方機、ミサイル、地上部隊、電子戦妨害――すべてがリアルタイムで表示される。
F-35パイロットは、「戦場の神の視点」を持っている。
3. ネットワーク中心戦――「一機で見たものを、全軍で共有」
F-35のセンサー情報は、リンク16やMADL(Multifunction Advanced Data Link)を通じて、味方全体と共有される。
つまり、1機のF-35が発見した敵情報を、他のF-35、F-22、AWACS、地上部隊、海軍艦艇――すべてが即座に受信できる。
| 従来の空戦 | F-35のネットワーク戦 |
|---|---|
| 各機が個別に敵を探す | 1機が見れば全軍が知る |
| 無線で声で情報共有 | データリンクで瞬時に共有 |
| パイロットの判断に依存 | AIが最適解を提示 |
これが、「ネットワーク中心戦」の威力だ。
4. 多用途性――「あらゆる任務に対応」
F-35は、以下のすべての任務をこなせる。
| 任務 | 対応能力 |
|---|---|
| 制空戦闘 | AIM-120C/D長射程ミサイルで先制攻撃 |
| 対地攻撃 | GBU-31 JDAM精密誘導爆弾、AGM-158 JASSM巡航ミサイル |
| 対艦攻撃 | JSM(Joint Strike Missile)で敵艦撃沈 |
| 電子戦 | 敵レーダー妨害、電子情報収集 |
| 偵察 | 光学・赤外線センサーで詳細な情報収集 |
F-35は、「スイスアーミーナイフ」のような戦闘機だ。
F-35の弱点
もちろん、F-35にも弱点はある。
1. 機動性の限界
F-35は、F-22やSu-57ほどの機動性はない。
ドッグファイト(近距離格闘戦)になれば、第4世代機にすら負ける可能性がある。
だが、F-35の戦術は「ドッグファイトを避ける」ことだ。長射程ミサイルで先制攻撃し、敵が接近する前に撃墜する――これがF-35の戦い方だ。
2. コストの高さ
F-35Aの単価は、約8,000万ドル(約120億円)。
さらに、1飛行時間あたりの運用コストは約3万ドル。F-16の約2倍だ。
予算が限られる国にとって、F-35は「高嶺の花」だ。
3. アメリカへの依存
F-35の運用には、米国の許可とサポートが必須だ。
- ソフトウェアのアップデートは米国が管理
- 整備部品の供給も米国次第
- 機密情報の共有レベルも米国が決定
つまり、F-35を買うことは「米国との同盟を深める」ことと同義だ。
実戦での評価:イスラエル・英国での実績
F-35は、既に実戦経験が豊富だ。
イスラエル空軍の使用例
- シリア空爆:2018年、F-35Iでシリア国内の目標を攻撃(世界初の実戦使用)
- イラン核施設への警告:イランの防空網を突破して偵察飛行
- 対ハマス作戦:ガザ地区への精密攻撃
イスラエルは、「F-35なしでは戦えない」と公言している。
英国空軍の評価
- 空母クイーン・エリザベスへの配備:F-35Bを運用
- レッドフラッグ演習:米軍との共同訓練で高評価
- ロシア軍機への対応:バルト海・北海上空での警戒任務
総合評価:「最強」は、もはやスペックでは決まらない
F-35は、単体性能では最強ではない。
だが、システムとしての総合力では、圧倒的に最強だ。
- 世界最大の配備数
- 完璧なセンサー融合
- 同盟国全体でのネットワーク共有
- 継続的なアップデートによる進化
これが、F-35を第1位とした理由だ。
もし第三次世界大戦が起きたとしたら――F-35は、最も多くの敵を撃墜し、最も多くの味方を守る戦闘機となるだろう。
関連記事:日本が保有するF-35の詳細については、日本の戦闘機一覧を参照。航空自衛隊の運用体制も解説している。
第6世代戦闘機の衝撃――空戦の未来を変える次世代計画
F-35が最強だと言ったばかりだが、その地位も長くは続かないかもしれない。
なぜなら、「第6世代戦闘機」の開発が、世界中で本格化しているからだ。
第6世代戦闘機とは何か?
第6世代戦闘機には、明確な定義はまだない。だが、以下の特徴が共通して挙げられる。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 有人・無人協働 | 有人戦闘機が「母艦」となり、複数の無人僚機を指揮 |
| AI支援 | AIがパイロットの判断を支援、最適な戦術を提示 |
| 極限のステルス性 | 第5世代をさらに上回るRCS低減 |
| 指向性エネルギー兵器 | レーザー兵器、マイクロ波兵器の搭載 |
| 極超音速ミサイル | マッハ5以上の速度で飛翔するミサイル |
| クラウド連携C2 | 戦場全体をクラウドで管理、リアルタイム情報共有 |
つまり、第6世代機は「戦闘機」というより「戦闘システムの中核」だ。
主要な第6世代戦闘機計画
1. NGAD(アメリカ空軍)
- 正式名称:Next Generation Air Dominance(次世代航空優勢)
- 配備目標:2030年代初頭
- 特徴:
- 既に試作機が秘密裏に初飛行済み(2020年)
- 「デジタル・エンジニアリング」で設計期間を大幅短縮
- CCAs(Collaborative Combat Aircraft)と呼ばれる無人僚機と協働
- 推定価格:1機あたり2億ドル以上
NGADは、F-22の後継として開発されている。2030年代には、F-22を完全に置き換える計画だ。
2. F/A-XX(アメリカ海軍)
- 正式名称:F/A-XX(次世代艦載戦闘機)
- 配備目標:2030年代中盤
- 特徴:
- 空母艦載型の第6世代機
- F/A-18E/Fスーパーホーネットの後継
- NGADとの技術共有も検討中
3. GCAP(日英伊)
既に解説したとおり、日本・イギリス・イタリアが共同開発中。2035年配備を目指す。
4. FCAS(独仏西)
既に解説したとおり、ドイツ・フランス・スペインが共同開発中。2040年配備を目指す。
5. 中国の次世代戦闘機(J-XX)
中国も、第6世代戦闘機の開発を進めていると見られる。
- 噂される機体名:J-36、J-40など(確定情報なし)
- 特徴:
- 全翼機(Flying Wing)デザインの可能性
- 超長距離作戦を想定
- 無人機との協働も計画
中国は、米国の技術を「参考」にしながら独自開発を進めるだろう。
第6世代機は「本当に必要」なのか?
ここで、重要な問いを投げかけたい。
第6世代機は、本当に必要なのか?
F-35は既に、圧倒的な性能を持っている。さらに上を目指す必要があるのか?
答えは、「ある」――だが、その理由は「性能」ではない。
理由は、「対抗手段の進化」だ。
- 中国のJ-20が量産され、配備数を増やし続けている
- ロシアのS-400/S-500防空システムが、ステルス機を探知できると主張
- 極超音速ミサイルが実戦配備され、迎撃が困難
つまり、F-35の優位性は、徐々に失われつつある。
第6世代機は、この「優位性の喪失」を防ぐための手段だ。
空戦の未来像:ステルスからAI、無人機協働へ
ここまで、現代のステルス戦闘機と次世代計画を見てきた。
最後に、「未来の空戦」がどうなるのかを考えてみよう。
1. 「見えない戦い」から「見せない戦い」へ
ステルス技術の進化により、空戦は「見えない敵との戦い」になった。
だが、今後はさらに進化する――「そもそも戦闘していることすら見せない」戦いへ。
- 電子戦:敵のレーダーやセンサーを無力化
- サイバー攻撃:敵の指揮統制システムを麻痺させる
- 情報戦:偽情報を流して敵を混乱させる
物理的な「撃墜」よりも、「無力化」が重視される時代が来るだろう。
2. 無人機が「消耗品」になる時代
第6世代機は、複数の無人僚機を従える。
だが、この無人機は「使い捨て」だ。
- 低コスト:1機あたり数億円程度(有人機の10分の1以下)
- 危険な任務専用:敵防空網への突入、囮、特攻攻撃
- 大量生産:失われても即座に補充可能
つまり、無人機は「ミサイル」と「戦闘機」の中間的存在となる。
3. AIが「副操縦士」になる
近い将来、AIは単なる「支援システム」ではなく、「副操縦士」としてパイロットと対話するようになるだろう。
- 戦術提案:「敵機を迂回して背後に回るのが最適です」
- 脅威警告:「3時方向から対空ミサイル接近。回避機動を推奨」
- 自動戦闘:パイロットが気絶した場合、AIが自動で帰還
最終的には、完全無人戦闘機も登場するだろう。
4. 宇宙が「第二の戦場」になる
現代の戦闘機は、高度2万メートルまでしか飛べない。
だが、将来的には「宇宙戦闘機」が登場するかもしれない。
- 弾道飛行:大気圏外を経由して高速移動
- 衛星攻撃:敵の偵察衛星・通信衛星を破壊
- 軌道爆撃:宇宙から地上目標を攻撃
X-37B(米空軍の無人宇宙機)は、既にこの方向への第一歩だ。
5. 「戦闘機パイロット」という職業の終焉?
最も衝撃的な予測は、これだ。
「戦闘機パイロット」という職業は、いずれ消滅するかもしれない。
理由は単純だ――AIと無人機のほうが、人間より優れているからだ。
| 項目 | 人間パイロット | AI+無人機 |
|---|---|---|
| 反応速度 | 約0.2秒 | 約0.001秒 |
| G耐性 | 最大約9G | 制限なし |
| 疲労 | あり | なし |
| コスト | 訓練に数億円 | ソフトウェア更新のみ |
もし完全無人戦闘機が実用化されれば、有人機は「時代遅れ」になる。
だが、それは同時に「人間が戦争の主役でなくなる」ことを意味する。
果たして、それは「進歩」なのか?
まとめ:ステルス戦闘機ランキングが示す「空の未来」
この記事では、2025年最新のステルス戦闘機TOP10を徹底比較してきた。
改めて、ランキングを振り返ろう。
| 順位 | 機体 | 評価のポイント |
|---|---|---|
| 1位 | F-35 | センサー融合とネットワーク能力で現代戦を支配 |
| 2位 | F-22 | 空対空戦闘最強、だが生産終了済み |
| 3位 | J-20 | 中国の量産体制確立、米国に次ぐステルス大国へ |
| 4位 | Su-57 | 超機動性は圧巻、だがステルス性と配備数に課題 |
| 5位 | B-21 | 第6世代志向の戦略爆撃機 |
| 6位 | KF-21 | コスパ最強、段階的進化で将来性大 |
| 7位 | J-35 | 中国空母の切り札、艦載ステルス機 |
| 8位 | GCAP | 日英伊の第6世代機、2035年配備目標 |
| 9位 | FCAS | 欧州の第6世代システム、2040年配備目標 |
| 10位 | Su-75 | 低コストステルス機の夢、だが実現性低い |
この記事から見える「3つの真実」
1. 「ステルス」は、もはや”必須条件”
かつて、ステルス技術は「あれば有利」な要素だった。
だが今や、ステルス性がなければ、生き残れない。
第4世代機(F-15、F-16、Su-27など)は、確実に「時代遅れ」になりつつある。
2. 「数とネットワーク」が勝敗を分ける
F-22は最強の個体性能を持つ。
だが、戦争は「個」では勝てない。
F-35のように、「数」と「ネットワーク」で圧倒するほうが、現代戦では有利だ。
3. 「第6世代」への競争が、既に始まっている
F-35の優位性は、今後10〜15年で失われるだろう。
米国、中国、日英伊、独仏西――各国が第6世代機開発にしのぎを削っている。
2030年代は、「第6世代機の時代」となる。
僕たちが学ぶべきこと
ここまで読んでくれた皆さんに、最後に伝えたいことがある。
空の戦いは、技術だけでは決まらない。
第二次世界大戦で、日本は零戦という傑作機を持っていた。だが、最終的には物量と国力で押し潰された。
現代も同じだ。
- F-35は技術的に優れているが、その背景には莫大な予算と同盟国ネットワークがある
- J-20は性能では劣るが、中国の国家的意志と量産体制が支えている
- GCAPは未完成だが、日英伊の技術力と政治的意志が結集している
空の支配は、国家の総力を映し出す鏡だ。
僕たちの先祖が、零戦や紫電改で成し遂げようとした夢――「技術力で世界と渡り合う」という誇り。
その精神は、GCAPという形で受け継がれている。
2035年、日本の空を守るのは、僕たちが作った戦闘機かもしれない。
その未来を、一緒に見届けよう。
あなたにオススメの関連記事
🔗 戦闘機関連記事
- 【現役限定】世界最強戦闘機ランキングTOP10|徹底比較2025年版
現役配備機だけを厳選したランキング。F-35、F-22、ラファール、タイフーンなど - 【2025年最新版】日本の戦闘機一覧|航空自衛隊が誇る空の守護者たち
零戦から最新F-35まで、日本の戦闘機の歴史と現在 - 第二次世界大戦・太平洋戦争で活躍した日本の戦闘機一覧
零戦、紫電改、疾風――先祖が命を懸けて飛んだ名機たち
🔗 海軍戦力関連記事
- 【2025年最新版】海上自衛隊の艦艇完全ガイド
いずも型空母、まや型イージス艦、たいげい型潜水艦など - 【完全保存版】大日本帝国海軍の潜水艦全型一覧
伊号潜水艦から特殊潜航艇まで、帝国海軍が誇った水中戦力
🔗 陸軍戦力関連記事
- 【2025年最新版】陸上自衛隊の日本戦車一覧
10式戦車、16式機動戦闘車――戦後日本が築いた技術力 - 【2025年最新版】世界最強戦車ランキングTOP10
レオパルト2A7、M1A2エイブラムス、K2ブラックパンサーなど
🔗 防衛産業関連記事
- 日本の防衛産業・軍事企業一覧【2025年最新】
三菱重工、川崎重工、IHI――日本を守る企業たち - 【2025年最新】三菱重工の防衛産業
F-35の最終組立、潜水艦、ミサイル――日本最大の防衛企業
最後まで読んでくれて、ありがとう。
この記事が、あなたの「空への興味」を少しでも深めるきっかけになれば嬉しい。
次の記事で、また会おう。
この記事は2025年11月の情報に基づいています。最新情報は随時更新していきます。




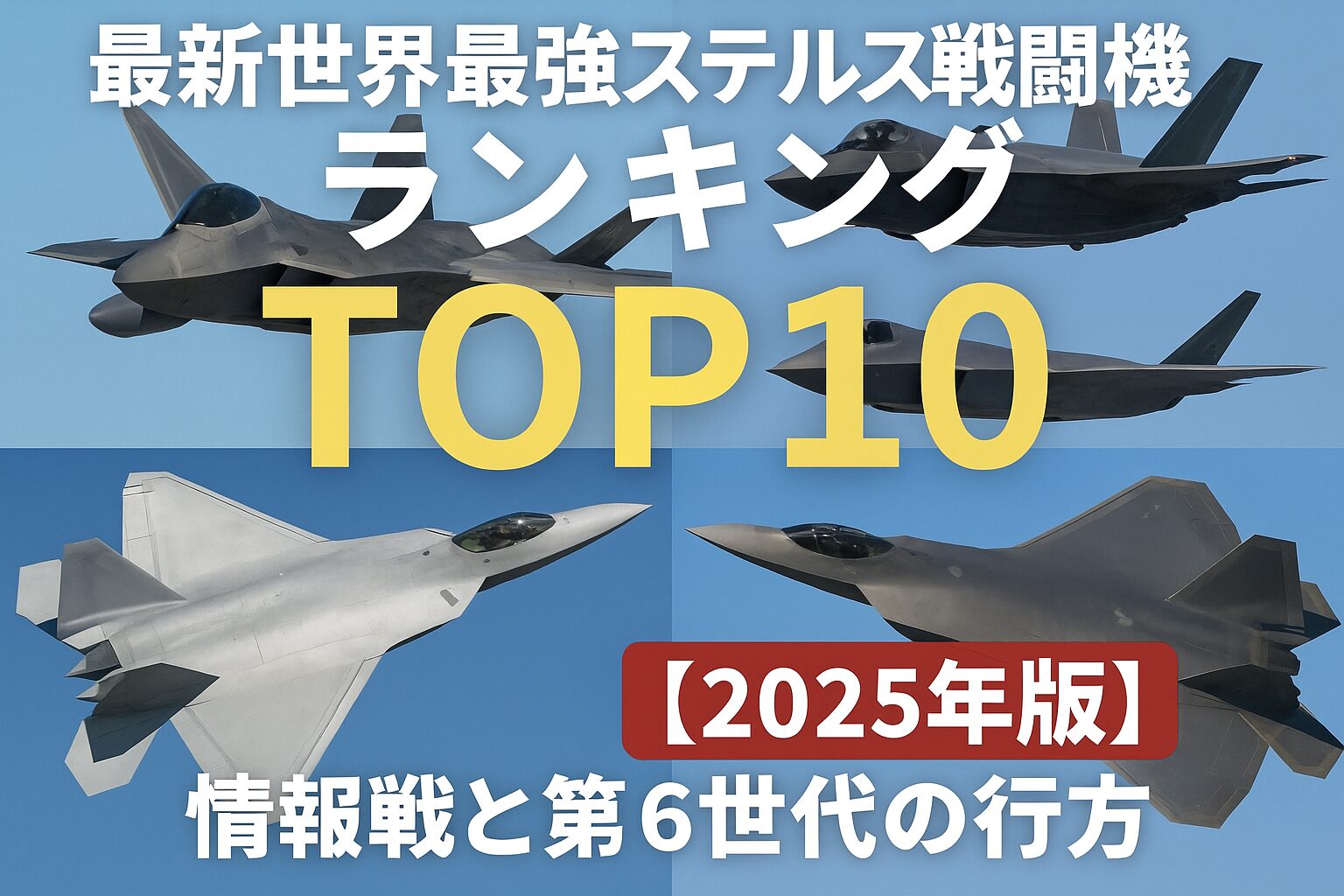








コメント