「神は人間を創り、コルトは彼らを平等にした。」
この有名なフレーズが示すのは、コルト社のリボルバーが“個人の力の均衡”を象徴する道具になったという事実です。19世紀前半、サミュエル・コルトは回転式シリンダーによる連発機構を実用レベルにまとめ上げ、工業的な大量生産とブランド戦略で一気に普及させました。南北戦争、フロンティア開拓、20世紀の警察・競技射撃、そして21世紀の高級嗜好へ――コルトの系譜は、アメリカ社会と文化の変遷そのものです。
本記事は、コルトのリボルバーを歴史(時代区分)/モデル系譜/技術・文化インパクトの3層で整理。主要モデルを時系列で追いながら、要点を初心者にもわかる言葉で解説します。
※安全・法令順守は大前提です。本記事は歴史と製品史の解説であり、使用を助長するものではありません。
記事の読み方
- 時代で俯瞰:前装式(パーカッション)→金属薬莢→SAA黄金期→ダブルアクション成熟→再興。
- モデルで深掘り:各時代の代表作とバリエーション、フレームサイズや口径の狙いを解説。
- 文化で味わう:軍・警察採用、法執行の実務、映画・TV・音楽における象徴性まで。
0. まず押さえる用語ミニ解説
最初にここだけ読んでおくと、この先がグッとわかりやすくなります。むずかしい言葉はできるだけカンタンに。
シングルアクション/ダブルアクション
- シングルアクション(SA):撃つ前に自分でハンマーを起こすタイプ。トリガーは「落とすだけ」なので引き味が軽くてキレが良い。代表例はコルトSAA(ピースメイカー)。
- ダブルアクション(DA):トリガーを引くとハンマーが起きて、そのまま落ちる。素早く連射しやすい反面、トリガーはやや重め。のちの警察用コルトはだいたいこちら。
パーカッション(前装式)→金属薬莢(後装式)
- パーカッション(前装式):紙や裸の弾丸+黒色火薬を前から込める方式。シリンダー後ろに**キャップ(雷管)**を挿して撃ちます。南北戦争頃までの主流。
- 金属薬莢(後装式):現在と同じく一体型カートリッジを後ろから込める方式。装填・排莢が速く、雨にも強い。19世紀後半に一気に主役へ。
スイングアウト・シリンダー
- シリンダーが左側にスイングして開く仕組み。一気に排莢→再装填ができて実戦的。コルトのダブルアクションは、ここから本領発揮します。
フレームサイズの感覚
- 小型(“Dフレーム”など):隠匿携行・護身向け。例:ディテクティブ・スペシャル、コブラ。
- 中型(“E/Iフレーム”など):警察・汎用。例:オフィシャル・ポリス、パイソン(Iフレーム)。
- 大型(“Nフレーム相当”級):軍用・マグナム対応・狩猟。例:ニューサービス、アナコンダ。
※コルトは時代で呼び方が揺れますが、「小・中・大」の三段くらいで捉えればOKです。
代表的な口径のざっくりキャラ
- .36 / .44(前装期):船乗りや騎兵に好まれた歴史的口径。黒色火薬時代の主役。
- .38 Special:20世紀の警察スタンダード。反動控えめ、命中精度も扱いやすい。
- .357 Magnum:.38を高圧化した“上位互換”。パイソンのイメージはコレ。
- .44 Magnum:さらに大パワー。コルトではアナコンダが代表。
- .45 Colt:SAAの看板口径。**“西部劇の一発”**といえばコレ。
こんな感じの用語イメージをポケットに入れておけば大丈夫。
次はいよいよ物語の始まり――「1. パーカッション期(1836–1872)」に進みます。
1. パーカッション期(1836–1872)— コルトの出発と確立
火薬も弾も“前から込める”、いわゆる前装式の時代。ここでコルトは**「回転弾倉(シリンダー)×量産の発想」**を固め、いきなりアメリカの主役に躍り出ます。まずは始祖から順に。
コルト・パターソン(Colt Paterson, 1836)
- 時代背景:アメリカ最初期の実用的リボルバー。テキサス・レンジャーが活用して名を上げました。
- 口径・装弾数:.28~.36口径が中心、5連発。
- 特徴:折りたたみ式トリガー(ハンマーを起こすと出てくる)で携行性良し。
- ここがポイント:まだ脆さもあったけれど、「5発を連続で撃てる」衝撃は計り知れず。後のすべてのコルトに通じるDNAがここで芽生えます。
コルト・ウォーカー(1847)
- 時代背景:メキシコ戦争期、騎兵のための“史上級”パワーを目指して設計。レンジャー隊員サミュエル・ウォーカーの名を冠します。
- 口径・装弾数:.44、6連発。
- 特徴:とにかく巨大で重い(約2kg級)。黒色火薬を大盛りで詰められるのが売り。
- ここがポイント:火力は抜群、ただし持ち歩きと反動が凄まじい。この反省が次の改良へつながります。
コルト・ドラグーン(Dragoon, 1st~3rd Model)
- 位置づけ:ウォーカーの改良型で、重量・サイズをやや現実的に。
- 口径・装弾数:.44、6連発。
- 特徴:シリンダーの容量と強度のバランスが良く、軍用として定評。
- ここがポイント:“実戦で回せる大口径”の完成度が一段アップ。南北戦争前夜の主力格に。
モデル1849 ポケット(Model 1849 Pocket)
- 位置づけ:市民の護身用として大ヒットした小型モデル。
- 口径・装弾数:主に.31、5~6連発。
- 特徴:軽くて携行しやすい。商人・旅人の**“お守り”**的存在。
- ここがポイント:コルトが民間市場でも“一家に一丁”の座をつかんだ象徴。量産と流通の勝利です。
モデル1851 ネイビー(Model 1851 Navy)
- 位置づけ:.36口径のベストセラー。海軍名だけど陸でも大人気。
- 口径・装弾数:.36、6連発。
- 特徴:扱いやすい反動と良好なバランス。銃身下のローディングレバーで前装の手間を軽減。
- ここがポイント:当時の有名人・用心棒・ガンマンにも愛用者多数。“これぞコルト”の風貌を決定づけました。
モデル1855 サイドハンマー(“ルート”)
- 位置づけ:コルトの実験気質が光る、サイドハンマー機構の変わり種。設計者名から**“ルート”**の愛称。
- 口径・装弾数:小口径中心、リボルビング・ライフル版も存在。
- 特徴:ハンマーが側面にあり、機構のコンパクト化を狙った意欲作。
- ここがポイント:主流にはなれなかったものの、派生の幅と挑戦心を示す一章。
モデル1860 アーミー(Model 1860 Army)
- 位置づけ:南北戦争の北軍を代表する主力。
- 口径・装弾数:.44、6連発。
- 特徴:ドラグーン系よりスリムで軽量。携行性と威力のバランスが秀逸。
- ここがポイント:戦場での信頼性がブランドを押し上げ、のちの金属薬莢時代へ**“看板の座”**を引き継ぎます。
モデル1861 ネイビー(Model 1861 Navy)
- 位置づけ:1851ネイビーの洗練版。
- 口径・装弾数:.36、6連発。
- 特徴:外観とバランスがよりスマートに。射撃感も好評。
- ここがポイント:**“ネイビー口径の完成形”**として、民間・軍ともに愛されました。
モデル1862 ポリス(Model 1862 Police)
- 位置づけ:携行性を重視したスリムなポケット・アーミー的存在。
- 口径・装弾数:.36、5連発が一般的。
- 特徴:細身のフォルムで隠匿携行がラク。市民警察や私服用の需要にマッチ。
- ここがポイント:**“持ち歩ける安心感”と“十分な威力”**の妥協点を提示。都市化する社会のニーズにフィットしました。
この時代のまとめ:
- コルトは**「連発」×「量産」×「ブランド」**を同時に走らせて、軍にも民間にも浸透。
- ウォーカー~ドラグーンで大火力の夢を、1849~1862系で携行と実用の現実を、見事に両立させました。
- そして次は、世界が**金属薬莢(後装式)**へと大転換していく局面。コルトは既存銃を巧みに改造しながら、新時代に橋を架けます。
2. 金属薬莢への過渡(1868–1872)
南北戦争が終わり、銃の世界は大きな転換点を迎えます。
それまで主流だったパーカッション(前装式)から、**金属薬莢を後ろから込める「後装式」**へと一気に移り変わる時代です。
しかし特許や技術の問題もあり、コルトはすぐに新銃を作れなかったため、既存のパーカッション銃を“改造”して対応していきました。
スアー改造(Thuer Conversion)
- 特徴:シリンダー後部を加工して、専用のテーパード薬莢を込められるようにした改造。
- ポイント:世界初の実用的“カートリッジ改造”でしたが、薬莢が特殊すぎて普及は限定的。
- 意味合い:それでも「旧式リボルバーを後装化できる」と示したのは大きな一歩。
リチャーズ改造(Richards Conversion)
- 対象:主にモデル1860アーミー。
- 特徴:シリンダー後部にリボルビング・リングを取り付け、薬莢対応化。後部にエジェクターロッドを追加して、排莢を簡単に。
- ポイント:見た目はまだ“前装式の名残”がありますが、実戦的にはかなり使いやすく進化。
リチャーズ=メイソン改造(Richards-Mason Conversion)
- 対象:1851ネイビーや1861ネイビーなども含む。
- 特徴:さらに改良され、シンプルな後装式機構へ。シリンダーやフレームのラインも洗練。
- ポイント:南北戦争で使われた大量の前装リボルバーを、余すところなく再利用できた。
- 意味合い:この改造があったからこそ、**“金属薬莢時代へのスムーズな移行”**が可能になりました。
1871–72 オープントップ(Colt 1871–72 Open Top)
- 特徴:最初から後装式として設計されたリボルバー。フレーム上部が“オープン”で、伝統的なパーカッションの流れを色濃く残すスタイル。
- 口径:.44リムファイア。
- ポイント:アメリカ陸軍のトライアルに出されたものの、「フレーム強度が不足」と判断され正式採用ならず。
- 意味合い:ただし、この経験が後の**1873年 シングルアクション・アーミー(SAA)**の誕生に直結しました。
この時代のまとめ
- コルトは**「古い銃を捨てずに進化」**させることで、膨大なユーザー層をつなぎとめました。
- 改造銃から完全新設計へ――まさに橋渡しの時代。
- そして1873年、ついにあの「ピースメイカー」が登場し、リボルバーの歴史を決定づけることになります。
次はお待ちかね、3. シングルアクションの黄金期(1873–)—“ピースメイカー”の時代 がやってきます。
3. シングルアクションの黄金期(1873–)— “ピースメーカー”の時代

ついに来ました。リボルバーの代名詞といえばこの銃、コルト・シングルアクション・アーミー(SAA)。
西部劇から現代の射撃競技まで、「コルト=アメリカの銃」というイメージを決定づけた伝説的モデルです。
1873 シングルアクション・アーミー(SAA/“Peacemaker”)
- 登場背景:アメリカ陸軍制式拳銃として採用。以後、コルトの名を世界に轟かせる。
- 口径:主に.45 Colt、後に.44-40、.38-40なども。
- 装弾数:6連発。ただし安全のため「実際は5発装填(1つ空室)」が基本。
- 特徴:シンプルなシングルアクション機構、頑丈なクローズドフレーム、操作の軽快さ。
- 文化的影響:西部開拓、ガンマン伝説、映画・TV、カントリーミュージックの歌詞…「ピースメイカー=西部劇の象徴」。
バリエーションいろいろ
SAAはバリエーションが非常に多彩です。代表的なものをピックアップすると――
- フロンティア・シックスシューター
- .44-40弾仕様。ウィンチェスターライフルと同じ弾を使えるので、開拓民や保安官に人気。
- ビズリー(Bisley Model)
- 1890年代に登場。握りやすいグリップと低めのハンマー。射撃競技向けに人気を集めました。
- シェリフス/ストアキーパー
- 短銃身モデル。隠匿携行や護身用に重宝されたタイプ。
- ニューフロンティア
- 20世紀中期に登場。可動式リアサイトを備えた射撃競技向けモデル。
世代ごとの違い
SAAは長い歴史の中で「世代」で区切られることが多いです。
- 第1世代(1873–1941)
- オリジナル。西部開拓とともに歩んだ伝説期。
- 第2世代(1956–1974)
- 西部劇ブームで再生産。品質も安定。
- 第3世代(1976–現在)
- 細部の設計変更あり。今も限定生産され、**“現役の伝説”**として君臨。
SAA以外のシングルアクション
もちろんSAAだけではなく、同時代にはこんな仲間たちもいました。
- ニューライン(New Line)
- 小型リボルバー。護身用や市民向け。
- ハウス・ピストル(Cloverleaf Model)
- 4連発のユニークなシリンダー形状。“クローバーリーフ”の愛称で知られる。
ダブルアクション草創期の試み
SAAと同時代、コルトは「ダブルアクション」リボルバーにも挑戦しています。
- モデル1877
- 愛称は口径ごとに違い、ライトニング(.38)、サンダラー(.41)、レインメーカー(.32)。
- ただし機構がデリケートで故障しやすく、愛憎入り混じる評価。
- モデル1878
- 大型のダブルアクション。威力と信頼性を求めた軍・警察向け。
この時代のまとめ
- SAAは**「西部を作った銃」**とまで呼ばれる歴史的存在。
- バリエーションと世代交代で100年以上現役という驚異のロングセラー。
- コルトは同時にダブルアクションへも足を踏み入れ、次の時代へ布石を打っていました。
ここでリボルバーは「伝説」から「実用品」へと進化していきます。
次は**4. スイングアウト・ダブルアクションの成立(1892–1917)**です
4. スイングアウト・ダブルアクションの成立(1892–1917)
ここからコルトは現代的な“左側に開くシリンダー”を手に入れ、警察・軍で一気に存在感を増していきます。キーワードはスイングアウト機構と、誤射を防ぐポジティブ・ロック(安全機構)。実用性能がぐっと上がり、**「伝説」から「標準装備」**へと役割が変わっていきました。
New Army & Navy(1892/1894/1896/1901/1903)
- 位置づけ:コルト初期の本格スイングアウト・ダブルアクション。アメリカ陸軍・海軍の採用を見据えたシリーズ。
- 主な口径:.38 Long Colt ほか。
- 特徴:
- 左側にシリンダーがスイングアウト、スター形エキストラクターで一気に排莢。
- 初期は強度や発火薬の仕様に課題があり、改良を重ねて“1892→1903”と進化。
- ポイント:のちの“真打ち”誕生へつながる、技術の土台を築いた存在。
ニューサービス(New Service, 1898)
- 位置づけ:大型フレームの**“ヘビー級”コルト**。軍・保安官・辺境警備のニーズに対応。
- 主な口径:.45 Colt、.44-40、のちに.45 ACP(ムーンクリップ併用)など。
- 特徴:
- 頑丈なフレームと長銃身の選択肢で、パワーと耐久性が売り。
- 一部は第一次世界大戦期に.45 ACPで運用(ムーンクリップで装填・排莢を高速化)。
- ポイント:のちのマグナム時代の先取り。大口径×DAの“正解”を提示しました。
ポリス・ポジティブ(Police Positive, 1905)/ポリス・ポジティブ・スペシャル(1907)
- 位置づけ:都市警察の“相棒”として大ヒットした小~中型フレーム。
- 主な口径:
- ポリス・ポジティブ:.32、.38 S&W など軽中口径。
- ポリス・ポジティブ・スペシャル:.38 Special対応で警察スタンダードへ。
- 特徴:
- **ポジティブ・ロック(安全機構)**で落下時の誤射を抑制。
- スリムで携行しやすく、制服勤務から私服・刑事まで幅広く浸透。
- ポイント:“ポリスのコルト”と言えばコレというくらい、20世紀前半の街に馴染んだ名作。
ポケット・ポジティブ(Pocket Positive, 1905)
- 位置づけ:護身用・私服用の小型スナブノーズ。
- 主な口径:.32口径中心。
- 特徴:短銃身・軽量で隠匿携行が容易。
- ポイント:のちに続くコルトの“小さくて頼れる”系譜の原点のひとつ。
アーミー・スペシャル(Army Special, 1908)→ オフィシャル・ポリス(Official Police, 1927改名)
- 位置づけ:中型フレームの万能選手。
- 主な口径:.38 Special ほか。
- 特徴:
- しっかりした**サイト(照準)**と扱いやすいバランス。
- 公的機関の採用が進み、**“ザ・サービスリボルバー”**として地位を確立。
- ポイント:名称変更でオフィシャル・ポリスに。以後、警察需要を支える中核モデルに成長します。
ディテクティブ・スペシャル(Detective Special, 1927)
- 位置づけ:2インチ銃身の**“本格.38スペシャル×スナブ”**という完成形。
- 主な口径:.38 Special。
- 特徴:小型Dフレームながら6連発を維持(競合の5発より優位とされた時期も)。
- ポイント:後のコブラ(軽量版)やエージェントへ続く、私服警官・探偵のアイコン。
バンカーズ・スペシャル(Bankers Special, 1928)
- 位置づけ:銀行員や特定職種向けの超コンパクト護身仕様。
- 主な口径:.22、.38 S&W など。
- 特徴:口径控えめで反動が小さく、携行性重視。
- ポイント:ニッチながら、用途特化の派生が豊富だったコルトらしさ。
オフィサーズ・モデル(Officer’s Model, ~1930s)
- 位置づけ:競技射撃(ターゲット)用の精密モデル。
- 主な口径:.38 Special、.22 LR など。
- 特徴:良質なトリガーとサイト、バレルの出来が評価され、のちのパイソンへと続く“高精度コルト”の系譜に直結。
- ポイント:実務だけでなく、スポーツで勝てるコルトをアピールした重要シリーズ。
この時代の見どころ(要点まとめ)
- スイングアウト機構の完成で、装填・排莢が飛躍的に高速化。
- ポジティブ・ロックなどの安全機構で、日常運用(警察・民間)に最適化。
- 小型~大型までフレームを細かく棲み分けし、軍・警察・競技・護身の各ニーズに応答。
- 後の**パイソン(精密・高級路線)やコブラ(携行性)**へつながる設計思想が、すでに芽生えています。
次は5. 戦後~ミッドセンチュリーの名作(1950s–1970s)――パイソン登場以降の“コルト神話ふたたび”です。
5. 戦後~ミッドセンチュリーの名作(1950s–1970s)
第二次大戦が終わり、コルトは**“実用品+高級感”という二本柱で評価を取り戻します。象徴はもちろんコルト・パイソン(1955)。精密射撃の血統を民生市場に落とし込み、「高級リボルバー=コルト」**のイメージを決定づけました。
コルト・パイソン(Colt Python, 1955)
- 立ち位置:中型Iフレームの**“プレミアム.357”**。ターゲット用のオフィサーズ・モデル系譜を一般市場へ展開した頂点作。
- 主な口径・装弾数:.357 Magnum(.38 Specialも使用可)/6連発。
- 特徴:
- ベンテッド・リブ(通気リブ)とフルアンダーラグで重量配分が前寄り、反動復帰が速い。
- ロイヤルブルーに代表される上質仕上げ、手作業のフィッティングによる滑らかなトリガー。
- バレルの内面精度とサイトが優秀で、**「箱出しで当たる」**と評判。
- 魅力のコア:精密さと“所有欲”を両立。**「撃って良し、眺めて良し」**の名作。
トルーパー(Trooper:初代~Mk III/Mk V)
- 初代トルーパー(1953~):.38 Special/.357 Magnumの汎用実戦モデル。
- トルーパー Mk III(1969~):新設計アクション(転倒ハンマー+トランスファー・バー)で強度と安全性をアップ。
- トルーパー Mk V(1980前後):トリガー改良などの近代化。
- 位置づけ:パイソンほどの豪華仕上げは不要だけど、実用で強い.357が欲しい層をガッチリ掴みました。
ローマン(Lawman)/ローマン Mk III、メトロポリタン・ポリス(Metropolitan Police)、ローンマン(Lawm a n? → Lawman)、ローマンは**“Roman”ではなく“Lawman”**です
- Lawman Mk III(1969~):実戦特化の.357。固定サイトで頑丈、制服勤務や車載にも好適。
- Metropolitan Police(1969~):.38 Special主体の行政・自治体向けパッケージ。
- ポイント:**「タフで手頃」**を標榜したMk III世代の柱。保守がラクで、公的調達に向いた設定。
コブラ(Cobra, 1950)/エージェント(Agent, 1955)
- 立ち位置:Dフレームの軽量スナブノーズ。アルミ合金フレーム。
- 口径:.38 Special ほか。
- 特徴:“6発入る小型リボルバー”というコルトの強みを、軽さと携行性で最大化。
- 用途:私服警官・探偵・民間護身。ディテクティブ・スペシャルの軽量版という理解でOK。
ダイアモンドバック(Diamondback, 1966)
- 立ち位置:小~中型の“ミニ・パイソン風”。リブ付きバレル、調整式サイト。
- 口径:.38 Special/.22 LR。
- 魅力:見た目の満足感と軽快さを両立。.22の入門~ターゲット練習にも愛された一本。
ディテクティブ・スペシャル(Detective Special)の継続的人気
- ポイント:1927登場の名作ですが、戦後も改良を重ねて定番に。
- 強み:小型なのに6連発、適度な重量で.38スペシャルの反動をコントロールしやすい。
この時代の総括(1950s–1970s)
- パイソン=高級感と精密さの頂点。所有する喜びまで含めて価値提案が完成。
- Mk III世代の実用群(Trooper/ Lawman / Metropolitan Police)=強度・安全・保守性で組織需要に応答。
- **Dフレームの軽量携行(Cobra/Agent)が“小さくて頼れるコルト”**の看板を守り、
- Diamondbackが趣味性と扱いやすさで裾野を広げました。
次は**6. 低迷と一時撤退(1980s–2000s)**に進み、キングコブラ/アナコンダから、生産縮小~DA撤退の流れまで一気に整理します。
6. 低迷と一時撤退(1980s–2000s)
80年代後半から2000年代にかけて、コルトのリボルバーはコスト・品質・市場構造の三重苦に直面します。
ポリマーフレームの自動拳銃(オート)全盛、製造コストの上昇、職人依存の仕上げ――どれもリボルバーには不利でした。そんな中でも、キングコブラやアナコンダなどの話題作は誕生しますが、最終的には多くのDA(ダブルアクション)モデルが生産終了へ。ここは“冬の時代”です。
キングコブラ(King Cobra, 1986~)
- 立ち位置:.357 Magnum対応の実用重視モデル。
- 特徴:堅牢なフレーム、ラバーグリップ、実用サイト。パイソンほどの豪華仕上げは求めない層に刺さる一本。
- 評価ポイント:**「タフで扱いやすい.357」**として警察・民間両方で堅実な人気。
アナコンダ(Anaconda, 1990~)
- 立ち位置:.44 Magnum/.45 Colt対応の大型マグナム。
- 特徴:フルラグ重バレル、調整式サイト、ステンレス仕上げ。S&Wの.44Mag対抗として投入。
- 評価ポイント:迫力と精度でコルトの存在感を示したが、高価格と時代の逆風がつきまとう。
SF-VI/DS-II(1990s)/マグナム・キャリー(Magnum Carry, 1999)
- 立ち位置:Dフレームの現代化系。
- SF-VI:ステンレス小型リボルバーの新設計。
- DS-II:伝統のDetective Special系をステンレスで再解釈。
- Magnum Carry:小型×.357という欲張り仕様。
- 評価ポイント:どれも良いコンセプトだが、採算とライン維持が難しく短命に。
パイソンの翳りと「高級仕上げの重さ」
- 背景:パイソンは手作業フィッティングと仕上げに依存し、生産コストが非常に高い。
- 結果:市場は安価で大量生産しやすいポリマー・オートへ。パイソンは嗜好品化し、やがて生産停止へ向かいます。
組織としての“選択”
- 軍・公的市場の重視:リボルバーよりも、AR系ライフルや1911系オートなど、他セグメントへ注力。
- 生産縮小:DAリボルバーの多くが終売し、SAA(シングルアクション・アーミー)は限定的に継続する体制に。
- 要するに:コルトは**「全部を守る」のではなく、「勝てる領域」を守る**戦略に舵を切りました。
この時代のまとめ
- King Cobra/Anacondaは**“最後の実戦派・大口径派”**として存在感。
- **小型ステンレス路線(SF-VI/DS-II/Magnum Carry)**は魅力的だったが、短命。
- パイソンの高級仕上げは時代と逆行気味で、量産ビジネスの壁に直面。
- コルトはDAを大幅縮小し、SAAや他ジャンルに資源を再配分して生き残りを図りました。
次は7. リボルバーの復活(2017–現在)――コブラ/キングコブラ/パイソン/アナコンダの再登場と、現代的な改良点をまとめます。
7. リボルバーの復活(2017–現在)
ここから物語は“再会編”。長い冬を越えて、コルトは現代仕様にアップデートしたリボルバーを次々と復活させます。見た目は昔の名作そのまま、でも中身はCNC加工や新素材・新設計でタフ&扱いやすく――というのが全体のトレンドです。
コブラ(Cobra, 2017復活)
- 立ち位置:伝統のDフレーム系スナブを、ステンレス主体でリブート。
- 口径・装弾数:.38 Special(+P対応)、6連発。
- 特徴:
- しっかり握れるモダンなグリップ角、視認性の良いサイト。
- 旧来の“繊細さ”を感じさせない堅牢な日常携行リボルバーに。
- 派生:Cobra Target(長銃身・可動式サイト)など、実射向けバリエーションも展開。
キングコブラ(King Cobra, 2019復活)
- 立ち位置:**.357 Magnum対応の“実戦派中核”**が回帰。
- 口径・装弾数:.357 Magnum(.38 Special可)、6連発。
- 特徴:
- ステンレス重バレルで反動コントロールがしやすい。
- 日常携行~レンジまで万能感が強い仕立て。
- 派生:King Cobra Carry(短銃身・固定サイト・携行特化)、King Cobra Target(可動式サイト・長銃身)など。
パイソン(Python, 2020再登場)
- 立ち位置:コルト復活の象徴。**“プレミアム.357”**が帰ってきた。
- 口径・装弾数:.357 Magnum/6連発。
- 特徴:
- 伝統のリブ付きフルラグ・バレル、高品位ステンレス仕上げ。
- 内部機構は現代的に最適化され、耐久・メンテ性が改善。
- トリガーの滑らかさとサイトの見やすさは健在で、**“撃って気持ちいい”**が戻ってきた。
- 派生:3.0/3.5/4.25/6/8インチ級など多彩な銃身長を展開(市場や年ごとに変動)。ターゲット志向の調整式サイトモデルが主流。
アナコンダ(Anaconda, 2021再登場)
- 立ち位置:.44 Magnumの大型フラッグシップが復活。
- 口径・装弾数:.44 Magnum(.44 Special可)/6連発。
- 特徴:
- 迫力のフルラグ重バレル、ステンレスの質感と剛性感。
- 反動吸収を意識した重量配分と良質なトリガー。
- 用途:レンジの大口径遊びからハンドガン・ハンティングまで。
“現代コルト”の改良ポイント(総論)
- 加工精度と耐久の底上げ:CNC前提の設計最適化で“当たりハズレ感”を抑制。
- 実用視認性:ホワイトアウトラインやファイバーサイト等、見やすい照準を積極採用。
- メンテ性・安全性:内部機構の再設計でタフさと扱いやすさを向上(分解・整備のハードルを下げる方向)。
- ラインナップの役割分担:
- Cobra/King Cobra=携行~汎用の主力。
- Python=所有満足+精密射撃の看板。
- Anaconda=大口径の夢と迫力。
現行を選ぶ時のヒント
- 携行優先:Cobra / King Cobra Carry(短銃身・軽快・素早いサイトピクチャ)。
- レンジで楽しく:King Cobra Target / Python(調整式サイト、銃身長の選択肢が多い)。
- 大口径の醍醐味:Anaconda(反動は強め。重量とグリップでコントロール)。
- 弾の現実性:.357は**.38での練習**がしやすく、運用コストが現実的。
この“復活編”でコルトは、伝統と最新を両立させる道を選びました。
8. 一覧でわかる主要モデル比較表(コピペ用)
| 時代 | モデル | 主口径(※代表) | 装弾 | 作動 | フレーム感 | 主用途 | トピック/メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830s–40s | Paterson (1836) | .28–.36 | 5 | SA | 小 | 初期護身・騎兵 | 折りたたみトリガー/実用的連発の嚆矢 |
| 1847 | Walker | .44 | 6 | SA | 大 | 騎兵 | 超大火力・超重量/改良の母となる |
| 1848–60s | Dragoon (1st–3rd) | .44 | 6 | SA | 大 | 軍用 | Walkerを実用域に調整 |
| 1849–70s | Model 1849 Pocket | .31 | 5–6 | SA | 小 | 市民護身 | 大ヒットの“お守り銃” |
| 1851–70s | Model 1851 Navy | .36 | 6 | SA | 中 | 軍・民 | バランス優秀、西部の顔 |
| 1855 | Sidehammer “Root” | 小口径 | 5 | SA | 小 | 護身・実験作 | サイドハンマーの意欲作 |
| 1860–70s | Model 1860 Army | .44 | 6 | SA | 中 | 軍用主力 | スリム化で携行性向上 |
| 1861–70s | Model 1861 Navy | .36 | 6 | SA | 中 | 軍・民 | 1851の洗練版 |
| 1862–70s | Model 1862 Police | .36 | 5 | SA | 小 | 私服・市民 | スリムな携行重視 |
| 1868– | Thuer Conversion | 専用テーパー | 5–6 | SA | 中 | 過渡 | 世界初級の実用的後装改造 |
| 1871– | Richards Conversion | .44 ほか | 6 | SA | 中 | 軍・民 | 1860 Armyの薬莢化/排莢ロッド |
| 1871– | Richards–Mason Conversion | .36/.44 | 6 | SA | 中 | 広域 | 1851/1861等の後装改修の本命 |
| 1871–72 | Open Top | .44 RF | 6 | SA | 中 | 軍試験・民間 | 採用見送り→SAA誕生の布石 |
| 1873– | SAA “Peacemaker” | .45 Colt※ | 6 | SA | 中 | 軍・民 | 西部の象徴/第1~3世代 |
| 1870s | SAA派生:Bisley | .45等 | 6 | SA | 中 | 競技 | 低ハンマー・競技グリップ |
| 1870s | SAA派生:Frontier Six Shooter | .44-40 | 6 | SA | 中 | 開拓民 | ライフル共弾で人気 |
| 1870s | New Line / House “Cloverleaf” | 小口径 | 4–5 | SA | 小 | 護身 | ポケット系の多彩さ |
| 1877 | Model 1877(Lightning/.38, Thunderer/.41, Rainmaker/.32) | 口径各種 | 6 | DA | 小中 | 護身 | 初期DA、デリケートで有名 |
| 1878 | Model 1878 | .45等 | 6 | DA | 大 | 軍・保安 | 大型DAの先駆け |
| 1892–1903 | New Army & Navy | .38 LC | 6 | DA | 中 | 軍・海軍 | 初期スイングアウトの土台 |
| 1898– | New Service | .45 Colt等 | 6 | DA | 大 | 軍・辺境 | 後のマグナム時代の先取り |
| 1905– | Police Positive | .32/.38 S&W | 6 | DA | 小中 | 警察 | ポジティブ・ロック搭載 |
| 1907– | Police Positive Special | .38 Special | 6 | DA | 中 | 警察標準 | 20世紀前半の主力 |
| 1905– | Pocket Positive | .32系 | 6 | DA | 小 | 私服・護身 | 小型スナブの原点 |
| 1908→1927改名 | Army Special → Official Police | .38 Special | 6 | DA | 中 | サービス | “ザ・サービスリボルバー” |
| 1927– | Detective Special | .38 Special | 6 | DA | 小 | 私服・探偵 | 小型で6連発の強み |
| 1928– | Bankers Special | .22/.38 S&W | 6 | DA | 小 | 職域護身 | 反動小・ニッチ需要 |
| ~1930s | Officer’s Model(Target/Match) | .38/.22 | 6 | DA | 中 | 競技 | 精密系譜→Pythonへ |
| 1950– | Cobra(軽量) | .38 Special | 6 | DA | 小 | 携行 | アルミ合金フレーム |
| 1955– | Agent(軽量) | .38 Special | 6 | DA | 小 | 携行 | Cobraのバリエーション |
| 1955– | Python | .357 Mag | 6 | DA | 中 | 競技・高級 | リブ+フルラグ/仕上げの頂点 |
| 1953–80s | Trooper(~Mk III/Mk V) | .357 Mag | 6 | DA | 中 | 汎用実戦 | 新機構で強度・保守性向上 |
| 1969– | Lawman Mk III | .357 Mag | 6 | DA | 中 | 警察 | 固定サイトのタフ仕様 |
| 1969– | Metropolitan Police | .38 Special | 6 | DA | 中 | 行政調達 | 公的機関向けパッケージ |
| 1966–83 | Diamondback | .38/.22 | 6 | DA | 小中 | 趣味・入門 | ミニ・パイソン風 |
| 1986– | King Cobra(初代) | .357 Mag | 6 | DA | 中 | 実用 | ラバーグリップの実戦派 |
| 1990– | Anaconda(初代) | .44 Mag/.45 Colt | 6 | DA | 大 | 大口径 | 迫力と精度の大型 |
| 1990s | SF-VI / DS-II | .38/.357 | 6 | DA | 小 | 携行 | ステンレス小型の新設計 |
| 1999 | Magnum Carry | .357 Mag | 6 | DA | 小 | 携行 | 小型×.357の野心作 |
| 2017– | Cobra(再登場) | .38 Special +P | 6 | DA | 小 | 携行~汎用 | 現代サイト・剛性向上 |
| 2019– | King Cobra(再登場) | .357 Mag | 6 | DA | 中 | 汎用 | Carry/Targetなど派生豊富 |
| 2020– | Python(再登場) | .357 Mag | 6 | DA | 中 | 精密・高級 | 内部最適化で耐久UP |
| 2021– | Anaconda(再登場) | .44 Mag | 6 | DA | 大 | 大口径 | 現代仕立てのフラッグシップ |
9. コルトが変えた「銃の運命」
コルトは“いい銃を作った会社”にとどまりません。工業・制度・文化の3つをまとめて動かし、アメリカの銃史の流れそのものを変えました。
産業面:交換可能部品と大量生産のロールモデル
- 交換可能部品(インターチェンジャブル・パーツ)
バラつきが出やすい時代に、規格化された部品で素早く組み、素早く直せる体制を構築。銃だけでなく、アメリカ機械産業の標準化に寄与しました。 - 流れ作業・品質の見える化
工程を分解し、組立と検査を徹底。結果として安定品質×大量出荷が可能に。 - ブランドと“商品企画”
同一フレームから口径・銃身長・仕上げを派生させ、ユーザーごとに“ちょうど良い”仕様を用意。製品ラインの考え方を早くから確立していました。
制度・現場:軍・警察の“標準”を作った
- 軍制式化で“基準”ができる
SAAをはじめ、コルトは軍の試験・採用を通じて“銃の要件”を具体化。使い勝手・耐久・補給に関する基準が現場に根づきました。 - 法執行機関への浸透
Police Positive、Official Police、Detective Specialなどで**“制服から私服まで”の装備体系**を提供。**安全機構(ポジティブ・ロック)**も、街中での運用にマッチ。 - 後装式へのスムーズな橋渡し
リチャーズ/リチャーズ=メイソン改造で既存銃を活かしつつ、Open Top→SAAへ移行。現場が混乱せずに**“新旧交代”**できたことは大きな価値でした。
文化:神話とリアリティの両方を手に入れた
- 西部開拓神話の“アイコン”
SAAは西部劇の象徴。スクリーンの中で“決闘の一丁”として記憶され、**「アメリカらしさ」**を視覚化しました。 - 音楽・文学・テレビ
名称やシルエットが歌詞や小説に登場し、「持っているだけで意味が生まれる」記号性を獲得。 - “高級リボルバー”というジャンル
パイソンが**「精密+上質」**の基準を作り、所有体験そのものが価値になる市場を拓きました。
技術思想の継承:伝統と現代の両立
- 昔ながらの操作感+現代加工
2017年以降の復活モデルは、見た目はクラシック、機構は今。CNC×新素材×最適化で“当たり外れ”を減らし、使い続けやすいコルトになりました。 - サイズと役割の明確化
Cobra/King Cobra/Python/Anacondaがそれぞれの目的地(携行/汎用/精密/大口径)を担当し、ユーザーは選びやすくなっています。
要するに――**コルトは“銃を作った会社”というより、“銃の時代を作った会社”でした。
生産方式から制度、文化記号に至るまで、“コルト以前”と“コルト以後”**で景色が変わったのです。
10. まとめ(読み解きのコツと鑑賞ポイント)
ここまでの内容を、**要点と“見どころ”**にぎゅっと整理しました。博物館や資料、写真を見るときの参考にどうぞ。
要点の再確認
- コルトは「量産と規格化」で時代を動かした:交換可能部品、流れ作業、明快な製品ライン。
- 系譜は「前装 → 改造 → SAA → スイングアウトDA → 現行復活」:過渡期を上手に繋いだのが強み。
- 役割分担がわかると迷わない:携行(Cobra)、汎用(King Cobra)、精密・高級(Python)、大口径(Anaconda)。
鑑賞のチェックポイント
- フレーム形状:オープントップか、トップストラップのあるクローズドか。時代感がひと目でわかる。
- シリンダーの開き方:固定ピン式か左スイングアウトか。エキストラクターの動きも注目。
- サイト(照準):固定/可動、リブ付きバレルやフルアンダーラグはパイソンらしさのサイン。
- 刻印と仕上げ:ロイヤルブルー/ステンレスの質感、モデル名の刻印、年代の手がかり。
- グリップ:ビズリー型(競技向け)か、Dフレーム系の小型か。握り心地が用途を物語る。
用語・系譜のミニ復習
- SA/DA:SAはハンマーを起こしてから撃つ“軽いキレ”、DAはトリガー一つで素早く連射。
- 前装→後装:スアー/リチャーズ/リチャーズ=メイソン改造が時代の橋渡し。
- SAA(1873–):西部の象徴。第1~3世代まで続く“現役の伝説”。
- スイングアウトDA:Police Positive/Official Policeで都市の標準装備に。
- プレミアム路線:Pythonは**「当たる×美しい」**の両立でジャンルを確立。現行はCNCで安定度が向上。
よくある誤解をさっと解消
- 「SAAは常に6発満装」:安全運用では5発+空室が基本。
- 「小型=非力」:Dフレームでも.38 Specialは十分実用域。**目的(携行・隠匿)**を考えると納得。
- 「パイソンは見た目だけ」:外観だけでなくバレル精度・トリガー・フィッティングが本質。
FAQ
Q1. コルトSAA(ピースメイカー)の世代差はどこを見ればわかりますか?
主に製造年代による仕上げや細部の設計差です。第1世代(~1941)は西部劇期のオリジナル、第2(1956–)は復刻で品質安定、第3(1976–)は細部変更と現行の供給体制が特徴です。
Q2. パイソンとキングコブラの違いは?
パイソンは「精密・高級」の頂点設計(リブ+フルラグ、滑らかなトリガー)。キングコブラは「実用重視」で、携行~レンジまでの万能さが魅力です。
Q3. 小型Dフレームの利点は?
隠匿性と携行性。ディテクティブ・スペシャルやコブラは小型でも6連発を確保した点が強みです。
Q4. 前装式から後装式への移行でコルトが果たした役割は?
スアー/リチャーズ/リチャーズ=メイソン改造で既存銃を活かしつつ、Open Top→SAAへ橋渡しを実現しました。
Q5. 現行で最初の1丁を選ぶなら?
携行・日常重視ならCobra/King Cobra Carry、レンジでの快適さならKing Cobra Target/Python。大口径体験ならAnaconda。
次に読みたい関連記事(内部リンク向け)
- SAAの世代別・口径別ガイド
- Police PositiveとOfficial Policeの装備史
- Python vs. King Cobra:射撃フィールと価格差
- リチャーズ=メイソン改造のメカ解説
- “小型で6発”Dフレーム史:Detective Special/Cobra/Agent





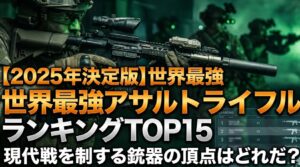







コメント