1. 【導入】”造船と重工業の老舗”は、なぜ日本の防衛を支えているのか
静かな深海を、音もなく滑るように進む一隻の潜水艦。
その艦内には、世界最高水準の静粛性を誇るディーゼルエンジン、リチウムイオン電池、最新のソナーシステムが搭載されている。
これが、海上自衛隊の「たいげい型」潜水艦だ。
そしてこの潜水艦を建造しているのが、株式会社IHI(旧・石川島播磨重工業)——多くの人には「ジェットエンジンの会社」「橋を作る会社」として知られる総合重工業メーカーである。
三菱重工業、川崎重工業と並び、日本の防衛産業を支える”ビッグスリー”の一角を担うIHI。
だが、その防衛事業の全貌は意外にも知られていない。
「IHIって、何を作っているの?」
「三菱や川崎とどう違うの?」
「なぜ潜水艦建造に強いの?」
本記事では、そんな疑問に答えるべく、IHIの防衛事業を徹底解説する。
潜水艦建造から航空機エンジン、ロケット開発、陸上装備まで——日本の安全保障を”見えないところ”で支える巨人の姿を、一緒に見ていこう。
2. IHIとは何者か?—石川島播磨重工業から続く150年の系譜
2-1. 会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式社名 | 株式会社IHI(IHI Corporation) |
| 旧社名 | 石川島播磨重工業株式会社(〜2007年) |
| 設立 | 1853年(石川島造船所として) |
| 本社所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 井手 博 |
| 従業員数 | 連結約30,000人(2024年3月期) |
| 売上高 | 連結1兆7,264億円(2024年3月期) |
| 事業内容 | 航空・宇宙・防衛、社会基盤・海洋、資源・エネルギー・環境、産業機械・物流 |
2-2. 歴史—幕末から令和まで、日本の近代化と共に歩んだ170年
IHIの起源は、1853年(嘉永6年)、江戸・石川島に開設された「石川島造船所」にさかのぼる。
ペリー来航と同じ年。
徳川幕府が海防強化のために設立したこの造船所は、日本初の洋式造船所として、日本の近代工業の黎明を象徴する存在だった。
明治維新後、官営から民営へと移行し、1876年に平野富二が石川島造船所を買収。
以降、軍艦、商船、橋梁、鉄道車両、航空機エンジンなど、あらゆる重工業分野で技術を蓄積していく。
1945年、敗戦。
GHQの指導により、一時は航空機・兵器製造を禁じられたが、朝鮮戦争を契機に再軍備が始まると、再び防衛産業へ参入。
海上自衛隊の潜水艦・護衛艦、航空自衛隊のジェットエンジン整備・製造へと事業を拡大していった。
2007年、社名を「IHI」へ変更。
グローバル展開を加速し、現在では航空エンジン、宇宙ロケット、LNGタンク、橋梁、プラントなど、幅広い分野で世界トップクラスの技術を誇る総合重工業メーカーとして君臨している。
そしてその技術力の根幹には、170年にわたる”ものづくりへの執念”がある。
3. IHIの防衛事業:全体像と売上構成
3-1. 防衛事業の位置づけ
IHIの2024年3月期の売上高は約1兆7,264億円。
このうち、防衛事業の売上高は約1,200億円規模とされ、全体の約7%を占める。
一見すると「少ない」ように見えるかもしれない。
だが、この数字には大きな意味がある。
防衛事業は、IHIの技術開発力の”核”である。
潜水艦建造で培った溶接技術、航空機エンジンで磨いた精密加工、ロケット開発で得た燃焼制御——これらの技術は、民生品にもフィードバックされ、IHI全体の競争力の源泉となっている。
つまり、IHIにとって防衛事業は、「単なる売上」ではなく、「技術の最前線」なのだ。
3-2. IHI防衛事業の4本柱
IHIの防衛事業は、大きく以下の4つに分類できる。
| 分野 | 主要製品・サービス | 特徴 |
|---|---|---|
| ①艦艇建造 | 潜水艦(そうりゅう型、たいげい型)、護衛艦(あさひ型、もがみ型等) | 世界最高水準の潜水艦技術 |
| ②航空機エンジン | F-15、F-35用エンジン部品製造・整備、民間機エンジン(GE、P&W、RR提携) | 国際共同開発への深い関与 |
| ③ロケット・宇宙 | H-IIA/H-IIIロケット、イプシロンロケット、小型衛星 | 日本の宇宙開発の中核企業 |
| ④陸上装備等 | ターボチャージャー、特殊車両、弾薬関連 | 産業機械技術の応用 |
これらすべてに共通するのは、“高精度・高品質・高信頼性”という、日本のものづくりの真骨頂だ。
では、それぞれの事業を詳しく見ていこう。
4. 【主要事業①】艦艇建造—潜水艦と護衛艦で海自を支える

4-1. 世界最高峰の通常動力型潜水艦を作る技術
「日本の潜水艦は世界最強」——そう言われることがある。
正確には、「通常動力型潜水艦(ディーゼル・エレクトリック方式)としては世界最高水準」というのが正しい。
原子力潜水艦は持たない日本だが、通常動力型潜水艦の技術では、アメリカすら一目置くレベルに到達している。
その技術を支えるのが、三菱重工業神戸造船所と、IHIの横浜事業所(旧・石川島播磨重工横浜第1工場)だ。
特にIHIは、以下のような潜水艦建造における”職人技”を保有している。
① 高張力鋼の溶接技術
潜水艦の船体には、深海の水圧に耐えるため、高張力鋼(NS鋼)が使われる。
これを歪みなく、気密性を保ちながら溶接する技術は、極めて高度だ。
IHIはこの溶接技術で、世界トップクラスの品質を誇る。
② 静粛性の追求
潜水艦にとって、「静かであること」は生存そのものを意味する。
敵に探知されないため、あらゆる騒音源を徹底的に排除する。
IHIが手がける潜水艦には、防振ゴム、二重船殻構造、静粛性ディーゼルエンジンなどが組み込まれ、「海の忍者」と呼ばれるにふさわしい静けさを実現している。
③ AIP(非大気依存推進)システムとリチウムイオン電池
これについては次項で詳しく解説しよう。
4-2. そうりゅう型潜水艦—AIP(非大気依存推進)の先駆者
そうりゅう型潜水艦は、海上自衛隊が2009年から就役させている世界初の本格的AIP搭載潜水艦だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就役期間 | 2009年〜2020年(全12隻建造) |
| 全長 | 約84m |
| 排水量 | 水上2,950トン、水中4,200トン |
| 乗員 | 約65名 |
| 兵装 | 533mm魚雷発射管×6、ハープーン対艦ミサイル |
| 建造 | 三菱重工業神戸造船所、IHI横浜事業所 |
AIP(Air-Independent Propulsion)とは何か?
通常のディーゼル潜水艦は、水中では電池で動く。
だが電池が切れると、浮上してディーゼルエンジンを動かし、充電しなければならない。
この「浮上」が、敵に探知される最大のリスクとなる。
AIPシステムは、大気(酸素)を使わずに発電できる装置だ。
そうりゅう型では、スターリングエンジン(外燃機関)を採用し、液体酸素とディーゼル燃料を使って発電する。
これにより、最大2週間、浮上せずに潜航し続けることが可能になった。
この技術の導入において、IHIは三菱重工と共に、スウェーデンのコックムス社からの技術導入と国産化を推進。
世界でも類を見ない長時間潜航能力を実現した。
4-3. たいげい型潜水艦—リチウムイオン電池で”革命”を起こす
そして、そうりゅう型の後継として2022年から就役しているのが、たいげい型潜水艦だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就役開始 | 2022年〜(計画12隻) |
| 全長 | 約84m |
| 排水量 | 水上3,000トン、水中4,300トン |
| 乗員 | 約70名 |
| 最大の特徴 | 世界初のリチウムイオン電池搭載潜水艦 |
| 建造 | 三菱重工業神戸造船所、川崎重工業神戸工場、IHI横浜事業所 |
リチウムイオン電池が潜水艦に革命を起こした
たいげい型最大の特徴は、AIPを廃止し、リチウムイオン電池を採用したことだ。
「え、AIPやめちゃったの?」と思うかもしれない。
だが、これは技術的な大きな前進なのだ。
リチウムイオン電池のメリット
- エネルギー密度が高い:従来の鉛蓄電池の約2倍
- 急速充電が可能:短時間のシュノーケリング(半潜航状態)で充電完了
- 高出力・高速航行:水中でも高速移動が可能
- メンテナンスが容易:AIPのような複雑な整備が不要
つまり、「浮上せずに長時間潜る」から、「短時間で充電し、高速で動く」へ——戦術思想そのものが進化したのだ。
このリチウムイオン電池システムの開発と搭載には、IHIの電池技術とシステムインテグレーション能力が大きく貢献している。
4-4. 護衛艦建造—あさひ型、もがみ型への参画
IHIは、潜水艦だけでなく、護衛艦の建造にも参画している。
あさひ型護衛艦(DD)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就役 | 2018年〜(全2隻) |
| 基準排水量 | 約5,100トン |
| 全長 | 約151m |
| 兵装 | Mk 41 VLS、62口径5インチ砲、CIWS、対艦ミサイルなど |
| 建造 | 三菱重工業長崎造船所(あさひ)、IHI横浜事業所(しらぬい) |
IHIは2番艦「しらぬい」を建造。
最新のイージスシステムこそ搭載していないものの、汎用護衛艦として高いバランスを持つ艦だ。
もがみ型護衛艦(FFM)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就役開始 | 2022年〜(計画22隻) |
| 基準排水量 | 約3,900トン |
| 全長 | 約133m |
| 特徴 | コンパクト・多機能・省人化 |
| 建造 | 三菱重工業、三井E&S造船、IHI(一部参画) |
もがみ型は、少人数(約90名)で運用できるコンパクトな多目的護衛艦として注目されている。
IHIは、艦内システムや推進装置の一部を担当し、間接的に建造に貢献している。
4-5. IHI造船所の現在と未来
IHIの艦艇建造の中心は、横浜事業所(横浜市磯子区)だ。
ここでは、潜水艦の最終組立、艤装(ぎそう:内部設備の取り付け)、試験が行われる。
だが、近年、IHIの造船事業は大きな転換期を迎えている。
民間造船からの撤退と防衛特化
IHIは2021年、商船建造事業をジャパン マリンユナイテッド(JMU)へ統合し、民間造船から事実上撤退。
今後は、防衛艦艇と特殊船舶(LNG船など)に特化する方針だ。
これは、「選択と集中」——限られたリソースを、最も技術力が求められる分野に注ぐ戦略である。
今後の展開
- たいげい型の量産体制確立
- 次世代潜水艦(29SS)の開発参画
- 無人潜水艇(UUV)などの新技術開発
IHIの艦艇建造は、日本の海上防衛力の”静かな柱”として、これからも進化を続けるだろう。
5. 【主要事業②】航空機エンジン—空を支える”心臓部”
5-1. 日本の航空機エンジン産業におけるIHIの位置
「日本の航空機産業」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは三菱重工業だろう。
だが、航空機エンジンに限れば、IHIこそが日本のトップランナーだ。
IHIの航空・宇宙・防衛事業における売上高は約5,000億円超(2024年3月期)。
このうち、航空エンジン関連が約6割を占める——つまり、IHIにとって航空エンジンは最大の稼ぎ頭なのだ。
しかも、その技術力は世界レベル。
GE(ゼネラル・エレクトリック)、プラット・アンド・ホイットニー(P&W)、ロールス・ロイス(RR)といった欧米の巨人たちと肩を並べ、国際共同開発プロジェクトに深く関与している。
では、IHIの航空機エンジン事業がどのように防衛と結びついているのか、詳しく見ていこう。
5-2. 民間機エンジンと防衛エンジンの”二刀流”
IHIの航空エンジン事業は、大きく民間機用と防衛用に分かれる。
民間機エンジン
IHIは、世界の主要民間機エンジンの国際共同開発パートナーとして参画している。
| エンジン名 | 搭載機 | IHIの役割 | パートナー |
|---|---|---|---|
| GE90 | ボーイング777 | ファンケース、低圧タービン部品 | GE |
| GEnx | ボーイング787、747-8 | 低圧タービンブレード、ファンケース | GE |
| LEAP | エアバスA320neo、ボーイング737MAX | 低圧タービン、ファンケース | CFMインターナショナル(GE+Safran) |
| Trent1000/XWB | ボーイング787、エアバスA350 | 中圧圧縮機部品 | ロールス・ロイス |
| PW1100G | エアバスA320neo | ギヤードターボファン部品 | プラット・アンド・ホイットニー |
世界中を飛ぶ旅客機の多くに、IHI製の部品が組み込まれている——これは、日本の技術力の証明だ。
防衛用エンジン
一方、防衛分野では、自衛隊の戦闘機・ヘリコプター用エンジンの製造・整備を担っている。
| エンジン名 | 搭載機 | 特徴 | IHIの役割 |
|---|---|---|---|
| F110-GE-129 | F-15J(航空自衛隊) | 推力約13トン | ライセンス生産・整備 |
| F110-GE-132 | F-2(航空自衛隊) | F-15用を改良 | ライセンス生産・整備 |
| F135-PW-100 | F-35A/B(航空自衛隊) | 推力約19トン、世界最強クラス | 部品製造・整備参画 |
| T700-IHI-401C | UH-60J、SH-60K(海自・空自ヘリ) | ターボシャフトエンジン | ライセンス生産 |
| XF9-1 | 次世代戦闘機(開発中) | 純国産ジェットエンジン | 主契約企業 |
特に注目すべきは、XF9-1エンジンだ。
5-3. XF9-1エンジン—純国産ジェットエンジンの挑戦
XF9-1は、IHIが防衛装備庁の支援のもと開発した、日本初の本格的な高性能ターボファンエンジンである。
XF9-1の基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種類 | アフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジン |
| 推力 | ドライ推力:約11トン、アフターバーナー使用時:約15トン |
| 推力重量比 | 約7.8〜8.0(世界トップクラス) |
| 特徴 | 高温動作、ステルス性配慮、高効率燃焼 |
| 開発期間 | 2010年代〜2020年代 |
なぜXF9-1が重要なのか?
戦闘機の心臓部であるエンジンは、国家の安全保障そのものだ。
もしエンジンを他国に依存していれば、輸出規制や政治的圧力によって、戦闘機が飛べなくなるリスクがある。
実際、過去には以下のような事例があった:
- イランへのF-14輸出停止(1979年、米国がエンジン供給を停止)
- インドへのカヴェリエンジン開発失敗(国産化に失敗し、外国製に依存)
日本も、F-2戦闘機のエンジン(F110)をアメリカから調達している。
つまり、「本当の意味での独立した防衛力」を持つには、国産エンジンが不可欠なのだ。
XF9-1の技術的特徴
① 高温耐熱材料
ジェットエンジンは、燃焼室で約1,600℃以上の高温が発生する。
この高温に耐えるため、IHIは単結晶超合金タービンブレードを開発。
この技術は、世界でもトップクラスだ。
② 推力重量比8.0超え
推力重量比とは、「エンジン自体の重さ」に対して「どれだけの推力を出せるか」を示す指標だ。
XF9-1の推力重量比は約8.0——これは、F-35のF135エンジン(約7.5)を上回る数値である。
つまり、「軽くて強力」——戦闘機にとって理想のエンジンなのだ。
③ ステルス性への配慮
現代の戦闘機において、ステルス性(敵のレーダーに映りにくい)は必須の性能だ。
XF9-1では、排気ノズルの形状を工夫し、赤外線放射(熱)を抑える設計が施されている。
XF9-1は次世代戦闘機「F-X」に搭載されるのか?
現在、防衛省は次世代戦闘機(F-X、後に「GCAP」として国際共同開発へ)の開発を進めている。
当初、XF9-1がそのまま搭載される予定だったが、2024年、日本・イギリス・イタリアの3カ国共同開発へと方針転換。
イギリスのロールス・ロイスが開発する次世代エンジンとの統合が検討されている。
だが、XF9-1で培った技術は、共同開発エンジンにも反映される見込みだ。
つまり、IHIの技術が、世界最先端の戦闘機エンジンの一部になる——これは、日本の航空技術にとって歴史的な一歩である。
5-4. F-35エンジン整備への参画
日本は、F-35A/B戦闘機を147機導入する計画だ。
このF-35に搭載されるF135エンジンの整備・修理を、IHIは担当している。
アジア太平洋地域の整備拠点
IHIは、瑞穂工場(東京都瑞穂町)にF-35エンジンの整備施設を設置。
アジア太平洋地域における整備拠点として、日本だけでなく、同盟国のF-35エンジン整備も受け入れる体制を構築している。
これにより、以下のメリットがある:
- 整備期間の短縮(米国まで送る必要がない)
- コスト削減
- 技術ノウハウの蓄積
つまり、IHIは「日本の防衛力」だけでなく、「地域の安全保障」にも貢献しているのだ。
5-5. ヘリコプターエンジンと将来展望
IHIは、ヘリコプター用エンジンでも実績を持つ。
T700エンジン
T700-IHI-401Cは、海上自衛隊・航空自衛隊の主力ヘリコプターに搭載されている。
| 搭載機 | 用途 |
|---|---|
| UH-60J | 救難ヘリコプター(空自) |
| SH-60K/J | 哨戒ヘリコプター(海自) |
このエンジンは、高い信頼性と整備性で知られ、日本の海空を支えている。
今後の展開
- 無人航空機(UAV)用エンジンの開発
- 電動推進システム(ハイブリッド航空機)への参入
- 次世代ティルトローター機への対応
航空技術は、今後も進化を続ける。
そしてIHIは、その最前線に立ち続けるだろう。
6. 【主要事業③】ロケット・宇宙開発—日本の宇宙開発を支える
6-1. IHIと日本の宇宙開発
「IHIってロケット作ってるの?」——そう驚く人もいるかもしれない。
だが、日本の宇宙開発の歴史において、IHIは不可欠な存在だ。
IHIは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と共に、以下のロケット開発に参画してきた。
| ロケット | 初打ち上げ | IHIの役割 |
|---|---|---|
| H-IIAロケット | 2001年 | 第1段エンジン(LE-7A)製造、固体ロケットブースター(SRB-A) |
| H-IIBロケット | 2009年 | H-IIAの大型版、第1段・SRB製造 |
| H3ロケット | 2023年(試験機2号機成功) | 第1段エンジン(LE-9)主契約、SRB-3製造 |
| イプシロンロケット | 2013年 | 固体燃料ロケット、第2段・第3段製造 |
特に、H3ロケットは、IHIの技術力が結集された最新鋭ロケットだ。
6-2. H3ロケット—次世代基幹ロケットの心臓部を作る
H3ロケットは、H-IIA/Bの後継として開発された、日本の次世代基幹ロケットである。
H3ロケットの基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全長 | 約63m(標準型) |
| 打ち上げ能力 | 静止トランスファ軌道(GTO):約6.5トン |
| 第1段エンジン | LE-9(液体水素・液体酸素エンジン)×2または3基 |
| 固体ロケットブースター | SRB-3×0〜4本 |
| 開発目標 | 打ち上げコストを半減、高い柔軟性 |
LE-9エンジン—IHIが作る日本最強のロケットエンジン
LE-9は、IHIが主契約企業として開発した、日本最大級の液体ロケットエンジンだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 推力 | 真空中約150トン |
| エンジンサイクル | エキスパンダーブリードサイクル |
| 燃料 | 液体水素・液体酸素 |
| 特徴 | 高信頼性、低コスト、環境に優しい |
エキスパンダーブリードサイクルとは?
従来の大型ロケットエンジン(例:H-IIAのLE-7A)は、2段燃焼サイクルを採用していた。
これは高性能だが、構造が複雑で、コストが高いという欠点があった。
一方、エキスパンダーブリードサイクルは、液体水素の冷却能力を利用してタービンを駆動する仕組みだ。
メリット:
- 構造がシンプル
- 製造コストが低い
- 信頼性が高い
つまり、LE-9は「安く、確実に、大きな推力を出す」——まさに次世代ロケットにふさわしいエンジンなのだ。
H3の試験と成功
H3ロケットは、開発過程で困難に直面した。
- 2023年3月、試験機1号機打ち上げ失敗(第2段エンジン点火せず)
- 2024年2月、試験機2号機打ち上げ成功
この成功により、H3は実用段階へと進んだ。
IHIの技術が、日本の宇宙開発を支えている。
6-3. 固体ロケットブースター(SRB)—打ち上げ初期の”爆発的推進力”
ロケット打ち上げの瞬間、両脇で白煙を噴き上げる細長い筒——それが、固体ロケットブースター(SRB)だ。
SRBの役割
SRBは、打ち上げ初期に強力な推力を発生させる補助ロケットだ。
液体燃料ロケットエンジンだけでは推力が不足する場合、SRBを追加することで、重いペイロード(衛星など)を持ち上げることができる。
IHI製SRB-3
H3ロケットに搭載されるSRB-3は、IHIが開発・製造している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全長 | 約15.1m |
| 直径 | 約2.5m |
| 推力 | 約280トン(海面上) |
| 燃焼時間 | 約100秒 |
SRB-3は、従来のSRB-Aよりも軽量化・高性能化されている。
6-4. イプシロンロケット—小型衛星打ち上げの担い手
イプシロンロケットは、小型衛星を低コストで打ち上げるために開発された、固体燃料ロケットだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全長 | 約26m |
| 打ち上げ能力 | 低軌道(LEO):約1.5トン |
| 特徴 | 固体燃料のみ、迅速な打ち上げ準備 |
IHIは、イプシロンの第2段・第3段モーターを製造している。
なぜ固体燃料ロケットが重要なのか?
固体燃料ロケットは、液体燃料に比べて準備が簡単で、短期間で打ち上げ可能だ。
これは、緊急時の偵察衛星打ち上げや、軍事利用において極めて重要な特性である。
つまり、イプシロンロケットは、日本の「独立した宇宙アクセス能力」を保証するものなのだ。
6-5. 防衛とつながる宇宙開発
「ロケットって、防衛とどう関係あるの?」——そう思う人もいるだろう。
実は、ロケット技術は、ミサイル技術と表裏一体だ。
弾道ミサイルとの技術的共通点
| 技術 | ロケット | 弾道ミサイル |
|---|---|---|
| 推進システム | 液体・固体燃料エンジン | 同じ |
| 誘導制御 | 慣性誘導、GPS | 同じ |
| 空力設計 | 高速飛行、耐熱 | 同じ |
つまり、ロケット開発能力を持つことは、「必要に応じてミサイル技術に転用できる」ことを意味する。
これは、抑止力としても機能する。
7. 【主要事業④】陸上装備・その他防衛技術—見えない場所で支える技術力
7-1. IHIの陸上装備事業の特徴
IHIの防衛事業というと、どうしても潜水艦や航空機エンジンに目が行きがちだ。
だが実は、陸上装備や特殊技術の分野でも、IHIは重要な役割を果たしている。
ただし、三菱重工業のように戦車や装甲車を丸ごと作るわけではない。
IHIの強みは、「システムの心臓部」を作ることだ。
7-2. ターボチャージャー—戦車・装甲車のパワーを引き出す
戦車や装甲車のエンジンには、ターボチャージャー(過給機)が搭載されている。
ターボチャージャーとは、排気ガスの力でタービンを回し、エンジンに大量の空気を送り込む装置だ。
これにより、エンジンの出力を大幅に向上させることができる。
IHIは、産業用・船舶用ターボチャージャーで世界トップクラスのシェアを持つ。
そしてその技術は、陸上自衛隊の戦車・装甲車にも応用されている。
10式戦車へのターボチャージャー供給
10式戦車は、陸上自衛隊の最新主力戦車だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配備開始 | 2012年 |
| 全備重量 | 約44トン(軽量化) |
| エンジン | 水冷4サイクルV型8気筒ディーゼル(1,200馬力) |
| 最高速度 | 約70km/h |
| 主砲 | 44口径120mm滑腔砲 |
この1,200馬力のエンジンを支えているのが、IHI製ターボチャージャーだ。
10式戦車は、「世界最高水準の機動性」を誇る。
その秘密の一つが、高効率ターボチャージャーによる高出力エンジンなのである。
7-3. 特殊車両・装備品への部品供給
IHIは、特殊車両や装備品の部品供給も行っている。
具体的には:
- 油圧システム(クレーン車、架橋車両など)
- 駆動系部品(トランスミッション関連)
- 冷却システム(高出力エンジン用)
これらは、「縁の下の力持ち」として、自衛隊の装備を支えている。
7-4. 弾薬・ロケット弾関連技術
IHIは、IHIエアロスペース(子会社)を通じて、ロケット弾や誘導弾の開発・製造にも関与している。
多連装ロケットシステム(MLRS)
MLRS(Multiple Launch Rocket System)は、短時間に大量のロケット弾を発射できる火力支援システムだ。
陸上自衛隊も、アメリカから導入したM270 MLRSを運用している。
IHIエアロスペースは、このMLRSに使用されるロケット弾の国産化・整備に携わっている。
今後の展開:長射程ミサイルへの参画
防衛省は現在、スタンド・オフ・ミサイル(長射程ミサイル)の開発を進めている。
これは、敵の射程外から攻撃できるミサイルであり、島嶼防衛において極めて重要な兵器だ。
IHIは、ロケット技術と誘導技術を持つため、この分野への参画が期待されている。
7-5. 電子戦・サイバー防衛への技術提供
現代の戦争は、「見えない戦場」でも戦われている。
電子戦(EW: Electronic Warfare)やサイバー防衛は、今や防衛力の中核だ。
IHIは、情報通信システムやセンサー技術を持つため、この分野でも貢献している。
具体的には:
- レーダーシステムの部品供給
- 通信機器の冷却・電源システム
- 無人機(UAV)用エンジン開発
これらは、「公表されない技術」であることが多いが、確実に日本の防衛力を支えている。
8. IHIの防衛事業における「強み」と「弱み」
8-1. IHIの強み
① 世界トップクラスの「精密加工技術」
IHIの最大の強みは、「精密加工技術」だ。
- 航空機エンジンのタービンブレード(誤差0.01mm以下)
- 潜水艦の高張力鋼溶接(気密性と強度の両立)
- ロケットエンジンの燃焼室(1,600℃超の高温に耐える)
これらすべてに共通するのは、「ミクロン単位の精度」だ。
この技術力は、150年以上の蓄積があってこそ成り立つ。
② 民生技術と防衛技術の「相互フィードバック」
IHIは、民間事業と防衛事業を両立している。
例えば:
- 航空機エンジン技術→戦闘機エンジンへ応用
- ロケット技術→ミサイル技術へ転用可能
- ターボチャージャー技術→戦車エンジンへ供給
この「技術の循環」が、IHIの競争力の源泉だ。
③ 国際共同開発への深い関与
IHIは、国際共同開発プロジェクトに積極的に参加している。
- GE、P&W、RRとの航空機エンジン共同開発
- F-35エンジン整備のアジア拠点
- 次世代戦闘機(GCAP)への参画
これにより、世界最先端の技術に常に触れることができる——これは、国内だけで開発している企業にはない強みだ。
8-2. IHIの弱み・課題
① 防衛事業の売上比率が低い
IHIの防衛事業売上は、全体の約7%にとどまる。
これは、「防衛事業だけで経営を支えられない」ことを意味する。
もし民間事業が不調に陥れば、防衛事業への投資余力が減るリスクがある。
② 潜水艦建造ペースの減少
海上自衛隊の潜水艦保有数は、現在22隻体制だ。
だが、予算制約により、建造ペースは年1隻程度にとどまる。
IHIと三菱重工、川崎重工の3社で分担しているため、IHIが受注できるのは数年に1隻という状況だ。
これでは、熟練工の技術継承が困難になる。
③ 国際競争の激化
防衛装備品の輸出は、「防衛装備移転三原則」により、厳しく制限されている。
一方、欧米の防衛企業は、世界中に輸出することで、スケールメリットを得ている。
日本企業は、国内市場だけでは規模の経済が働かない——これが、国際競争力の低下につながっている。
9. IHI防衛事業の未来—これから何が起きるのか?
9-1. 防衛費増額とIHIへの影響
日本政府は、2027年度までに防衛費をGDP比2%(約11兆円)に引き上げる方針を示している。
これは、IHIにとって大きなチャンスだ。
予想される受注増加分野
| 分野 | 予想される案件 |
|---|---|
| 潜水艦 | たいげい型の追加建造、次世代潜水艦(29SS)開発 |
| 航空機エンジン | F-35整備拡大、次世代戦闘機(GCAP)エンジン開発 |
| ロケット・ミサイル | スタンド・オフ・ミサイル開発、H3ロケット量産 |
| 無人機 | UAV用エンジン開発、無人潜水艇(UUV)開発 |
特に、次世代潜水艦(29SS)は、2030年代の就役を目指しており、IHIが主契約企業の一つになる可能性が高い。
9-2. 次世代戦闘機(GCAP)への期待
GCAP(Global Combat Air Programme)は、日本・イギリス・イタリアの3カ国共同開発による次世代戦闘機プロジェクトだ。
IHIは、エンジン開発でロールス・ロイスと協力する見込みだ。
もしこのプロジェクトが成功すれば、IHIは世界最先端の戦闘機エンジン技術を手に入れることになる。
これは、日本の航空産業にとって歴史的な一歩だ。
9-3. 宇宙・ミサイル防衛への展開
宇宙は、次の戦場だ。
日本政府は、宇宙状況監視(SSA)や衛星コンステレーション(多数の小型衛星ネットワーク)の構築を進めている。
IHIは、H3ロケット、イプシロンロケットを持つ——つまり、「宇宙へのアクセス能力」を持つ企業だ。
今後、防衛用衛星の打ち上げ需要が増えれば、IHIの役割はさらに大きくなる。
9-4. 技術継承と人材育成
防衛産業にとって、最大の課題は「技術継承」だ。
潜水艦の溶接、航空機エンジンの精密加工——これらは、「職人技」であり、簡単にマニュアル化できない。
IHIは、「技能五輪」への参加や「社内技術学校」を通じて、若手技術者の育成に力を入れている。
だが、防衛事業の受注が減れば、技術者を維持できない——これは、日本の防衛産業全体が抱えるジレンマだ。
10. まとめ—IHIは、日本の防衛力の「見えない柱」
ここまで、IHIの防衛事業について、以下の内容を解説してきた。
本記事のまとめ
| 分野 | IHIの役割 |
|---|---|
| 艦艇建造 | そうりゅう型・たいげい型潜水艦、護衛艦建造—世界最高水準の潜水艦技術 |
| 航空機エンジン | F-15、F-35、民間機エンジン—国際共同開発の中核企業 |
| ロケット・宇宙 | H3、イプシロンロケット—日本の宇宙開発を支える |
| 陸上装備 | ターボチャージャー、ロケット弾、無人機—「心臓部」を作る技術力 |
IHIは、「目立たないが、不可欠な存在」だ。
三菱重工業のように戦車や戦闘機を丸ごと作るわけではない。
だが、潜水艦の心臓部、航空機エンジンの精密部品、ロケットの推進システム——これらすべてに、IHIの技術が息づいている。
もし、IHIが防衛事業から撤退したら?
日本の潜水艦は作れなくなり、戦闘機は飛べなくなり、ロケットは打ち上げられなくなる。
それほどまでに、IHIは日本の安全保障の「見えない柱」なのだ。
11. あなたも「防衛産業」を学ぼう—おすすめ書籍・資料
もっと深く知りたい人のために、おすすめの書籍・資料を紹介する。
おすすめ書籍
『日本の防衛産業』(東洋経済新報社)
日本の防衛産業全体を俯瞰できる一冊。IHI、三菱、川崎の役割分担がよくわかる。
『潜水艦の技術』(ブルーバックス)
潜水艦の構造、推進システム、静粛性技術を科学的に解説。
『航空機エンジンの科学』(SBクリエイティブ)
ジェットエンジンの仕組みから、最新技術まで網羅。
関連記事
- 日本の防衛産業・軍事企業一覧【2025年最新】
IHI、三菱、川崎など、日本の防衛企業を完全網羅。 - 【2025年最新版】海上自衛隊の艦艇完全ガイド
IHIが建造した潜水艦・護衛艦の全貌。 - 【2025年最新版】日本の戦闘機一覧
IHIが関わる航空機エンジンの実力。
12. 最後に—「見えない技術」に敬意を
僕たちは、普段、「見えるもの」にしか目が行かない。
戦車、戦闘機、潜水艦——これらは、確かにカッコいい。
だが、その「心臓部」を作っているのは誰か?
それが、IHIのような「見えない技術」を持つ企業だ。
もし、あなたが「日本の防衛力を支えたい」と思うなら——
まず、「見えない技術」に敬意を払うことから始めてほしい。
そして、もし可能なら、IHIのような企業で働くことを考えてみてほしい。
日本の未来は、「見えない技術」を守る人々にかかっている。





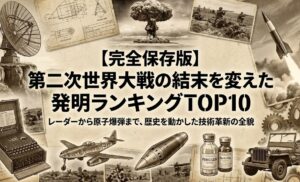




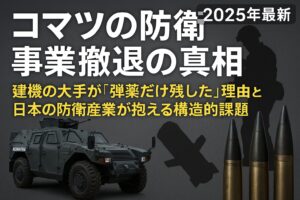

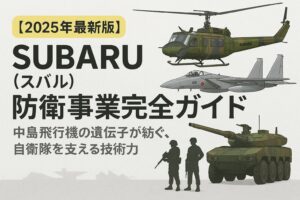
コメント