あなたが知らない”もうひとつの富士通”
パソコンを開く。スマホを手にする。クラウドにアクセスする──。
僕たちが毎日当たり前のように使っている”IT”の世界で、富士通という名前を知らない人はいないでしょう。世界最速のスーパーコンピュータ「富岳」、ノートPC「LIFEBOOK」、そして企業向けの基幹システム。日本を代表するテクノロジー企業として、その名は確固たる地位を築いています。
でも──あなたは知っていますか?
その富士通が、日本の防衛を”裏側”から支えていることを。
レーダーに映る無数の光点を瞬時に解析し、敵味方を識別する指揮統制システム。潜水艦や護衛艦が交わす暗号化通信を守るネットワーク基盤。そして、サイバー攻撃から国家を守る情報セキュリティ技術──。
これらはすべて、富士通が長年にわたって磨き上げてきた”見えない技術”です。
2025年、防衛産業が再び注目を集めています。日本政府は防衛費を過去最高水準へ引き上げ、三菱重工や川崎重工といった”表舞台”の企業に加えて、ITとサイバー領域を担う企業への期待が急速に高まっているのです。
そんな中、富士通のCEOは「防衛事業の開示を積極的に行う」と明言しました。これまで”控えめ”だった同社が、なぜ今、防衛分野での存在感を強調し始めたのか?
この記事では、富士通の防衛事業の全貌を徹底解説します。
富士通とは何者か──ITの巨人が歩んだ75年

1-1. 創業から現在まで:通信機器メーカーからITサービス企業へ
富士通の歴史は、1935年(昭和10年)に遡ります。
当時、富士電機製造株式会社(現・富士電機)の通信機部門として独立した「富士通信機製造株式会社」──これが富士通の原点です。
設立当初から、富士通は通信機器、特に電話交換機の製造を主力事業としていました。戦前・戦中には、軍需産業の一翼を担い、無線通信機器や暗号機の開発にも関与していたとされています(※詳細は機密扱いで公開資料は限定的)。
敗戦後、GHQによる財閥解体や軍需産業の規制を経て、富士通は民生用通信機器へと軸足を移します。そして1954年、日本初の商用リレー式計算機「FACOM 100」を開発。これが、富士通を”コンピュータ企業”へと変貌させる第一歩となりました。
1960年代から70年代にかけて、富士通はメインフレーム(大型汎用コンピュータ)市場で急成長。IBMを追う形で、官公庁や大企業向けに基幹システムを次々と納入していきます。
そして1980年代──。
スーパーコンピュータ「VP」シリーズの登場により、富士通は科学技術計算分野でも存在感を示し始めます。気象予測、核融合シミュレーション、そして──防衛省の各種シミュレーションにも採用されるようになったのです。
1990年代以降は、インターネットの普及とともにネットワーク機器、サーバー、ストレージへと事業を拡大。2000年代にはクラウドサービス、AI・ビッグデータ解析、IoTといった最先端技術へ投資を加速させました。
そして2020年──。
理化学研究所と共同開発したスーパーコンピュータ「富岳」が、計算速度ランキング「TOP500」で世界第1位を獲得。新型コロナウイルスの飛沫シミュレーションなどで社会的にも大きな注目を集めました。
現在の富士通は、売上高約3兆円(2024年度)、従業員約12万人を擁する、日本最大級のITサービス企業です。
富士通の事業構成──「見えるIT」と「見えないIT」
富士通の事業は、大きく以下の4つに分類されます。
| 事業セグメント | 主な内容 |
|---|---|
| テクノロジーソリューション | サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、システムインテグレーション(SI) |
| ユビキタスソリューション | パソコン(LIFEBOOK)、モバイル端末、POS端末 |
| デバイスソリューション | 半導体(LSI)、電子部品 ※2020年代に事業縮小・売却 |
| その他 | 官公庁向けシステム、防衛関連、研究開発 |
このうち、防衛事業は主に「その他」セグメントに含まれており、具体的な売上高や利益率は非公開です。
しかし、富士通のCEOが「防衛事業の開示を積極的に行う」と発言した背景には、防衛予算の拡大とサイバー・宇宙・電磁波といった新領域への投資増があると見られています。
富士通が防衛に関わり始めた歴史的背景
戦前・戦中:軍需産業としての富士通
富士通の前身である富士通信機製造は、戦前から軍用無線機や暗号機の開発に関与していました。
特に、大日本帝国陸軍が使用した九四式六号無線機や、九七式無線機などの通信機器は、富士通(当時)が製造に携わっていたとされています(※公式記録は限定的)。
また、戦時中には暗号機「九七式印字機」の改良にも関与したという記録が残っています。この暗号機は、陸軍の通信暗号を生成するための機械式タイプライターで、エニグマ(ドイツ)やパープル(日本海軍)ほど有名ではありませんが、陸軍の通信網を支える重要な装備でした。
しかし、敗戦によりこれらの技術は封印され、富士通は民生用通信機器へと転換を余儀なくされます。
戦後復興と自衛隊の発足──再び”国防”へ
1950年、朝鮮戦争が勃発。
GHQの指令により、日本には警察予備隊(後の自衛隊)が設立されます。そして1954年、防衛庁(現・防衛省)が発足し、本格的な防衛力整備が始まりました。
この時期、富士通は通信機器メーカーとして、自衛隊向けの無線通信装置や交換機を納入し始めます。特に、航空自衛隊のレーダーサイトや海上自衛隊の艦艇通信システムにおいて、富士通製の機器が採用されました。
そして1960年代後半──。
コンピュータ技術の進化とともに、富士通は指揮統制システム(C2システム)の開発に参入します。これが、現在のC4ISR(指揮・統制・通信・コンピュータ・情報・監視・偵察)へとつながる原点となりました。
冷戦期:ソ連の脅威と防空システムの高度化
1970年代から80年代にかけて、ソ連の軍事的脅威が高まる中、日本の防空体制は急速に強化されました。
特に、航空自衛隊の防空指揮システム「BADGE」(Base Air Defense Ground Environment)は、米軍の技術支援を受けつつも、国産化が進められました。
このBADGEシステムの中核を担ったのが、富士通とNECです。
富士通は、レーダー情報の処理、戦闘機への指示伝達、ミサイル発射管制といった、まさに”防空の頭脳”を構築しました。
そして1990年代──。
BADGEシステムはJADGE(Japan Aerospace Defense Ground Environment)へと進化し、イージス艦との連携や弾道ミサイル防衛(BMD)への対応が可能となります。
このJADGEの開発・運用にも、富士通は深く関与しています。
2000年代以降:サイバー・宇宙・電磁波──”新しい戦場”への対応
21世紀に入ると、戦争の形は大きく変わりました。
サイバー攻撃、宇宙空間での情報戦、電磁波妨害(EW)──。
これらは、もはや”物理的な戦場”だけでは語れない、情報領域での戦いです。
そして、この領域でこそ、富士通の技術が真価を発揮します。
- サイバーセキュリティ:防衛省や自衛隊のネットワークを守る暗号化技術、侵入検知システム
- 宇宙監視:人工衛星の軌道追跡、宇宙ゴミ(デブリ)の監視システム
- 電磁波管理:レーダー波の解析、電子戦(EW)への対応
これらの技術は、スーパーコンピュータ「富岳」やAI技術と組み合わせることで、さらに高度化しています。
富士通の防衛事業──4つの中核領域
ここからは、富士通が現在展開している防衛事業の具体的な内容を見ていきましょう。
指揮統制システム(C4ISR)
C4ISRとは、以下の頭文字を取った軍事用語です。
- Command(指揮)
- Control(統制)
- Communications(通信)
- Computers(コンピュータ)
- Intelligence(情報)
- Surveillance(監視)
- Reconnaissance(偵察)
簡単に言えば、「戦場の情報をリアルタイムで集め、最適な判断を下し、部隊に指示を出すシステム」です。
富士通は、このC4ISRシステムの中核を担っています。
具体例:航空自衛隊の「JADGE」
先ほど触れたJADGE(Japan Aerospace Defense Ground Environment)は、日本の防空を統括する”頭脳”です。
全国に配備されたレーダーサイトからの情報を集約し、戦闘機や地対空ミサイルに指示を出します。さらに、イージス艦やPAC-3といった弾道ミサイル防衛システムとも連携しています。
このJADGEの開発・運用に、富士通はシステムインテグレーターとして深く関与しています。
具体例:海上自衛隊の「艦隊指揮統制システム」
海上自衛隊の護衛艦や潜水艦は、単独で行動するのではなく、艦隊全体で連携して作戦を遂行します。
そのためには、リアルタイムでの情報共有が不可欠です。
富士通は、艦艇間の通信ネットワークや戦術情報処理システムを提供しており、特にイージス艦「こんごう」型や「あたご」型の指揮統制システムに関与しているとされています。
ネットワーク・通信基盤
現代の軍隊は、ネットワーク中心戦(Network-Centric Warfare, NCW)を前提としています。
これは、すべての部隊が情報ネットワークでつながり、リアルタイムで状況を共有し、迅速に行動するという戦い方です。
富士通は、このネットワーク基盤を支える技術を提供しています。
暗号化通信
軍事通信は、絶対に傍受されてはいけません。
富士通は、高度な暗号化技術を持ち、自衛隊の通信ネットワークを守っています。特に、量子暗号通信の研究開発にも取り組んでおり、将来的には”絶対に破られない通信”の実現を目指しています。
衛星通信
自衛隊は、防衛通信衛星「きらめき」を運用しており、これにより世界中どこでも通信可能な体制を構築しています。
富士通は、この衛星通信システムの地上局設備や通信プロトコルの開発に関与しています。
サイバーセキュリティ
2015年、日本年金機構がサイバー攻撃を受け、125万件もの個人情報が流出しました。
この事件をきっかけに、日本政府はサイバーセキュリティを国家の最重要課題と位置づけました。
そして、防衛省もサイバー防衛隊を設立し、サイバー攻撃への対応を強化しています。
富士通は、このサイバー防衛の最前線で技術を提供しています。
侵入検知システム(IDS/IPS)
富士通の侵入検知システムは、ネットワークに侵入しようとする不正アクセスをリアルタイムで検知し、自動的にブロックします。
防衛省や自衛隊のネットワークには、日々数万件ものサイバー攻撃が仕掛けられていると言われていますが、その大半はこうしたシステムによって水際で防がれています。
AI による異常検知
富士通は、AI技術を活用した異常検知システムも開発しています。
通常のアクセスパターンから逸脱した動きを自動的に検知し、未知の攻撃にも対応できるのが特徴です。
AI・HPC(高性能計算)の軍事応用
スーパーコンピュータ「富岳」は、単なる科学技術計算の道具ではありません。
その圧倒的な計算能力は、軍事シミュレーションにも応用可能です。
弾道ミサイルの軌道予測
北朝鮮が発射する弾道ミサイルの軌道を予測し、迎撃ポイントを計算するには、膨大な計算が必要です。
富士通のHPC技術は、こうしたリアルタイム計算を可能にしています。
電磁波シミュレーション
レーダーや電子戦装置の開発には、電磁波のシミュレーションが不可欠です。
富士通は、電磁波解析ソフトウェアを提供しており、防衛省の研究機関である防衛装備庁やATLA(防衛装備庁技術研究本部)と協力しています。
富士通ディフェンスシステムエンジニアリング──防衛専門子会社の実像
富士通には、防衛事業専門の子会社があります。
それが、株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング(FDSE)です。
FDSEの設立と役割
FDSEは、1970年代に設立されました(※正確な設立年は非公開)。
その目的は、防衛省・自衛隊向けのシステム開発を専門に行うことです。
FDSEは、以下のような業務を担当しています。
- 指揮統制システムの開発・保守
- 通信ネットワークの構築
- サイバーセキュリティ対策
- シミュレーションソフトウェアの開発
FDSEの公式サイトには、こう書かれています。
「防衛の最新動向をもとに提案活動にも取り組み、文字通り『国の安全・家族の安全』を担うシステムエンジニア集団です」
この一文からは、防衛事業への強い使命感が感じられます。
FDSEの従業員数と組織文化
FDSEの従業員数は非公開ですが、推定で数百名規模と見られています。
多くの社員は、防衛省や自衛隊との共同プロジェクトに従事しており、機密保持が徹底されています。
また、FDSEは富士通本体とは別の採用枠を持っており、防衛分野に特化したエンジニアを育成しています。
なぜ今、富士通は”防衛事業で表に出る”のか──CEOの戦略的意図
2024年、富士通のCEOは「防衛事業の開示を積極的に行う」と発言しました。
これは、極めて異例のことです。
なぜなら、防衛事業は機密性が高く、企業側も積極的に情報を公開してこなかったからです。
では、なぜ今、富士通は”表に出る”のか?
防衛予算の拡大と新領域への期待
日本政府は、2027年度までに防衛費をGDP比2%(約11兆円)に引き上げる方針を示しています。
この予算増の中で、特にサイバー・宇宙・電磁波といった新領域への投資が急増しています。
富士通にとって、これは大きなビジネスチャンスです。
投資家へのアピール
防衛事業は、安定した収益源です。
なぜなら、国が顧客であり、長期契約が前提だからです。
富士通のCEOは、この点を投資家にアピールすることで、株価の安定や企業価値の向上を狙っていると考えられます。
人材確保──”誇り”を持てる仕事としての防衛
IT業界は、深刻な人材不足に悩んでいます。
特に、高度なセキュリティ技術やAI・HPCを扱えるエンジニアは、引く手あまたです。富士通が防衛事業を”表に出す”ことで、「国を守る仕事」という誇りを前面に出し、優秀な人材を確保しようとしているのです
スーパーコンピュータ「富岳」と軍事シミュレーション

「富岳」とは何か──世界最速の計算能力
スーパーコンピュータ「富岳」は、2020年に理化学研究所と富士通が共同開発した、日本が誇る計算機です。
2020年から2021年にかけて、計算速度ランキング「TOP500」で4期連続世界第1位を獲得し、新型コロナウイルスの飛沫シミュレーションや創薬研究で社会的にも大きな注目を集めました。
富岳の性能(主要スペック)
| 項目 | 性能 |
|---|---|
| 理論演算性能 | 537PFLOPS(ペタフロップス) |
| 実効性能 | 442 PFLOPS |
| CPU | 富士通製 A64FX(ARM アーキテクチャ) |
| ノード数 | 158,976 ノード |
| 消費電力 | 約29.9 MW |
※ PFLOPS = 1秒間に1000兆回の浮動小数点演算が可能
この圧倒的な計算能力は、科学技術計算だけでなく、軍事シミュレーションにも応用可能です。
弾道ミサイルの軌道予測と迎撃計算
北朝鮮が発射する弾道ミサイルは、発射から着弾までわずか数分~十数分しかありません。
この短時間で、以下の計算を行う必要があります。
- ミサイルの軌道を予測する
- 着弾地点を推定する
- 迎撃ミサイル(PAC-3やSM-3)の最適な発射タイミングと角度を計算する
これらの計算には、膨大な演算能力が必要です。
富士通のHPC(高性能計算)技術は、こうしたリアルタイム計算を可能にしています。
特に、大気の密度変化や風の影響、地球の自転といった複雑な要素を考慮した精密な軌道予測には、富岳クラスの計算能力が不可欠です。
電磁波シミュレーションとレーダー開発
レーダーは、電磁波を発射し、その反射波を受信することで、敵機や敵艦の位置を探知します。
しかし、レーダーの性能を最大化するには、電磁波の伝播を正確にシミュレーションする必要があります。
-地形による反射・回折
- 大気中の水蒸気による減衰
- 敵の電子戦装置による妨害
これらを考慮した電磁波シミュレーションには、膨大な計算が必要です。
富士通は、電磁波解析ソフトウェアを提供しており、防衛装備庁や自衛隊の研究機関と協力してレーダー開発を支援しています。
気象予測と作戦立案
軍事作戦において、天候は極めて重要な要素です。
-航空作戦:視界不良や強風は飛行を困難にする
- 海上作戦:波の高さや潮流は艦艇の航行に影響する
- 陸上作戦:降雨や降雪は地形を変え、移動を困難にする
富士通の気象予測システムは、富岳の計算能力を活用し、数時間先から数日先までの天候を高精度で予測します。
これにより、自衛隊は最適なタイミングで作戦を実行できるのです。
「富岳NEXT」──日米共同開発が変える未来
エヌビディアとの協業の意味
2025年8月、理化学研究所は衝撃的な発表を行いました。
「富岳」の後継機「富岳NEXT」を、富士通と米エヌビディアとともに開発する」
これは、日本の旗艦スーパーコンピュータとして初めてGPU(グラフィック処理装置)を採用する試みです。
なぜエヌビディアなのか?
エヌビディアは、AI処理に最適化されたGPUで世界市場を席巻しています。特に、「CUDA」と呼ばれるソフトウェア環境は、世界中のAI開発者が利用する必須ツールです。
富士通のCPU「A64FX」の後継である「モナカX」と、エヌビディアのGPUを協調設計(コ・デザイン)することで、CPUとGPUの性能を最大限引き出すことが可能になります。
富士通のヴィヴェック・マハジャン副社長は、こう語っています。
「エヌビディアの膨大な資産を使えるのは大きい」
AI性能100倍の衝撃
富岳NEXTでは、富岳に比べてアプリケーション性能を最大で100倍に引き上げる目標を掲げています。
その内訳は以下の通りです。
| 項目 | 性能向上 |
|---|---|
| ハードウェア性能(富士通×エヌビディア) | 6倍 |
| ソフトウェア性能(理研の技術力) | 20倍 |
| 合計 | 最大100倍 |
さらに、AI処理の能力に限っては、ゼタフロップス(1兆の10億倍)規模を目指しています。
これがどれほど凄いかというと──。
現在の富岳は、AI処理において、エヌビディアの最新GPU「H100」を搭載したシステムに劣ります。しかし、富岳NEXTが完成すれば、世界最高水準のAI処理能力を持つことになるのです。
戦略的自律性と戦略的不可欠性
理研の松岡聡センター長は、富岳NEXTの意義をこう語っています。
「自国でAIを開発できるかどうかは、研究開発の自律性に直結する」
これは、防衛においても同じです。
もし、日本が海外製のAIに依存していたら?
-敵国がそのAIに「バックドア」を仕込んでいたら?
- 戦時に、AI の提供を拒否されたら?
こうしたリスクを避けるために、自国でAI を開発できる能力が不可欠なのです。
さらに、富士通のCPU技術は、世界で4社しか持たない貴重なものです。
「スパコン向けCPUを設計できるのは、米インテル、米AMD、米IBM、富士通だけだ」(松岡センター長)
この技術を持つことで、日本は「戦略的不可欠性」を確立できます。つまり、他国が日本の技術を必要とする状況を作り出せるのです。
量子暗号通信──”絶対に破られない”通信の実現へ
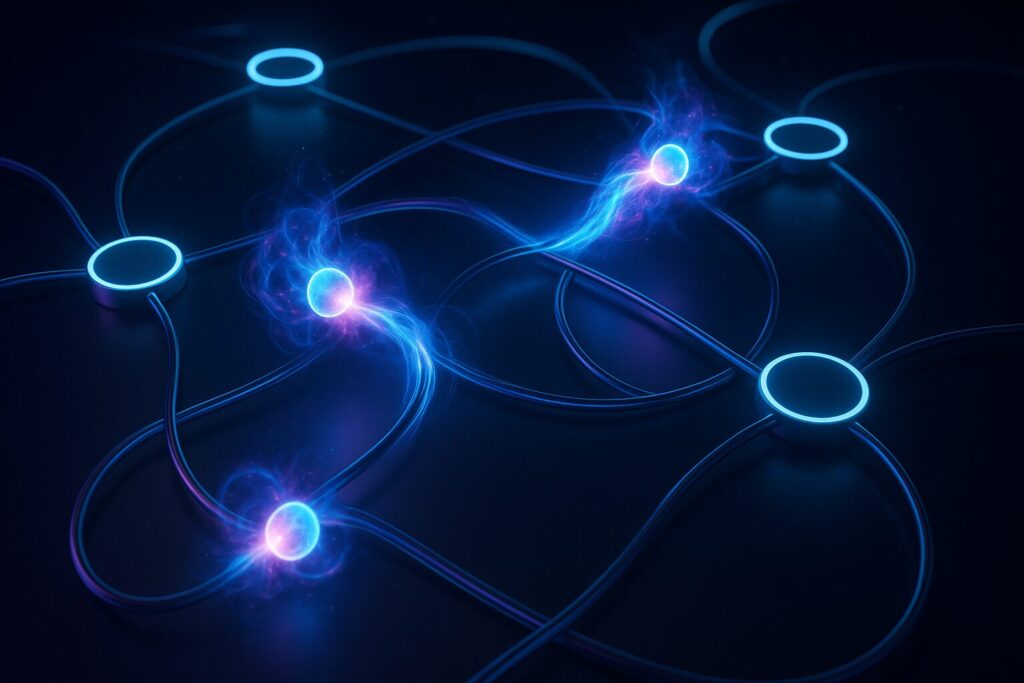
量子暗号とは何か?
現代の暗号技術は、「計算量的安全性」に基づいています。
つまり、「解読するのに膨大な時間がかかるから安全」という考え方です。
しかし、量子コンピュータが実用化されれば、現在の暗号は数分で破られる可能性があります。
そこで登場するのが、量子暗号です。
量子暗号は、「物理法則的に絶対に破られない」暗号です。
その原理は、量子力学の「観測すると状態が変わる」という性質を利用しています。
簡単に言えば──。
- 送信者Aが、光子(光の粒)を使って暗号鍵を送る
- もし、敵Cがその光子を盗聴しようとすると、光子の状態が変わる
- 受信者Bは、光子の状態が変わったことを検知し、盗聴されたことを知る
つまり、盗聴されたら必ずバレるのです。
富士通の量子暗号技術
富士通は、量子暗号通信の研究開発に長年取り組んでいます。
特に、「量子鍵配送(QKD: Quantum Key Distribution)」と呼ばれる技術に注力しています。
2020年には、富士通と東芝が共同で、長距離量子暗号通信の実証実験に成功しました。
さらに、富士通は「量子暗号ネットワーク」の構築も視野に入れています。これは、複数の拠点を量子暗号で結び、全国規模の安全な通信網を作るというものです。
3-3. 自衛隊への実装はいつ?
現時点では、自衛隊への量子暗号通信の実装は公式には発表されていません。
しかし、防衛省は「量子技術の防衛応用」を重要課題と位置づけており、富士通の技術が採用される可能性は高いと見られています。
特に、防衛通信衛星「きらめき」の後継機に量子暗号通信が搭載されるのではないか、という観測もあります¥>。
AIによるサイバー防衛──”見えない敵”との戦い

サイバー攻撃の現状
防衛省や自衛隊のネットワークには、毎日数万件ものサイバー攻撃が仕掛けられていると言われています。
その手口は、日々進化しています。
- 標的型攻撃:特定の組織を狙った高度な攻撃
- ゼロデイ攻撃:未知の脆弱性を突く攻撃
- APT攻撃:長期間にわたって潜伏し、情報を盗み続ける攻撃
こうした攻撃に対抗するには、人間の監視だけでは限界があります。
そこで、AIの出番です。
富士通のAI異常検知システム
富士通は、AI技術を活用した異常検知システムを開発しています。
このシステムは、通常のアクセスパターンを学習し、そこから逸脱した動きを自動的に検知します。
例えば──。
- 深夜に、普段アクセスしない部署のサーバーにアクセスがあった
- 大量のデータが短時間で外部に送信された
- 通常とは異なる経路で通信が行われた
こうした「おかしな動き」を、AIが自動的に見つけ出すのです。
さらに、富士通のAIは「未知の攻撃」にも対応できます。
従来のセキュリティシステムは、「既知の攻撃パターン」をデータベースに登録し、それに一致する攻撃をブロックするという方式でした。
しかし、これでは「未知の攻撃」には対応できません。
富士通のAIは、「正常な動き」を学習することで、「異常な動き」を自動的に検知します。つまり、攻撃パターンを知らなくても、攻撃を防げるのです。
マルチAIエージェントの可能性
富士通は、「マルチAIエージェント」の研究も進めています。
これは、複数のAIが協力して問題を解決するという仕組みです。
例えば──。
- AIエージェントA:ネットワークの監視を担当
- AIエージェントB:ログの解析を担当
- AIエージェントC:攻撃の予測を担当
これらのAIがリアルタイムで情報を共有し、協力して攻撃を防ぐのです。
富士通のロードマップによれば、2026年から2028年にかけて、マルチAIエージェントの実用化を目指しています。
富士通の防衛AI戦略──「Kozuchi」と「Takane」
「Fujitsu Kozuchi」とは何か?
「Fujitsu Kozuchi」(フジツウ コヅチ)は、富士通が提供するAIプラットフォームです。
「小槌(こづち)」という名前は、日本の民話に登場する「打ち出の小槌」から取られています。つまり、「AIで何でも生み出せる」という意味です。
Kozuchiは、以下の機能を提供します。
- 生成AI:文章や画像、プログラムコードを自動生成
- ナレッジグラフ拡張RAG:企業データを構造化し、AIが利用可能にする
- 業務特化型AIエージェント:特定の業務に特化したAIを構築
大規模言語モデル「Takane」の軍事応用
富士通は、独自の大規模言語モデル(LLM)「Takane」を開発しています。
Takaneは、1110億パラメータを持つ大規模モデルで、日本語処理に特化しています。
なぜ、日本独自のLLMが必要なのか?
もし、海外製のLLM(例:ChatGPT)に依存していたら──。
- 軍事機密を含むデータを、海外企業のサーバーに送ることになる
- 戦時に、LLMの提供を拒否される可能性がある
- 敵国が、LLMに「バックドア」を仕込んでいる可能性がある
こうしたリスクを避けるために、日本独自のLLMが必要なので。
富士通は、Takaneを「特化型AI蒸留」と「量子化」によって軽量化し、特定の業務に特化したAIモデルを生成する技術も開発しています。
例えば──。
- 防衛計画の立案に特化したAI
- サイバー攻撃の解析に特化したAI
- 兵站管理に特化したAI
こうした業務特化型AIを、自衛隊の各部署に配備することが可能になります。
ナレッジグラフ拡張RAGと業務特化型AIエージェント
RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、「検索拡張生成」と訳される技術です。
これは、AIが回答を生成する際に、データベースから関連情報を検索し、それを参照して回答するという仕組みです。
富士通は、このRAGを「ナレッジグラフ」と組み合わせることで、さらに高度化しています。
ナレッジグラフとは、情報を「ノード(点)」と「エッジ(線)」で表現したグラフ構造です。
例えば──。
- ノード:「F-15戦闘機」「三菱重工」「エンジン」
- エッジ:「F-15戦闘機」→「製造元」→「三菱重工」 「F-15戦闘機」→「搭載」→「エンジン」
このように、情報を構造化することで、AIが複雑な質問にも正確に答えられるようになります。
さらに、富士通は「業務特化型AIエージェント」の開発も進めています。
これは、特定の業務を自動化するAIです
例えば──。
- 兵站管理AIエージェント:弾薬や燃料の在庫を自動管理し、補給計画を立案
- 情報分析AIエージェント:偵察衛星やドローンからの画像を自動解析し、敵の動きを予測
- サイバー防衛AIエージェント:ネットワークを常時監視し、攻撃を自動でブロック
こうしたAIエージェントが24時間365日働くことで、人間の負担を大幅に軽減できるのです。
防衛装備移転と富士通──”武器輸出解禁”の中で
防衛装備移転三原則とは何か?
「日本は武器を輸出しない」──。
長年、これが日本の基本方針でした。
1967年、佐藤栄作内閣が打ち出した「武器輸出三原則」は、共産圏諸国、国連決議で武器輸出が禁止された国、紛争当事国への武器輸出を禁止し、事実上「武器輸出の全面禁止」を意味していました。
しかし、2014年、安倍政権はこれを見直し、「防衛装備移転三原則」を策定。条件付きで武器輸出を可能にしました。
そして2023年、岸田政権はさらに運用指針を見直し、「ライセンス生産された装備品の第三国輸出」や「共同開発した装備品の輸出」を解禁しました。
これにより、日本の防衛産業は「輸出市場」へと本格的に進出できる道が開かれたのです。
富士通が輸出可能な「装備品」とは?
しかし──。
富士通は、三菱重工のように戦闘機や護衛艦を作っているわけではありません。
では、富士通が輸出できる「装備品」とは何か?
それは、「ソフトウェア」と「システム」です。
具体的には以下のようなものが考えられます。
| 輸出可能な技術・システム | 想定される輸出先 |
|---|---|
| レーダー情報処理システム | 東南アジア諸国(フィリピン、ベトナムなど) |
| サイバーセキュリティ技術 | Quad諸国(米豪印)、NATO加盟国 |
| 指揮統制システム(C4ISR) | 同盟国・友好国 |
| 気象予測システム | 災害対策を名目に途上国へ |
| 量子暗号通信技術 | 同盟国への技術供与 |
これらは、「殺傷能力を持たない装備品」であり、政治的なハードルも比較的低いと言えます。
フィリピン・東南アジアへのレーダーシステム
2024年、日本政府はフィリピンへの警戒管制レーダーシステムの供与を決定しました。
このシステムは、航空自衛隊のレーダーサイトで使用されている技術をベースにしており、富士通が開発に関与したとされています。
フィリピンは、南シナ海での中国の軍事的圧力に直面しており、海空域の監視能力強化が急務です。日本から供与されるレーダーシステムは、フィリピンの領空監視能力を大幅に向上させることが期待されています。
さらに、ベトナム、インドネシア、マレーシアといったASEAN諸国も、同様のシステムに関心を示しています。
富士通にとって、これは新たな市場となる可能性があります。
サイバーセキュリティ技術の輸出
サイバーセキュリティ技術は、もはや「武器」と言っても過言ではありません。
富士通の侵入検知システムや、AIによる異常検知技術は、軍事ネットワークを守る「盾」として、同盟国から高い評価を受けています。
特に、Quad諸国(日米豪印)の間では、サイバーセキュリティ分野での協力が進んでおり、富士通の技術が「共通基盤」として採用される可能性があります。
また、NATO加盟国との協力も視野に入っています。2024年、日本政府はNATOとのサイバー防衛協力を強化する方針を打ち出しており、富士通はこの協力の中核を担う企業の一つと目されています。
国際協力──日米同盟とQuadの中での富士通
日米防衛協力と「富岳NEXT」の意味
「富岳NEXT」は、富士通と米エヌビディアの協業によって開発されます。
これは、単なる技術協力ではありません。
日米同盟の”デジタル版”と言えるものです。
なぜなら、AI技術は軍事的に極めて重要だからです。
米国は、「AI優位性」を国家安全保障の最優先課題と位置づけており、同盟国との技術共有を積極的に進めています。
富岳NEXTが完成すれば、日米両国は共通のAI基盤を持つことになります。これにより、以下のような協力が可能になります。
- 共同作戦計画の立案:日米のAIが連携し、最適な作戦を自動生成
- サイバー攻撃の共同防御:リアルタイムで脅威情報を共有し、協調防御
- 兵站の最適化:補給物資の配分や輸送ルートをAIが自動計算
これは、まさに「ネットワーク中心戦」の究極形です。
Quad(日米豪印)でのサイバー協力
Quad(日米豪印)は、もともと「自由で開かれたインド太平洋」を目指す枠組みとして発足しました。
しかし近年、その協力分野はサイバーセキュリティや技術協力へと広がっています。
2023年、Quad諸国は「サイバーセキュリティ・パートナーシップ」を立ち上げ、以下の分野での協力を進めています。
- サイバー攻撃の情報共有
- 共通のサイバー防衛基準の策定
- 人材育成プログラム
富士通は、この枠組みの中で技術提供者としての役割を果たすことが期待されています。
特に、インドは急速にサイバー能力を強化しており、富士通の技術は高い関心を集めています。
NATO諸国との連携の可能性
2024年、日本政府はNATOとの関係強化を打ち出しました。
これは、ウクライナ戦争を受けて、「自由主義陣営の結束」が重視されるようになったためです。
富士通にとって、NATO諸国との協力は新たなフロンティアです。
特に、以下の分野での協力が考えられます。
| 協力分野 | 想定される内容 |
|---|---|
| サイバー防衛 | NATO加盟国との脅威情報共有プラットフォームの構築 |
| AI技術 | 共同研究開発プロジェクトへの参加 |
| 量子暗号 | NATO通信網への量子暗号技術の供与 |
ただし、NATO諸国との協力には地理的距離や政治的ハードルがあり、実現には時間がかかる可能性があります。
株価と投資家の視点──防衛事業は”儲かる”のか?
富士通の防衛事業の売上規模(推定)
富士通は、防衛事業の売上高を公開していません。
しかし、業界関係者の推定によれば、富士通の防衛関連売上は年間500億円~1000億円規模とされています。
これは、富士通の総売上(約3兆円)の2~3%程度に過ぎません。
一見、小さく見えますが──。
利益率に注目すると、話は変わってきます。
防衛事業は、長期契約が前提であり、価格競争が少ないため、利益率が高いとされています。一般的なIT事業の営業利益率が5~10%程度であるのに対し、防衛事業は15~20%に達するとも言われています。
つまり、売上規模は小さくても、利益貢献度は大きいのです。
防衛予算拡大の恩恵は?
日本政府は、2027年度までに防衛費を11兆円に引き上げる方針です。
このうち、サイバー・宇宙・電磁波といった新領域への投資は、年間1兆円規模に達すると見られています。
富士通が、この1兆円の10~20%を獲得できれば、防衛事業の売上は1000億円~2000億円に倍増する可能性があります。
投資家が注目する「安定収益源」としての防衛
投資家にとって、防衛事業の魅力は「安定性」にあります。
なぜなら──。
- 顧客が国:倒産リスクがゼロ
- 長期契約:10年、20年単位の契約が一般的
- 景気に左右されにくい:防衛は「必要経費」であり、景気後退期でも削減されにくい
富士通のCEOが「防衛事業の開示を積極的に行う」と発言した背景には、こうした投資家へのアピールがあると考えられます。
実際、2024年の発言以降、富士通の株価はじわじわと上昇しています(※市場全体の動向もあり、防衛事業だけが理由ではない)。
ESG投資との矛盾?──防衛産業への投資は是か非か
しかし、ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)の文脈では、防衛産業への投資は議論の余地があります。
一部の投資家は、「武器製造企業への投資は倫理的に問題がある」と考え、防衛企業を投資対象から除外しています。
ただし、富士通の場合、「殺傷兵器を直接製造しているわけではない」という点が重要です。
富士通が提供するのは、情報システムやサイバーセキュリティ技術であり、これらは「防御的」な性格が強いと言えます。
このため、「防衛≠攻撃」という論理で、ESG投資の対象として許容される可能性があります。
実際、欧米の一部のESGファンドは、「防御的な防衛技術」への投資を認めています。
2030年の日本防衛──富士通が描く未来
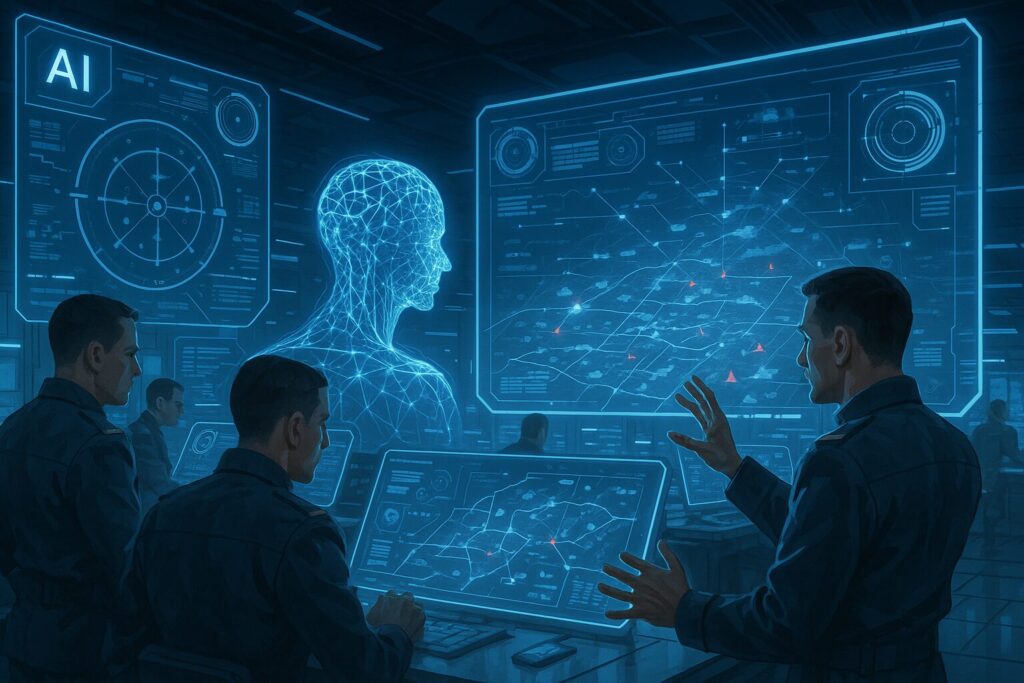
AI統合指揮システム──人間とAIの協働
2030年、日本の防衛はどう変わっているのか?
富士通が描く未来の一つは、「AI統合指揮システム」です。
これは、人間の指揮官とAIが協働して作戦を立案・実行するシステムです。
具体的には、以下のような流れになります。
- 偵察衛星・ドローン・レーダーが敵の動きを捉える
- AIが情報を瞬時に解析し、敵の意図を予測
- 複数の作戦案を自動生成し、人間の指揮官に提示
- 指揮官が最終判断を下す
- AIが部隊への指示を自動送信し、実行を支援
このシステムの鍵は、「人間の最終判断権を残す」ことです。
つまり、「AIは提案するが、決断は人間がする」というバランスです。
これは、倫理的にも重要な設計思想です。なぜなら、「殺傷の決定を機械に任せてはいけない」という国際的なコンセンサスがあるからです。
富士通は、この「ヒューマン・イン・ザ・ループ(人間を回路に残す)」の原則を堅持しています。
量子コンピュータと次世代暗号
2030年代には、量子コンピュータが実用化されると予測されています。
量子コンピュータは、現在のスーパーコンピュータでは数千年かかる計算を、数分で解くことができます。
これは、暗号技術にとって革命的な脅威です。
現在の暗号(RSA暗号など)は、量子コンピュータによって簡単に破られる可能性があります。
そこで、富士通が取り組んでいるのが「耐量子計算機暗号(PQC: Post-Quantum Cryptography)」です。
これは、量子コンピュータでも破れない暗号技術です。
富士通は、米国の標準化機関NIST(国立標準技術研究所)が進めるPQC標準化プロジェクトに参加しており、次世代暗号の開発に貢献しています。
さらに、富士通自身も量子コンピュータの研究を進めています。
2023年、富士通は64量子ビットの量子コンピュータの開発に成功したと発表しました。これは、まだ実用レベルには達していませんが、将来的には軍事シミュレーションや暗号解読に応用される可能性があります。
宇宙監視システムの強化
2030年、宇宙空間は新たな戦場となっています。
人工衛星は、GPS、通信、偵察、気象観測など、あらゆる軍事活動の基盤です。
しかし、この衛星が攻撃されるリスクが高まっています。
中国やロシアは、衛星攻撃兵器(ASAT)の開発を進めており、2021年にはロシアが実際に自国の衛星をミサイルで破壊する実験を行いました。
さらに、宇宙ゴミ(デブリ)も深刻な脅威です。現在、地球の周回軌道には数万個のデブリが漂っており、衛星と衝突する危険性があります。
富士通は、宇宙監視システムの開発を進めています。
このシステムは、地上レーダーと光学望遠鏡を組み合わせて、宇宙空間の物体を追跡・識別します。
さらに、AIによる軌道予測により、衝突リスクを事前に察知し、衛星の回避機動を支援します。
防衛省は、2023年に宇宙作戦群を新設し、宇宙監視能力の強化を図っています。富士通のシステムは、この宇宙作戦群の「目」となることが期待されています。
「ヒューマン・マシン・チーム」の実現
富士通が最終的に目指しているのは、「ヒューマン・マシン・チーム(HMT)」です。
これは、人間とAI、そしてロボット(無人機など)が一体となって作戦を遂行するという概念です。
例えば──。
- 無人偵察機(ドローン)が敵地を偵察
- AIがリアルタイムで画像を解析し、脅威を識別
- 人間のオペレーターが最終判断を下す
- 無人攻撃機が目標を攻撃(※ただし、発射指令は人間が出す)
このHMTの実現には、高速通信、AI処理能力、人間工学的インターフェースなど、多岐にわたる技術が必要です。
富士通は、そのすべてに関与しています。
富士通が直面する課題と限界
人材確保の困難さ
防衛事業の最大の課題は、人材確保です。
なぜなら──。
- 機密保持が厳しい:家族にも仕事内容を話せない
- 成果を公表できない:論文発表や学会参加が制限される
- 給与が民間IT企業に劣る:GAFAMなどと比べて魅力が薄い
特に、AI・サイバーセキュリティといった先端分野の人材は、世界中で奪い合いになっています。
富士通は、「国を守る仕事」という誇りをアピールすることで人材を集めようとしていますが、それだけでは不十分かもしれません。
機密保持とイノベーションのジレンマ
防衛事業は、機密保持が最優先です。
しかし、これがイノベーションの障害となることがあります。
なぜなら、最先端の技術開発には、オープンな情報共有や国際協力が不可欠だからです。
富士通は、このジレンマをどう乗り越えるのか?
一つの答えは、「デュアルユース技術」です。
つまり、民生用と軍事用の両方に使える技術を開発することで、オープンな研究と機密保持を両立させるのです。
スーパーコンピュータ「富岳」は、まさにその好例です。
5-3. 国際競争──米国・中国との技術格差
最後に、国際競争という現実があります。
米国は、国防予算が日本の10倍以上(約8000億ドル)であり、技術開発への投資も桁違いです。
中国も、急速に技術力を高めており、AI・量子技術では米国に迫る勢いです。
富士通が、この米中に伍して戦えるのか?
正直に言えば、単独では難しいでしょう。
だからこそ、国際協力が重要なのです。
日米同盟、Quad、NATOとの連携を通じて、技術力を結集することが、日本の生き残り戦略となります。
総括:富士通は日本の”見えない盾”であり続ける
最後に、全体を振り返りましょう。
- 富士通は、戦前から軍需産業に関与してきた歴史を持つ
- 戦後、自衛隊の発足とともに、通信機器・指揮統制システムを提供
- 現在は、C4ISR、ネットワーク、サイバーセキュリティ、AI・HPCの4領域で防衛を支えている
- スーパーコンピュータ「富岳」は、弾道ミサイルの軌道予測、電磁波シミュレーション、気象予測に活用
- 「富岳NEXT」は、エヌビディアとの協業により、AI性能を最大100倍に引き上げる
- 量子暗号通信は、「絶対に破られない」通信を実現し、自衛隊への実装が期待される
- AIによるサイバー防衛は、未知の攻撃にも対応でき、マルチAIエージェントによる協調防御が可能
- 防衛装備移転の解禁により、富士通のレーダーシステムやサイバー技術が輸出される可能性
- 日米同盟、Quad、NATOとの協力により、富士通の技術が国際的な防衛協力の基盤となる
- 防衛事業は、売上規模は小さいが利益率が高く、投資家にとって魅力的な「安定収益源」
- 2030年の未来では、AI統合指揮システム、量子暗号、宇宙監視、ヒューマン・マシン・チームが実現する
- ただし、人材確保、機密保持、国際競争という課題も存在する
富士通が守るもの──それは”日常”そのもの
最後に、僕たちが忘れてはいけないことがあります。
それは、富士通が守っているのは、僕たちの”日常”だということです。
朝、目覚まし時計が鳴る。
電車に乗って、会社や学校へ行く。
スマホで友達とメッセージを交わす。
夜、家族と夕食を囲む。
こんな当たり前の日常が、実は防衛によって支えられています。
もし、サイバー攻撃で電力網が麻痺したら?
もし、ミサイルが日本に飛んできたら?
もし、宇宙空間でGPS衛星が破壊されたら?
僕たちの日常は、一瞬で崩壊します。
富士通は、そうした“最悪のシナリオ”が起きないように、日夜、技術を磨き続けています。
それは、決して表に出ることのない、“見えない盾”です。
でも──。
その盾があるからこそ、僕たちは安心して眠ることができるのです。
最後に:あなたにできること
この記事を読んで、「防衛について考えるきっかけになった」と感じてくれたら、それが僕たちの願いです。
そして、もしあなたが──。
- 投資家なら:富士通の防衛事業を評価し、長期投資を検討してみてください
- 学生・エンジニアなら:富士通ディフェンスシステムエンジニアリング(FDSE)への就職を考えてみてください
- 一般市民なら:日本の防衛政策に関心を持ち、選挙で意思を示してください
日本の防衛は、誰かが守ってくれるものではありません。
僕たち一人ひとりが、何らかの形で関わっているものなのです。
【関連記事】




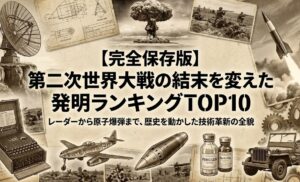




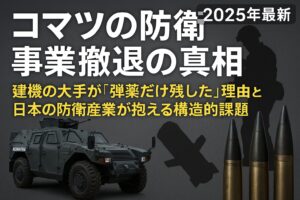
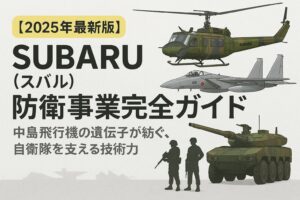

コメント