はじめに──なぜ今、この映画なのか
2025年12月5日。
日本のアニメーション史に、また新たな一本の作品が刻まれる。
映画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』──可愛らしい三頭身のキャラクターが、地獄のような戦場で懸命に生き抜こうとする姿を描いた、これまでにないタイプの戦争アニメーションだ。
「終戦80年」という節目の年。僕たちの祖父や曾祖父の世代が経験した戦争は、もはや”歴史”として教科書の中にしか存在しない。けれど、その戦場で何が起こり、若者たちが何を想い、どう生きたのか──それを知ることは、2025年を生きる僕たちにとって、決して”過去の話”では終わらない。
太平洋戦争における数多くの激戦地の中でも、ペリリュー島の戦いは「忘れられた戦い」と呼ばれてきた。1万人の日本兵が送り込まれ、生き残ったのはわずか34人。米軍も1600人以上が戦死し、海兵隊の死傷率は史上最高の約60%に達した。その凄惨さにもかかわらず、硫黄島や沖縄戦に比べて語られることが少なかった戦いだ。
しかし今、原作者・武田一義の漫画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』が劇場アニメーション化されることで、この”忘れられた戦い”に再び光が当たる。
この記事では、映画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』について、公開日やキャスト、あらすじといった基本情報はもちろん、原作の魅力、史実との関係、見どころまで、完全網羅でお届けする。映画を観に行く前に、ぜひこの記事で予習してほしい。
そして、この映画が問いかける「なぜ戦争を描くのか」「記憶をどう継承するのか」という問いについても、一緒に考えていきたい。
映画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』基本情報
公開日・配給
公開日: 2025年12月5日(金)
配給: 東映
終戦80年という歴史の節目に、年末の劇場を飾る本作。冬休みシーズンの公開ということもあり、多くの人々に届くことが期待されている。
スタッフ ーー 監督や脚本、主題歌など
原作: 武田一義「ペリリュー-楽園のゲルニカ-」(白泉社・ヤングアニマルコミックス)
監督: 久慈悟郎
脚本: 西村ジュンジ・武田一義(共同脚本)
制作: シンエイ動画 × 冨嶽
主題歌: 上白石萌音「奇跡のようなこと」
監督の久慈悟郎は、TVアニメ「妖怪ウォッチ」の演出や「魔都精兵のスレイブ」の監督を務めた実力派。劇場アニメーション映画の監督は本作が初めてとなる。
制作は、国民的アニメ「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」で知られるシンエイ動画と、「ドッグシグナル」などの話題作を手がけた気鋭の制作会社・冨嶽が共同で担当。安定した技術力と新しい感性が融合した作品となることが期待される。
そして注目すべきは、原作者の武田一義自身が西村ジュンジ(西村純二)と共同で脚本を執筆している点だ。原作者が映画化に深く関わることで、原作の魂をしっかりと映像に落とし込んだ作品になっている。
武田一義は脚本について、こうコメントしている。
「脚本の完成までに、本当に長い長い時間をかけました。『ペリリュー』原作漫画は外伝を除く本編だけでも11巻、これをどのように映画に落とし込むか。原作のすべてを入れようとして味気ないダイジェストのようになってしまうのは、原作者としても望まないことです。原作の前半だけを丁寧に作りあげる案もありましたが、やはり物語的に少し物足りない。そして何より原作だけでなく、この作品にはベースとなる史実――80年前の戦争があります。そこで生きた人々がいます。様々なことに思いを巡らせた映画版『ペリリュー』の脚本は、原作ファンの皆様にも自信を持ってお届けできるものになりました」
原作ファンも、そして初めてこの作品に触れる人も、満足できる内容になっているはずだ。
キャスト
田丸均(たまる ひとし): 板垣李光人
吉敷佳助(よしき けいすけ): 中村倫也
主人公・田丸均を演じるのは、2024年日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した板垣李光人。21歳の漫画家志望の日本兵という、難しい役どころに挑む。
板垣は本作に向けて、なんと実際にパラオ・ペリリュー島を訪れたという。現地の戦跡を自分の目で見て、肌で感じることで、役作りに活かしたのだ。
板垣はこうコメントしている。
「終戦80年という節目の年にこの作品に携わり、田丸均という役に命を吹き込むことができる運命には、非常に大きな意味と責任を感じています。田丸は、遺族に向けて戦場での仲間の最期を記す『功績係』を担っています。自分もいつ死ぬかわからない状況の中、ついさっきまで言葉を交わしていた仲間の最期を綴る残酷さ。そしてそんな残酷な現実を時には、愛する人を待つ家族のために美しく仕立てなければならない。そんな田丸なりの、激しくも繊細な葛藤や感情を大切に描いていきたいです」
そして、田丸の相棒となる頼れる上等兵・吉敷佳助を演じるのは中村倫也。実力派俳優が、極限状態の中で仲間を支え続ける吉敷の姿を熱演する。
この二人の演技にも大いに注目したい。
主題歌
主題歌を歌うのは、上白石萌音。曲名は「奇跡のようなこと」。
上白石萌音は、女優としても歌手としても活躍する才能あふれるアーティストだ。映画『舞妓はレディ』(2014)で初主演を飾り、第38回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。さらに映画『夜明けのすべて』(2024)では第48回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞している。
朝ドラ「カムカムエヴリバディ」での演技も記憶に新しい。そして歌手としてもデビュー10周年を迎え、その透明感のある歌声は多くのファンを魅了してきた。
戦場を生きた若者たちへの祈りを込めた、上白石萌音の歌声が、映画にどんな彩りを与えるのか。本予告映像でその一部を聴くことができるので、ぜひチェックしてほしい。
あらすじ──「功績係」が見た戦場
太平洋戦争末期の昭和19年(1944年)、南国の美しい島・ペリリュー島。
21歳の日本兵・田丸均(たまる ひとし)は、漫画家を夢見る若者だった。その絵の才能を買われ、田丸は「功績係」という特別な任務に就く。
「功績係」──それは、戦場で亡くなった仲間の最期の勇姿を、遺族に向けて書き記す仕事だ。
「お国のために勇敢に戦い、立派に散華されました」
田丸は、時に嘘を交えながら、仲間の死を美談に仕立て上げていく。遺族が少しでも慰められるように。愛する息子や夫が、意味のある死だったと思えるように。
しかし、現実の戦場は美談とは程遠い、地獄そのものだった。
昭和19年9月15日、米軍の猛攻が始まる。圧倒的な火力差。次々と倒れていく仲間たち。飢え、渇き、そして伝染病。いつ自分が死ぬかわからない恐怖の中で、田丸は正しいことが何なのかもわからなくなっていく。
そんな田丸を支えたのは、同期でありながら頼れる上等兵となった吉敷佳助の存在だった。
「生きて帰ろうな、田丸」
極限状態の中で、二人は互いに励まし合い、苦悩を分かち合いながら絆を深めていく。
しかし、戦いは終わらない。米軍1万人に対し、日本軍は4万人。圧倒的劣勢の中で、日本軍は「玉砕」ではなく「持久戦」を命じられる。一日でも長く米軍を足止めすること──それが、彼らに課せられた使命だった。
約2か月半にわたる死闘。その果てに、田丸と吉敷は何を見るのか。
これは、戦争の狂気の中で懸命に生きた若者たちの、友情の物語だ。
原作漫画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』について
連載概要
原作となる漫画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』は、白泉社の「ヤングアニマル」誌で2016年から2021年まで連載された。全11巻(外伝を除く)。
連載終了と同時にアニメ化が発表されていたが、4年の歳月を経て、終戦80年という最高のタイミングで劇場アニメーションとして結実した。
現在は「ペリリュー外伝」が不定期で連載されており、本編では描かれなかったエピソードや、他の登場人物の視点が描かれている。
受賞歴
2017年(平成29年)、第46回日本漫画家協会賞で優秀賞を受賞。
この賞は、ちばてつや(『あしたのジョー』『あした陸上部』)や高橋留美子(『うる星やつら』『らんま1/2』『犬夜叉』)といった日本を代表する漫画家たちが選考委員を務める権威ある賞だ。
戦争漫画という重いテーマを、親しみやすいキャラクターで描きながらも、戦場のリアリティと凄惨さを妥協なく表現した『ペリリュー』の価値が、業界のトップクリエイターたちから認められた証だ。
実際、ちばてつや、花沢健吾、重松清、有川ひろ、原泰久(『キングダム』)、里中満智子、三浦建太郎(『ベルセルク』)、奥浩哉(『GANTZ』)、吉田裕など、各界のクリエイター・識者から絶賛のコメントが寄せられている。
「戦争マンガの新たなる金字塔」──そう呼ぶにふさわしい作品だ。
原作の特徴──可愛い絵柄×凄惨な戦場
原作の最大の特徴は、そのギャップにある。
登場するキャラクターは、親しみやすい三頭身。丸っこくて可愛らしい絵柄だ。一見すると、とても戦争を描いた作品には見えない。
しかし、その可愛いキャラクターたちが体験するのは、想像を絶する戦場の現実だ。
砲弾が飛び交い、銃弾が身体を貫き、爆風で仲間が吹き飛ばされる。飢えで衰弱し、マラリアで倒れ、そして死んでいく。原作者の武田一義は、「兵器が人体を破壊するさまをきちんと描いてほしい」と映画化の際に要望したという。それほどまでに、戦争のリアリティにこだわっているのだ。
なぜ、可愛い絵柄で戦争を描くのか。
それは、「戦争が日常だった」ということを表現するためだ。戦場に送り込まれたのは、僕たちと同じような、ごく普通の若者たちだった。漫画家になりたいと夢を抱いていた田丸のような、どこにでもいる青年だった。
その普通の若者たちが、理不尽な暴力と死に直面する。「戦争」という狂気が、日常を侵食していく様子を、この絵柄だからこそ描けるのだ。
そして、可愛い絵柄だからこそ、多くの人が手に取りやすい。戦争という重いテーマに興味がなかった人も、この絵柄なら入りやすい。実際、アニメやゲームをきっかけに歴史に興味を持つ若い世代にとって、この作品は最高の入口になるはずだ。
史実との関係──ペリリュー島の戦いとは
映画を観る前に、史実としての「ペリリュー島の戦い」について、基本的なことを押さえておこう。
ペリリュー島の位置と戦略的重要性
ペリリュー島は、パラオ共和国を構成する島の一つだ。現在のパラオは、美しいサンゴ礁と青い海に囲まれた南国のリゾート地として知られている。
太平洋戦争中、パラオは日本の委任統治領だった。ペリリュー島には日本軍の飛行場があり、フィリピンとマリアナ諸島を結ぶ戦略的要衝だったのだ。
1944年(昭和19年)、マリアナ諸島のサイパン、グアム、テニアンが次々と陥落し、米軍はフィリピン奪還を目指していた。その過程で、ペリリュー島の飛行場を無力化し、米軍の拠点とすることが目的となった。
戦いの経過
開戦: 1944年(昭和19年)9月15日
終結: 1944年(昭和19年)11月27日(公式には。実際には12月以降も散発的戦闘が続いた)
日本軍兵力: 約1万人
米軍兵力: 約4万人
日本軍生存者: わずか34人(捕虜として生き残った者を除く)
米軍死者: 1,600人以上
米海兵隊死傷率: 約60%(史上最高)
米軍は、「3日で制圧できる」と見込んでいた。しかし、戦いは約2か月半にも及んだ。
「持久戦」への方針転換
ペリリュー島の戦いは、日本軍の戦術が大きく変わった転換点でもあった。
それまでの日本軍は、「バンザイ突撃」と呼ばれる一斉突撃による玉砕戦術をとっていた。敵陣に突入し、全員が自決覚悟で戦う──そうすることで、武士道精神を示し、敵に恐怖を与えようとしたのだ。
しかし、圧倒的な火力を持つ米軍に対して、この戦術は無意味だった。日本兵は次々と撃ち倒され、戦略的な意味を成さない「無駄死に」が続いたのだ。
ペリリュー島の守備隊長・中川州男(なかがわ くにお)大佐は、この方針を転換した。
「玉砕は禁ずる。一日でも長く米軍を足止めせよ」
島の地形を活かし、洞窟や地下陣地に立てこもる。米軍の上陸を一度に阻止するのではなく、徐々に消耗させる持久戦に持ち込んだのだ。
この戦術は、米軍に予想外の損害を与えた。ペリリュー島での経験は、その後の硫黄島の戦いにも引き継がれた。硫黄島で栗林忠道中将がとった戦術も、ペリリュー島での教訓に基づいている。
(詳しくは、当ブログの【完全解説】硫黄島の戦いをわかりやすくをご覧いただきたい)
「忘れられた戦い」
1万人の日本兵が送り込まれ、生き残ったのはわずか34人。米軍も海兵隊史上最高の死傷率を記録した。その凄惨さにもかかわらず、ペリリュー島の戦いは長らく「忘れられた戦い」と呼ばれてきた。
なぜか。
硫黄島や沖縄戦といった、より大規模な戦いに埋もれてしまったからだ。そして、途中で米軍がフィリピンを奪還してしまい、ペリリュー島を確保する戦略的意義が失われたにもかかわらず、戦いが続けられたという「無意味さ」も影響しているだろう。
しかし、その「無意味さ」こそが、戦争の本質を象徴しているのかもしれない。
戦争によって、人々は狂気に駆り立てられ、「無意味な死」へと追いやられる。戦争を美化することはできない。「お国のために立派に散華した」という美談では、済まされない現実がそこにはあったのだ。
そして今なお、ペリリュー島には千を超える日本兵の遺骨が収容されず、島に眠っている。
(ペリリュー島の戦いについて、さらに詳しく知りたい方は、当ブログのペリリュー島の戦い完全ガイドを参照してほしい)
守備隊長・中川州男大佐と水戸第二連隊
ペリリュー島の守備を担ったのは、陸軍歩兵第2連隊を中核とする部隊だった。
歩兵第2連隊は、茨城県水戸市の部隊であることから「水戸第二連隊」と呼ばれた。その9割が、ペリリュー島で命を落としている。
守備隊長の中川州男大佐は、最後まで持久戦を貫いた。そして、もはや戦えなくなったとき、部下を解散させ、自ら自決した。
中川大佐の戦いぶりは、敵である米軍からも称賛された。米軍の公式戦史には「日本軍の抵抗は、太平洋戦争で最も激烈だった」と記されている。
武田一義原作者は、この映画化にあたって、中川大佐の出身地・水戸の高校で講演を行っている。2025年8月6日、茨城県立水戸第一高等学校・附属中学校での「パブリックリーダースクール2025」という講演会で、生徒たちに作品に込めた思いを語ったのだ。
戦争を経験した世代がいなくなりつつある今、どう記憶を継承していくか。それは、僕たち全員が向き合うべき課題なのだ。
「功績係」とは何か──記憶を残す仕事
映画の主人公・田丸均は、「功績係」という任務に就いている。
これは、いったいどんな仕事なのだろうか。
遺族への手紙を書く係
「功績係」とは、戦死した兵士の最期の様子を記録し、遺族に伝える仕事だ。
戦場で仲間が倒れたとき、その死をただ記録するだけでは、遺族は納得できない。愛する息子や夫が、どんな最期だったのか。苦しまなかったか。立派に戦ったのか。そういったことを知りたいのだ。
だから、功績係は仲間の死を「美談」に仕立て上げる。
「敵陣に突入し、勇敢に戦い、名誉の戦死を遂げました」
「最期まで仲間を励まし、笑顔で散華されました」
たとえ実際には、砲弾の破片で即死したとしても。飢えとマラリアで衰弱して死んだとしても。遺族のために、少しでも慰めになる言葉を紡ぐのだ。
「嘘」と「優しさ」のはざまで
しかし、これは「嘘」だ。
戦場の現実は、美談とは程遠い。死は突然訪れ、意味もなく、理不尽に奪われる。
田丸は、その「嘘」と向き合い続ける。仲間の死を美談に仕立て上げることに、罪悪感を抱きながらも、それが遺族への最後の優しさだと信じて。
これは、映画の大きなテーマの一つだ。
「記憶をどう残すか」「どう語り継ぐか」
戦争を美化することはできない。しかし、遺族の悲しみを無視することもできない。そのはざまで、田丸は苦悩する。
史実における「戦死報告」の仕組み
史実においても、戦死した兵士の情報は部隊から遺族に伝えられた。
「戦闘詳報」と呼ばれる戦闘の記録が作成され、戦死者の名前や死亡状況がまとめられた。そして、部隊から遺族に「戦死公報」という通知が届くのだ。
ただし、その内容は必ずしも詳細ではなかった。激しい戦闘の中で、誰がいつどこで死んだのか、正確に把握することは困難だった。また、遺体を収容できないケースも多かった。
だからこそ、田丸のような「功績係」が、遺族への手紙という形で、より人間的な記録を残そうとしたのかもしれない。
それが、どれほど重い仕事だったか。想像するだけで胸が痛む。
映画の見どころ
①三頭身キャラクターが描く戦場のリアリティ
原作の最大の特徴である「可愛い絵柄×凄惨な戦場」のギャップが、アニメーションでどう表現されるのか。
シンエイ動画×冨嶽という制作体制は、このバランスを絶妙に表現できるはずだ。シンエイ動画は『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』といった親しみやすいキャラクターを長年描いてきた実績がある。その技術と、冨嶽の新しい感性が融合することで、これまでにない戦争アニメーションが生まれる。
場面写真を見ると、可愛らしいキャラクターたちが、銃を構え、洞窟に立てこもり、砲撃に晒される姿が描かれている。そのギャップこそが、「戦争は誰にでも起こりうる」というメッセージを強烈に伝えてくれるだろう。
②田丸と吉敷の友情
極限状態の戦場で、互いに支え合う田丸と吉敷の友情が、物語の核になる。
板垣李光人と中村倫也という実力派キャストが、どんな演技を見せてくれるのか。ティザービジュアルや予告映像を見る限り、二人の熱演が期待できる。
「生きて帰ろうな」
そんなシンプルな約束が、戦場ではどれほど重い意味を持つのか。僕たちは映画館のスクリーンで、その答えを目撃することになる。
③上白石萌音の主題歌「奇跡のようなこと」
戦場を生きた若者たちへの祈りを込めた、上白石萌音の歌声。
「奇跡のようなこと」というタイトルからも、生き延びることの難しさ、そしてそれでも生きようとすることの尊さが伝わってくる。
本予告映像で、その一部を聴くことができる。透明感のある歌声が、映画の世界観を優しく包み込んでくれるはずだ。
④原作者・武田一義が込めた「記憶の継承」への想い
武田一義は、映画化にあたって何度もこう語っている。
「戦争を経験したことのある人々が絶とうとしている今、戦争による『死』を美しく意味付けることに何の意味があるだろうか。今こそ『無残な現実』を継承すべき時なのではないか」
戦争を美化しない。しかし、戦場を生きた人々の記憶を忘れない。
その両立こそが、この作品のテーマであり、僕たちが受け取るべきメッセージなのだ。
映画を観終わった後、僕たちは何を感じ、何を考えるだろうか。それこそが、この映画の本当の価値なのかもしれない。
⑤終戦80年という節目
2025年は、終戦から80年という節目の年だ。
戦争を経験した世代は、もう90歳を超えている。戦争の記憶を直接語れる人は、もうほとんどいない。
だからこそ、今、この映画が公開されることに意味がある。
僕たちの世代、そしてこれから生まれてくる世代に、戦争の記憶を継承するために。二度と同じ過ちを繰り返さないために。
この映画は、歴史の証人となる作品なのだ。
パラオ・ペリリュー島への聖地巡礼
映画を観た後、実際にペリリュー島を訪れてみたい──そう思う人もいるかもしれない。
パラオは、現在では美しいサンゴ礁に囲まれた観光地として知られている。日本からは、直行便で約4時間半。比較的アクセスしやすい南国リゾートだ。
ペリリュー島へは、パラオの中心地・コロールからボートで約1時間。日帰りツアーや宿泊ツアーが催行されている。
島には、今も戦跡が残されている。
- 洞窟陣地
- 日本軍の遺構
- 米軍の戦車の残骸
- 慰霊碑
板垣李光人が訪れた際にも感じたように、教科書やテレビでは伝わらない「何か」が、そこには確かにある。
80年前、この島で何が起こったのか。若者たちがどう生き、どう死んだのか。その痕跡を、自分の目で見ることができる。
ただし、ペリリュー島は観光地であると同時に、慰霊の地でもある。訪れる際は、敬意を持ったマナーを守ることが大切だ。
- 戦跡を荒らさない
- 遺構に落書きをしない
- 大声で騒がない
- 写真撮影は慎重に
そして、できればガイド付きのツアーに参加することをおすすめする。現地のガイドから、戦いの経緯や、島の人々が今どう暮らしているかを聞くことで、より深い理解が得られるはずだ。
映画を観て、さらに史実に興味を持った人は、ぜひペリリュー島を訪れてみてほしい。
原作マンガの読み方ガイド
映画を観て、「原作も読んでみたい!」と思った人のために、原作マンガの情報もまとめておこう。
連載情報
- 掲載誌: ヤングアニマル(白泉社)
- 連載期間: 2016年〜2021年
- 単行本: 全11巻(本編)
- 外伝: 「ペリリュー外伝」として不定期連載中
どこで読めるか
原作マンガは、以下の方法で読むことができる。
- 紙の単行本: 全国の書店、Amazonなどで購入可能
- 電子書籍: Kindle、楽天Kobo、Apple Booksなどで配信中
- レンタル: 一部のレンタルコミックサービスで借りられる
まずは第1巻を読んでみて、世界観に浸ってみるのがおすすめだ。
映画はどこまで描かれるか
武田一義原作者のコメントによれば、映画は原作11巻全てをダイジェストにするのではなく、一部を丁寧に描く形になっているという。
「原作の前半だけを丁寧に作りあげる案もありましたが、やはり物語的に少し物足りない」とのことなので、おそらく前半〜中盤がメインになると予想される。
ただし、原作者自身が脚本に関わっているので、映画だけで一つの完結した物語として楽しめる内容になっているはずだ。
映画を観た後で原作を読めば、「ああ、あのシーンはここから来ていたのか」という発見があるだろう。逆に、原作を読んでから映画を観れば、「このシーンをこう表現したのか!」という驚きがあるはずだ。
どちらから入っても楽しめる──それが、この作品の魅力だ。
『ペリリュー』と他の戦争アニメ映画
戦争を描いたアニメーション映画は、日本には数多く存在する。
『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』を観る前、あるいは観た後に、こうした作品も合わせて鑑賞すると、より深く戦争について考えることができるだろう。
『火垂るの墓』(1988年)
高畑勲監督、スタジオジブリ制作。野坂昭如の小説を原作とした不朽の名作。
神戸大空襲で親を失った兄妹が、戦争末期の日本でどう生き、どう死んだのかを描く。戦争が民間人にもたらす悲劇を、容赦なく描き出した作品だ。
『ペリリュー』が「戦場の兵士」を描くのに対し、『火垂るの墓』は「銃後の民間人」を描く。両方を観ることで、戦争の全体像が見えてくる。
『この世界の片隅に』(2016年)
片渕須直監督、こうの史代の漫画を原作とした作品。
広島県呉市に嫁いだ主人公・すずが、戦時下の日常をどう生きたかを描く。戦争の中にも、日々の暮らしがあり、笑いがあり、愛があった。その「普通」の尊さを教えてくれる作品だ。
『ペリリュー』と同じく、可愛らしい絵柄で戦争を描いている点も共通している。
『はだしのゲン』(1983年)
中沢啓治の漫画を原作としたアニメーション映画。
広島への原爆投下を生き延びた少年・ゲンの物語。原爆の惨状を、アニメーションでありながら妥協なく描いた作品だ。
戦争の「終わり方」を考える上で、避けては通れない作品だろう。
『風立ちぬ』(2013年)
宮崎駿監督、スタジオジブリ制作。
ゼロ戦の設計者・堀越二郎をモデルとした物語。美しい飛行機を作りたいという夢と、その飛行機が戦争に使われるという現実のはざまで苦悩する姿を描く。
兵器を作る側の視点を描いた、稀有な作品だ。
『ペリリュー』の独自性
こうした先行作品と比較したとき、『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』の独自性は何だろうか。
それは、「記憶をどう残すか」というメタ的なテーマにあると思う。
『火垂るの墓』や『この世界の片隅に』が「体験」を描くのに対し、『ペリリュー』は「記録」を描く。主人公の田丸は、功績係として仲間の死を書き記す。つまり、「記憶を残す人」の視点から、戦争を描いているのだ。
これは、2025年という「戦争の記憶が失われつつある時代」だからこそ、重要なテーマだ。
戦争を経験した世代がいなくなったとき、僕たちはどうやって記憶を継承するのか。映画を観ることも、漫画を読むことも、一つの「記録」だ。そして、その記録をもとに、次の世代に語り継いでいく──それが、僕たちの役割なのかもしれない。
なぜ今、『ペリリュー』なのか──終戦80年の意味
2025年は、終戦から80年という節目の年だ。
厚生労働省は、遺骨収集事業を推進している。パラオ・ペリリュー島にも、今なお千を超える日本兵の遺骨が眠っている。
映画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』の製作委員会は、厚生労働省や自治体とも連携しているという。単なるエンターテインメント作品にとどまらず、平和教育や遺骨収集といった社会的な意義も持つ映画なのだ。
戦争の記憶が失われていく
戦争を直接経験した世代は、もう90歳を超えている。あと10年もすれば、戦争を語れる人はほとんどいなくなってしまう。
「戦争の悲惨さを語り継ぐ」──それは、僕たちの世代の責任だ。
しかし、どうやって語り継ぐのか。教科書を読むだけでは、実感が湧かない。映像作品、漫画、小説──様々な形で、戦争の記憶を伝えていく必要がある。
『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』は、まさにそうした「記憶の継承」の一翼を担う作品だ。
アニメやゲームから歴史に興味を持つ若い世代にとって、この映画は最高の入口になるだろう。可愛いキャラクターに惹かれて映画館に足を運んだ人が、戦争の現実に向き合い、考えるきっかけになる。
それこそが、この映画の存在意義なのだ。
僕たちにできること
映画を観た後、僕たちは何をすべきだろうか。
まず、戦争について考えることだ。なぜ戦争が起こったのか。どうすれば防げたのか。今の世界にも、同じような火種はないか。
そして、語り継ぐことだ。友人や家族と、この映画について話す。SNSで感想をシェアする。原作マンガを読み、さらに史実を調べる。
一人ひとりが、小さな「記録者」になることで、戦争の記憶は次の世代に継承されていく。
田丸が功績係として仲間の死を記録したように、僕たちも映画の記憶を記録し、語り継いでいこう。
まとめ──12月5日、劇場で会おう
2025年12月5日。
映画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』が、全国の劇場で公開される。
可愛らしい三頭身のキャラクターが、地獄のような戦場で懸命に生きる姿。功績係として仲間の死を記録し続ける田丸と、その相棒・吉敷の友情。そして、戦争の狂気と、人間の尊厳。
この映画は、単なるエンターテインメントではない。終戦80年という節目に、僕たちに問いかける作品だ。
「戦争とは何か」
「記憶をどう継承するか」
「二度と繰り返さないために、何ができるか」
原作者・武田一義、監督・久慈悟郎、そしてシンエイ動画×冨嶽のスタッフたちが、長い時間をかけて作り上げた渾身の一作。
板垣李光人と中村倫也の熱演。上白石萌音の透明感ある歌声。
すべてが、この映画を特別なものにしている。
僕は、公開日を心待ちにしている。
そして、映画館を出た後、何を感じるだろうか。何を考えるだろうか。それが楽しみでもあり、怖くもある。
戦争を描いた作品は、観る人の心に重い何かを残す。でも、その「重さ」こそが、大切なのだと思う。
2025年12月5日。
劇場で、この歴史的な一作を目撃しよう。
ペリリュー島で散った1万人の兵士たちへの鎮魂として。そして、未来への教訓として。
映画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』は、僕たちを待っている。
公式サイト: https://peleliu-movie.jp/
公開日: 2025年12月5日(金)全国ロードショー
配給: 東映
関連記事
本作の舞台となったペリリュー島の戦いについて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧いただきたい。
- ペリリュー島の戦い完全ガイド|73日間の死闘と今に残る教訓【わかりやすく解説】
- 硫黄島の戦いをわかりやすく – 栗林中将が米軍を震撼させた36日間の死闘
- 沖縄戦をわかりやすく解説|日本軍最後の大規模地上戦の全貌
- 太平洋戦争・激戦地ランキングTOP15
そして、戦争を描いたアニメーション作品に興味がある方は、『火垂るの墓』『この世界の片隅に』なども合わせて鑑賞することをおすすめする。
戦争の記憶を、共に語り継いでいこう。
あとがき──書き手としての想い
この記事を書きながら、僕は何度も考えた。
戦争を「エンタメ」として消費していいのか、と。
『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』は、確かに「映画」だ。娯楽作品だ。でも、その背景には、実際に80年前の戦場で死んでいった若者たちがいる。彼らの死を、僕たちは「面白かった」で済ませていいのか。
でも、原作者の武田一義は、あえて「可愛い絵柄」で描いた。それは、より多くの人に届けるためだ。戦争に興味がない人にも、手に取ってもらうためだ。
そして、映画という形で、さらに多くの人に届けようとしている。
それは、決して「エンタメ化」ではない。「記憶の継承」なのだ。
僕たちミリタリーファンは、時に「戦争を美化しているのではないか」と批判されることがある。兵器や戦術に興味を持つことが、戦争を肯定することだと誤解されるのだ。
でも、違う。
僕たちは、戦争を美化したいのではない。先人たちがどう戦い、何を想い、どう生きたのかを知りたいのだ。彼らの技術や精神力を尊敬したいのだ。そして、二度と同じ過ちを繰り返さないために、歴史から学びたいのだ。
大日本帝国は敗北した。それは悔しい。でも、敗北したからこそ、僕たちは「なぜ負けたのか」を冷静に分析できる。そして、「どうすれば防げたのか」を考えることができる。
映画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』は、そうした視点を持った作品だと思う。
戦争を美化しない。しかし、戦場を生きた人々を尊敬する。その両立こそが、この作品の真髄なのだ。
僕は、この映画を心から応援している。
そして、一人でも多くの人に観てほしいと思っている。
戦争を知らない世代だからこそ、この映画を観るべきだ。
アニメやゲームから歴史に興味を持った人だからこそ、この映画から何かを学べるはずだ。
2025年12月5日。
劇場で、皆さんと共に、この歴史的な一作を目撃できることを楽しみにしている。





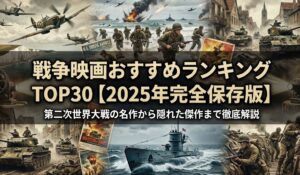
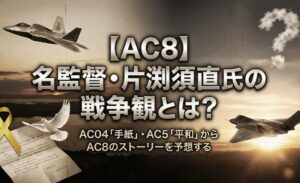

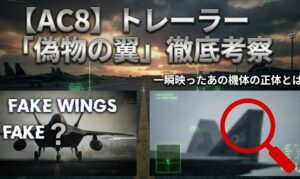


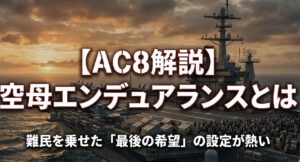

コメント