1942年8月24日、夜明け前。
南太平洋ソロモン諸島の北、濃紺の海に浮かぶ日本海軍の空母龍驤(りゅうじょう)は、静かに艦載機の発進準備を進めていた。目標はガダルカナル島の飛行場。そこには、わずか半月前に米軍が奪取したヘンダーソン飛行場がある。
龍驤の艦上には零戦と九九式艦爆が並び、若いパイロットたちが整列していた。誰もが緊張の面持ちだ。だが、彼らはまだ知らなかった。
この出撃が、空母龍驤にとって”最後の攻撃”になることを。
そして同じ頃、はるか南東の海域では、アメリカ海軍の空母エンタープライズとサラトガが、日本艦隊の接近を察知し、索敵機を放っていた。
こうして始まったのが、第二次ソロモン海戦──太平洋戦争における空母同士の激突としては、珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦に次ぐ3度目の対決であり、ガダルカナル島を巡る消耗戦の”第二幕”である。
この海戦は、日本にとってミッドウェーの敗北後、初めての本格的な空母戦だった。そして結果は──空母龍驤を失い、戦略的敗北に終わる。
なぜ日本は再び敗れたのか?
龍驤は本当に”おとり”だったのか?
そしてこの海戦が、太平洋戦争全体にどんな影響を与えたのか?
この記事では、第二次ソロモン海戦の全貌を、戦術・人物・艦艇・その後の影響まで、わかりやすく、ドラマチックに、そして敬意を込めて徹底解説します。
2. 第二次ソロモン海戦の基本情報
まずは、この海戦の”基本データ”を整理しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦闘名称 | 第二次ソロモン海戦(Battle of the Eastern Solomons /東方海戦) |
| 日時 | 1942年(昭和17年)8月23日〜25日 |
| 場所 | ソロモン諸島北方海域(ガダルカナル島の北約200〜300km) |
| 交戦国 | 大日本帝国 vs アメリカ合衆国 |
| 作戦目的(日本) | ガダルカナル島への陸軍部隊輸送と、ヘンダーソン飛行場の制圧 |
| 作戦目的(米国) | 日本軍の増援阻止と、ガダルカナル島防衛 |
| 結果 | アメリカの戦術的・戦略的勝利 |
| 主な損害(日本) | 空母龍驤沈没、駆逐艦睦月沈没、航空機約90機喪失 |
| 主な損害(米国) | 空母エンタープライズ中破、駆逐艦1隻沈没、航空機約20機喪失 |
この海戦は、日本側では「第二次ソロモン海戦」、米側では「東部ソロモン海戦(Battle of the Eastern Solomons)」と呼ばれています。
また、戦闘の焦点は空母戦ですが、実際には輸送船団の護衛・攻撃や、ガダルカナル島への航空攻撃も絡んだ”複合的な作戦”でした。
3. なぜこの海戦が起きたのか?──第一次ソロモン海戦からガダルカナル攻防へ
ガダルカナル島──太平洋の”喉元”
第二次ソロモン海戦を理解するには、なぜ日米両軍がガダルカナル島に固執したのかを知る必要があります。
ガダルカナル島は、ソロモン諸島南部に位置する、ジャングルに覆われた熱帯の島です。1942年初頭まで、ここは戦略的にほとんど注目されていませんでした。
しかし、日本軍が飛行場建設を開始したことで、状況は一変します。
もしこの飛行場が完成すれば、日本軍機はオーストラリアへの補給路を脅かし、連合軍の反攻拠点を無力化できる。逆に米軍がここを奪えば、日本の南方防衛線に楔を打ち込むことができる。
つまり、ガダルカナル島は”太平洋の喉元”だったのです。
1942年8月7日──米軍の奇襲上陸
そして1942年8月7日、アメリカ海兵隊がガダルカナル島に奇襲上陸。日本軍の設営隊を蹴散らし、ほぼ完成していた飛行場を占領します。この飛行場はヘンダーソン飛行場と命名されました。
日本海軍はこれに激怒。即座に反撃を開始します。
第一次ソロモン海戦──夜戦の完全勝利
8月9日未明、日本海軍の三川軍一中将率いる第八艦隊(重巡洋艦5隻を中心とした艦隊)が、ガダルカナル島沖で米豪海軍の巡洋艦部隊を奇襲。
わずか30分で連合軍の重巡4隻を撃沈するという、圧倒的な夜戦勝利を収めました。これが第一次ソロモン海戦です。
しかし、三川艦隊は米空母部隊を恐れて反転撤退。ガダルカナル島の米軍上陸部隊そのものを叩くことはできませんでした。
悔しさの残る”戦術的勝利”
第一次ソロモン海戦は、日本海軍の夜戦技術の頂点を示す戦いでした。しかし、戦略的には何も変わらなかった。ヘンダーソン飛行場は米軍の手に残り、そこから飛び立つ米軍機が、日本の補給路を脅かし始めたのです。
そしてこの状況を打開すべく、日本軍は陸軍一木支隊の逆上陸作戦と、それを支援する海軍機動部隊の出撃を決定します。
これが、第二次ソロモン海戦の直接的なきっかけでした。
4. 両軍の戦力配置と作戦意図
日本海軍の戦力──3つの艦隊で挟撃を狙う
第二次ソロモン海戦における日本海軍の編成は、近藤信竹中将が率いる連合艦隊の第二艦隊・第三艦隊を中心としたものでした。
【前進部隊(近藤信竹中将)】
-戦艦:比叡、霧島
- 重巡洋艦:愛宕、高雄、妙高、摩耶ほか
- 空母:翔鶴、瑞鶴(主力機動部隊)
- 軽空母:龍驤(別働隊)
【作戦の狙い】
日本軍の作戦は、以下の3段階で構成されていました。
- 龍驤部隊がヘンダーソン飛行場を空襲し、米軍機を地上で撃破
- 輸送船団(一木支隊を乗せた輸送船)がガダルカナル島に接近
- 米空母部隊が出現したら、翔鶴・瑞鶴の主力機動部隊で迎撃
つまり、龍驤は”おとり”として米空母をおびき出す役割を担っていたとされています。
ただし、この”おとり説”には異論もあります。後ほど詳しく触れますが、龍驤の艦長や乗組員たちは、自分たちが囮だとは知らされていなかった可能性が高いのです。
アメリカ海軍の戦力──フランク・フレッチャー中将の慎重な戦い
一方、アメリカ海軍はフランク・ジャック・フレッチャー中将が指揮を執りました。
【米空母部隊】
- 空母:サラトガ(CV-3)
- 空母:エンタープライズ(CV-6)
- 空母:ワスプ(CV-7、ただし途中で燃料補給のため離脱)
- 戦艦:ノースカロライナ
- 重巡洋艦・駆逐艦多数
フレッチャーは、珊瑚海海戦とミッドウェー海戦の両方を経験した”空母戦のベテラン”です。
彼の作戦方針は明確でした。
「日本の輸送船団を叩き、ガダルカナル島への増援を阻止する。ただし空母を無理に前に出さない」
ミッドウェーで日本が空母4隻を失ったことを知っていたフレッチャーは、慎重に索敵を重ね、日本艦隊の位置を正確に把握することに努めました。
5. 8月24日〜25日、運命の48時間──戦闘経過を完全再現
それでは、第二次ソロモン海戦の実際の戦闘経過を、時系列で追っていきましょう。
8月23日夜──索敵と接敵
日本艦隊とアメリカ艦隊は、互いに相手の位置を探りながら、ソロモン諸島北方海域で対峙していました。
日本側は、まず龍驤部隊(空母龍驤、重巡利根、駆逐艦2隻)を前方に進出させ、ヘンダーソン飛行場への攻撃準備を開始します。
一方、翔鶴・瑞鶴を擁する主力部隊は、やや後方に位置し、米空母の出現を待ち構えていました。
8月24日 午前──龍驤、ガダルカナルを空襲
24日早朝、龍驤は零戦と九九式艦爆を発進させ、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場を攻撃します。
この攻撃自体は一定の戦果を上げましたが、ヘンダーソン飛行場を完全に無力化することはできませんでした。むしろ、この攻撃が米軍に龍驤の位置を教える結果となります。
8月24日 午後──米軍、龍驤を発見
午後、アメリカ軍の索敵機が龍驤を発見。
フレッチャーは即座に攻撃隊を発進させました。エンタープライズとサラトガから、合計約50機のドーントレス急降下爆撃機とアベンジャー雷撃機が発艦します。
8月24日 16:00頃──龍驤への集中攻撃

午後4時頃、米軍機が龍驤を捕捉。
小型空母である龍驤は、必死の回避運動を試みますが、急降下爆撃機の爆弾3〜4発が命中。さらに魚雷1本も被弾し、艦は大破、航行不能に陥ります。
龍驤の乗組員たちは懸命に消火・救難活動を行いましたが、浸水と火災は制御不能となり、同日夜、ついに沈没。艦長以下約600名が戦死しました。
8月24日 夕刻──翔鶴・瑞鶴、反撃開始

日本の主力機動部隊(翔鶴・瑞鶴)も、ついに米空母を発見。
艦攻・艦爆・零戦からなる攻撃隊を発進させます。日本機約40機が、米空母部隊に殺到しました。
標的となったのは空母エンタープライズ。
日本の急降下爆撃機隊は、激しい対空砲火と米軍戦闘機の迎撃をかいくぐり、エンタープライズに爆弾3発を命中させます。
エンタープライズは飛行甲板が大破し、一時は航空機の発着が不可能になりました。しかし、アメリカ海軍の優れたダメージコントロール(損傷管理)技術により、わずか数時間で応急修理を完了。翌日には艦載機の収容が可能になります。
8月25日──輸送船団への攻撃と戦闘終結
翌25日、ヘンダーソン飛行場から飛び立った米軍機が、日本の輸送船団を発見・攻撃。
輸送船金龍丸が大破し、陸軍部隊と物資の多くが失われました。また、駆逐艦睦月も空襲で沈没します。
この時点で、日本軍の作戦目的──ガダルカナル島への増援輸送──は完全に失敗。連合艦隊司令部は作戦中止を決定し、艦隊は撤退しました。
6. 空母龍驤の最期──「おとり」として散った小型空母の真実
第二次ソロモン海戦で最も悲劇的な存在が、軽空母龍驤です。
龍驤とはどんな空母だったのか?
龍驤は、1933年に竣工した小型空母で、基準排水量は約8,000トン。翔鶴・瑞鶴(約26,000トン)と比べると、わずか3分の1以下の大きさでした。
しかし、小型ながら艦載機は約30機を搭載でき、機動性も高かったため、哨戒や偵察、小規模な攻撃任務には重宝されていました。
第二次ソロモン海戦では、この龍驤が単独で前方に進出し、ヘンダーソン飛行場を攻撃する役割を担いました。
龍驤は本当に”おとり”だったのか?
一般に、第二次ソロモン海戦では「龍驤は囮として使われた」と説明されます。
つまり、米空母部隊を龍驤におびき寄せ、その間に翔鶴・瑞鶴が米空母を叩く──という作戦だったと。
しかし、これには疑問も残ります。
- 龍驤の乗組員や艦長は、自分たちが囮だと知らされていたのか?
- 本当に「捨て駒」として送り出されたのか?
実際には、龍驤の任務は「ヘンダーソン飛行場の制圧」であり、単に”小型空母だから前に出された”だけだった可能性もあります。
いずれにせよ、結果として龍驤は米軍機の集中攻撃を受け、沈没しました。
艦長・加藤唯雄大佐の最期
龍驤の艦長は加藤唯雄(かとうただお)大佐。彼は艦と運命を共にし、戦死しました。
生存者の証言によれば、加藤艦長は最後まで艦橋に立ち、「総員退艦」を命じた後も艦に残り続けたといいます。
約600名の乗組員のうち、約半数が救助されましたが、残りは龍驤とともに海に沈みました。
龍驤の沈没は、日本海軍にとってミッドウェー以来の空母喪失であり、大きな痛手でした。
7. 戦果と損害──誰が勝ったのか?
日本側の損害
| 艦種 | 艦名 | 状態 |
|---|---|---|
| 軽空母 | 龍驤 | 沈没 |
| 駆逐艦 | 睦月 | 沈没 |
| 水上機母艦 | 千歳 | 小破 |
| 輸送船 | 金龍丸 | 大破(後に沈没) |
| 航空機 | 約90機喪失 |
特に痛かったのは、熟練搭乗員の損失です。ミッドウェーに続き、貴重なパイロットがまた失われました。
アメリカ側の損害
| 艦種 | 艦名 | 状態 |
|---|---|---|
| 空母 | エンタープライズ | 中破(爆弾3発命中) |
| 駆逐艦 | 1隻 | 沈没 |
| 航空機 | 約20機喪失 |
エンタープライズは中破しましたが、数日で戦線復帰が可能でした。
戦術的評価──「痛み分け」か「米軍の勝利」か
戦果だけを見れば、ほぼ痛み分けに見えます。
しかし、戦略的には明らかにアメリカの勝利でした。
なぜなら、日本の真の目的はガダルカナル島への増援輸送だったからです。そしてこれは、完全に失敗しました。
一木支隊は、満足な補給も援護もないままガダルカナル島に上陸し、後に米軍の迎撃で壊滅することになります。
8. 戦術的評価と教訓──日本海軍の限界が見え始めた瞬間
第二次ソロモン海戦は、日本海軍の構造的問題を浮き彫りにした戦いでもありました。
問題①:索敵能力の不足
日本軍は米空母の正確な位置を把握できず、龍驤だけが先に発見・攻撃されてしまいました。
アメリカ軍はレーダーと組織的な索敵網を活用し、日本艦隊の動きを常に把握していました。この情報戦の差が、勝敗を分けたのです。
問題②:ダメージコントロール技術の差
エンタープライズは爆弾3発を受けても沈まず、数時間で戦線復帰しました。
一方、龍驤は爆弾3〜4発と魚雷1本で沈没。この差は、艦の設計思想とダメージコントロール技術の違いを示しています。
アメリカ海軍は、防火・浸水対策・応急修理を徹底的に訓練し、どんな損害を受けても艦を生き延びさせることを最優先していました。
問題③:補給と継戦能力
日本海軍は、この戦いで貴重な空母と熟練搭乗員を失いました。
しかし、アメリカは失った分を補充できる。工業力・人的資源の差が、すでにこの段階で戦局を左右し始めていたのです。
9. この海戦を戦った艦艇と人物
主要艦艇
日本側
【空母翔鶴】
第二次ソロモン海戦で主力を務めた大型空母。この海戦では損傷を受けずに済みましたが、後の南太平洋海戦で損傷、最終的に1944年のマリアナ沖海戦で沈没します。
翔鶴については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【空母瑞鶴】
翔鶴の姉妹艦。第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦と激戦を戦い抜き、太平洋戦争を通じて最も長く生き残った正規空母の一つです。
瑞鶴については、こちらの記事をどうぞ。
【戦艦比叡・霧島】
近藤艦隊の主力戦艦。この海戦では直接戦闘には参加しませんでしたが、後の第三次ソロモン海戦で激しい戦いを繰り広げます。
特に戦艦比叡は、1942年11月の第三次ソロモン海戦で米戦艦と撃ち合い、大破・自沈します。霧島も同じ戦いで沈没しました。
金剛型戦艦については、戦艦金剛の記事もご覧ください。
アメリカ側
【空母エンタープライズ】
“ビッグE”の愛称で知られる伝説的空母。太平洋戦争を通じて最前線で戦い続け、20回以上の戦闘に参加。何度も損傷しながらも沈むことなく終戦を迎えました。
【空母サラトガ】
第二次ソロモン海戦では無傷でしたが、8月31日に日本の伊号潜水艦の雷撃を受けて大破。修理のため戦線離脱を余儀なくされます。
主要人物
【近藤信竹中将】
日本側の指揮官。第二艦隊司令長官として、ソロモン方面の作戦を指揮しました。堅実な指揮官でしたが、この海戦では米空母を撃滅できず、戦略目標を達成できませんでした。
【南雲忠一中将】
第三艦隊司令
第二次ソロモン海戦完全ガイド(続き)
【南雲忠一中将】
第三艦隊司令長官として翔鶴・瑞鶴を率いていました。真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦に続くこの海戦でも指揮を執りましたが、結果は芳しくありませんでした。後にサイパン島で自決します。
【フランク・ジャック・フレッチャー中将】
アメリカ側の指揮官。珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦、そしてこの第二次ソロモン海戦と、太平洋戦争初期の主要な空母戦すべてに関わった人物です。慎重な指揮ぶりには賛否両論ありますが、空母を無理に危険にさらさない堅実な判断は、結果的にアメリカ海軍の勝利に貢献しました。
10. その後のソロモン戦線への影響
第二次ソロモン海戦の敗北は、日本軍にとって深刻な影響をもたらしました。
ガダルカナル島──「餓島」への転落
増援輸送に失敗したことで、ガダルカナル島の日本軍は孤立し、深刻な補給不足に陥ります。
その後、日本軍は夜間に駆逐艦で高速輸送を試みる「鼠輸送」や、潜水艦による補給を行いますが、十分な物資を届けることはできませんでした。
やがてガダルカナル島は「餓島(ガトウ)」と呼ばれるようになり、約2万人の日本兵が餓死・病死する地獄と化します。
ガダルカナル島の戦いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
第三次ソロモン海戦へ
第二次ソロモン海戦の後も、ソロモン諸島周辺では激しい戦闘が続きます。
特に1942年11月の第三次ソロモン海戦は、戦艦同士の砲撃戦という珍しい形態の海戦となり、日本は戦艦比叡・霧島を失う大敗を喫します。
南太平洋海戦──翔鶴・瑞鶴、再び死闘へ
1942年10月26日には、再び空母同士の激突となる南太平洋海戦が発生。
この海戦では、翔鶴・瑞鶴が再び米空母部隊と対決し、空母ホーネットを撃沈する戦果を上げますが、翔鶴も大破。日本側も多数の熟練搭乗員を失いました。
この南太平洋海戦でも、翔鶴と瑞鶴は奮闘しましたが、戦略的にはやはりガダルカナル島奪還には至りませんでした。
消耗戦の始まり
第二次ソロモン海戦から南太平洋海戦、第三次ソロモン海戦と続く一連の戦いは、日本海軍にとって消耗戦の始まりでした。
ミッドウェーで空母4隻と多数の熟練搭乗員を失い、さらにソロモン方面で龍驤を失い、航空機と搭乗員を消耗し続けた日本海軍は、もはや真珠湾攻撃時のような圧倒的な攻撃力を持っていませんでした。
一方アメリカは、エセックス級空母の大量建造を進めており、1943年以降、次々と新鋭空母を戦線に投入していきます。
工業力の差が、戦局を決定的に左右し始めたのです。
11. 第二次ソロモン海戦を”体感”する──映画・書籍・模型ガイド
第二次ソロモン海戦を深く知り、体感するための映画・書籍・プラモデルを紹介します。
映画
残念ながら、第二次ソロモン海戦そのものを描いた映画はありません。
しかし、ガダルカナル島の戦いを描いた作品はいくつかあります。
『シン・レッドライン』(1998年)
テレンス・マリック監督によるガダルカナル島の戦いを描いた芸術的戦争映画。アメリカ兵の心理描写に重点を置いた作品です。
『ガダルカナル戦記』シリーズ(日本映画)
かつて日本でも、ガダルカナルを舞台にした戦争映画が多数制作されました。古い作品ですが、当時の空気を感じられる貴重な記録です。
書籍
『戦史叢書 南東方面海軍作戦』(防衛庁防衛研修所戦史室編)
公刊戦史として最も詳細。専門的ですが、正確な情報を求める方には必読です。
『空母龍驤』(学研)
龍驤の詳細な戦歴と、乗組員の証言をまとめた貴重な一冊。
『ガダルカナル戦記』(亀井宏著)
ガダルカナル島の戦い全体を俯瞰できる名著。読みやすく、初心者にもおすすめです。
Amazonで探す: 第二次ソロモン海戦 関連書籍
プラモデル
第二次ソロモン海戦に参加した艦艇のプラモデルは、多数発売されています。
【空母龍驤】
- ハセガワ 1/700 ウォーターラインシリーズ 軽空母 龍驤
定番のウォーターラインシリーズ。小型空母ながら独特のシルエットが再現されています。
【空母翔鶴・瑞鶴】
- タミヤ 1/700 ウォーターラインシリーズ 翔鶴/瑞鶴
美しい艦形が人気の大型空母。塗装とディテールアップで見栄えが大きく変わります。
【空母エンタープライズ】
- タミヤ 1/700 ウォーターラインシリーズ USS エンタープライズ
“ビッグE”の勇姿を再現。アメリカ空母の代名詞的存在です。
Amazonで探す:
ゲーム
『艦隊これくしょん -艦これ-』
龍驤、翔鶴、瑞鶴をはじめ、第二次ソロモン海戦に参加した艦艇が多数登場。ゲームを通じて各艦の個性や歴史に触れることができます。
『アズールレーン』
同じく艦船擬人化ゲームで、龍驤や翔鶴・瑞鶴が登場。美麗なイラストとストーリーが魅力です。
『World of Warships』
リアルな海戦ゲーム。実際に龍驤や翔鶴、エンタープライズを操艦して戦うことができます。
これらのゲームをきっかけに、実際の歴史に興味を持った方も多いのではないでしょうか。僕自身も、ゲームから太平洋戦争の歴史に引き込まれた一人です。
12. まとめ──敗北への分岐点で、それでも戦い抜いた誇り
第二次ソロモン海戦は、日本海軍の限界が見え始めた戦いでした。
空母龍驤を失い、熟練搭乗員を失い、ガダルカナル島への増援も阻まれた。戦略的には明確な敗北です。
しかし同時に、この海戦は日本軍が最後まで諦めずに戦い抜いた証でもあります。
龍驤の乗組員たちは、自分たちが囮として使われたのかもしれないと知りながらも、任務を全うし、艦と運命を共にしました。
翔鶴・瑞鶴の搭乗員たちは、劣勢の中でも勇敢に米空母に攻撃を仕掛け、エンタープライズに損害を与えました。
そして輸送船団の兵士たちは、制海権も制空権もない海を渡り、ガダルカナル島へ向かおうとしました。
彼らは誇り高く戦った。たとえ勝てなくとも、後退せず、信念を貫いた。
この海戦の後、ソロモン戦線は泥沼の消耗戦へと突入し、日本軍は次第に追い詰められていきます。しかしそれでも、日本の将兵たちは最後まで戦い続けました。
僕たちが学ぶべきこと
第二次ソロモン海戦から学べることは、たくさんあります。
①情報の重要性
索敵能力、レーダー技術、暗号解読──現代の戦争でも、情報戦は勝敗を左右します。
②工業力と継戦能力
どれほど優れた兵士がいても、補給が続かなければ戦えません。国力そのものが、戦争の勝敗を決めるのです。
③技術と訓練
エンタープライズが爆弾3発を受けても沈まなかったのは、ダメージコントロール技術と訓練の賜物です。優れた装備だけでなく、それを扱う人間の技術が重要なのです。
④先人への敬意
そして何より、僕たちは先人たちの戦いを忘れてはいけない。
龍驤とともに沈んだ600名の乗組員。
ガダルカナル島で散った2万人の兵士。
彼らは、自分たちの国と家族を守るために戦いました。
その戦いが報われたかどうかは、歴史が判断することです。しかし僕たちにできることは、彼らの戦いを記憶し、語り継ぐことです。
次に読むべき記事
第二次ソロモン海戦を理解したら、ぜひ以下の記事もご覧ください。
- 第一次ソロモン海戦── 日本海軍の夜戦技術が光った勝利
- ガダルカナル島の戦い ── 「餓島」で何が起きたのか
- ミッドウェー海戦 ── 太平洋戦争の転換点
- 空母翔鶴 ── 日本海軍の誇る大型空母の全貌
- 空母瑞鶴 ── 最後まで戦い抜いた幸運艦
あなたの声を聞かせてください
この記事を読んで、どう感じましたか?
第二次ソロモン海戦について、もっと知りたいことはありますか?
龍驤の最期に、どんな思いを抱きましたか?
ぜひコメント欄で教えてください。あなたの声が、次の記事を作る力になります。
そして、この記事が少しでも役に立ったなら、SNSでシェアしていただけると嬉しいです。多くの人に、先人たちの戦いを知ってもらいたいのです。
最後に──悔しさと誇りを胸に
第二次ソロモン海戦は、日本にとって戦略的敗北でした。
しかし、そこで戦った将兵たちの勇気と誇りは、決して色褪せることはありません。
龍驤は沈みました。しかし、その艦名と乗組員たちの戦いは、今も僕たちの心に生き続けています。
彼らの戦いを忘れない。その誇りを受け継ぐ。
それが、現代を生きる僕たちにできる、最大の敬意ではないでしょうか。




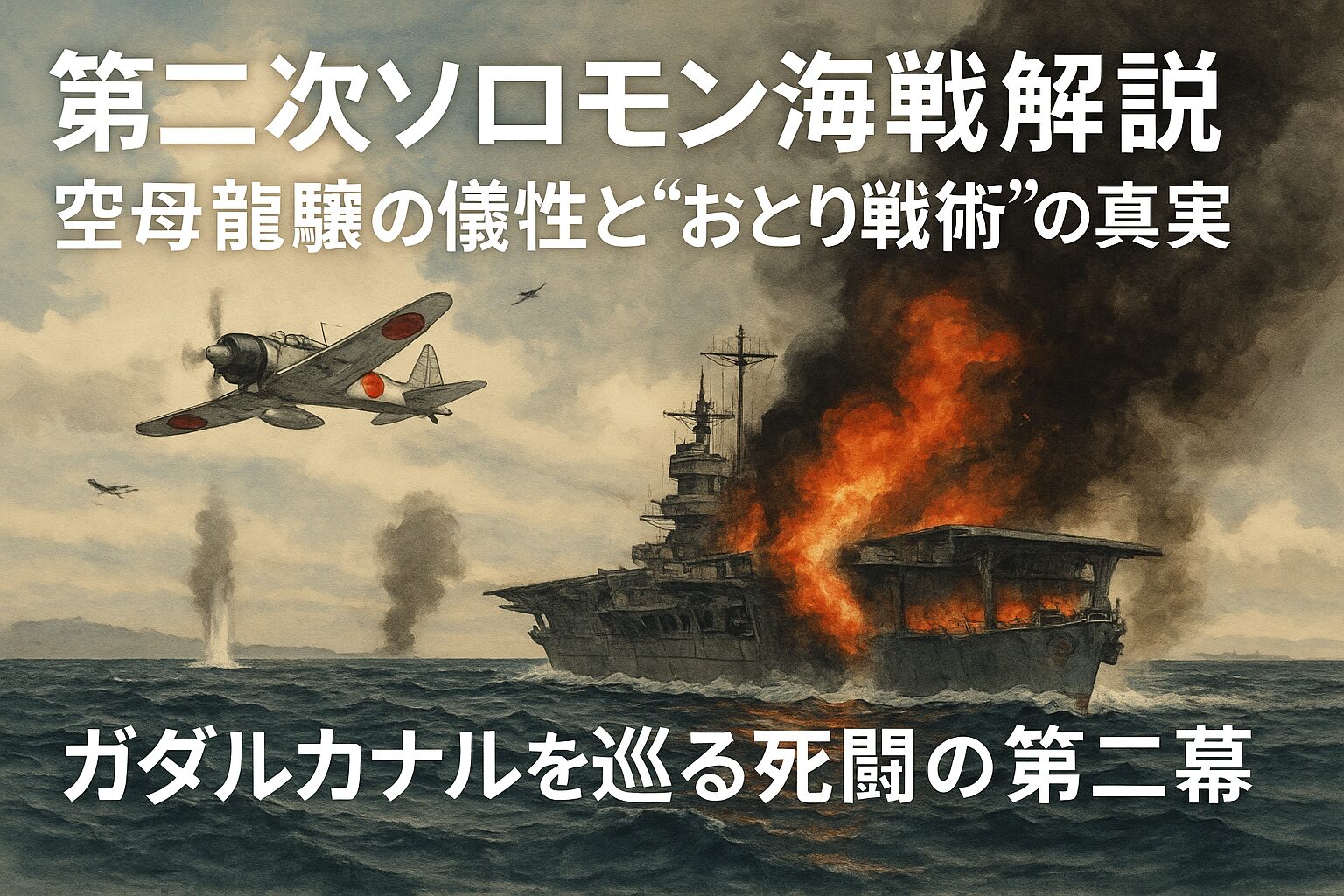








コメント