第1章 戦艦加賀とは何か?──「誤解」と「真実」を最初に整理
「戦艦加賀」は、厳密には“存在していない”。――ここがまず最初のキモです。
加賀は本来、土佐型戦艦(二番艦)として起工された巨大艦でしたが、ワシントン海軍軍縮条約と関東大震災という歴史のうねりに飲み込まれ、未完成の戦艦 hull を空母へ改造、最終的に「空母加賀」として就役しました。いわゆる“戦艦加賀が海戦で活躍した”というイメージは、計画(未成艦)と、完成後の空母が頭の中で混線した結果なんです。
1-1 なぜ今も「戦艦加賀」で検索されるのか
- 設計段階の「土佐型戦艦・加賀」は41cm級主砲×10門(5連装砲塔×2ではなく、連装×5基)など、当時の日本海軍が目指した“最強”級の火力を想定していました。完成していれば長門型の発展型として艦隊決戦ドクトリンの中核を担ったはず――この“もしも”が強烈に人を惹きつけます。
- 一方で、現実の“加賀”は空母です。条約で建造中止となった巡洋戦艦「天城」の代艦として、加賀の船体が空母に転用され、1928年に完成・試運転、1929年に第一線入りしました。名称は同じでも「艦種」と「運用思想」はまったく別物。
編集部コメント:
“戦艦加賀”という言い回しは、設計図のロマンと就役艦の現実を一言で包んでしまう魔性のフレーズ。模型界隈では「未成艦としての加賀」をテーマにしたキットや作例があるので、余計に混同が起きがちです(箱絵に“主砲”がドーンと描かれていたりね…)。
1-2 年表で俯瞰する「戦艦→空母」への転身
- 1920年7月:神戸・川崎造船所で土佐型戦艦「加賀」起工。
- 1921年11月:進水。
- 1922年:軍縮条約で戦艦としては中止。
- 1923年:関東大震災で「天城」被害→代艦として加賀の空母化が正式決定。
- 1928年3月:空母として完成(以後試運転)。
- 1929年11月:連合艦隊に編入、空母“加賀”として本格運用へ。
編集部コメント:
もし条約がなく、地震もなかったら――“主砲10門の最強級戦艦として海に出る加賀”を私たちは見られたかもしれない。歴史は紙(条約)と地震という、艦載砲よりも強い力で進路を変えることがあります。
1-3 用語ミニ解説(初心者向け)
- 未成艦:設計・起工はされたが、完成・就役まで至らなかった艦。加賀の「戦艦としての姿」は未成艦にあたります。
- 代艦案:条約などで中止・廃艦となる艦の代わりに、別の船体を同一カテゴリー(この場合は“空母枠”)として転用・建造すること。天城→加賀の置き換えが代表例。
- 全通(ぜんつう)甲板:艦の前後を遮らず、甲板全体を滑走路として連続させた構造。加賀は完成後しばらく多段飛行甲板でしたが、のちの大改装で全通甲板化されます(詳細は第4章)。
1-4 結論:「戦艦加賀」は“設計上の加賀”、戦場の主役は“空母加賀”
検索キーワードとしての「戦艦 加賀」は間違いではありません。**土佐型の設計思想(性能・比較・“最強”論)を語る入口としては正しい。一方、太平洋戦争で活躍したのは空母加賀であり、以降の章では空母としての近代化・性能・運用・最後(ミッドウェー)・現在(海底調査や護衛艦「かが」との関係)**まで丁寧に追っていきます。
他の戦艦・空母はこちらの記事にまとめています。

第2章 誕生の背景:土佐型「戦艦加賀」の計画と設計思想
「最強の戦艦」を目指す――大日本帝国海軍が**“八八艦隊”**構想の仕上げとして用意した答えのひとつが、土佐型戦艦(二番艦=加賀)でした。前級・長門型の延長ではなく、ユトランド沖海戦の戦訓(上空からの急降下弾=弾道落角への備え、弾薬庫防護の強化)まで取り込んだ“増厚・改良版”の設計です。
2-1 スペックでみる「もし完成していたら」の加賀
- 主砲:41cm(16.1inch)連装×5基=10門。日本独自設計の**“三年式41cm砲”**を採用(長門型と同系)。連射性能は毎分約2発が想定。
- 副砲:14cm砲×20門(舷側ケースメイト配置)。対空用に8cm級高角砲も計画。
- 魚雷兵装:61cm発射管×8門。
- 防御:水線装甲280mm、甲板102mm、バーベット229–305mm、艦橋356mm。傾斜装甲帯や対魚雷バルジで水上・水中防御を底上げ。
- 機関・速力:艦本式水管缶12基/91,000shp、26.5ノット。前級の出力を維持しつつボイラー数を圧縮。
- 主要寸法・排水量:全長234.1m、幅30.5m、満載44,200t。
編集部コメント:
「連装5基10門」はロマンの塊。長門型(8門)に“もう一段”の火力を積み、なお26.5ノットで隊形運動に付いていく――この“欲張り加減”が土佐型の魅力です。
2-2 設計思想のキモ:長門型の発展+戦訓の取り込み
設計主任平賀譲のチームは、長門型で採り入れた**“オール・オア・ナッシング”(要所集中防御)思想に加え、バルジ拡大や装甲帯の傾斜など、当時入手した英米艦の情報と実験結果を反映。弾薬庫・主砲塔の防護強化と甲板装甲の増厚**で“上からの一撃”にも耐える方向へ振りました。
編集部コメント:
図面を追うと「砲10門+26.5ノット+厚装甲」という三立てが見えてきます。矛と盾をどちらも盛る、当時の日本海軍らしい“質で勝つ”マインドですね。
2-3 同時代戦艦との文脈(性能・比較)
- 米コロラド級:16inch×8門、21ノット。砲の口径は同等でも、加賀(想定:10門・26.5ノット)は「火力+機動」で上回る設計。一方、標準戦艦コンセプトゆえの復原性・被害管制の堅さはコロラドに分があります。
- 長門型(日本側の基準艦):41cm×8門/26.5ノット。土佐型は主砲+2門分と装甲・水中防御の底上げで“決戦主力の完成形”を狙った位置づけ。
編集部コメント:
“最強”の定義は人それぞれですが、10門ぶんの同時斉射は索敵・測距が未熟な時代の“的確な初弾効果”という意味で強い。対して米海軍は損傷制御と電測の強化で受けに振る――発想の違いが面白いところです。
2-4 なぜ「空母加賀」に転じたのか(ここだけ先取り)
1922年のワシントン海軍軍縮条約で戦艦としては中止。さらに1923年の関東大震災で「天城」損傷→“代艦案”として加賀の空母化が決まります。こうして未成の戦艦船体が空母へ――この“転身”が後の太平洋戦争で大きな意味を持つことに。詳細は第3章で掘り下げます。
2-5 用語ミニ解説
- 八八艦隊:8隻の戦艦+8隻の巡洋戦艦で最新戦力をそろえる日本海軍の国家計画。老朽化前に常に16隻を維持する狙い。
- 傾斜装甲帯:装甲帯を内側に傾けて配置し、水平に近い遠距離弾への実効厚を稼ぐ工夫。
- 対魚雷バルジ:舷側に**膨らみ(バルジ)**を設けて爆発エネルギーを吸収、浸水を分散させる水中防御。
- 三年式41cm砲:日本初の本格16インチ級主砲。長門型に装備、土佐型(加賀)にも搭載予定だった。
編集部ひとこと:
机上のスペックだけ見れば「加賀(戦艦案)は日本軍の“最強”候補」と評したくなるのは正直なところ。ただ、歴史は図面のまま進まない。条約と地震が艦種を変え、航空主兵の時代を押し広げました。
第3章 ワシントン海軍軍縮条約と運命の転換
“主砲10門の戦艦加賀”が、どうして空母加賀になったのか。答えは紙1枚――ワシントン海軍軍縮条約(Five-Power Treaty, 1922)にあります。条約は主力艦の保有比率を「5:5:3」(米・英・日)に固定し、空母総トン数の上限(米英13万5千t、日本8万1千t)と個艦の上限27,000tを設定。ただし**「建造中の主力艦なら2隻まで空母へ改造可」**という“抜け道”を認め、その場合は33,000tまで拡大できる――これが“加賀の転身”の法的レールでした。
編集部コメント:
条文を読むと、「空母化」こそが節約策として推奨されていたのがよく分かります。スクラップにするくらいなら、飛行甲板を載せて再活用――合理的だけど、艦隊の性格は根本から変わるんですよね。
3-1 “代艦案”の現場:当初は「赤城+天城」、地震で「赤城+加賀」へ
日本海軍は条約の空母化特例(2隻まで/33,000t)を活用し、当初は巡洋戦艦「赤城」「天城」の2隻を空母へ転用する計画でした。ところが1923年9月1日の関東大震災で天城の船体が致命的損傷を受け、代艦として“戦艦”加賀の船体を空母に振り替える決定が下ります(正式決定は1923年12月13日)。条約と天災――この二つが、加賀の航路を文字通りねじ曲げたわけです。
- 加賀の経歴(要点)
1920年7月起工/1921年11月進水(土佐型“戦艦”として)→1928年3月完成→1929年11月就役(連合艦隊編入)。計画は戦艦、実物は空母という“二つの顔”を持つゆえんです。
3-2 条文が作った空母の“かたち”:武装とトン数の縛り
条約は空母の武装にも口を出します。8インチ(20cm)超の砲は禁止、重砲は合計10門まで、かつ個艦は27,000t(改造艦なら33,000t)が基本線。だからこそ赤城/加賀は当初8インチ級砲を採用しつつ(のち撤去・縮小)、航空運用能力と復原性のバランスを探っていくことになります。条約の文字が、飛行甲板の長さ・艦橋配置・兵装レイアウトまでに影を落としていたのです。
編集部コメント:
「空母に大砲?」と驚く方もいるはず。当時は“空母=脆い補助艦”という先入観が強く、自衛火力を持たせる発想が一般的でした。実戦と航空機の大型化が進むと、**“砲より飛行甲板”**へ舵が切られていきます。
3-3 多段飛行甲板という過渡期の解答
初期の加賀は三段の飛行甲板(上・中・下)を採用。着艦と発艦の同時並行を狙った“教科書的”解ですが、中・下甲板は短すぎて実用性が限定的。1933~35年の大改装で全通(フラッシュ)甲板に改め、**艦橋(アイランド)を新設、機関換装で速力・航続力も底上げ――ここでようやく“近代空母・加賀”**が完成します。
- 施策のキモ
- 中・下甲板の廃止→格納庫化、上甲板を艦首まで延長(発着艦余裕の確保)
- 機関更新・船体延長・バルジ追加(復原性と被雷耐性の補強)
- 航空兵装運用の動線見直し(弾薬・燃料エレベーターの直通化 ほか)
いずれも大型化・高性能化する艦上機に合わせるための“必然の近代化”でした。
編集部コメント:
三段甲板は時代の実験作。模型で見ると映えますが、現場の整備・運用は地獄だったはず。最終形の“全通甲板+アイランド”は、太平洋戦争で“最強の空母像”として標準化していきます。
3-4 “紙の条約”が変えた艦隊ドクトリン
条約は保有量を削るだけでなく、運用思想まで変えました。空母トン数枠の空白が各国に“空母建造の余地”を与え、日本は赤城・加賀のコンビを軸に、のちの機動部隊(第一航空艦隊=機動部隊/機動部隊=「連合した空母群」)という発想へ進みます。空母を束ねて“先制・集中打撃”――この考えが真珠湾~インド洋作戦の成功、そしてミッドウェーの失敗まで、長い影を落としました。
編集部コメント:
わたしたち編集部の実感として、**“戦艦の時代を終わらせたのは条約”という見方は半分正解。もう半分は“条約に適応した現場”**の勝利です。加賀の近代化は、まさにその学習曲線の結晶でした。
第4章 空母への改造と近代化:加賀はどう変わったか
“戦艦加賀”の船体に、航空主兵のノウハウをどこまで盛り込めたか――ここを押さえると、太平洋戦争期の「空母加賀」の性能・近代化・運用上の癖が見えてきます。結論から言うと、加賀は初期の多段飛行甲板という過渡期の解でスタートし、1933–35年の大改装で**全通甲板+アイランド(艦橋)**という“王道”へ到達。機関も一新され、28ノット/搭載機90機級の主力空母に化けました。
4-1 初期形態:多段飛行甲板という「実験作」
- 三段(上・中・下)飛行甲板:発艦と着艦を同時進行させたい――理屈は分かるが、中・下甲板は短すぎて実用性が限定的。軽量・短距離で飛べる時代の機体ならともかく、すぐに大型化の波に追い付けなくなりました。
- 重砲の搭載:条約時代の先入観で、当初は20cm級砲も持たされました(のち撤去・縮小)。「空母も自衛火力を」という発想が残っていた名残です。
編集部コメント:
写真映えは満点。でも、甲板サイクル(発着艦の回し方)と整備動線が厳しい。現場は「かっこいい」より「回せる」が正義です。
4-2 大改装(1933–35):すべては“回すため”の近代化
大改装のメニューをひとことで言えば、**「短い甲板をやめ、機関と艤装を“今の航空機”に合わせて作り直した」**です。
- 甲板と格納庫:中・下甲板は格納庫化、上甲板は艦首まで延長→全通化。前方エレベーターの新設(計3基)、弾薬・魚雷の昇降装置を飛行甲板直通に改め、搭載機は**90機(72運用+18予備)**規模へ。小型の右舷アイランドも設置され、運用の見通しが一気に良くなります。
- 対空火器の更新:高角砲は12.7cm連装(九八式=Type 89)へ、機銃は25mm(Type 96)連装×11基を中心に強化。のちの戦訓でさらに積み増されていきます。
- 機関・船体:缶・タービンを総入れ替え、出力127,400shp/公試28ノット。艦尾延長や追加バルジで抵抗低減と復原性を改善(友鶴事件の教訓も反映)。結果、標準排水量は約38,200t級まで増えました。
4-3 それでも残った“構造的な弱点”
- 燃料タンクの取り付け方法:船体構造に燃料タンクを組み込む設計で、衝撃でクラック→漏洩が起きやすい。
- 密閉型の二層格納庫:蒸気(可燃性ガス)がこもりやすいうえ、消火系の冗長性が乏しく、被害管制が難しい。
- “整備は格納庫で”の運用慣行:燃料・兵装の取り扱いを甲板下で実施する文化が温存され、火災拡大リスクを上げてしまった。
これらはミッドウェーでの“最後”に直結する要因でもありました。
編集部コメント:
当時の日本軍は**「速攻・集中打撃」**の思想が強く、整備の安全余裕はどうしても後回し。**被害管制(ダメージコントロール)**の思想と設備は、米海軍に一歩遅れを取りました。
4-4 数字で見る「改装後の加賀」【性能まとめ】
- 速力:28ノット
- 搭載機:90機(72運用+18予備)(1936目安)
- 兵装:12.7cm高角砲×8基(連装)、25mm機銃×11基(連装)、(当初の20cm砲は段階的に撤去)
- 全長:247.65m、標準排水量:約38,200t
- 真珠湾時の定数:零戦21/九九艦爆27/九七艦攻27(計75機+予備)
このスペックは翔鶴型の登場まで日本側の“主力空母の標準”を形づくりました。

編集部コメント(比較の予告):
同時代の赤城とは「回しやすさ(甲板長・排気処理・艦橋配置)」で悩みが似ており、近代化でどちらも“まとも”になります。一方、のちの翔鶴型は最初から運用最適化の設計思想。図面スタートの強みが出ます(比較は次章でがっつり)。
4-5 用語ミニ解説(初心者向け)
- 全通(ぜんつう)甲板:艦首から艦尾まで遮らない一本滑走路。発着艦のサイクル効率が高い。
- アイランド:飛行甲板右舷の艦橋ブロック。風圧や視界に配慮して基本は右舷配置。
- アレスティング・ギア:着艦機のワイヤー制動装置。改装により国産システムへ更新。
- 被害管制(ダメコン):損傷時の隔壁閉鎖・消火・排水・応急修理を組み合わせて生残性を高める考え方。
4-6 編集部の総括:近代化で“主力”に、クセは最後まで
紙の上では日本軍“最強”の一角に見える改装後の加賀。ただし、格納庫運用の危うさや防火・消火の冗長性不足など、“設計由来のクセ”はミッドウェーまで尾を引きます。近代化=万能化ではない――ここが、加賀という艦の面白さであり、悲劇でもあります。
※主要数値・改装内容の要旨は、各種一次・二次資料を突き合わせています(公試28ノット/127,400shp、全通化とアイランド新設、搭載機90機級、対空兵装の更新、条約に基づく重砲制限など)。条約の具体条項はワシントン海軍軍縮条約本文と米海軍の解説記事を参照。運用・改装年表やエアグループの変遷はCombinedFleetのTRM(Tabular Record of Movement)でも確認できます。
第5章 性能と比較:「最強」だったのかを冷静に検証
“戦艦の器を持つ空母”――加賀の強みは大きな船体=大きな航空隊でした。いっぽうで速力や被害管制(ダメコン)、格納庫運用の安全性では、のちの新型や米海軍に遅れが出ます。ここでは赤城・蒼龍・飛龍・翔鶴、さらに米ヨークタウン級と**比較(性能・運用)**して、「最強」の中身を分解します。
5-1 同世代・日本艦との比較
加賀 vs 赤城(改装後基準)
- 航空隊規模:加賀90機(72+18予備)級/赤城91機。いずれも“質より量”で一撃の厚みを作れるのが武器。
- 速力:加賀約28ノット、赤城31ノット。追随性・回頭性では赤城が上。
- 共通の弱点:密閉気味の二層格納庫、甲板下での燃料・兵装取扱いという運用慣行。火災拡大リスクが残りました。
編集部コメント:
“最強の一撃”を担う二大主力。ただし回せる速さとダメコン余裕は新造空母に譲る…というのが現場感です。
加賀 vs 蒼龍・飛龍(運用最適化の俊足コンビ)
- 速力:蒼龍34ノット(飛龍も同系)、機動で優位。
- 航空隊規模:蒼龍70機前後と加賀より少なめだが、格納庫・エレベーター配置が近代的でサイクル効率は良好。
- 総評:**機動力と運用性=“回しやすさ”**は蒼龍側、**一撃の“厚み”**は加賀側。状況で優劣が入れ替わります。
加賀 vs 翔鶴型(早期戦のベンチマーク)
- 速力:34ノット級、防御・搭載量とも高水準。日本側の“完成度”では頭ひとつ抜けた主力。
- 編集部の見立て:日本海軍の“最強(バランス最良)”は早期戦なら翔鶴型でほぼ異論なし。加賀は“量で殴る役”として機動部隊の厚みを作った存在、という位置づけです。
5-2 米空母との比較(ヨークタウン級を軸に)
レーダー・警戒
- ヨークタウン級は戦前からCXAMレーダーを搭載し、早期警戒と管制で優位。日本側(加賀含む)にはこの段階で同等の装備はなく、迎撃・回避の初動に差が出ました。ウィキペディア
被害管制(ダメコン)と格納庫設計
- 米海軍は教範・訓練の体系化と開放型ハンガー(通風・排煙が容易)で火災拡大を抑えやすい設計・運用。対して日本の主力空母は密閉気味の格納庫・甲板下整備の文化が強く、燃料・弾薬の誘爆→手に負えない火災に至りやすい構造的リスクを抱えました。
編集部コメント:
“最強”を分けたのは一撃の厚みよりも、壊れたあとに踏ん張れるか。ここで米海軍の地力(レーダー+ダメコン)が効いてきます。
5-3 数字でざっくり“横見せ”比較(代表値)
| 艦 | 速力 | 搭載機(目安) | 特徴メモ |
|---|---|---|---|
| 加賀 | 28 kt | ~90(72運用+18予備) | 大型船体で“厚い一撃”。格納庫運用・防火が弱点。 |
| 赤城 | 31 kt | ~91 | 三段甲板→全通化。旗艦適性・運用力は高い。 |
| 蒼龍 | 34 kt | ~70 | 小柄・俊足。サイクル効率が良い。 |
| 翔鶴 | 34 kt | ~84–96(時期で変動) | 早期戦の完成形。防御と運用のバランス良。 |
| ヨークタウン級 | 32.5 kt | ~90 | 早期にレーダー装備、ダメコン文化が強い。 |
※搭載数は時期・任務で変動します。表は代表的な「目安」です。
5-4 結論:「最強」の定義しだいで、加賀は“厚撃の王様”
- 一撃の“厚み”=同時打撃力で見れば、加賀は当時の日本軍でも最強クラス。真珠湾・インド洋のような「先手・集中」の場面では、大搭載量がそのまま戦果に直結しました。
- しかし継戦力(被害管制・警戒・復旧)まで含めた総合力なら、翔鶴型やヨークタウン級に軍配。ミッドウェーで分岐が露呈したとおり、格納庫の安全性・運用手順・ダメコンの差が、結果を左右しています。
編集部の総括:
“最強”=最大火力では加賀に華。“最強”=“壊れても戦える”なら米・新型空母が強い。――だから面白いし、模型の作り分けも楽しいんです。
第6章 太平洋戦争での活躍:真珠湾から南方作戦、そしてミッドウェーへ

結論から言うと――加賀は“開戦ダッシュ”の主力であり、決戦ミッドウェーで散りました。途中のインド洋作戦(Operation C, 1942年4月)には不参加というのがポイント。年表を“運用の手触り”で追っていきます。
6-1 真珠湾攻撃(1941年12月7日):“六空母機動部隊”の一角
開戦劈頭、第一航空艦隊(機動部隊=赤城・加賀・蒼龍・飛龍・翔鶴・瑞鶴)の一隻として加賀はハワイ作戦に参加。六隻合計420機超が二波に分かれて発進し、戦艦戦力の無力化に成功しました。ここでの加賀の“役割”は、大量の攻撃隊の1/6を安定供給する“厚み”。個艦の数字ではなく、束ねて殴るコンセプトの中の一駒として機能しています。
編集部コメント:
開戦時点の「最強」は個艦性能より**“まとまり”**。六空母一体運用という“回し方”が、そのまま戦果に直結しました。
6-2 南方作戦:ラバウル空襲~ダーウィン空襲(1942年1–2月)
ラバウル・カビエン空襲(1月20–22日)
トラック泊地を基点に、加賀は**ラバウル(ニューギニア)・カビエン(ニューアイルランド)を攻撃。20日にB5N“九七艦攻”などを投入し、21日はD3A“九九艦爆”**中心、22日も再攻撃――占領作戦の前衛として制空・制圧を担いました。
事故:パラオで暗礁接触(2月9日)
パラオ停泊中に暗礁へ接触し、前部ビルジ損傷→速力18ノットに低下(応急修理)。それでも作戦行動は継続します。
ダーウィン空襲(2月19日)
第一・第二航空戦隊(赤城・加賀・蒼龍・飛龍)が豪州ダーウィンを空襲。加賀はB5N×27(爆装)/D3A×18/A6M×9を投入、艦船・港湾施設に大打撃を与えました。米海軍の公式解説や豪州の記録でも四空母の参加が確認できます。
編集部コメント:
パラオで速度を落としつつも**“やる時はやる”**のがこの頃の機動部隊。長距離一撃→即転進のテンポは、開戦~前半戦ならではの“速攻美学”です。
6-3 インド洋作戦は“欠席”(1942年4月)
4月の**インド洋作戦(Operation C)**は、赤城・蒼龍・飛龍・翔鶴・瑞鶴が主力。加賀は2月の損傷修理で佐世保へ回航し、乾ドック(3月27日~5月4日)だったため参加せず。ここは意外と見落とされがちなトリビアです。
編集部コメント:
“インド洋で暴れた加賀”という混同、実は多いです。年表の穴を埋めると史実がくっきりします。
6-4 ミッドウェー(1942年6月4日):加賀「最後」の一日

出撃と第1撃
5月27日出撃。空母群(赤城・加賀・蒼龍・飛龍)は6月4日未明にミッドウェー北西約250海里に到達。加賀は九九艦爆18+零戦9でミッドウェー島施設を攻撃(午前)。ここまでは“定石”どおりのサイクルでした。
航空サイクルと“神話”の修正
しばしば語られる**「日本空母は飛行甲板に爆装・給油中の機が溢れていた」神話は、研究の進展で修正されています。日本空母は“デッキロード”方式(甲板に載せられる分だけ一波ずつ回す)で、被弾時甲板上はむしろ空に近かった可能性が高い。ただし、密閉気味の二層格納庫での燃料・兵装取扱いが内部爆発・火災拡大**を招きやすかったことは事実です。
編集部コメント:
“回し方は巧い、でも壊れ方は脆い”――ここが日本空母の最大のジレンマ。整備・弾薬処理を“甲板下”に抱え込む文化が、被害管制の余裕を削りました。
致命弾と火災の拡大
正午前後、エンタープライズ基幹の急降下爆撃隊が空母群を捕捉。加賀は複数の250kg級爆弾直撃を受け、格納庫の航空燃料系・弾薬に引火、連鎖爆発→制御不能の火災に。動力喪失・舵効かずとなり、夕刻、駆逐艦「萩風」の雷撃で19:25自沈。戦死者は約800名とされます。
6-5 “甲板運用の現場感”:当時の1サイクル(超要約)
- **CAP(直衛戦闘機)を常時回しつつ、2) 打撃一波を甲板上で整列→発艦、3) 回収→次波を格納庫で整備・再武装、4) 状況次第で対艦/対地の弾薬入れ替え――という“回し続ける仕事”**でした。レーダーやダメコンの差が、**迎撃の初動と“壊れた後の復元力”**に直結していたのは米側記録・研究でも明瞭です。
編集部コメント:
“最強”は、殴る瞬間だけの称号ではない。殴った後に立っていられるかまで含めての総合点――ここで加賀と日本空母の弱点が露わになりました。
小まとめ
- 開戦~南方作戦:加賀は**大搭載量の“厚撃”**で機動部隊の要。ダーウィン空襲でも実効打。
- インド洋作戦:修理で欠席。
- ミッドウェー:運用は巧み、被害管制は脆弱。格納庫内の火災拡大が致命傷となり、夕刻自沈。
第7章 「最後」の一日:ミッドウェーで何が起きたのか
加賀の“最後”は、一撃で燃え尽きたという単純な話ではありません。10時22分ごろ、エンタープライズ艦載の急降下爆撃隊(VB-6/VS-6)が上空に現れ、指示の行き違いで二隊が同時に加賀へ降下。隊長リチャード・“ディック”・ベストは二機とともに離脱して赤城へ向かい、ほぼ一個群が丸ごと加賀に殺到しました――この“集中”こそが致命傷になりました。

7-1 被弾と初期損害:500/1,000ポンド弾が襲う
複数の500・1,000ポンド爆弾が飛行甲板~格納庫を貫通し、三~五発の直撃(諸説あり)で複合火災が発生。艦橋付近の直撃で岡田次作艦長が戦死、指揮中枢は瞬時に麻痺しました。火災は航空燃料(アブガス)系統と搭載弾薬に波及し、格納庫の側壁を吹き飛ばす規模の爆発へ拡大します。
編集部コメント:
“最強の一撃”を受けたのは、まさに最も厚い一撃を放てる大柄な加賀だった――皮肉です。
7-2 なぜ火が止まらなかったのか:設計と運用の合わせ技
- 燃料・消火系の損傷:爆発でアブガス配管が破断、主消火主管(ファイアメイン)や非常発電機まで損傷。CO₂消火装置も機能低下し、初動の“押さえ”を失います。ウィキペディア
- 密閉気味の二層格納庫:通風・排煙が難しく、可燃ガスが滞留。設計思想と現場慣行(整備・再武装を“甲板下”で回す)が火災拡大に不利でした。
編集部コメント:
“甲板は戦う場所、格納庫は働く場所”という日本海軍の文化が、被害管制の余裕を削ってしまった感は否めません。
7-3 神話の再点検:「5分で発艦」でも「甲板ぎっしり」でもない
古い定説では「日本空母は5分で発艦できる状況」「燃料・爆装済みの機が甲板に並んでいた」が広まりましたが、研究の進展(Shattered Sword系の知見)と米海軍史料の再検討で大幅に修正されています。実際は発艦準備まで約45分を要し、“デッキロード(甲板に並べられる分だけ一波ずつ回す)”が基本。つまり致命弾の時、甲板上は空に近かった可能性が高く、格納庫内の燃料・弾薬処理こそが“火の芯”でした。
7-4 退艦から自沈まで:長い“死闘”の午後
昼前の被弾後も、加賀はすぐには沈みません。救難・応急が続けられましたが、火勢は制御不能に。夕刻、乗員は駆逐艦へ移乗し、19時25分、駆逐艦萩風が魚雷2本を撃ち込んで自沈処置――加賀は艦尾から沈没しました。損耗は約800名規模(記録により811~814名などの幅あり)。“一撃必沈”ではなく、燃え続けた末の幕引きでした。
編集部コメント:
個艦の復元力というより、ダメコンの組織力と設備冗長性の差がモロに出た――これが編集部の総括です。
7-5 当日の流れ(簡易タイムライン)
- 10:22頃:VS-6/VB-6が加賀へ同時降下、多発直撃。ベスト隊長の三機は赤城へ。
- 午前~午後:格納庫火災→弾薬誘爆、消火系統の損傷で被害拡大。
- 14:00~17:00:乗員退艦・救助(駆逐艦へ収容)。
- 19:25:萩風の魚雷で自沈、加賀は海底へ。
7-6 用語ミニ解説
- CAP(Combat Air Patrol):空母直衛の戦闘機待機・迎撃シフト。日本側は零戦の性能は高いが、管制・警戒の仕組み(レーダー)に弱点。迎撃の“初動差”が痛かった。
- デッキロード運用:甲板に載せられる分だけ一波を並べて発進・回収し、残りは格納庫で整備・再武装。**“甲板ぎっしり神話”**と実像の違いを理解する鍵。
7-7 小まとめ:偶然と必然の交差点
- 偶然:VS-6/VB-6の“二重降下”という集中が生じた。
- 必然:密閉気味の格納庫設計+甲板下運用+冗長性に乏しい消火・ダメコンが、止められない火災を生んだ。
- 結末:最強クラスの一撃力を誇った加賀は、継戦力という別の“最強”を持つ相手の前で崩れ落ちた
第8章 現在につながる加賀:海底の調査と“現代の加賀”
いまも太平洋の闇の底に、あの日の加賀は眠っている。
そして令和の海では、**新しい「かが」**がF-35Bを迎える準備を終えつつある――。
8-1 海底で見つかった“最後の加賀”:発見と新知見のアップデート
- 初出の手掛かり(1999)
米Nauticos社と米海軍の調査で、加賀の一部残骸(格納庫隔壁や25mm機銃座など)が約5,200m級の深海で確認されました。母体は見つからず“断片のみ”。 - 本体の位置特定(2019)
ポール・アレンの探査船R/V Petrelがミッドウェー海域を広域測量し、加賀の船体を水深約5,400mで発見。船体は直立、飛行甲板は大きく失われ、激しい戦闘損傷が確認されました。調査は**米保護海域(パパハナウモクアケア海洋国定公園)**内で行われています。 - 精密可視化(2023)
Ocean Exploration Trust(E/V Nautilus)とNOAAが加賀・赤城・ヨークタウンを連続運用のROVで考古学的に詳細記録。**加賀の舷側ケースメイト(副砲座)**など、戦艦生まれの“多世代技術の同居”が映像で裏付けられました。初の本格可視化として米海軍協会や各メディアも報道。
編集部コメント:
“厚撃の王様”だった加賀が、直立のまま静止しているのは妙に胸に来ます。映像で見る副砲痕跡は、「戦艦として生まれた過去」を無言で語る遺物でした。
8-2 “現代の加賀”こと護衛艦「かが」(DDH-184):空を運用する新しい器
- 艦の素性
海上自衛隊のいずも型二番艦。全長約248m/満載2.7万t級/速力30ノット超。発着艦スポットを5つ持つ大型飛行甲板と、国産AESAレーダーFCS-3系などを備える多用途ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)として就役しました。 - F-35B対応の近代化(第1段階:~2024年春完了)
耐熱塗装、夜間発着灯、そして艦首の台形→矩形化(スクエアバウ)など固定翼STOVL運用のための改修を実施。2024年10月、米海軍のF-35Bが初めて「かが」に着艦・発艦し、開発試験が始まりました。 - 実機の受け入れ状況(2025年時点)
日本はF-35Bを42機調達計画。2025年夏に最初のF-35Bが新田原基地へ配備されたと報じられ、将来はいずも/かがの両艦で運用される見込みです(段階的に訓練・運用を拡大)。
編集部コメント(比較の視点):
旧**“空母加賀”は艦上機を大量に“回す”器**、新しい**“かが”は同盟運用に組み込むプラットフォーム**。レーダー・リンク・ダメコンといった“見えない性能”の比重が、令和基準ではケタ違いです。
8-3 名前は同じ、役割は違う:**「加賀/かが」**という継承
- 命名の系譜
いずも型の艦名は旧国名に由来(出雲・加賀)。“加賀”の名は、旧帝国海軍の栄枯盛衰を想起させつつも、**法制度上は“護衛艦”**であり、攻勢航空打撃の専任艦ではない点に留意が必要です。 - 装備思想の違い
旧加賀:大搭載量+集中打撃/新かが:同盟共同運用・多任務対応(ASW・対潜哨戒・災害派遣)+限定的固定翼運用。時代が求める“最強”の定義が変わりました。
編集部コメント:
名前の継承は“史観の継承”でもあります。私たちは海底の加賀の教訓(被害管制・安全余裕)を、**現代の「かが」**の運用思想に重ね合わせて見てしまうのです。
8-4 用語ミニ解説
- DDH(ヘリ搭載護衛艦):ヘリ運用を主軸に設計された護衛艦区分。日本独自の呼称で、国際的にはヘリ空母に相当。
- STOVL(短距離離陸・垂直着陸):F-35Bが採る運用形態。カタパルト無しで発艦でき、耐熱甲板や飛行甲板形状が鍵。
- Papahānaumokuākea:ミッドウェー周辺の米保護海域。2019年の加賀発見や2023年の詳細調査は、この保護区内の許可のもとで実施。
小まとめ
- 海底の加賀は2019年に水深約5,400mで本体が特定、2023年にはROVで精密可視化が進み、戦艦生まれの痕跡が明瞭に。
- **現代の「かが」はF-35B対応改修の第1段階完了(2024)→米機での初発着(2024年10月)**を経て、日本配備のF-35B受け入れフェーズへ。同盟運用の要としての役割が濃くなっています。
第9章 ポップカルチャーの加賀:艦これ・アズレンでの描かれ方
ゲームの中の加賀は、史実の「空母加賀」をベースに、赤城との相棒感や**“狐”モチーフなどの演出で“人格”を与えられています。ここでは艦これ**(『艦隊これくしょん』)とアズレン(『アズールレーン』)の両作での表現を、史実との接点/乖離を軸に整理します。
※作品の設定はアップデートで変わる場合がありますが、ここでは“定番の印象”を扱います。
9-1 共通するモチーフ:赤城との“二人三脚”と「静の加賀」
- 相棒構図:両作品とも赤城×加賀を機動部隊の中核コンビとして描写。史実の**連携運用(旗艦・僚艦)**を分かりやすく擬人化した形です。
- 性格付け:赤城=情熱/姉属性、加賀=寡黙・クールという対比が定番。編集部としては「“厚撃の王様”だった加賀=淡々と仕事をこなす現場の人」というニュアンスにうまくハマっていると感じます。
- 和風・狐意匠:とくにアズレンは九尾・狐面といった**“サクラ帝国”**の演出が強め。これは史実ではなく、国風の記号化による世界観作りです。
編集部コメント:
「静の加賀、動の赤城」。このコンビ感は、“大量の航空隊を黙って回す”加賀という実像を、キャラの空気感でうまく伝えている良演出だと思います。
9-2 艦これの加賀:運用感を“装備スロット”で再現
- 大容量スロットの象徴:ゲーム上の搭載機スロットが大きいのが加賀の特徴。これは**“大船体=厚い一撃”という史実の強みを、そのままゲームメカニクス**に落とし込んだもの。
- 赤城とのセット運用:任務・編成ボーナスやイベントでも赤城とペアで扱われることが多く、六空母の記憶(真珠湾~ミッドウェー前)を想起させます。
- ストイックなセリフ回り:感情より機能、という**“現場の空気”**が台詞で表現されがち。ここも編集部的に“納得の解釈”。
史実との距離
- 合理的に“厚撃”を担うキャラ付けは◎。
- 一方、被害管制(ダメコン)や格納庫運用の危うさといった“弱点”はゲームでは深掘りされにくく、“強みの部分”が増幅されている印象です。
9-3 アズレンの加賀:世界観の記号性と“二人の加賀”
- 航空母艦・加賀(Sakura Empire):赤城と並ぶ主役格。狐意匠・和装に妖艶/寡黙が重なる表現で、**“神秘的な切れ味”**が演出されています。
- **戦艦・加賀(BB)の存在:アズレンには“戦艦案の加賀”**に相当する別個体が登場(イベント等)。**未成の戦艦としての“もしも”**をキャラ化したもので、設計図のロマンを二次創作的に拾い上げています。
- スキン・イベント:和風・狐面・神社モチーフなど、史実ではなく文化的記号で“サクラ帝国”を描くのが持ち味。
史実との距離
- 二人の加賀という発想は、史実の「戦艦として計画→空母に転身」を大胆にエンタメ変換した好例。
- ただし、装備・戦術の描写は演出優先。整備・補給・ダメコンの生々しさは意図的に薄められています。
編集部コメント:
“BB加賀”の存在は、模型界隈の未成艦キットと同じムーブ。**「図面のif」**を遊べるのはアズレンの強みですね。
9-4 ゲーム→史実へ“逆引き”するコツ(新規ファン向け)
- 「なぜ赤城と組むのか?」を史実で確認
→ 機動部隊の一体運用、真珠湾までの六空母という“回し方”を知ると、キャラの並べ方の意味がわかります。 - スロット=運用サイクルに置き換えて読む
→ 「大スロット=大搭載量=一撃が厚い」。加賀の役割が腑に落ちます。 - if(戦艦加賀)と現実(空母加賀)を分けて楽しむ
→ 土佐型戦艦としての数値ロマンと、空母加賀の“実戦の手触り”は別腹。混ぜないのが吉。 - 弱点もチェック
→ 格納庫の安全性・ダメコンの差がミッドウェーの鍵。“強みだけ”で見ないと、歴史が立体になります。
9-5 用語ミニ解説
- 擬人化:兵器の性能・来歴を人格やビジュアルに置き換えて伝える表現。強みの誇張と弱みの省略が起きやすい。
- if艦:未成艦・計画艦の「もし完成していたら」を前提にキャラ化/キット化した存在。創作の自由度は高いが、史実と混同しやすい。
9-6 編集部の総括
- 艦これは**“運用メカニクスで史実のポジションを伝える”**タイプ。
- アズレンは**“世界観とビジュアルで記号化する”**タイプ。
- どちらも**加賀=“厚い一撃を担うクールな主力”**という核を外していません。入口はエンタメでOK、奥座敷は史料。この往復がいちばん楽しい。
第10章 モデラー向け・おすすめプラモデルと製作のコツ
まずは結論:最短で“加賀らしさ”が掴めるのは1/700、作り応えの極みは1/350。そして三段飛行甲板期と**全通甲板(最終形)**のどちらを作るかを最初に決めると、道に迷いません。
10-1 キットの選び方(スケール別・時代別の“正解”)
A. 手軽に全体像を掴む(1/700・全通甲板=最終形)
- フジミ 1/700「航空母艦 加賀(フルハル)」
近年リニューアルのフルハル版。船体分割が素直で、初心者でも破綻せず“加賀のシルエット”に到達できます。発売情報はScalematesがまとまっていて便利(番号 45145)。
B. “過渡期のロマン”を味わう(1/700・三段飛行甲板)
- フジミ 1/700「加賀 三段飛行甲板 スペシャル」
文字どおり“実験時代”の加賀。甲板の段差や各層のサイズ感が立体で分かります。スペシャル版はエッチング同梱。
C. 作り応えの頂点(1/350・全通甲板=最終形)
- フジミ 1/350「航空母艦 加賀」
大面積の飛行甲板・格納庫ディテールまで作り込める名キット。大型故に“ディテールアップ沼”にもハマれます(在庫は流通ショップ・マーケットプレイスで確認)。アマゾン+1
価格や在庫は動きます。ビックカメラ/楽天/Amazon等の国内量販リンクやマーケットプレイスの在庫・価格も随時チェックを。
10-2 “伸びしろ”を足すなら:純正&社外ディテールアップ
- 1/350用 総合ディテールセット
Tetra Model Works SE-35008(木甲板・真鍮挽物・PEのフルセット)。“甲板の目地・ネット・ラッタル”が一気に実艦の空気に。レビューも豊富。 - 1/350用 木甲板単品
Shipyard 350020 木製甲板(フジミ用)。広い甲板は“木目の説得力”が命。貼るだけで写真映えが段違い。 - 1/700用 エッチング
Five Star Model 1/700 加賀用セット。手すり・ネット・小艤装の情報量が跳ね上がります。 - (参考)加賀用PEの新作・再販動向
2025年も国内ショップで加賀用PE+木甲板の新規入荷が確認できました(ホビーサーチの新着)。
編集部コメント:
“素組→手すり→木甲板→総合PE”の順で段階的に盛ると失敗が少ないです。いきなり全部盛りは作業密度>モチベになりがち。
10-3 塗装レシピの現実解(“工廠色”の扱い)
IJNグレーは4系統(呉/佐世保/舞鶴/横須賀)が定番の考え方。加賀は時期で塗装や整備拠点が変わるため、キットの指示色 or 作りたい時期の資料に合わせるのが安全策です。
- Mr.カラー系:C-32 横須賀工廠色、C-31 米海軍ダークグレー(1)、C-29 艦底色 など。
- TAMIYA/XF&LP系:XF-75(呉)/XF-77(佐世保)/XF-87(舞鶴)/XF-91(横須賀)、LP-15 横須賀 など。
- 新しめの専用色ライン(Acrylic等)も選択肢。
編集部コメント:
**“正解は一色ではない”**が現場感。キット説明書+近年の研究を両にらみで“あなたの加賀”の色を決めましょう。
10-4 マーキングの注意点(ミッドウェー日の丸など)
- ミッドウェー期の甲板識別:資料やキット解説では飛行甲板に“日の丸”を描いた例が紹介されます(艦によって差・時期差あり)。加賀もMI作戦仕様のキットでは甲板日の丸が示されることがあります。再現は資料確認のうえ自己判断で。
- “着艦円(Landing Circles)”:白い円形標識を描くケースも資料に見えます。時期差があるので必ずキットの指示&写真を参照。
- デカール補助:1/1800用ですが**甲板マーキング(真珠湾/ミッドウェー両対応)**デカールの例。パターンの把握に便利。
10-5 “破綻しない”組み立て順(編集部の手堅い手順)
- 時代設定を決める(三段甲板 or 全通甲板、真珠湾 or MI)
- 船体の歪み取り→甲板の反り矯正(大型面は先に整えておくのが吉)
- 甲板の着色&コーティング(木目+スミ入れ→つや消し)
- 艤装をブロック化(アイランド、クレーン、対空機銃スポンソンを別ユニットで仕上げ)
- エレベーター井桁の影色を先に吹いて、最後にフチを筆入れ
- エアグループ(零戦/九九/九七)は識別帯・隊長帯から先にデカール→つやで統一感
- 例:隊長機の水平尾翼3本線など、部隊標識の基礎知識も面白い。
失敗ポイント共有:
- 手すり先付け→指で曲げる事故が頻発。最後に一気付けが正解。
- **甲板ネットはPEの“伸び”**に注意。軽く曲げグセを付けてから瞬着点付け。
10-6 買うならどれ?編集部の“鉄板三択”
- 初心者の鉄板:フジミ 1/700「加賀(フルハル)」…破綻しない分割と最新リサーチ。
- 過渡期ロマン派:フジミ 1/700「三段飛行甲板 スペシャル」…“教科書の図”を立体で。
- 大型で作り込む:フジミ 1/350「加賀」+TetraのSE-35008…一生モノの作り応え。
第11章 まとめ:戦艦加賀が残した“転身”のレガシー
最初に立てたテーマは「戦艦加賀の解説」でした。結局のところ、“戦艦”加賀は未成、実戦を走り切ったのは“空母”加賀。ここが出発点であり終着点です。
本章では、これまで見てきた性能・比較・近代化・最後・現在を一度リセットして、“加賀という名前”が今も語られる理由を、編集部の視点で手短に総括します。
11-1 5つのキーインサイト(最短で本質)
- 図面のロマン × 現場のリアル
土佐型「戦艦加賀」は最強級スペックの志向を体現。一方で“空母加賀”は運用(回し方)で強さを作った艦。スペック≠戦果を教えてくれます。 - 近代化の核心は“サイクル”
三段飛行甲板から全通甲板+アイランドへの改装は、数字よりも航空サイクル最適化が効いた。エレベーター位置・弾薬/燃料動線の再設計こそ勝負所。 - “最強”は定義しだい
一撃の厚みでは加賀はトップクラス。継戦力(レーダー+ダメコン+被害管制)まで含めると、新鋭の翔鶴型や米ヨークタウン級が優勢――というのが冷静な結論。 - ミッドウェーの教訓は“壊れ方”
“甲板がぎっしり”の神話より、格納庫運用と防火・消火の冗長性不足という構造的弱点が火災拡大を招いた点が本質。運用文化も強さ/脆さを作る。 - 名前は生き続ける
海底の加賀と、令和の護衛艦「かが」。艦種・任務は違っても、「航空戦力を運用する大きな器」というスピリットは継承され、今の“最強”の定義を問い続けています。
編集部コメント:
「図面は理想、甲板は現実」。加賀の物語は、ミリタリーを学ぶうえでの最高の教材でした。
11-2 キーワードで振り返る(SEO要点の“再配置”)
- 戦艦/加賀/日本軍/大日本帝国:未成の土佐型戦艦という“原点”。
- 最強/性能/比較:一撃の厚み vs 継戦力の二軸で評価。
- 近代化:全通甲板化・機関更新・対空強化で主力化、ただし被害管制は最後まで課題。
- 最後/第二次世界大戦/太平洋戦争:ミッドウェーでの火災拡大が決定打。
- 現在:海底調査と**護衛艦「かが」**で“名前の連続性”。
- 艦これ/アズレン:キャラ化で“厚撃のクールさ”が普及、**if(戦艦加賀)**も楽しめる。
- おすすめプラモデル:1/700で“らしさ”、1/350で“作り応え”。ディテールアップは段階投入が吉。
11-3 “学び直し”の導線(これから深掘りしたい人へ)
- 一次資料優先:年表・装備・改装は一次史料/公式記録から。
- “運用”の視点:甲板サイクル、整備動線、被害管制の三点セットで読むと“数字”が立体に。
- 比較の癖付け:日本艦同士だけでなく、米英空母のレーダー/ダメコンを並べると“最強”の定義が変わる体験ができます。
- 模型で理解を固定:飛行甲板・エレベーター・格納庫を手で作ると、文章で読んだ弱点/強みが身体化します。
編集部コメント:
**“読む→作る→また読む”**のループが最短ルート。机上の加賀と、あなたの机の上の加賀を、往復してください。
11-4 用語ミニ解説(おさらい)
- 代艦案:条約/事故で建造中止の艦の代わりに別船体を転用する施策。
- 全通甲板:艦首から艦尾まで連続した滑走路。発着艦効率の基盤。
- デッキロード運用:甲板に載る分だけ一波ずつ回す空母運用。
- ダメコン(被害管制):損傷時の消火・排水・応急修理の総称。
- “最強”:火力・機動・防御・継戦・運用のどこを重視するかで答えが変わる“可変概念”。
11-5 編集部の締め
戦艦として“最強”を夢見て生まれ、空母として“厚い一撃”で戦果を出し、継戦の弱さで倒れ、名前は今に残る――。
加賀は、性能と運用、理想と現実、勝利と教訓の交差点に立つ艦でした。あなたが次に「最強」を語るとき加賀のことを必ず思い出してほしい。
そんなキザなセリフで、記事を締めさせて頂きます。
こちらの記事から他の戦艦の解説もご覧ください

おまけ:よくある質問(FAQ)
Q1. 「戦艦加賀」は実在した? 空母と何が違うの?
A. 実在は“未成艦”として。**土佐型戦艦(二番艦)「加賀」**は1920年起工・1921年進水しましたが、条約で戦艦としては完成せず、船体を転用して空母「加賀」として1928–29年に完成・就役しました。
戦艦=巨砲で殴る“砲戦プラットフォーム”、空母=航空機を運用する“打撃プラットフォーム”。同じ「加賀」でも艦種も戦い方も別物です。
Q2. どうして“最強”と言われることがあるの?
A. 戦艦案は41cm砲×10門/26.5kt級という“ロマン値MAX”。空母としても90機級の大搭載量で**「厚い一撃」が持ち味でした。
ただし“最強”の定義は火力だけでは決まりません。ダメコン(被害管制)やレーダー警戒を含む継戦力**まで入れると、翔鶴型や米ヨークタウン級が上というのが冷静な評価です(本文第5章)。
Q3. ミッドウェーで沈んだ一番の理由は?(一言で)
A. 急降下爆撃の集中直撃 → 甲板下(格納庫)の燃料・弾薬に火が入る → 消火・換気系が損傷して連鎖拡大 → ダメコン限界。夕刻、味方駆逐艦の魚雷で自沈処置(第6–7章)。
Q4. 「現在の加賀」って何を指すの?
A. 文脈で二つ。
- 海底の“加賀”:2019年にミッドウェー海域の水深約5,400mで本体発見、2023年にROVで詳細可視化。
- 海自の「かが」(DDH-184):いずも型二番艦。F-35B対応改修を進める“令和の加賀”。名前は継承でも、**法制度・役割(護衛艦)**は別(第8章)。
Q5. 赤城と加賀、どっちが強い?
A. 状況次第。「一撃の厚み」は加賀(大搭載量)、「追随性・旗艦適性」は赤城(速力・指揮設備)。どちらも格納庫運用とダメコンの脆さは共通の弱点(第5章)。編集部の雑感:ペアで回して強い二枚看板。
Q6. インド洋作戦(1942年4月)に加賀は出た?
A. 不参加。2月の損傷修理で佐世保ドック入りしていました(第6章)。
Q7. 当時の運用で“神話”と違った点は?
A. よくある「甲板ぎっしり爆装機」は再検証で修正。日本空母の基本は**“デッキロード”=一波ずつ回す運用で、被弾時甲板は空に近かった可能性**。問題は甲板下(格納庫)での再武装・給油文化でした(第7章)。
Q8. プラモデルは何から始めればいい?(おすすめ)
A. 迷ったらこの三択(第10章)。
- 入門:フジミ 1/700 加賀(最終形/フルハル)
- 過渡期ロマン:フジミ 1/700 三段飛行甲板 スペシャル
- 作り込み:フジミ 1/350 加賀 + Tetra総合PE
ディテールアップは素組→手すり→木甲板→総合PEの順で段階投入が安定。




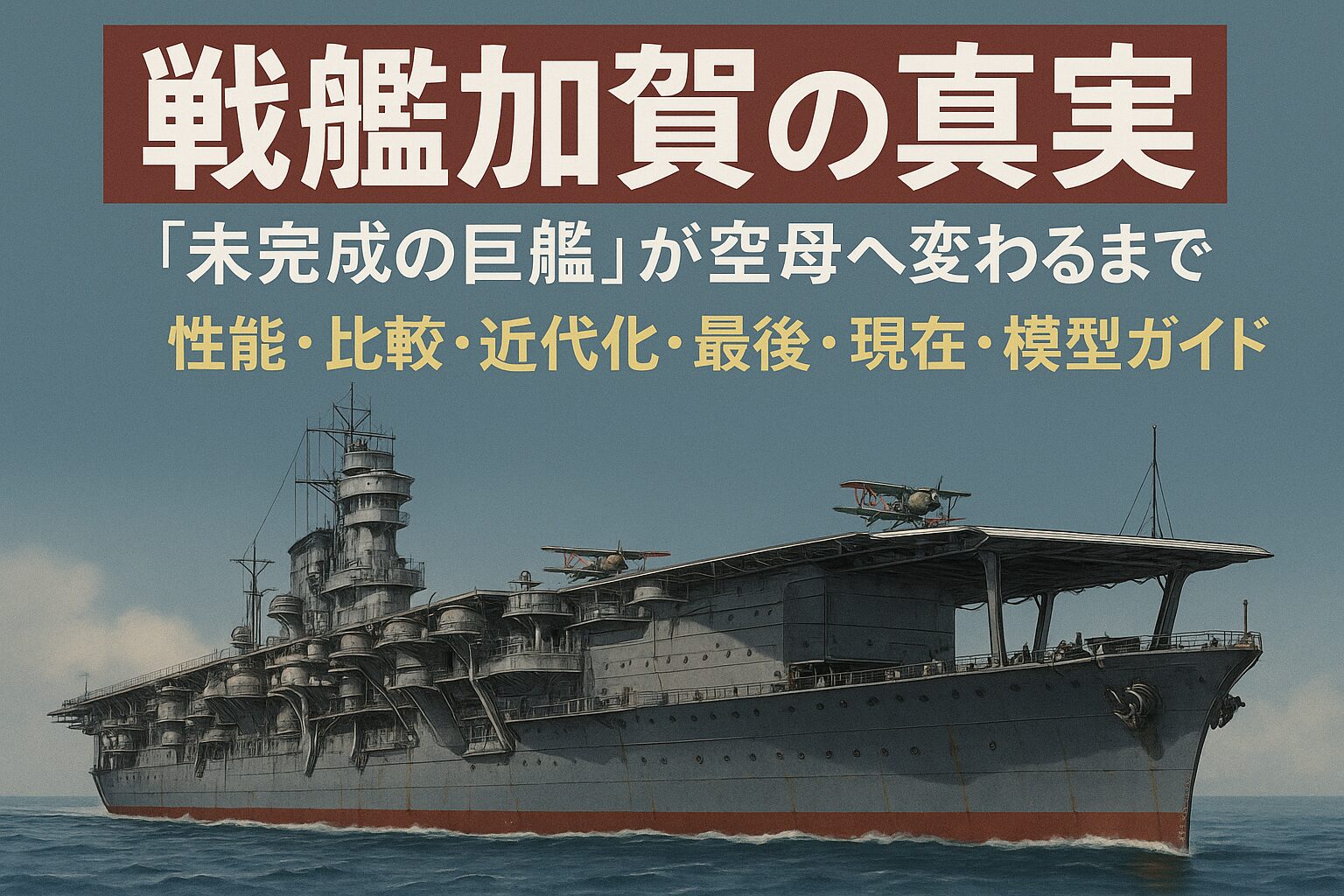








コメント