大艦巨砲の時代に生まれ、最後は“空を見上げた戦艦”。――
「戦艦伊勢」「戦艦日向」は、主砲12門を誇る純粋な戦艦として誕生しながら、太平洋戦争の荒波の中で“航空戦艦”へと姿を変えました。扶桑型の改良として設計され、長門型へ至る“橋渡し”を担った伊勢型。その性能と活躍、2隻の違い、そして最後(沈没/着底)までを、史実と模型・ゲームの視点からやさしく深掘りします。
伊勢型戦艦とは?誕生背景と基本プロフィール

扶桑型の改良として生まれた伊勢型
伊勢型戦艦(伊勢/日向)は、先行の扶桑型をベースに改良された大日本帝国海軍の弩級戦艦です。設計の狙いは、主砲配置や防御・速力のバランス改善。両艦は14インチ(356mm)連装砲×6基=12門を一直線に配した“長艦橋・六連装砲塔”スタイルで、のちの近代化で“パゴダマスト(多段艦橋)”を備える典型的な日本戦艦のシルエットへと成長しました。伊勢型は扶桑型の改良であり、のちの長門型へ至る中間世代として位置づけられます。ウィキペディア+1
用語ミニ解説
・弩級戦艦(どきゅう):ドレッドノート型に代表される“主砲多数・高速”志向の近代戦艦。
・パゴダマスト:改装で増設された多層式の艦橋構造。索敵・射撃指揮設備の搭載スペースを確保する狙い。
建造と就役年(年表で把握)
- 伊勢:1915年5月5日起工(川崎・神戸)/1916年11月12日進水/1917年12月15日就役。ウィキペディア
- 日向:1915年5月6日起工(三菱・長崎)/1917年1月27日進水/1918年4月30日就役。ウィキペディア
両艦とも第一次大戦末期~戦後直後に就役し、1920年代はシベリア出兵支援や震災救難などにも従事。1930年代の段階的改装で、バルジ装着・装甲強化・機関換装といった近代化を受けます。結果として、全長は約215.8m、基準外形寸法や吃水も拡大、深負荷排水量で約4.27万トン規模へ。機関は石炭混焼→重油専焼となり、速力は実測で約25ノット級に達しました(伊勢公試25.3kt記録)。
用語ミニ解説
・バルジ:水線下に付加する膨らみ。魚雷の爆圧を減衰し、復元性(安定)も改善。
・基準排水量/深負荷排水量:装備・燃料搭載量による排水量の基準。記事内では大まかな規模感を示すため“深負荷”を併記。
兵装とレイアウトの特徴(“六連装砲塔”の意味)
就役時の主砲は356mm連装×6=12門。前方2基、中央2基、後方2基という縦一列配置が特徴で、艦中心線上に火力を集中できる反面、中央部の砲塔と煙突配置の干渉や、被弾時のリスク集中が課題でした。1930年代の改装で、高角砲(12.7cm両用砲)・25mm機銃の強化、魚雷発射管の撤去など対空・対水上戦闘の再最適化が進みます。ウィキペディア
用語ミニ解説
・両用砲(DP):対艦・対空の両任務に対応する砲。日本海軍では12.7cm高角砲が主力。
“航空戦艦”化への伏線
伊勢型を語るうえで外せないのが航空戦艦化。ミッドウェーの大敗(1942年6月)で空母戦力を急速補填する必要が生じ、後部主砲2基(第5・第6砲塔)を撤去し短い飛行甲板+2基の回転式カタパルトを載せる“ハイブリッド”改装が決定。発艦は可能だが着艦は不可という割り切りの運用構想でした(艦上では彗星(D4Y)や瑞雲系/晴嵐系の運用が想定されたが、実戦配備・練度・機材不足で運用は限定的)。ウィキペディア+2navweaps.com+2
ここがポイント
・“戦艦の火力”と“航空の目(索敵・打撃)”を一体化する苦肉の設計。
・発艦偏重(片カタパルト運用が実質的限界)で、本格空母の代替には非力だったのが実情。
H2 「性能」をやさしく解説:伊勢型の船体・装甲・兵装
まず“最終形(1944–45年の航空戦艦状態)”を念頭に、伊勢・日向の基本的な性能像をつかみましょう。
※数値は改装段階や資料によって差があります(特に“幅”)。代表値は下記参照。
- 排水量(深負荷):約4.2万トン級/全長:219.62m(飛行甲板増設後)
- 幅:31.7m(英語版資料の代表値)〜33.83m(日本語資料の代表値)
- 速力:おおむね25ノット(80,000shp)/航続距離:16ノットで約9,000〜9,500海里
- 乗員:1,400名台後半(期末1,463名の記録あり)
- 航空設備:カタパルト2基+搭載想定22機(実戦運用は限定的)
出典例:英語版・日本語版「伊勢型戦艦」・「伊勢」項に基づく代表値。ウィキペディア+3ウィキペディア+3ウィキペディア+3
H3 主砲・副砲・高角砲の配置と“性格”
- 主砲(就役時):356mm(14インチ)連装×6=計12門。1〜6番砲塔を艦中心線上に縦一列で配し、強力な正横一斉射を得る一方、艦中央の砲塔は煙突・上部構造物との干渉や被害集中の懸念がありました。砲そのものは四一式45口径(36cm/45)系で、近代化で仰角拡大・弾薬改良が進みます(後部2砲塔は構造深さの制約で一部改修が制限)。ウィキペディア+1
- 副砲(改装前):14cm単装×20門のケースメイト配置 → 1930年代改装後は14cm×16門に減少。ウィキペディア
- 両用高角砲(対空主砲):改装で12.7cm/40(八九式)連装×4基=8門(のち増備)を装備。以降は25mm機銃(九六式)を連装→三連装主体で多数増設し、**1944年には“31基三連装+11基単装=計104門(銃身)”**規模まで膨張。ウィキペディア
- 航空戦艦化による射界の変化:艦中央寄りの両舷カタパルトが中部砲塔の射界を部分的に制約。純戦艦時代に比べ、総合火力・射撃自由度は“やや目減り”します。ウィキペディア
用語ミニ解説
両用砲(DP)=対艦・対空に使える主に12.7cm級の砲。
ケースメイト=舷側の砲郭(開口)に副砲を収める配置。荒天時の運用に弱点。
H3 防御:装甲と浮力保持の“和の鎧”
- 主装甲帯:水線装甲299mm(ヴィッカース硬化装甲)。上下に100mmの下帯や斜め装甲 deckを組み合わせる日本流の多層防御。ウィキペディア
- 甲板装甲:改装で機関部・弾薬庫上を合計140mm級まで強化(多層)。砲塔天蓋も増厚。ウィキペディア
- 対魚雷・被害制御:バルジ増設に加え、二重底の深さを3.58m(弾薬庫周り)へ拡大、水密区画は660室に達し粘り強い浮力保持を狙いました。ウィキペディア
H3 推進・速力と改装の“効き目”
- 機関:重油専焼ボイラー8基+ギヤード・タービン4基/4軸で80,000shp。近代化前の混焼から更新し、25ノット級へ。ウィキペディア
- 航続性能:16ノットで約9,000〜9,500海里の代表値。改装に伴う重量増と艤装変更を、機関更新と船体改良で相殺した“実用速度域の維持”が特徴です。ウィキペディア+1
H3 近代化改装で“何が変わった”?
- 1930年代の第一次大改装
- 装甲強化(甲板多層化/増厚)、機関換装、パゴダマスト化、対空装備追加、魚雷発射管撤去。結果として25ノット・**航空作業(射出機1基/水偵3機)**が可能に。ウィキペディア
- 1943–44年の航空戦艦化
- 後部主砲2基撤去+70m級飛行甲板+回転式カタパルト2基を新設。搭載想定はD4Y「彗星」×11+E16A「瑞雲/景雲系“Paul”」×11=計22機だが、機材不足と練度問題で実戦発艦はほぼ無し。また中部主砲の射界制約・対空火器偏重など“攻守の再配分”が性能上の個性になりました。ウィキペディア
- 砲の細かな違い
- 主砲の仰角拡大などの改修は後部2砲塔では構造制約あり(十分な深さが確保できず)。これは実戦での遠距離交戦力に、わずかながら影響しました。navweaps.com
要するに――
伊勢型の「性能」は、堅実な防御と25ノット級の巡航力を基盤にしつつ、航空戦艦化で“艦砲火力の一部を航空・対空力へ置き換えた”点が肝。紙の上では“なんでも屋”ですが、射界制約や航空機・人員の不足が重なり、純戦艦/純空母の代役としては限界がありました。
H2 太平洋戦争での「活躍」:各作戦の足跡
H3 開戦〜1943年:出撃は少なくも“要所の後方支援”
- 日向は開戦直後、真珠湾攻撃の“遠距離支援”として小笠原方面へ出動。その後もしばらくは大決戦に出番はなく、戦列保持と訓練が中心でした。ウィキペディア
- 伊勢・日向はいずれも第二戦隊として、ドーリットル空襲(1942年4月18日)に対する追撃出動や、ミッドウェー作戦期のアリューシャン支援部隊同行など、戦略規模の作戦に“後備戦力”として関与します(交戦自体は限定的)。ウィキペディア
- 1942年5月、日向の第五砲塔で爆発事故(戦死51)。これがのちの航空戦艦化へと舵を切る一因になりました。ウィキペディア
H3 1943–44年:航空戦艦として戦列復帰、しかし航空戦力は伸び悩み
- 後部主砲2基を撤去して短甲板+回転式カタパルト×2を備える“航空戦艦”へ改装。搭載予定の**D4Y「彗星」やE16A「瑞雲」**は陸上基地を拠点に訓練する場面が多く、艦上での実戦運用は十分に整いませんでした。ウィキペディア
H3 レイテ沖海戦(エンガノ岬沖、1944年10月):囮部隊の中核
- 連合艦隊は**小沢治三郎中将の“北方(主隊)”**に空母と伊勢・日向(第四航空戦隊)を集め、囮作戦で米機動部隊を北へ引き離す計画を採用。出撃時、伊勢・日向には実質的な艦載機が搭載されておらず、対空砲火と煙幕、回避運動で艦隊を守る役回りでした。ウィキペディア+1
- 10月25日の攻撃では、空母群(瑞鶴・瑞鳳・千歳・千代田)が次々撃沈される一方、伊勢・日向は爆弾命中や至近弾を受けつつも生還。囮としての任務は達成したものの、制空を持たない“航空戦艦”の限界が露わになりました。ウィキペディア+1
H3 1944年末〜45年初頭:南方展開と「北号作戦」
- レイテ後、両艦は東南アジア方面(リンガ泊地など)へ展開。**1945年2月の「北号作戦」**では、伊勢・日向・軽巡「大淀」ほかがシンガポールから日本本土へ戦略物資(ガソリン・ゴム・錫 等)を強行輸送。連合軍は潜水艦と航空で待ち伏せしたものの、両艦は無事内地へ到着しました。ウィキペディア+2combinedfleet.com+2
H3 1945年:燃料欠乏下の“浮き要塞”化と対空戦
- 帰投後は燃料・航空機ともに欠乏し、呉・広島湾で事実上の対空砲台(浮き要塞)に。3月19日の呉空襲で日向が爆弾3発命中の被害。以降はカモフラージュ・曳航移動で温存されます。combinedfleet.com
- 7月24日・28日の連続空襲(呉・瀬戸内海空襲)で両艦とも浅い海で沈座。伊勢は7/24に小破(1発)・7/28に8発命中で沈没、日向は7/24に10発・7/28に多数命中し、広島湾で沈座しました。ウィキペディア
まとめ:“活躍”の実像
・戦前設計の堅艦として戦列を保ち、囮作戦(レイテ)や資源輸送(北号)など戦略上の要所を支えたのが伊勢型の持ち場。
・しかし、航空戦艦という“折衷案”は、航空機・燃料・練度の不足の前に力を発揮できず、終盤は本土防空の要塞化に傾きました。
H2 「最後」と「沈没」:呉空襲で迎えた伊勢型の最期

1945年夏、瀬戸内海は“動かぬ巨艦”を狙う空の戦場になりました。燃料も航空機も尽きた伊勢と日向は、**呉空襲(7月24・28日)**で浅海に沈座——“沈没=着底”という結末を迎えます。ここでは、いつ・どこで・何が起きたのかを時系列で整理します。
H3 3月19日:予告編のような初撃(TF58空襲)
- 連合軍の大規模空襲が呉を初めて叩いたのは1945年3月19日。この攻撃で伊勢に2発、日向に3発の命中弾。いずれも戦闘力を根こそぎ奪うほどではないものの、以後の“止め”を予感させる被害でした。ウィキペディア+1
H3 7月24日:第一次呉空襲—“浮き要塞”の抗戦
- 終戦間近の7月24日、米機動部隊(第3艦隊/TF38)は呉軍港・広島湾一帯の残存艦艇を重点攻撃。
- この日の戦果一覧でも、**「伊勢:1発(軽損)」「日向:10発(大破)」**が明記されています。ウィキペディア
H3 7月28日:第二次呉空襲—“止め”の一撃
- 7月28日、再び航空隊が襲来。
- 攻撃全体の戦果集計でも、**「伊勢:28日に8発命中・その場で沈没」「日向:24日に10発命中・広島湾で沈座」**という整理になっています。ウィキペディア
ミニ解説:沈没と着底
深海に没して行方不明になる“沈没”に対し、浅海で海底に座り込むのが“着底”。記録上は「沈没」と記されても、写真で艦体が見えるのはこのためです(上の航空写真参照)。ウィキペディア
H3 その後:除籍・解体と“戦跡”としての記憶
- 除籍:両艦とも1945年11月20日付で除籍。ウィキペディア+1
- 解体:戦後、播磨造船(呉造船所)が現地で解体。伊勢は1946年10月9日~1947年7月4日、日向は1946年7月2日~1947年7月4日にかけて撤去されました。ウィキペディア+1
- どこで沈んだ?
要するに——
伊勢は24日中破→28日とどめで沈没(音戸瀬戸)、日向は24日の集中被弾で致命傷→数日かけて広島湾で沈座。どちらも“海に消えた”のではなく、浅海で身を横たえ、戦後まで姿を留めたのが「最後」の実像でした。
H2 「違い」はどこにある?――伊勢と日向を並べて見分け方を探る
“同型艦=同じ”ではありません。建造所や改装タイミング、事故・装備更新、旗艦経験、戦末の被害状況まで、伊勢と日向にははっきりした差分があります。要点をコンパクトに整理します。
H3 年表で見る“決定的イベント”の差
- 日向:第五砲塔の爆発事故(1942年5月)
砲術訓練中に第五砲塔の薬室が破裂し51名戦死。後部弾薬庫を急速注水で救い、第五砲塔は撤去→防楯板で塞ぎ25mm三連装機銃を増設。この事故が、のちの後部2砲塔撤去=航空戦艦化を後押しした現実的要因になりました。ウィキペディア - 改装ヤードと時期
伊勢は呉海軍工廠で1943年2月~10月にかけてハイブリッド化(後部2砲塔撤去・短甲板+回転カタパルト2基)。ウィキペディア
日向は佐世保海軍工廠で1943年5月~11月に同様の改装。改装場所と時期の差は、のちの装備更新(対空火器・レーダー)のタイミング差にもつながります。WW2DB
H3 レーダー・電探の“時期差”:誰が先に何を付けた?
- 伊勢:1942年2月の機関室浸水事故の修理中に、実験用の九三式電探(Type 21)を一時搭載→のち撤去。1944年5月に二二号(Type 22)×2、7月に十三号(Type 13)×2と**敵味方識別(Type 2 IFF)**などを順次追加。ウィキペディア
- 日向:1942年5月の砲塔事故修理中に、実験的な二二号(Type 22)を一時搭載→のち撤去。最終形(1945年時点)では二一号×1、十三号×2、二二号×2という“空・水上監視のフルセット”構成でした。ウィキペディア+1
ひと口メモ
Type 21=初期の対空警戒用(長波・早期警戒)。
Type 22=対水上目標探知・測距寄り。
Type 13=簡素・長波の早期警戒。
いずれも性能は米英に劣り、運用熟度と対空火力の総合で埋めるのが日本海軍の実情でした。
H3 旗艦経験・運用ポジションの違い
- 伊勢は1941年11月に第一艦隊・第二戦隊の旗艦となり、開戦時から“戦列の要”として位置づけ。CombinedFleetの記録でも、**「第一艦隊の旗艦(BatDiv2)」**と明記があります。ウィキペディア+1
- 日向は平時・戦時を通して旗艦任務の記録は限定的ですが、1944年夏には第四航空戦隊の旗艦として記録され、“航空戦艦隊”の看板を務めました。ウィキペディア
H3 対空兵装の違い(最終形)
- 共通点:両艦とも12.7cm両用砲×8(連装×4)と25mm機銃の大増備(三連装主体+単装)で“浮き要塞”化。
- 微差:換装時期のズレにより、機銃の台数・配置、電探の取り付け位置に小さな差。記事「性能」章で触れた通り、1944年~45年の代表値ではいずれも25mm銃身100本級に達します(伊勢の1944年6月時点で104挺)。ウィキペディア
H3 レイテ沖・戦末の“当たり方”の差
- エンガノ岬沖(1944年10月)では両艦とも艦載機をほぼ積まず、囮主力の艦隊防空に徹しました(これは“航空戦艦”構想の逆説)。ウィキペディア
- **呉・広島湾の空襲(1945年7月)**では、日向が24日に10発直撃で致命傷→数日かけて沈座、伊勢は24日小破→28日の追撃で多数命中し音戸瀬戸で沈没(着底)という被害推移の違いが最後まで残りました。ウィキペディア
H3 建造所・艦内文化・名前の由来(小ネタ)
- 建造:**伊勢=川崎(神戸)/日向=三菱(長崎)**という“関西二大造船所のライバル”。ウィキペディア+1
- 由来:伊勢は伊勢国、日向は日向国にちなむ“旧国名ペア”。(日本の戦艦は旧国名・県名からの命名が原則)ウィキペディア+1
- 艦内“らしさ”:日向は砲塔事故が艦の人生を大きく変え、伊勢は戦隊旗艦としての儀礼・行事の記録が比較的豊富(例:1922年に伊勢が皇太子(後のエドワード8世)を接遇)。
まとめ(違いの要点)
- 日向は砲塔事故→後部撤去の既成事実化、伊勢は旗艦色が強い。
- レーダーは伊勢がType21、日向がType22を先に“お試し”→いずれも1944年にType22/13を本格装備。
- 改装ヤード・時期差が“細部の違い”(対空兵装・電探の取り付け、作戦期の装備密度)を生んだ。
H2 「現在」どう語られる?資料・遺構・見学アイデア
結論から言うと、実艦の大きな遺構は残っていません。両艦とも戦後に現地解体されました。ただし、**資料・写真・“現場の地形”**から伊勢・日向の「最後」をいまも辿れます。
H3 まずは“現地”へ:呉でたどる伊勢型の痕跡
- 大和ミュージアム(呉市海事歴史科学館)
呉軍港と大規模空襲の流れを学ぶ拠点。2025年2月17日〜2026年3月末ごろまで本館は改修休館、期間中は代替展示の**「Yamato Museum Satellite」**が開設されています。訪問計画は最新の案内をご確認ください。 yamato-museum.com - 海上自衛隊 呉史料館(てつのくじら館)
呉と海自の歴史を通史で展示。隣接で回りやすく、潜水艦「あきしお」の実艦展示も。伊勢・日向“単体”の展示は限定的ですが、呉の軍港史を立体的に掴めます。 jmsdf-kure-museum.go.jp+1 - 音戸の瀬戸公園(展望)
伊勢が最終的に沈座した海域=音戸の瀬戸を一望。海峡の地形を眺めると、浅海に“着底”した理由が腑に落ちます(眺望スポット情報)。 ウィキペディア+1
ワンポイント
・伊勢は音戸の瀬戸で沈座(のち現地解体)。日向は広島湾内浅海で沈座。どちらも“深海に消えた”のではなく浅海で横たわったのが実像です。写真・記録で位置関係を確認すると現地の理解が早いです。 ウィキペディア+1
H3 デジタルで“最後の姿”を見る:公的フォト&空撮
- 米海軍 歴史遺産司令部(NHHC)の戦後撮影:
1945年10月撮影の伊勢(音戸の瀬戸沖)、**日向(呉沖)**の航空写真が公開。シルエットや周囲の浅瀬がよくわかります。 海軍歴史センター+1 - World War II Database(WW2DB):
1945年夏〜秋の呉空襲後の港湾や日向の沈座写真がまとまっています(出典は米海軍や航空博物館コレクション)。 WW2DB+2WW2DB+2 - 国土地理院・空中写真(1945〜50):
終戦直後の呉周辺の空中写真を公開。現在の地図タイルと重ねながら、どの入江・水道に艦が横たわっていたかを地形から復元できます。 e-Govデータポータル+1
H3 史料を“一次資料”から当たる:無料アーカイブ活用術
- アジア歴史資料センター(JACAR)
旧海軍の公文書や写真・地図のデジタル化ポータル。艦名(例:「伊勢」「日向」)や作戦名、部局名(軍令部・第二戦隊など)で検索。 アジア歴史資料センター+1 - 防衛研究所(NIDS)・戦史叢書/戦史史料検索
太平洋戦争の公式戦史集成**『戦史叢書』**のデジタル閲覧や、所蔵史料の横断検索が可能。海軍作戦の通史と照合できます。 防衛省ネットワーク情報システム+1 - 国立公文書館デジタルアーカイブ
官公文書・地図・写真などの横断閲覧口。JACARと合わせて使うとヒット率が上がります。 デジタルアーカイブ - CombinedFleet.com(TROM)
伊勢・日向の**行動年表(Tabular Record of Movement)**で日付・位置・被害状況の整理に便利。一次史料ではありませんが、検索の道標として優秀。
H2 ゲームで知る伊勢・日向:艦これ/アズールレーン
史実で“航空戦艦”となった伊勢・日向は、ゲームでも**「艦砲+航空」ハイブリッドの個性で描かれます。ここでは艦これ(KanColle)とアズールレーン(アズレン)**の表現・強みの違いを、要点だけサクッと整理。
H3 艦これ:改二で“海空立体攻撃”を使える航空戦艦に
- 実装と改二
- 伊勢改二:2018年6月13日実装。en.kancollewiki.net+2ととねこのゲーム攻略所+2
- 日向改二:2019年3月27日実装。en.kancollewiki.net+2WIKIWIKI+2
- 専用カットイン
改装航空戦艦の伊勢改二/日向改二は、装備条件と制空状態を満たすと**「海空立体攻撃(瑞雲立体攻撃)」が発動。昼戦で艦砲+艦載機を組み合わせた独自の一撃を繰り出します。運用の肝は制空補助(瑞雲等)と主砲の両立**です。WIKIWIKI - 担当CV・イラスト
2隻ともCV:大坪由佳、イラストはしばふ担当(九周年ビジュアル等でも言及)。ウィキペディア+2X (formerly Twitter)+2
ひとこと攻略:
航戦2隻で制空補助→昼連撃/カットインの土台を作ると、イベント海域の道中安定に効きます。瑞雲・水戦の熟練度と索敵値の確保を忘れずに。WIKIWIKI
H3 アズールレーン:レトロフィットで“BBV(航空戦艦)”化
- 基本像
アズレンでは伊勢/日向とも戦艦スタート。**レトロフィット(改造)で航空戦艦(BBV)**に強化でき、**艦載機による空襲(Airstrike)**や固有スキルを獲得します。アズールレーンウィキ - 伊勢(Retrofit)
スキル**「Aviation Battleship Fleet(改造で解禁)」により、最初の2回の空襲の装填短縮+「彗星」追撃機を追加発艦。艦隊に空母系がいれば全空襲に効果拡張され、“艦砲+空襲”の回転が良くなります。基礎スキル「Cover Fire」**で自艦の火力バフも可。艦船少女情報サイト - 日向(Retrofit)
「Artillery Command: Main Fleet」で主力(後列)全体の火力を底上げ。さらに改造後スキル「Melee Artillery」で近距離バラージ(一定間隔で自動発動)を獲得し、防空と接近戦の面制圧に強み。艦船少女情報サイト - 分類・データ参照の目安
Koumakan系/Fandom系のIse/Hyuuga個別ページやスキル一覧で、効果文と倍率を確認すると編成最適化が速いです。艦船少女情報サイト+2艦船少女情報サイト+2
ひとこと編成:
・伊勢(改造)+空母1以上の主力で空襲回転をブースト → 道中掃除が快適に。
・日向(改造)は主力火力バフ+近距離バラージで弾幕タンク寄り。**扶桑・山城(改造)**らのBBVと並べ、艦攻・艦爆の補助を分担すると扱いやすいです。艦船少女情報サイト+1
H3 小まとめ:ゲームで見える“伊勢型の個性”
- 艦これでは**史実の航戦化→「海空立体攻撃」**という“ハイブリッドの妙味”がそのままギミック化。
- アズレンではレトロフィットでBBV化し、伊勢=空襲回転の加速/日向=主力バフ+近距離弾幕という姉妹で役割差が明快。
- どちらも**「艦砲+航空」運用をどう噛み合わせるか**が楽しみどころです。
H2 初心者向け「おすすめプラモデル」&制作のコツ
まずはどの姿を作りたいかを決めましょう。
- 12門の主砲をそなえた戦艦時代(〜1942)か、後部砲塔を撤去し甲板とカタパルトを載せた航空戦艦(1944)か。──答えが決まるとスケール選び(1/700 or 1/350)**もすんなり決まります。
迷ったらこの9点(定番だけピックアップ)
後ほど記載予定
どう選ぶ?かんたん指針
- 最短で完成したい(入門)
→ ハセガワの1/700 戦艦 伊勢/日向は部品点数が穏当で扱いやすい価格帯。“戦艦時代”の迫力が手早く味わえます。 - 史実の“航戦”が作りたい(中級)
→ フジミの1/700 航空戦艦 伊勢/日向(1944)は後部甲板・カタパルト・対空火器がしっかり形になります。 - 存在感重視(上級)
→ 1/350の伊勢/日向は全長60cm級。配線・艦載機・手すりまで作り込むと**“浮き要塞”の密度**を再現可能。 - もう一歩上へ(ディテール追加)
→ 1/350艦橋セット/1/700装備セットで25mm機銃や探照灯、測距儀を強化すると1944–45年の密集感が一気に出ます。
製作のコツ(“航戦”らしさを引き出すチェックリスト)
- 時代を決めてから資料集め
レイテ直前(1944秋)と終盤(1945夏)では機銃の密度・電探位置が違います。作例写真を1–2枚“基準”に選定。 - 甲板色の作り分け
艦首〜中央は木製甲板、後部短甲板(飛行甲板)は鋼板+非滑走塗装の表現に差を出すと“航戦”感がグッと増します。 - カタパルトとクレーンを細く見せる
成形色のままより、ダークグレー→エッジに薄いグレーでドライブラシ。陰影が立ってメカ感UP。 - 25mm機銃は“まとまり”で見せる
三連装は銃身端の黒鉄色+台座はやや明るめで塗り分け。乱立する機銃群が**“面”として映ります。** - 主砲の砲口開口
0.8–1.0mm程度のピンバイスで軽くさらうだけでも精密感が段違い。 - 艦載機(瑞雲・彗星)の透明部
キャノピーの枠は半艶の濃グレーで細線塗装。プロペラ端に赤帯を入れると写真映えします。 - スミ入れは控えめに
実艦は海上で汚れが流れやすい。甲板は薄茶、艦体はニュートラルグレーで細線にだけ流すのが上品。 - アンカーチェーンと空中線
チェーンは黒鉄+銀で軽いドライブラシ。空中線は0.06〜0.08mmの糸(または伸ばしランナー)で最少限に。 - “戦艦時代”と“航空戦艦”の違いを意識
後部砲塔が2基あるか、短い飛行甲板+カタパルト×2か。ここを外さなければ全体の印象は迷いません。 - 最後のワンポイント
艦橋窓のクリア感(光沢ニス)と信号旗(薄紙の自作)を足すと、撮影したときの“情報量”が跳ねます。
ゲーム勢向けミニTip:
艦これ/アズレンの“航戦イメージ”を模型に移すなら、機銃と電探を少し盛る・艦載機を2–4機見える位置に置く──これだけで**“らしい”伊勢型**に仕上がります。
H2 まとめ:伊勢型が残したもの
“戦艦から航空戦艦へ”。伊勢型は、日本海軍が太平洋戦争(第二次世界大戦)の現実に追い込まれながら模索した苦心の回答でした。
- 位置づけ:扶桑型の改良として生まれ、長門型へつながる中間世代の戦艦。
- 性能:356mm連装×6=12門の火力と25ノット級の速力、堅実な防御。改装で対空火力と電探を増備。
- 航空戦艦化:後部砲塔2基を撤去し短い飛行甲板+カタパルトを装備。発艦はできるが着艦できないという割り切りが、のちの運用限界に直結。
- 活躍:序盤は戦列温存と後方支援、レイテ沖(エンガノ岬)では囮部隊の中核として生還。北号作戦では戦略物資輸送を完遂。
- 最後(沈没/着底):**呉・広島湾空襲(1945年7月24日/28日)で浅海に沈座(着底)**し終戦を迎える。
- “違い”:日向の第五砲塔事故が改装判断を後押し/伊勢は旗艦色が強い。電探や対空兵装は時期差による小さな違いが点在。
- 現在:実艦遺構は解体済みだが、写真・公文書・博物館展示で足跡を辿れる。
- ゲーム&模型:艦これの「海空立体攻撃」、アズレンのBBV化で“艦砲+航空”の個性が光る。おすすめプラモデルは1/700の入門から1/350の大型まで幅広い。
要するに──伊勢型は「時代に合わせて自らを作り替えた戦艦」。その試行錯誤は、いま史料・艦これ/アズレン・模型づくりの三方向から、私たちに鮮やかに“再現”されています。
H2 よくある質問(FAQ)
Q. 伊勢と日向の一番大きな“違い”は?
A. 戦中の第五砲塔事故(日向)が象徴的。これが後部砲塔撤去→航空戦艦化の“現実味”を増しました。運用面では伊勢が旗艦経験多め、装備は導入時期のズレで小差が出ます。
Q. 航空戦艦は実戦で役立った?
A. **索敵・対空強化の“補助戦力”**としては機能しましたが、艦載機・燃料・練度不足の壁が厚く、空母の代替にはなりませんでした。
Q. 「最後」は沈没?着底?
A. いずれも浅海での着底=沈座。記録上は「沈没」と表記されつつ、海面上に艦体の一部が残る状況で終戦を迎え、戦後に現地解体されています。
Q. “伊勢型の性能”をひと言で?
A. 頑丈で足もそこそこ速い(25ノット級)万能寄りの戦艦。近代化で防御・機関・対空を底上げし、終盤は対空火力の塊になりました。
Q. 艦これとアズレンでの立ち位置の違いは?
A. 艦これは改二で航戦化→「海空立体攻撃」のギミックが要。アズレンはレトロフィットでBBV化し、伊勢=空襲回転、日向=主力バフ+近距離弾幕という役割差が明快です。
Q. 初めて作るおすすめプラモデルは?
A. **1/700の“戦艦時代”キット(ハセガワ)**が扱いやすいです。航戦仕様を作りたいならフジミの1/700(1944)が定番。慣れてきたら1/350で存在感を楽しみましょう。
次の一手(深掘りしたくなったら)
- レイテ沖海戦(エンガノ岬沖)の戦術を俯瞰して、伊勢・日向の囮役の意味を再確認。
- 装備ピンポイント研究:Type21/22/13電探・25mm機銃の配置変化を年代別にスケッチ化。
- 模型派は**資料写真1〜2枚を“仕様の基準”**に決め、機銃密度と電探位置を合わせると“通”の仕上がりに。




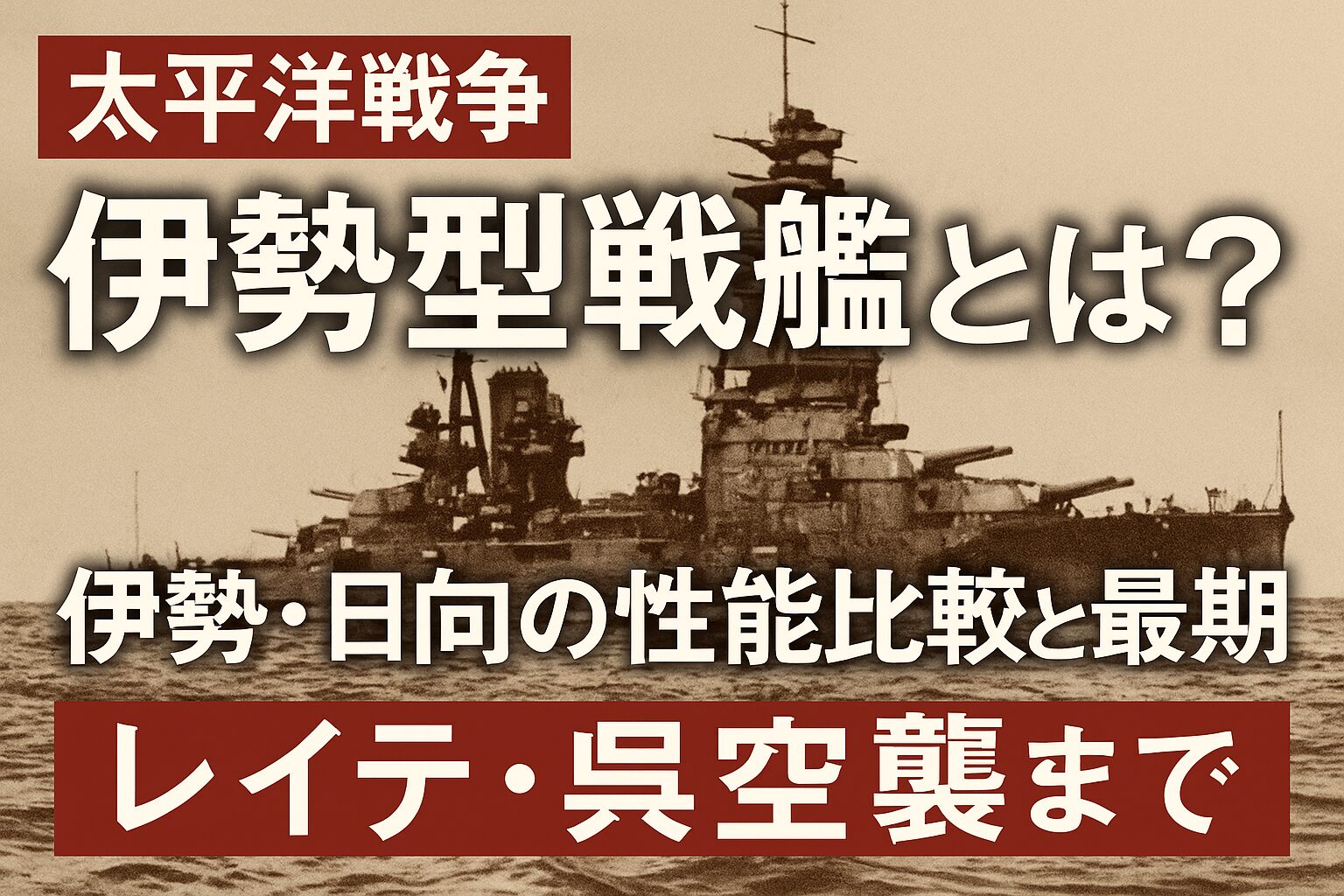








コメント