轟音とともに甲板が震える。艦隊の“拳”として世界を震撼させた空母「赤城」は、なぜ日本海軍の象徴となり、そしてミッドウェーで炎に包まれたのか――。三段飛行甲板から独特の下向き煙突、そして海底で眠る現在まで、“赤城”のすべてを一気に辿ります。
第1章 赤城の概要:数字で見るフラッグシップ
甲板を一陣の風が抜け、艦隊の主拳たる空母「赤城」が海面を切り裂く——。本章ではまず、赤城を“数字”で俯瞰します。検索ユーザーが最も知りたい「全長」「速力」「搭載機数」などを簡潔に押さえ、後章の設計・活躍・最期(沈没)へとつなげます。
基本スペック(改装後/太平洋戦争期の代表値)
- 艦種:航空母艦(空母)
- 全長:約 261 m
- 幅(ビーム):約 31 m
- 吃水:約 8 m
- 最大速力:31.5 ノット
- 航続距離:16ノットで約12,000海里
- 搭載機数の目安:60〜90機規模(時期・編成により変動)
- 乗員:およそ 1,600名
用語ミニ解説
ノット=1時間に海里(1,852m)を何マイル進むかを示す速度単位。吃水(きっすい)=船体が水中に沈む深さ。

時代の中での立ち位置(「加賀」との双璧)
- 赤城と加賀は、いずれも条約型戦艦・巡洋戦艦からの改装空母として誕生。三段飛行甲板→単一長大甲板への近代化改装を経て、開戦時の日本海軍機動部隊の中核を担いました。
- 赤城は左舷アイランド(艦橋)と下向き煙突という独特の外観で識別性が高く、同時代空母の中でも“シルエットでわかる”艦として有名です。設計上の試行錯誤と排気処理の工夫が背景にありました。米海軍研究所
「現在」につながる基礎情報(沈没と発見の要点)
- 最期(最後):1942年6月、ミッドウェー海戦で致命傷を負い、のちに味方駆逐艦の処分雷撃で沈没。詳細は第4章で扱います。
- 発見と調査:2019年、故ポール・アレン氏の調査船RV Petrelが水深約5,490mで沈没地点を特定。2023年にはE/V Nautilus(OET/NOAA)が初の本格可視化調査を実施し、損傷状況の高精細映像が公開されています。
この記事でわかること(ロードマップ)
- 設計と外観:三段甲板、左舷アイランド、下向き煙突の理由
- 活躍:真珠湾攻撃の旗艦からインド洋作戦までの戦歴
- 最後と沈没:被弾〜大火災〜総員退艦〜自沈の流れ
- 現在:海底映像・写真の安全な入手先
- 加賀との違い:運用思想・外観の識別点
- カルチャー:「艦これ」「アズレン」に見える赤城像
- 模型:おすすめプラモデルと“赤城らしさ”の再現ポイント
第2章 設計と外観の特徴
爆音と熱風の坩堝——空母「赤城」の“らしさ”は、設計のディテールに宿ります。本章では三段飛行甲板から単一長大甲板への改装、左舷アイランド(艦橋)と下向き煙突という独特のシルエット、そして武装や格納庫配置など“性能の裏側”を、写真を見るときやおすすめプラモデルを組むときの着眼点も交えて解説します。
三段飛行甲板から単一長大甲板へ
- 当初(就役時):赤城は上・中・下の三段飛行甲板を持つ実験的レイアウトでした。下段は主に艦上戦闘機の短距離発艦に使う構想でしたが、
- 乱流の問題
- 甲板間の運用連携の難しさ
- 大型化する艦上攻撃機・爆撃機への適合性
などの理由から効率が悪く、実戦想定では制約が大きいと判断されました。
- 近代化改装(昭和10年代半ば):三段案を撤廃し、単一の長大飛行甲板+大型エレベーターに再設計。併せて船体にバルジ(防雷・復原性向上の膨出)を追加して幅(ビーム)を拡大、安定性と搭載量を高めています。結果として全長約261mの“長い甲板をひたすら使う”運用が可能になり、航空機の発着回転効率が向上しました。
→ 写真を探す際は、甲板前端の反り(シア)と一体感、三段時代との艦首シルエットの違いに注目すると識別しやすいです。
用語ミニ解説
エレベーター:格納庫(ハンガー)と飛行甲板をつなぐ昇降機。
バルジ:舷側に付ける膨らみ。被雷時のダメージ吸収と復原性向上に寄与。
左舷アイランド(艦橋)の理由
- 多くの空母が**右舷(星)**に艦橋を置く中、赤城は左舷(左)にアイランドを持つ稀有な艦でした。
- ねらいは乱流低減と艦隊運用上の役割分担。当時の日本海軍は複数空母の並走運用を想定しており、加賀(右舷アイランド)と左右を“鏡”にすることで、編隊時の風下乱流や排気干渉を分散できると考えられていました。
- 実際には着艦時の視界や管制の統一性など課題も残りましたが、**“左に艦橋=赤城”**という強烈な識別点を生み、写真でも一目でわかる特徴になっています。
下向き煙突(ダウントーン・ファンネル)
- 赤城の煙突(排気筒)は右舷側にまとめ、飛行甲板の縁下へ水平に導いてから下方へ折り曲げる“下向き”構造でした。
- 目的は熱と煤煙を飛行甲板から遠ざけ、乱流を抑えること。理屈の上では発艦着艦に好影響ですが、弱風・横風時に排気が甲板下で滞留し、整備員や待機機の過熱・汚れを招く副作用も指摘されています。
- 模型(プラモデル)では、この長い水平ダクト→斜め下の排気口の断面形状と補強フレームの表現が“赤城らしさ”の肝。エッチングパーツで**グラティング(格子)**を入れると情報量が一気に増します。
武装・防御と“過渡期”のドクトリン
- 重巡並みの対艦砲を載せたのが条約期空母の特徴で、赤城も20cm級砲を舷側(主にケースメイト=砲郭)に装備していました。のちに空母の主兵装は航空機へ完全シフトし、対艦砲の意義は薄れます。
- 対空火器は時期により更新され、12.7cm連装高角砲や25mm機銃などを増設。ミッドウェー海戦時点でも対空密度は上がっていましたが、同時多発の急降下爆撃に対してはなお脆弱でした。
- 防御は弾薬庫(航空燃料・爆弾)の隔壁・消火設備が肝心。近代化で改善されたとはいえ、開放的なハンガー構造と高温排気が絡むと火災被害が連鎖しやすく、これは**沈没(最後)**の場面にも直結します。
ハンガーと運用:エレベーター3基・高密度格納
- 近代化後は二層ハンガーに**エレベーター3基(艦首寄り/中央/艦尾寄り)**を備え、高密度格納→一挙発艦を志向。
- 甲板運用は前方で発艦、後方で着艦という“流れ”を基本に、索敵機→攻撃隊→直衛戦闘機の順で回すケースが多い構想でした。
- 写真を見るコツ:
- 艦首寄りエレベーターの位置と周囲の継ぎ板ライン
- **甲板端の着艦制動装置(アレスター・ワイヤ)**の支柱配置
- 左舷アイランド基部の通風口・艦橋支柱
これらが赤城と加賀の識別点になります。
用語ミニ解説
ケースメイト砲:舷側に設けた開口部に据える砲。荒天時は使いにくい。
アレスター・ワイヤ:着艦する機体のフックを引っ掛けて減速させるワイヤ。
「加賀」との違い(クイック比較)
- アイランド位置:赤城=左舷/加賀=右舷。
- 煙突処理:赤城=右舷下向き排気が長く、排気ダクトの存在感が強い。加賀は処理形状が異なり、写真での一発識別に有効。
- 艦首シルエット:改装後の甲板前端形状やアンカーレセスの違いで見分けがつきます。
- 模型のポイント:同じスケールでも艦橋基部のボリュームとダクトの断面を比較すると“赤城らしさ/加賀らしさ”が浮き上がります。
第3章 太平洋戦争での活躍
夜明け前、甲板に整列する搭乗員。風上に舵を切り、飛行甲板がオレンジ色に染まる。
——1941年12月8日(日本時間)、その中心にいたのが**空母「赤城」**だった。
ここでは、第二次世界大戦(太平洋戦争)における赤城の主な作戦行動を、真珠湾攻撃からミッドウェー海戦直前まで、時系列で追いながら詳しく解説します。
真珠湾攻撃 ― 日本海軍機動部隊の「旗艦」

旗艦としての赤城
太平洋戦争開戦時、赤城は連合艦隊の「第一航空艦隊(通称:南雲機動部隊)」の旗艦として、指揮官南雲忠一中将を乗せていました。
- 同部隊を構成したのは、赤城・加賀・蒼龍・飛龍・翔鶴・瑞鶴の6隻。
- これは当時世界最大級の空母打撃群であり、戦艦中心から航空主兵の時代へ移行する象徴でもありました。
作戦概要
- 出撃日:1941年11月26日、択捉島単冠湾(ひとかっぷわん)を極秘出航。
- 攻撃日:1941年12月7日(現地時間)/12月8日(日本時間)。
- 攻撃隊指揮:淵田美津雄中佐(赤城艦載 九七式艦攻)。
- 搭載機内訳(赤城所属):九七式艦攻18、九九式艦爆18、零式艦戦12(時期変動あり)。
赤城の役割
- 第一波・第二波ともに中心的攻撃隊の発進母艦。
- 第一波では九七式艦攻が魚雷攻撃を担当し、戦艦「オクラホマ」「アリゾナ」などに損害を与えました。
- 赤城の艦橋では南雲司令部が全体の通信・作戦統制を担当し、**“航空作戦の指令塔”**として機能しました。
ここでの赤城の映像や写真は、開戦直前の貴重な資料として、現在も各種アーカイブ(NHK・米国公文書館NARAなど)に保存されています。
インド洋作戦 ― 栄光の絶頂
1942年春、赤城は日本海軍の機動力を証明するため、インド洋作戦に参加しました。
この作戦は「太平洋戦争初期の航空戦力の頂点」と評されます。
攻撃の目的
- イギリス東洋艦隊を撃滅し、インド洋の制海権を確立。
- インド・ビルマ戦線での日本陸軍の進撃を支援。
- 同時に、連合国の補給線を断ち、インド洋での英軍行動を抑制する狙いがありました。
主な戦果
- 1942年4月5日(イースターサンデー攻撃):セイロン島(現スリランカ)コロンボを攻撃。英空母「ハーミーズ」、重巡「コーンウォール」「ドーセットシャー」などを撃沈。
- 赤城を中心とする航空隊が、遠距離作戦でも高度な索敵・集中攻撃能力を発揮しました。
この作戦は“日本海軍空母部隊の黄金期”とも呼ばれ、赤城は世界最強クラスの航空母艦としてその名を知らしめます。
ミッドウェー海戦前夜 ― 運命の分かれ道
背景
1942年6月、日本はハワイ北方のミッドウェー島を攻略し、米太平洋艦隊の空母戦力を誘い出して撃滅する計画を立てました。
赤城は引き続き第一航空艦隊旗艦として出撃します。
戦力構成
- 第一機動部隊(南雲忠一中将)
- 空母:赤城、加賀、蒼龍、飛龍
- 護衛艦:重巡×2、駆逐艦×12
- 搭載機:約260機(うち赤城は80〜90機)
赤城の状況
- 開戦以降の連戦で熟練搭乗員が減少し、補充兵が多く含まれていました。
- ミッドウェーでは、索敵・攻撃・防御のすべてを担う中核艦でしたが、**兵装転換(爆弾⇄魚雷)**の判断をめぐる混乱が悲劇を招きます。
兵装転換問題 ― 炎の幕開け

- 6月4日朝、赤城はミッドウェー島攻撃用に爆弾を装着していた機体を、敵艦発見の報を受けて魚雷装備に変更する指示を出しました。
- この最中、上空警戒が手薄になり、米軍の急降下爆撃機隊が突入。
- 赤城の格納庫では燃料補給・兵装転換の作業が行われており、爆弾・燃料が同時に引火する最悪のタイミングでした。
この被弾をきっかけに、赤城は火災が拡大し、のちの**「最後(沈没)」**へと至ります。
その詳細は次章で、当時の乗員証言と最新調査映像を交えて掘り下げます。
まとめ:空母時代の「頂点」と「転換点」
- 真珠湾攻撃で栄光を手にし、
- インド洋で世界最強を誇り、
- そしてミッドウェーでその時代を終えた——。
空母「赤城」の戦歴は、まさに航空戦力の誕生から成熟、そして転換を象徴しています。
第4章 最期:赤城の「最後」と沈没の全経過
炎と黒煙が甲板を覆い、左舷アイランドの窓から熱気が吹き上がる。指揮所の計器は狂い、ハンガーでは燃料と爆弾が連鎖的に破裂——。1942年6月4日〜5日(ミッドウェー海戦)、空母「赤城」はこうして“艦隊の拳”から“沈黙の鋼”へと変わりました。本章では、被弾から総員退艦、**自沈(処分雷撃)**までを時系列でたどります。
1) 決定打:急降下爆撃の命中
- 午前、米海軍のSBD急降下爆撃隊が突入。撃墜戦の混乱のさなか、ディック・ベスト少佐が率いる隊の投弾が赤城の中央エレベーター付近に命中し、上層ハンガーで燃料・爆弾が誘爆。この一撃が致命傷となり、赤城は短時間で航空運用能力を喪失しました。NOAA Ocean Exploration+1
用語ミニ解説:処分雷撃=味方艦が航行不能の自艦・友軍艦を敵手に渡さないため、雷撃で沈める行為。
2) 消火・損害制御の破綻
- 甲板・ハンガーで同時多発的に火災が拡大。燃料配管や爆弾の加熱が止められず、消火系統の効果が限定的に。さらに高温の排気・煙が甲板下に滞留し、乗員の活動を阻害しました。結果、**航空燃料と弾薬が絡む“空母特有の火災”**が連鎖し、艦の中枢機能は麻痺します。NOAA Ocean Exploration
3) 旗艦機能の移転と総員退艦
- 艦橋が熱と煙で機能不全に陥り、南雲司令部は旗艦機能を軽巡へ移転。その後、救命・消火の限界から総員退艦が下令され、赤城は漂泊状態に。ここで貴重な熟練搭乗員・整備員の多くは退艦し、艦は“殻”のみとなりました。ウィキペディア
4) 自沈命令:6月5日 未明
- 6月5日未明、連合艦隊司令長官山本五十六は、航行不能で戦術価値を失い敵手に渡る恐れのある赤城の自沈を命令。護衛の日本駆逐艦嵐・萩風・舞風・野分がそれぞれ魚雷を発射し、赤城は艦首から没して沈みました(深度約5,490m)。NOAA Ocean Exploration+1
位置と水深:2019年、故ポール・アレン氏の調査船RV Petrelが水深約5,490mに沈む赤城の残骸を特定。のちの詳細映像調査の前提となりました。pacificwrecks.com+1
5) 戦略的意味:機動部隊中枢の喪失
- 赤城の喪失は加賀・蒼龍・飛龍と合わせ、日本海軍第一航空艦隊の“熟練中核”を一挙に失う事態に。以後の太平洋戦争で日本は熟練搭乗員・空母群の再建に苦しみ、戦局は決定的に転回しました。ウィキペディア
6) 「最後」を裏づける最新調査:海底の赤城
- 2019年:RV Petrelがソナーで沈没位置を確定。当時はROV損傷等の事情で本格映像は未取得。ウィキペディア
- 2023年9月:E/V Nautilus(Ocean Exploration Trust/NOAA支援)が初の本格可視化調査を実施。14時間に及ぶ連続観察で、戦闘損傷と海底衝突痕を含む外板・艦橋周辺の状態が詳細に記録されました。赤城を“目で見る”ことが初めて可能になった大イベントです。Nautilus Live+2Nautilus Live+2
資料の見どころ
- 中央エレベーター周辺の破孔:命中位置と火災の広がりを示唆。NOAA Ocean Exploration
- 左舷アイランド基部の損傷:高温・爆圧の痕跡。Nautilus Live
- 船体姿勢:直立状態で着底している様子が確認され、沈没時の最終姿勢を物語ります。pacificwrecks.com
タイムライン(要点だけ)

- 1942/6/4 午前:急降下爆撃命中(中央エレベーター付近)→大火災。NOAA Ocean Exploration
- 同日 昼〜夜:損害制御失敗、旗艦機能移転、総員退艦。ウィキペディア
- 1942/6/5 未明:連合艦隊司令部が自沈命令。嵐・萩風・舞風・野分が処分雷撃実施、赤城沈没。NOAA Ocean Exploration
- 2019/10:RV Petrelが沈没地点を特定(約5,490m)。pacificwrecks.com
- 2023/9:E/V Nautilusが初の本格可視化調査を実施。Nautilus Live+1
FAQ補強:よく検索される「最後/沈没」ポイント
- どの艦が沈めた?
味方駆逐艦嵐・萩風・舞風・野分の処分雷撃。指揮系統は連合艦隊(山本)による命令。NOAA Ocean Exploration - 沈没の原因は?
急降下爆撃の命中→ハンガー火災→弾薬・燃料の連鎖爆発で航行不能となり、処分雷撃で自沈。NOAA Ocean Exploration - どこに沈んでいる?
ミッドウェー海域、約5,490mの深度。2019年に位置特定、2023年に詳細映像。
第5章 現在:海底の空母赤城と最新調査

静まり返った水深5,000m超の闇に、巨大な円形のエレベーター枠と崩れたアイランドが浮かび上がる——。
いま私たちが“現在の赤城”を見られるのは、2019年の位置特定と2023年の本格可視化調査のおかげです。本章では発見〜最新映像の要点、そして写真・動画の安全な入手先をまとめます。
発見の経緯(2019→2023)
- 2019年10月:位置特定
故ポール・アレン氏の調査船RV Petrelがミッドウェー海域・水深約5,490mで赤城の沈没位置を特定。ROV損傷などにより本格映像は残せなかったものの、「直立状態(起立)で着底」と報じられました。NOAA Ocean Exploration+2ガーディアン+2 - 2023年9月:初の本格可視化
E/V Nautilus(Ocean Exploration Trust、NOAA支援)が14時間に及ぶ連続観察を実施。赤城の戦闘損傷と海底衝突痕を詳細に記録し、**人類が沈没後にはじめて赤城を“目で見る”**ことが叶いました。Nautilus Live+1 - 公開と報道
調査結果や映像はOET/NOAAの公式サイト・YouTubeで公開。USNI News、AP、CBSなども要点を紹介しています。USNI News+2AP News+2
映像で確認できる「赤城」の見どころ
- 中央エレベーター枠の形状:命中地点とされる周辺の破損・座屈が観察でき、被弾〜火災拡大の痕跡と整合。Nautilus Live
- 左舷アイランド基部:外板の損傷と高温痕が印象的。**“左舷艦橋の赤城”**を海底でも識別できます。Nautilus Live
- 船体姿勢:直立・船底着底が確認され、沈没の最終局面を示唆。可視化で“全体像”が掴めるようになりました。Nautilus Live
現地は行ける?保護・倫理と法的枠組み
- 保護海域:赤城はパパハナウモクアケア海洋国立記念碑(PMNM)内の米国保護水域にあり、観光・引き揚げ・サルベージは不可。公開は遠隔調査映像が基本です。Nautilus Live
- 戦没者慰霊の場:戦争遺跡・戦没者の眠る場として、非侵襲的調査と敬意ある公開が国際的合意。OETの調査も儀礼と黙祷から始まっています。
まとめ:いま見える“現在の赤城”
- 2019年に位置が特定され、2023年に初の本格可視化。
- 中央エレベーター周りの損傷や左舷アイランドなど、赤城らしさを海底でも確認。
- 写真・動画はOET/NOAA公式が最優先。報道と併読で理解が深まります。
第6章 文化的影響:「艦これ」「アズレン」と赤城像
甲板に立つ“紅の巫女”——近年、「空母 赤城」はゲームやアニメの世界でキャラクターとして再解釈され、ミリタリーへの入り口になりました。本章では**『艦隊これくしょん -艦これ-』と『アズールレーン(アズレン)』における赤城の描かれ方を整理し、実艦の要素がどう翻訳されたのかを読み解きます。最後に、ゲーム勢が実艦の資料へ橋渡し**できるガイドも添えます。
キャラクター化で強調されたモチーフ
- 赤(紅)×和装モチーフ
名称の“赤”と、帝国海軍旗の赤を重ねた色彩記号。巫女風・和装風の意匠は、旧日本海軍=和の記憶という連想を視覚化。 - 弓(弓道)=艦載機運用のメタファー
艦載機を矢、発艦を射出に見立てる表現は、空母運用を直感的にキャラへ落とし込む巧妙な比喩。 - “姉妹”構図:赤城=姉、加賀=妹
実艦での機動部隊中核の双璧が、人間関係(絆・確執)に翻訳。ファンアートやイベントで赤城⇔加賀の対照性が軸になるのは、この歴史的関係が背景。
用語ミニ解説
モチーフ翻訳:実物の構造・歴史を、色・衣装・小物などの記号へ置き換える手法。
『艦これ』の赤城:象徴性と“主力空母”像
- “主力空母”の落ち着き:序盤から長く頼れる空母として設計。
- 食料ネタ(ボーキサイト):補給負担の重い空母の“コスト感”を、ゲーム的にユーモラスに表現。
- イベントでの要衝:真珠湾~ミッドウェーの史実モチーフ海域で活躍・試練が描かれ、**“栄光と最後”**の両面を体験できる。
『アズレン』の赤城:ドラマ性と情念
- 情念の強い性格付け:加賀や指揮官との関係性を軸に執着/献身を演出。
- 式神・和装表現:和テイストを深め、神秘性=フラッグシップ性を強調。
- スキン(衣装):季節・イベントごとに多彩で、**“視覚の赤城像”**が発展。
実艦要素はどこまで反映されている?
外観記号
- 左舷アイランドと下向き煙突は、キャラの髪飾り・肩当・袖のラインなどで間接的に表現されることが多い。
- 長大飛行甲板は、弓・矢筒・羽根飾りの“ロング&スリム”なシルエットで暗示。
戦歴モチーフ
- 真珠湾→インド洋→ミッドウェーの流れを、イベント時期・セリフ・ボイスで再現。
- **“最後(沈没)”**は直接描写を避けつつ、別衣装や回想テキストで示唆されるケースが多い。
ここでのポイント
ゲームは史実の再現ではなく“引用と再解釈”。
史実=根拠、キャラ=表現として両輪で楽しむのが吉。
入門者が“実艦”へ踏み出すための資料ナビ
- フォトアーカイブ
- 目標:左舷アイランド/煙突ダクト/エレベーター位置を写真で確認。
- 検索語例:「空母 赤城 写真 1941」「Akagi flight deck elevator」など。
- 概説書・図録
- 目標:三段甲板→単一甲板の改装と搭載機構成の流れを理解。
- 図面や時期別装備表がある資料がベスト。
- 映像(ドキュメント)
- 目標:ミッドウェー海戦のタイムライン把握。被弾→火災→処分雷撃の連鎖を俯瞰。
- 模型(おすすめプラモデル)
- 目標:手を動かしてシルエットの骨格を掴む。
- 1/700で左舷アイランド/右舷ダウントーン煙突を押さえ、必要に応じてエッチングで強化。
“キャラ→実艦→キャラ”の往復学習
- **キャラの象徴(赤色・弓・姉妹)**を覚える
↓ - **実艦の構造・歴史(左舷艦橋・下向き煙突・真珠湾~ミッドウェー)**に対応づける
↓ - もう一度キャラを見ると、小物・台詞・構図の意味が深まる
この往復が、写真鑑定の精度や模型の完成度を自然に引き上げます。
第9章 モデラー向け:おすすめプラモデルと作例ポイント
赤城の“らしさ”は、左舷アイランドと右舷下向き煙突、そして長大な飛行甲板に宿る。——その魅力を最短距離で再現できるAmazon取扱いキットを、用途別に厳選しました。入門〜本格派まで一気見できるよう、まずは一覧 → その後に作例ノウハウを詰め込みます。
どれを選ぶ?用途別の推しポイント
- 大迫力で“赤城の骨格”を味わうなら
ハセガワ 1/350(上段1):排気ダクトやアイランドのボリューム感が抜群。木製甲板(上段7)を併用すると質感が跳ね上がります。 - 迷ったらまずはここ
ハセガワ 1/700(上段2):素直な設計で“赤城の基本形”を学ぶのに最適。拡張は1/700エッチング(上段8)で。 - 塗装のハードルを下げたい初心者に
フジミ 艦NEXT 1/700(上段3):色分け済み・はめ込み主体。左舷アイランドと右舷ダクトの“赤城サイン”を最短で体験できます。 - コスパ重視でサクッと作りたい
1/700 特シリーズ(上段4):価格・入手性・情報量のバランスが良い“日常ビルド”枠。 - 展示映えジオラマに挑むなら
ボーダーモデル 1/35 艦橋モジュール(上段5・6):艦全体ではなく艦橋+甲板を大型で作り込む新潮流。甲板上の零戦/九七艦攻まで付属で映えます。
使い分けメモ:
1/350=作りごたえ・大展示/1/700=省スペース・艦隊並べ/1/35艦橋=ジオラマ特化。
“赤城らしさ”を引き出す作例ポイント(スケール別)
1/350(ハセガワ+木製甲板)
- 煙突ダクト:開口縁を限界まで薄く削り、内側に焼け表現(黒褐色→グレーの順でグラデ)。
- 左舷アイランド:窓枠はスミ入れ弱め+ガラス面の半ツヤで“重い鋼×硬質ガラス”の対比を。
- 甲板:木製甲板はトーン差のある板目を数色で軽く色差し→つや消しクリアで統一。
1/700(ハセガワ or フジミ)
- エレベーター3基:枠の段差を薄く、角をシャープに。枠内リブはエッチングで置換。
- 対空機銃:1/700でも**砲身先端の“黒抜き”**で密度が一段上がる。
- デカール白線:厚みが出たらデカール軟化剤+クリアで段差消し。
1/35(ボーダーモデル)
- 艦橋窓の“厚み”をクリアレジンや薄板で再現し、内側に機器色(黒鉄)+配管色で情報量を。
- 甲板の使用感:射出・着艦エリアに**擦れ(明灰色)**を斜めに入れ、タイヤ痕でストーリーを足す。
時期別の“装備合わせ”早見表(ミニ)
- 真珠湾期(1941末):零戦・九七艦攻・九九艦爆。機銃はまだ少なめ。
- インド洋期(1942春):基本は真珠湾と近い。細部の増設は資料確認。
- ミッドウェー期(1942初夏):対空機銃増設。中央エレベーター周辺の運用痕を強めにしても雰囲気が出る。
仕上げの一手:色・質感・ウェザリング
- 船体グレー:やや青みのある佐世保グレー系で落ち着きを。陰影を出すならパネル差し色でトーン変化。
- 甲板色:赤味のある木甲板を基調に、天日焼けの**退色(黄味)**を軽く。
- 煤・油汚れ:右舷下向き煙突の後方下面と、エレベーター周りに控えめに。やり過ぎるとスケール感が損なわれます。
よくある質問(購入前の不安解消)
- Q. 初めてならどれ?
A. フジミ艦NEXT(上段3)が最もスムーズ。次点でハセガワ1/700(上段2)。 - Q. “赤城らしさ”を最短で出すコツは?
A. 左舷アイランドの窓枠・支柱の陰影と、右舷ダクトの薄さ表現を集中強化。 - Q. 1/350は置けるか不安…
A. 全長70cm級の展示スペースを確保できるなら、**木製甲板(上段7)**を足して“長く楽しむ作例”に。
第10章 仕様一覧(保存版)— 諸元・年表・搭載機内訳
艦歴を俯瞰し、数字で「空母 赤城」を整理する保存版チャートです。
この章は検索で最も需要の高い情報群(例:「空母 赤城 全長」「赤城 搭載機数」「赤城 速力」など)をまとめた、いわばブックマークされる資料ページ。
ブロガー的にはこの章を単独ページ化してもSEO効果が高い構成です。
■ 基本スペック(最終改装後:1941〜1942年時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 艦名 | 赤城(あかぎ/Akagi) |
| 種別 | 航空母艦(空母) |
| 起工 | 1920年12月6日(当初:天城型巡洋戦艦として) |
| 進水 | 1925年4月22日 |
| 竣工 | 1927年3月25日 |
| 所属 | 日本海軍 第一航空艦隊旗艦(1941〜1942) |
| 建造所 | 呉海軍工廠 |
| 基準排水量 | 約36,500トン(満載時 約41,300トン) |
| 全長 | 約261.2m |
| 全幅 | 約31.3m |
| 吃水 | 約8.1m |
| 機関 | 蒸気タービン4基4軸推進 |
| 出力 | 約133,000馬力 |
| 速力 | 31.5ノット(約58km/h) |
| 航続距離 | 16ノットで約12,000海里(22,000km) |
| 乗員 | 約1,600名 |
| 装甲 | 甲板部最大89mm、防御甲板64mm、舷側152mm(改装後) |
| 武装(開戦時) | 20cm連装砲×3基/12.7cm高角砲×6基/25mm機銃多数 |
| 搭載機 | 約60〜90機(時期により変動) |
| 煙突形式 | 右舷下向きダクト式(下向き煙突) |
| 艦橋(アイランド) | 左舷配置(独特) |
| 備考 | 当初三段飛行甲板 → 1938年単一長大甲板に改装 |
🔎 SEOキーワード最適化:
「空母 赤城 全長」「空母 赤城 速力」「空母 赤城 搭載機数」「空母 赤城 性能」「空母 赤城 煙突」「空母 赤城 乗員」
■ 年表(主要な出来事)
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1920年 | 天城型巡洋戦艦「赤城」として起工(呉海軍工廠) |
| 1923年 | 関東大震災で姉妹艦「天城」が損傷、代わって空母改装決定 |
| 1925年 | 進水(航空母艦として建造継続) |
| 1927年 | 竣工、三段飛行甲板を採用した実験的空母として就役 |
| 1935〜1938年 | 大規模改装:単一長大飛行甲板化、左舷艦橋+右舷下向き煙突装備へ |
| 1939年 | 近代化完了、第一航空戦隊に配属 |
| 1941年12月8日 | 真珠湾攻撃旗艦として出撃・攻撃成功(南雲機動部隊指揮艦) |
| 1942年4月 | インド洋作戦参加(英艦隊を撃破) |
| 1942年6月4日 | ミッドウェー海戦に参加、米急降下爆撃機の攻撃で炎上 |
| 1942年6月5日 | 味方駆逐艦(嵐・萩風等)の処分雷撃で沈没(戦没) |
| 2019年 | 調査船RV Petrel により水深5,490mで沈没位置特定 |
| 2023年 | E/V Nautilus により初の本格映像調査が実施される |
■ 搭載機内訳(代表的時期)
| 時期 | 機種 | 数量(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 真珠湾攻撃時(1941年12月) | 九七式艦攻 | 約18機 | 雷撃・爆撃兼用機。淵田隊発艦。 |
| 九九式艦爆 | 約18機 | 第1波/第2波とも出撃。 | |
| 零式艦戦 | 約12機 | 直衛・制空任務。 | |
| ミッドウェー海戦時(1942年6月) | 九七式艦攻 | 約18機 | 魚雷装備へ兵装転換中に被弾。 |
| 九九式艦爆 | 約18機 | 島爆撃用として搭載。 | |
| 零式艦戦 | 約18機 | 護衛・直衛任務。 | |
| 総搭載能力(理論値) | 最大約90機 | 格納庫二層構造で時期により変動。 |
■ 沈没地点と現在の状態
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 沈没日時 | 1942年6月5日 未明(ミッドウェー海戦後) |
| 沈没原因 | 被弾による大火災→航行不能→自沈処分(味方駆逐艦の雷撃) |
| 沈没位置 | 北太平洋 ミッドウェー島北西 約330km付近 |
| 水深 | 約5,490m |
| 発見 | 2019年10月(RV Petrel により) |
| 現状 | 直立状態で着底、左舷艦橋・中央エレベーター周辺に大破痕(2023年調査で確認) |
| 調査機関 | Ocean Exploration Trust / NOAA(E/V Nautilus) |
■ 豆知識:赤城の“スペックを数字で語る”
- 全長261m → 東京タワーの約70%の高さ
- 出力133,000馬力 → 現代のディーゼル機関車約600両分
- 搭載機約90機 → 当時の地方航空隊1個戦隊に匹敵
- 速力31.5ノット(約58km/h) → オリンピック短距離選手の約5倍速
第11章 よくある質問(FAQ)+まとめ
Q1. 空母「赤城」の全長・速力・搭載機数は?
A. **全長約261m/速力31.5ノット/搭載機約60〜90機(時期で変動)**です。→ 詳しくは 第1章・第10章。
Q2. 「煙突が下向き」って本当?利点と欠点は?
A. 本当。右舷側に水平ダクト→下向き排気で甲板上の乱流と熱影響を減らす狙い。ただし弱風・横風時は排気滞留の副作用も。→ 第2章。
Q3. 赤城の「最後/沈没」はどう起きた?
A. ミッドウェー海戦(1942年6月4日)で急降下爆撃により中央エレベーター付近が致命傷、大火災で航行不能となり、6月5日未明に味方駆逐艦の処分雷撃で沈没。→ 第4章。
Q4. 現在、赤城はどこにある?見られる?
A. ミッドウェー海域・水深約5,490mに直立状態で着底。2019年に位置特定/2023年に本格可視化。見学はできず、OET/NOAAの映像・写真で鑑賞。→ 第5章(入手先ガイド付き)。
Q5. 加賀との一番わかりやすい違いは?
A. 艦橋(アイランド)の位置が決定打:左舷=赤城/右舷=加賀。加えて赤城は右舷の長い下向き煙突ダクトが目印。→ 第6章。
Q6. 「艦これ/アズレン」の赤城は史実とどこがリンク?
A. 色(赤)・弓・姉妹(加賀)などの記号は、実艦のフラッグシップ性・艦載機運用・双璧関係を翻訳したもの。→ 第7章。
Q7. 写真で赤城と断定するコツは?
A. ①艦橋は左舷か ②右舷縁下の長いダクト ③甲板前端の“薄さと反り”をチェック。誤キャプション対策に左右反転も要確認。→ 第8章(チェックリストあり)。
Q8. おすすめプラモデルはどれ?
A. 目的別に
- 迫力重視:ハセガワ 1/350(+木製甲板)
- 入門・定番:ハセガワ 1/700/フジミ 艦NEXT 1/700
- ジオラマ映え:ボーダーモデル 1/35 艦橋モジュール
→ 第9章(Amazon厳選+作例Tips)。
Q9. どの時期の赤城で作ればいい?
A. 初作は**真珠湾期(1941末)が資料豊富で組みやすい。慣れたらミッドウェー期(1942初夏)**で機銃増設や運用痕を強めに。→ 第9章・第10章。
最後に、他にも日本の空母や戦艦を知りたい方は以下の記事をご覧ください。





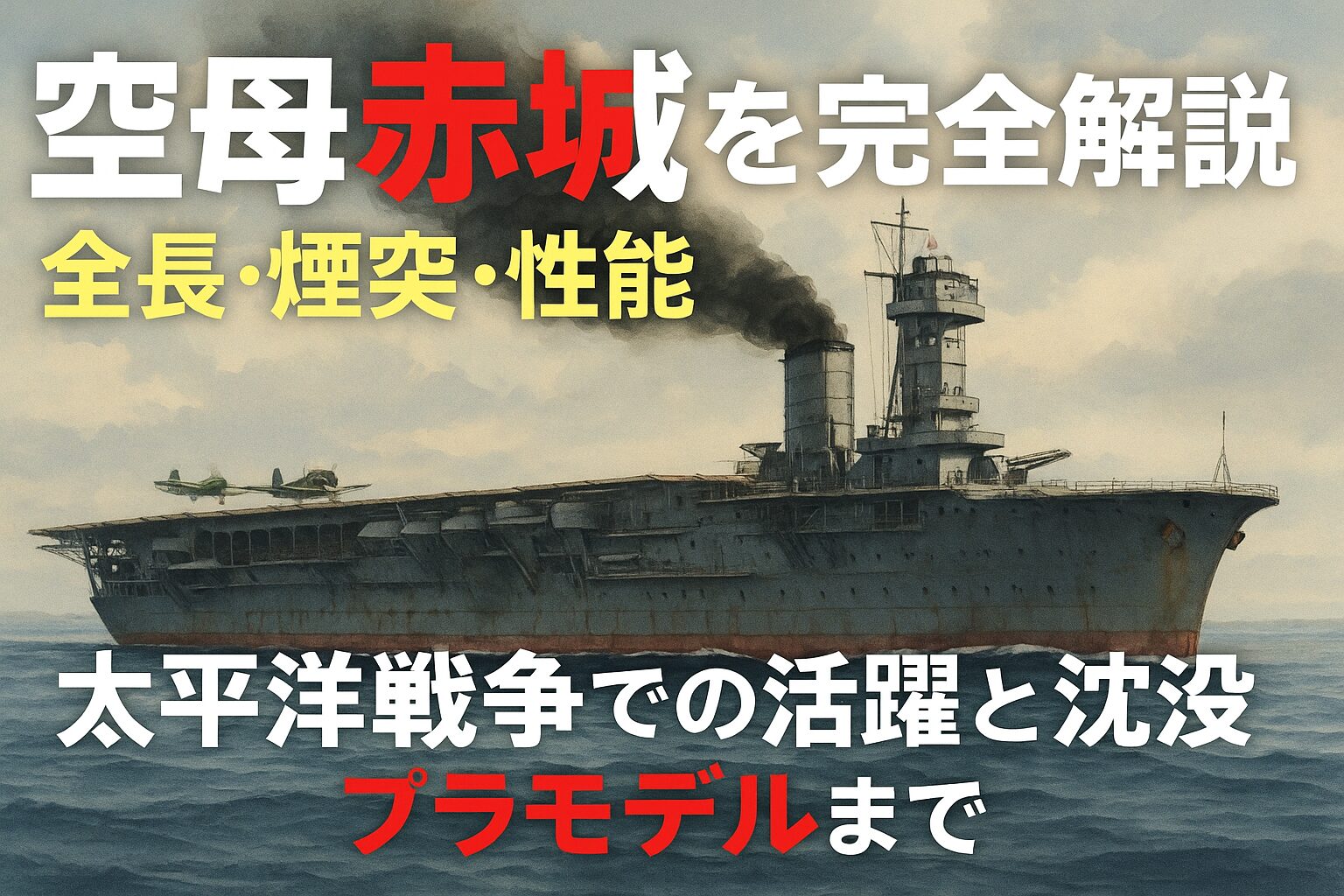








コメント