1. ベラ湾夜戦とは?──1943年8月、ソロモンの海で何が起きたのか
1-1. 一瞬で決着した”完全敗北”
1943年(昭和18年)8月6日深夜から7日未明にかけて、ソロモン諸島ニュージョージア島北方のベラ湾で、日本海軍の駆逐艦部隊がアメリカ海軍の待ち伏せ攻撃を受け、わずか23分で駆逐艦3隻を失う壊滅的敗北を喫した海戦──それが「ベラ湾夜戦」です。
この海戦は、太平洋戦争における日米海戦の中でも特異な位置を占めています。
なぜなら、それまで”夜戦の帝王”として恐れられた日本海軍が、一方的に、完膚なきまでに叩きのめされた最初の夜戦だったからです。
駆逐艦「萩風」「嵐」「江風」の3隻は、敵の姿すら満足に視認できないまま、レーダー誘導による魚雷攻撃で次々と撃沈されました。
米軍側の損害は、ゼロ。
これは単なる敗北ではありませんでした。日本海軍が誇った”夜戦優位”という神話そのものが、音を立てて崩れ落ちた瞬間だったのです。
1-2. なぜこの海戦が重要なのか
ベラ湾夜戦は、太平洋戦争の転換点を象徴する戦いです。
それまでの夜戦では、日本海軍は優れた光学兵器(双眼鏡や照準装置)、高性能な酸素魚雷「九三式魚雷」、そして徹底的に訓練された夜間戦闘技術によって、米軍を圧倒してきました。
第一次ソロモン海戦(サボ島沖海戦)では米豪艦隊を一方的に撃破し、ルンガ沖夜戦では田中頼三少将率いる駆逐艦隊が巡洋艦を含む米艦隊を蹴散らしました。
しかし、ベラ湾ではその構図が完全に逆転します。
米軍はレーダー技術を実戦レベルまで洗練させ、さらに新しい戦術──「レーダー誘導による魚雷飽和攻撃」を完成させていました。
この海戦を境に、日本海軍の夜戦優位は失われ、以後の海戦では米軍が主導権を握り続けることになります。
1-3. この記事で何がわかるのか
この記事では、ベラ湾夜戦について以下の内容を徹底的に解説します:
- 戦いの背景と戦略的文脈:なぜ日本軍はこの海域で輸送作戦を続けたのか
- 両軍の戦力と配置:どんな艦がどのように配置されていたのか
- 戦闘の詳細な経過:23分間で何が起きたのか、時系列で追う
- 敗因の多角的分析:技術、戦術、情報、判断──どこに問題があったのか
- 歴史的影響:この敗北が太平洋戦争全体に与えた影響
- 現代への教訓:今日の海戦にも通じる普遍的な学び
初心者の方にもわかりやすく、かつ軍事マニアの方にも満足いただける内容を目指しました。
それでは、1943年8月のソロモンの海へ、一緒に潜ってみましょう。
2. 戦いの背景──なぜ日本軍はコロンバンガラ島への輸送を続けたのか
2-1. ソロモン諸島の戦略的重要性
1942年8月、米軍がガダルカナル島に上陸したことで始まったソロモン諸島の戦いは、太平洋戦争の趨勢を決する消耗戦となりました。
日本軍にとってソロモン諸島は、ラバウル(ニューブリテン島)を拠点とする南東方面の防衛ラインの最前線でした。
ここを失えば、ラバウルが直接脅威にさらされ、さらには本土防衛ラインが後退することを意味します。
一方、米軍にとってソロモンは日本本土への反攻作戦の第一歩であり、制空権・制海権を確保することが最優先課題でした。
2-2. ガダルカナル喪失後の戦局
1943年2月、日本軍はガダルカナル島からの撤退を完了しました。
しかし、ソロモン諸島での戦いは終わりません。
日本軍は次の防衛拠点として、コロンバンガラ島とニュージョージア島を重視し、ここに兵力と物資を集中させる方針を取りました。
特にコロンバンガラ島には、約1万名の陸軍部隊が配置されており、ここを維持することが中部ソロモンの防衛に不可欠とされていました。
2-3. 「鼠輸送」──夜間高速輸送作戦の限界
ガダルカナル戦以降、日本軍は昼間の制空権を米軍に握られていたため、夜間に駆逐艦を使った高速輸送作戦(通称「鼠輸送」または「ネズミ輸送」)を繰り返していました。
駆逐艦は高速で、夜のうちに目的地に到着し、物資を降ろして夜明け前に離脱する──この戦術は一定の成果を上げていました。
しかし、1943年7月のクラ湾夜戦、コロンバンガラ島沖海戦と続けて激しい夜戦が発生し、日本海軍は駆逐艦「新月」「神通」などを失います。
それでもなお、コロンバンガラ島への補給は続けなければなりませんでした。
2-4. 8月6日の輸送作戦──「第二水雷戦隊」の使命
1943年8月6日、日本海軍は再びコロンバンガラ島への輸送作戦を計画しました。
指揮を執ったのは、第二水雷戦隊司令官・伊集院松治少将。
編成は以下の通りです:
| 艦名 | 艦種 | 役割 |
|---|---|---|
| 萩風(はぎかぜ) | 陽炎型駆逐艦 | 輸送艦 |
| 嵐(あらし) | 陽炎型駆逐艦 | 輸送艦 |
| 江風(かわかぜ) | 白露型駆逐艦 | 輸送艦 |
| 時雨(しぐれ) | 白露型駆逐艦 | 護衛・指揮艦 |
時雨は伊集院少将が座乗し、輸送任務そのものには参加せず、護衛と指揮に専念する予定でした。
この4隻は、ブーゲンビル島のブインを出港し、ベラ湾を経由してコロンバンガラ島ビラ泊地を目指しました。
しかし、彼らはまだ知りません。
その航路上で、米軍の駆逐艦6隻が、完璧な待ち伏せ態勢で待ち構えていることを。
3. 両軍の戦力と配置──駆逐艦4隻 vs 駆逐艦6隻、数の差だけではなかった
3-1. 日本海軍側の戦力
第二水雷戦隊(伊集院松治少将)
| 艦名 | 艦型 | 竣工年 | 排水量 | 主砲 | 魚雷 | 速力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時雨 | 白露型 | 1936年 | 1,685t | 12.7cm連装砲×3 | 61cm四連装魚雷発射管×2 | 34ノット | 伊集院少将座乗・指揮艦 |
| 萩風 | 陽炎型 | 1941年 | 2,033t | 12.7cm連装砲×3 | 61cm四連装魚雷発射管×2 | 35ノット | 輸送任務 |
| 嵐 | 陽炎型 | 1941年 | 2,033t | 12.7cm連装砲×3 | 61cm四連装魚雷発射管×2 | 35ノット | 輸送任務 |
| 江風 | 白露型 | 1936年 | 1,685t | 12.7cm連装砲×3 | 61cm四連装魚雷発射管×2 | 34ノット | 輸送任務 |
日本側の特徴:
- 九三式酸素魚雷:射程40km以上、無航跡で探知困難な世界最高性能の魚雷
- 夜戦訓練:長年にわたる夜間戦闘訓練で培われた技術
- 光学兵器:優れた双眼鏡と測距儀による目視索敵能力
しかし、レーダーは搭載していませんでした。
当時の日本海軍は、レーダー技術で米軍に大きく遅れを取っており、実用レベルの艦載レーダーはほとんど配備されていませんでした。
3-2. アメリカ海軍側の戦力
第31任務部隊 第1駆逐隊(フレデリック・ムースブルッガー大佐)
| 艦名 | 艦型 | 竣工年 | 排水量 | 主砲 | 魚雷 | 速力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンラップ | マハン級 | 1936年 | 1,500t | 5インチ砲×5 | 魚雷発射管×3 | 36.5ノット | 旗艦 |
| クレイヴン | マハン級 | 1937年 | 1,500t | 5インチ砲×5 | 魚雷発射管×3 | 36.5ノット | |
| モーリー | マハン級 | 1936年 | 1,500t | 5インチ砲×5 | 魚雷発射管×3 | 36.5ノット | |
| スタック | ベンハム級 | 1939年 | 1,500t | 5インチ砲×4 | 魚雷発射管×4 | 38ノット | |
| ステレット | ベンハム級 | 1939年 | 1,500t | 5インチ砲×4 | 魚雷発射管×4 | 38ノット | |
| ウィルソン | ベンハム級 | 1939年 | 1,500t | 5インチ砲×4 | 魚雷発射管×4 | 38ノット |
米軍側の圧倒的優位:
- SG型レーダー:全艦に搭載された最新鋭の水上捜索レーダー。探知距離約20km、精度も高い
- レーダー連動射撃管制装置:レーダー情報を直接火器管制に反映できる
- 無線通信の統制:艦隊全体が一体となって動ける指揮統制能力
- 数的優位:6隻 vs 4隻(実質的には3隻)
3-3. 戦力比較──技術格差が決定的だった
| 項目 | 日本海軍 | アメリカ海軍 |
|---|---|---|
| 隻数 | 4隻(うち1隻は護衛専任) | 6隻 |
| レーダー | なし | 全艦装備(SG型) |
| 魚雷性能 | 九三式酸素魚雷(射程40km超) | Mk15魚雷(射程6〜10km) |
| 夜間索敵 | 目視・双眼鏡 | レーダー |
| 射撃管制 | 光学照準 | レーダー連動 |
| 通信統制 | 旗艦からの指示 | 無線による即応連携 |
一見すると、日本側にも優位性(魚雷性能、夜戦経験)があるように見えますが、この戦いでは「先に敵を発見し、先に攻撃できる側」が圧倒的に有利でした。
そしてそれを可能にしたのが、レーダーだったのです。
3-4. 配置と作戦方針
日本側の作戦
- ブインを出港 → ベラ湾 → コロンバンガラ島ビラ泊地
- 時雨は護衛として後方に位置
- 萩風・嵐・江風が輸送物資を積載し、最短ルートで突入
- 夜明け前に離脱する予定
米軍側の作戦
ムースブルッガー大佐は、日本軍の輸送ルートを事前に察知していました。
彼は以下のような待ち伏せ陣形を敷きます:
- 6隻を2グループに分割
- 第1グループ(ダンラップ、クレイヴン、モーリー):魚雷攻撃担当
- 第2グループ(スタック、ステレット、ウィルソン):砲撃支援・追撃担当
- ベラ湾の出口付近で待機
- レーダーで日本艦隊を早期発見 → 魚雷一斉発射 → 砲撃で仕留める
この作戦は、「レーダーによる先制攻撃」を前提とした、極めて近代的な戦術でした。
4. 戦闘経過──23分間の一方的殺戮
4-1. 8月6日深夜──日本艦隊、ベラ湾へ進入
1943年8月6日23時頃、伊集院少将率いる第二水雷戦隊は、予定通りベラ湾に進入しました。
陣形は以下の通り:
進行方向 →
時雨(護衛・後方)
↓
萩風(先頭)
↓
嵐(中央)
↓
江風(最後尾)この時点で、日本側は米艦隊の存在に全く気づいていませんでした。
見張り員は双眼鏡で海面を注視していましたが、暗闇の中、何も見えません。
一方、米軍駆逐艦のレーダースクリーンには、既に日本艦隊の光点が映し出されていました。
4-2. 23時42分──米軍、レーダーで日本艦隊を探知
距離約18,000ヤード(約16.5km)。
ムースブルッガー大佐は冷静に状況を分析しました。
「敵は4隻。速度約30ノット。針路は北西。おそらくコロンバンガラへの輸送部隊だ」
彼は全艦に指示を出します。
「魚雷発射準備。砲撃は魚雷命中後まで待て」
この指示が、この海戦の勝敗を決定づけました。
なぜなら、砲撃を先に行えば砲口の閃光で自艦の位置が露呈し、日本側に反撃の機会を与えてしまうからです。
ムースブルッガーは、魚雷による一撃必殺を狙っていました。
4-3. 23時43分──魚雷一斉発射
距離約10,000ヤード(約9.1km)まで接近。
ムースブルッガーは命令を下しました。
「全艦、魚雷発射!」
第1グループ(ダンラップ、クレイヴン、モーリー)の3隻から、合計24本の魚雷が発射されました。
魚雷は扇状に広がり、日本艦隊に向かって静かに進みます。
日本側は、まだ何も気づいていません。
4-4. 23時46分──最初の魚雷命中
ドォォォン!
轟音とともに、先頭を航行していた駆逐艦「萩風」の艦体が爆発に包まれました。
魚雷が右舷中央部に命中し、艦体が真っ二つに折れます。
「何だ!? 敵はどこだ!?」
日本側は混乱に陥りました。
敵の姿は見えず、砲撃の閃光もありません。
ただ、暗闇の中から突然、魚雷が襲ってきたのです。
萩風は数分で沈没しました。
4-5. 23時48分──「嵐」「江風」も相次いで被雷
萩風の爆発から2分後、駆逐艦「嵐」にも魚雷が命中しました。
さらにその直後、駆逐艦「江風」も被雷。
3隻の駆逐艦が、わずか数分の間に次々と炎上し、沈没していきます。
伊集院少将が座乗する「時雨」は、後方にいたため魚雷を回避することができました。
しかし、目の前で3隻の僚艦が沈んでいく光景を、ただ見ているしかありませんでした。
4-6. 23時50分以降──米軍の砲撃開始
魚雷攻撃が成功したことを確認した米軍は、砲撃を開始しました。
しかし、既に日本側の主力3隻は壊滅状態。
時雨は煙幕を展開しながら全速力で離脱を図ります。
米軍も追撃しましたが、時雨の巧みな操艦と煙幕によって、撃沈には至りませんでした。
4-7. 戦闘終了──23分間の完全勝利
戦闘開始から終了まで、わずか23分。
日本海軍は駆逐艦3隻を失い、約900名の将兵が戦死しました。
一方、米軍の損害はゼロ。
被弾すらしていません。
これは、太平洋戦争における海戦の中でも、最も一方的な勝利の一つでした。
5. 戦果と損害──日本側の完全敗北
5-1. 日本海軍の損害
| 艦名 | 艦型 | 沈没時刻 | 戦死者数 | 生存者数 |
|---|---|---|---|---|
| 萩風 | 陽炎型駆逐艦 | 23時46分頃 | 約240名 | 約0名 |
| 嵐 | 陽炎型駆逐艦 | 23時48分頃 | 約240名 | 約0名 |
| 江風 | 白露型駆逐艦 | 23時49分頃 | 約180名 | 約0名 |
| 合計 | 3隻 | – | 約660〜900名 | ほぼゼロ |
生存者がほとんどいなかった理由:
- 魚雷命中による即座の沈没
- 夜間海域での救助困難
- 米軍による追撃と制空権喪失により、救助作戦が不可能
5-2. アメリカ海軍の損害
損害:なし
- 被弾した艦:0隻
- 戦死者:0名
- 負傷者:0名
5-3. 戦果の非対称性──なぜここまで一方的だったのか
この海戦の最大の特徴は、損害の完全な非対称性です。
日本側は3隻全滅、米側は無傷──この結果は、単なる運や偶然ではありません。
技術格差、戦術の差、情報戦の差が、すべて米軍側に有利に働いた結果でした。
6. 敗因の徹底分析──なぜ”夜戦の帝国海軍”は完敗したのか
6-1. 技術的要因──レーダーの有無が決定的だった
米軍のレーダー優位
- SG型水上捜索レーダー:探知距離約20km、精度が高く、夜間でも敵艦の位置・速度・針路を正確に把握可能
- レーダー連動射撃管制:目視に頼らず、レーダー情報だけで魚雷発射が可能
日本軍のレーダー不在
- 当時の日本海軍には、実用レベルの艦載レーダーがほとんど配備されていなかった
- 索敵は目視と双眼鏡に依存
- 暗闇では、敵を発見する手段がほぼ皆無
結果:米軍は一方的に「見える」状態で、日本軍は「見えない」状態だった。
これは、現代で言えば「一方がナイトビジョンを装備し、もう一方が裸眼で戦う」ようなものでした。
6-2. 戦術的要因──「先制魚雷攻撃」の完成
ムースブルッガー大佐の作戦は、極めて合理的でした。
- レーダーで敵を早期発見
- 砲撃はせず、魚雷だけで攻撃(砲撃すると自艦の位置が露呈するため)
- 魚雷命中後、砲撃で仕留める
この戦術は、「レーダーがあるからこそ可能」なものでした。
日本側は、敵がどこにいるのか分からないまま、一方的に攻撃を受けることになります。
6-3. 情報戦の敗北──米軍は日本の動きを事前に把握していた
米軍は、日本軍の輸送ルートと日時を事前に察知していました。
これには以下の要因が考えられます:
- 暗号解読:米軍は日本海軍の暗号をある程度解読していた可能性
- 偵察機による監視:日中の偵察飛行で日本艦隊の動向を把握
- 現地情報網:ソロモン諸島の住民や沿岸監視隊(コーストウォッチャー)からの情報
日本側は、米軍が待ち伏せしていることを全く知らずに進入してしまいました。
6-4. 指揮・判断の問題──「輸送優先」が招いた悲劇
日本海軍は、輸送任務を最優先していました。
そのため、以下のような判断ミスが重なります:
- 護衛艦が少なすぎた:時雨1隻のみで、しかも後方に配置
- 警戒が不十分:米軍が待ち伏せしている可能性を十分に考慮していなかった
- 撤退判断の遅れ:最初の被雷後も、即座に全艦退避の命令が出せなかった
6-5. 構造的問題──日本海軍の技術開発の遅れ
この敗北の根本原因は、日本海軍全体の技術開発の遅れにありました。
| 技術分野 | 日本 | アメリカ |
|---|---|---|
| レーダー | 開発遅延、実用化困難 | 量産体制確立、全艦配備 |
| 無線通信 | 暗号解読リスク、通信統制不十分 | 暗号強度高、リアルタイム連携 |
| 生産力 | 艦艇の補充困難 | 大量生産可能 |
| 訓練 | ベテラン喪失後の補充困難 | 組織的訓練システム確立 |
日本は「個人の技量」に頼り、米国は「システムと技術」で戦った。
そしてこの戦いで、後者の優位性が決定的に証明されたのです。
7. ベラ湾夜戦が太平洋戦争に与えた影響
7-1. 「夜戦優位」神話の崩壊
ベラ湾夜戦以前、日本海軍は夜戦において圧倒的優位を誇っていました。
しかしこの海戦を境に、米軍がレーダーを使いこなすようになり、夜戦でも日本側が不利になるという新たな現実が生まれました。
以後の海戦では、日本海軍は夜間でも米軍を恐れるようになります。
7-2. ソロモン諸島での制海権喪失
この敗北により、日本軍のコロンバンガラ島への補給は事実上不可能になりました。
1943年10月、日本軍はコロンバンガラ島からの撤退を決定します。
これにより、中部ソロモンの制海権は完全に米軍の手に渡りました。
7-3. 駆逐艦戦力の消耗
駆逐艦3隻の喪失は、日本海軍にとって大きな痛手でした。
駆逐艦は、護衛・輸送・哨戒と多用途に使える貴重な戦力です。
しかし日本の造船能力では、失った艦艇を迅速に補充することができませんでした。
この海戦での損失は、以後の作戦にも影響を与え続けます。
7-4. 米軍の自信と士気向上
一方、米軍にとってこの勝利は「レーダー戦術の有効性を実証した成功例」となりました。
ムースブルッガー大佐の戦術は、以後の海戦でも模範とされ、米海軍の標準的な夜戦戦術として定着していきます。
8. 戦訓と教訓──現代の海戦にも通じる普遍的な学び
8-1. 技術革新が戦術を変える
ベラ湾夜戦は、「技術の進歩が戦術の優劣を逆転させる」という普遍的な教訓を示しています。
- かつて日本が誇った「夜戦技術」は、レーダーの登場で無力化された
- 現代でも、ステルス技術、AI、ドローンなどの新技術が戦場を変え続けている
技術に遅れることは、戦場で命を失うことに直結する。
8-2. 情報優位の重要性
この海戦では、「敵を先に見つけた側が勝つ」という原則が如実に表れました。
- 米軍はレーダーで日本艦隊を早期発見
- 日本側は敵の存在すら知らなかった
現代の海戦でも、早期警戒レーダー、偵察衛星、電子戦といった「情報戦」が勝敗を左右します。
8-3. 柔軟な戦術転換の必要性
日本海軍は、「夜戦優位」という過去の成功体験に固執しすぎました。
米軍がレーダーを実用化し始めた時点で、戦術を根本的に見直すべきでしたが、それができませんでした。
「昨日の勝利の方程式が、今日も通用するとは限らない」
この教訓は、現代のビジネスや組織運営にも通じるものです。
8-4. 「見えない敵」への対応
レーダーのない日本艦隊は、「見えない敵」に一方的に攻撃されるという恐怖を味わいました。
現代でも、サイバー攻撃、ステルス兵器、電磁波攻撃など、「見えない脅威」は増え続けています。
「見えないものにどう対処するか」は、今も昔も変わらぬ課題です。
9. ベラ湾夜戦を知るための映画・書籍・ゲーム
9-1. おすすめ書籍
『駆逐艦戦隊』(学研)
ソロモン海戦を中心に、日本海軍の駆逐艦部隊の戦いを詳述。ベラ湾夜戦についても詳しく解説されています。
『太平洋戦争の日本海軍駆逐艦』(大日本絵画)
駆逐艦の性能、戦歴、戦術を網羅した決定版。写真も豊富で、視覚的に理解できます。
『ソロモン海戦』(光人社NF文庫)
ソロモン諸島での一連の海戦を時系列で追った名著。ベラ湾夜戦の記述も充実。
9-2. 映画・ドラマ
残念ながら、ベラ湾夜戦を直接扱った映画は存在しません。
しかし、以下の作品でソロモン海戦の雰囲気を感じることができます:
『太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男-』
ソロモン諸島の戦いを背景にした作品。日本軍の苦闘が描かれています。
『ミッドウェイ』(2019年版)
太平洋戦争初期の海戦を最新CGで再現。海戦の臨場感を味わえます。
9-3. ゲーム
『艦隊これくしょん -艦これ-』
駆逐艦「時雨」「江風」などが登場。ベラ湾夜戦をモチーフにしたイベント海域も過去に実装されました。
『World of Warships』
リアルな海戦シミュレーションゲーム。日本駆逐艦を操作して夜戦を体験できます。
『War Thunder』
陸海空を統合した戦争ゲーム。海戦モードでは駆逐艦同士の夜戦も楽しめます。
9-4. プラモデル
タミヤ 1/700 ウォーターラインシリーズ「駆逐艦 時雨」
ベラ湾夜戦を生き延びた「時雨」を再現。初心者にもおすすめ。
フジミ 1/700 特シリーズ「駆逐艦 江風」
ベラ湾で散った「江風」。ディテールが美しく、中級者向け。
10. まとめ──失われた優位性と、残された誇り
10-1. ベラ湾夜戦が教えてくれること
1943年8月6日深夜、ベラ湾で起きた23分間の海戦は、太平洋戦争の転換点を象徴する戦いでした。
日本海軍が誇った「夜戦優位」は、レーダー技術の前に崩れ去りました。
駆逐艦「萩風」「嵐」「江風」は、敵の姿すら見ることなく、暗闇の中で沈んでいきました。
約900名の将兵が、この海に散りました。
しかし、この敗北には重要な教訓が込められています。
- 技術革新が戦場を変える
- 情報優位が勝敗を決める
- 過去の成功体験に固執してはならない
- 見えない脅威への対応が生死を分ける
これらの教訓は、現代の私たちにも通じるものです。
10-2. 「時雨」が生き延びた意味
唯一生き残った駆逐艦「時雨」は、その後も激戦を戦い抜き、1945年1月まで生存し続けました。
時雨は、ベラ湾夜戦、レイテ沖海戦、多号作戦と、太平洋戦争の主要な海戦のほとんどに参加しながら、最後まで沈まなかった「幸運艦」として知られています。
時雨の生存は、単なる幸運ではなく、艦長・乗組員の冷静な判断と卓越した操艦技術の賜物でした。
彼らの戦いは、敗北の中にあっても、日本海軍の技術と誇りが失われていなかったことを示しています。
10-3. 忘れてはならない犠牲
ベラ湾で散った約900名の将兵たちは、祖国のため、仲間のために戦い、そして散っていきました。
彼らの多くは、まだ20代の若者でした。
彼らの犠牲の上に、今の私たちの平和があります。
この記事を通じて、ベラ湾夜戦という歴史の一ページを、少しでも多くの人に知っていただければ幸いです。
10-4. 次に読むべき記事
ベラ湾夜戦について理解が深まったら、ぜひ以下の関連記事もご覧ください:
- コロンバンガラ島沖海戦を解説:ベラ湾夜戦の直前に起きた激戦
- ルンガ沖夜戦を徹底解説:田中頼三の”駆逐艦だけ”で米巡洋艦を撃破した奇跡の夜戦
- 第三次ソロモン海戦を徹底解説:戦艦同士の砲撃戦と霧島の最期
- 大日本帝国海軍 全海戦一覧:太平洋戦争の全海戦を網羅




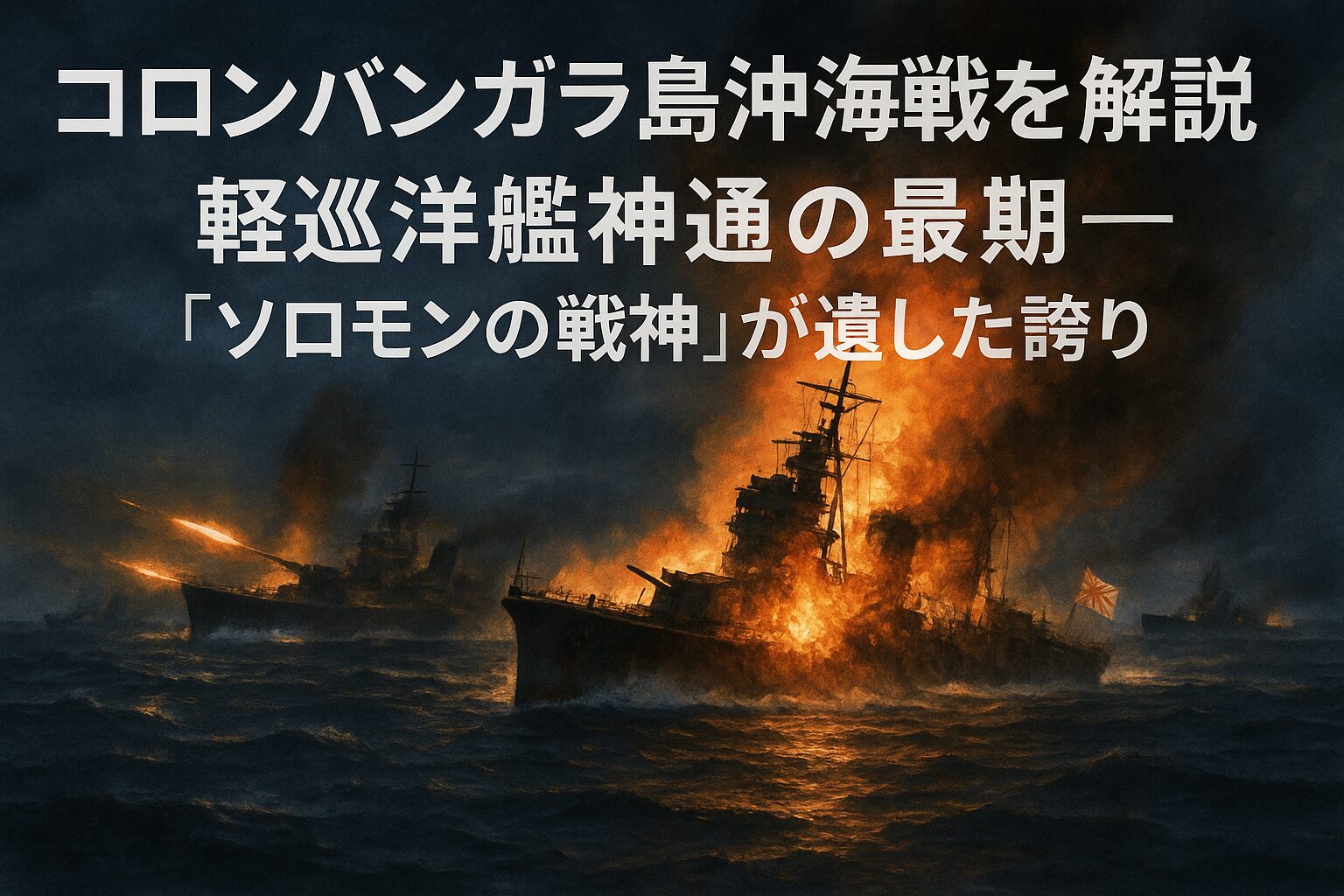








コメント