はじめに――「押すだけで都市が消える」部隊の正体
僕たちが暮らす日本列島から、わずか数百キロ。そこには、ボタンひとつで日本の主要都市を灰燼に帰すことのできる組織が存在している。
中国人民解放軍ロケット軍。
かつて「第二砲兵部隊」と呼ばれていたこの組織は、2015年の軍改革で独立した「軍種」へと格上げされた。その背景にあるのは、習近平政権が掲げる「強軍の夢」と、台湾有事・日米同盟への対抗という明確な戦略意図だ。
「ロケット軍って、要するにミサイル部隊でしょ?」
その理解は半分正しくて、半分危険なほど甘い。なぜなら、ここで扱われるのは単なる「兵器」ではなく、国家の意思を物理的に投射する「戦略そのもの」だからだ。核弾頭を搭載した大陸間弾道ミサイル(ICBM)から、空母を沈める対艦弾道ミサイル、さらには極超音速兵器まで。中国ロケット軍は、現代の戦争における「見えない主役」として、着々と能力を拡大し続けている。
この記事では、日本のミリタリーファンとして——そして敗戦国の末裔として——中国ロケット軍の実態を冷静に、しかし危機感を持って解説していく。彼らがどれほどの脅威なのか、自衛隊はどう対抗しているのか。そして、もし日中が本当に衝突したら、何が起こるのか。
悔しいが、認めなければならない。今、この瞬間も、中国ロケット軍の照準は僕たちに向けられている。
中国ロケット軍の成り立ち——「第二砲兵」から独立軍種へ

建国から文化大革命期:核保有への執念
中国ロケット軍の歴史を語る上で外せないのが、1964年10月16日。中国初の核実験が成功した日だ。
当時、米ソ冷戦の最前線に立たされていた中華人民共和国にとって、核兵器は「生存のための最低条件」だった。朝鮮戦争で米軍の核使用を恐れ、台湾海峡危機ではソ連の「核の傘」に頼らざるを得なかった屈辱。毛沢東は「ズボンを穿かなくても核を持つ」と宣言し、国家の全資源を核開発に注ぎ込んだ。
そして1966年、弾道ミサイルと核の運用を専門に扱う「第二砲兵部隊」が正式に設立される。名称の「第二」は「第一砲兵(通常の火砲部隊)」に続くという意味だが、実際には最高機密であり、その存在すら長らく公にされなかった。
当時の装備は旧ソ連の技術を基にした中距離弾道ミサイル「東風(DF)-2」や「東風-3」。射程は1000〜3000km程度で、主に台湾や在日米軍基地を射程に収める「地域抑止力」としての性格が強かった。
改革開放と「殺手鐧(さっしゅかん)」思想の芽生え
1980年代、鄧小平の改革開放路線によって経済が発展すると、軍の近代化も加速する。ここで注目すべきは「殺手鐧(サーシュージエン)」という概念だ。
直訳すれば「切り札」「奥の手」だが、軍事的には「弱者が強者を倒すための非対称兵器」を意味する。湾岸戦争(1991年)でイラク軍が米軍に完敗した姿を見た中国軍は、「通常戦力では米軍に勝てない」と悟った。ならば、どうするか?
答えは「米軍が近づけない環境を作る」こと。つまり、接近阻止・領域拒否(A2/AD)戦略の中核として、弾道ミサイルを「空母キラー」へと進化させる道を選んだのだ。
1990年代後半には、世界初の対艦弾道ミサイル「東風-21D」の開発が始まる。これは後に「空母キラー」として西側諸国を震撼させる兵器となる。
2015年軍改革:独立軍種への格上げ
そして2015年12月31日、習近平国家主席は歴史的な発表を行う。
「中国人民解放軍ロケット軍を設立する」
第二砲兵部隊は、陸海空に並ぶ「第4の軍種」へと昇格した。これは単なる名称変更ではない。予算配分の優先権、人事の独立性、装備開発の自由度——すべてが格段に向上したのだ。
同時に、組織規模も約12万人から15万人規模へと拡大。司令部は北京西山に置かれ、全国に6つの「基地」(旧称:軍区)を配置している。
この改革の背景には、「台湾統一」と「対米抑止」という二つの明確な戦略目標がある。習近平は「中華民族の偉大なる復興」を掲げるが、その最大の障害が米軍の介入だ。ロケット軍は、まさにその「米軍介入を躊躇させる力」として位置づけられている。
中国ロケット軍の組織構造と配備状況

6つの基地と役割分担
中国ロケット軍は、全国に6つの「基地」を展開している。各基地は旧来の軍区に対応し、それぞれ異なる戦略的役割を担っている。
- 第61基地(北京) – 対米ICBM運用。東風-41などの最新鋭大陸間弾道ミサイルを配備。
- 第62基地(瀋陽) – 朝鮮半島・日本方面。中距離弾道ミサイルの集中配備地域。
- 第63基地(昆明) – 東南アジア・インド方面。対印抑止が主任務。
- 第64基地(蘭州) – 中央アジア・ロシア方面。旧ソ連との対峙時代の名残が色濃い。
- 第65基地(南京) – 台湾有事の最前線基地。短距離弾道ミサイル(DF-15/16)を大量配備。
- 第66基地(広州) – 南シナ海方面。対艦弾道ミサイルの主力運用拠点。
特に日本にとって脅威なのは、**第62基地(瀋陽)と第65基地(南京)**だ。両基地には合計で500発以上の中短距離弾道ミサイルが配備されており、その射程は日本全土をカバーする。
部隊編成:「旅」単位の機動運用
ロケット軍の実戦部隊は「旅(りょ)」と呼ばれる規模で編成される。1個旅は約6〜12基の発射機(TEL:車載移動式発射台)を保有し、独立して作戦行動が可能だ。
注目すべきは、ほぼすべてのミサイルが車載移動式であること。これにより、衛星やレーダーで捕捉されても、数時間で位置を変え、先制攻撃を回避できる。冷戦期のソ連が固定サイロに頼ったのとは対照的に、中国は「動く標的」として生存性を高めている。
また、山岳部に掘られた地下トンネル網(通称:地下長城)も重要だ。中国西部の山岳地帯には総延長5000km以上とも言われる巨大トンネルが張り巡らされており、ミサイルは平時ここに隠匿されている。敵が攻撃しようにも、どこに何があるか特定できない——これが中国式の「核の生存性」だ。
主要装備一覧:「東風(DF)」シリーズの全貌

中国ロケット軍の主力は「東風(ドンフォン、Dong Feng)」シリーズだ。「東風」とは毛沢東の詩「東風、西風を圧す」に由来し、「東洋(中国)が西洋(米国)を圧倒する」という政治的メッセージが込められている。
短距離弾道ミサイル(SRBM)
DF-15(射程:600km)
台湾海峡危機を想定した短距離ミサイル。CEP(誤差半径)50m以下と高精度で、台湾の空軍基地や港湾施設の破壊を目的とする。推定配備数は300〜400発。
DF-16(射程:800〜1000km)
DF-15の改良型。射程延伸により、沖縄の在日米軍基地も射程に収める。台湾有事の初動で、嘉手納基地や普天間基地を無力化する「第一撃」を担う。
中距離弾道ミサイル(MRBM/IRBM)
DF-21D「空母キラー」(射程:1500〜2000km)
世界初の対艦弾道ミサイル(ASBM)。終末誘導装置により、移動する空母を標的にできるとされる。実戦使用例はないが、米海軍は「ゲームチェンジャー」として警戒している。
DF-26「グアムキラー」(射程:3000〜4000km)
核・通常弾頭の両用型。グアムの米軍基地まで届くため「グアムエクスプレス」とも呼ばれる。通常弾頭では対艦攻撃も可能で、第2列島線(グアム〜パラオライン)まで中国の影響圏を拡大する意図が明確だ。
大陸間弾道ミサイル(ICBM)
DF-31AG(射程:11200km)
移動式ICBM。米本土西海岸を射程に収める。車載移動式のため、衛星監視をかいくぐって展開できる。
DF-41(射程:12000〜15000km)
中国最新鋭のICBM。複数弾頭(MIRV)搭載可能で、最大10個の核弾頭を個別に目標へ誘導できる。米本土全域が射程内であり、米国の弾道ミサイル防衛(BMD)を飽和させる能力を持つ。
極超音速兵器
DF-17(極超音速滑空体搭載)
弾道ミサイルの弾頭部に、マッハ5以上で不規則機動する「極超音速滑空体(HGV)」を搭載。既存のミサイル防衛システムでは迎撃困難とされる。
DF-ZF(極超音速滑空体)
DF-17に搭載されるHGV本体の開発名称。米国防総省は「現時点で迎撃不可能」と公式に認めている。
ロケット軍の「殺傷力」——数字で見る脅威

配備ミサイル総数:約2000発以上
米国防総省の報告書によれば、中国ロケット軍は通常弾頭弾道ミサイル約1500発、核弾頭搭載可能なICBM約500発を保有している。これは冷戦期のソ連に匹敵する規模だ。
特に台湾正面に配備された短距離ミサイルは年間50〜80発のペースで増産されており、現時点で台湾全土の軍事施設を3回以上飽和攻撃できる火力を持つ。
核弾頭数:2030年までに1000発超へ
中国の核弾頭保有数は2020年時点で約350発だったが、米国防総省は「2030年までに1000発、2035年までに1500発に達する」と予測している。これは米ロに次ぐ「第三の核大国」への道を意味する。
しかも、中国は「先制不使用(NFU)」を公式方針としているが、実際には「核の傘を無力化するための核増強」を進めている。つまり、日本が米国の核抑止に依存する限り、中国は「米国の核報復を躊躇させるほどの核戦力」を整備する——というロジックだ。
発射準備時間:15分以内
冷戦期の固定サイロ式ICBMは、発射準備に数時間を要した。だが、中国のTEL(車載移動式発射台)は、命令から発射までわずか15分とされる。
これは何を意味するか?
仮に日米が中国のミサイル基地への先制攻撃を計画したとしても、衛星で捕捉した時点では「既に別の場所へ移動済み」か「既に発射済み」という事態になる。つまり、完全な先制攻撃は不可能なのだ。
対日戦略におけるロケット軍の役割

シナリオ1:台湾有事初動の「基地無力化」
中国が台湾侵攻を決断した場合、最初の30分で何が起こるか?
ロケット軍は、まず在日米軍基地——嘉手納、横田、横須賀、佐世保、岩国——に対し、DF-16による飽和攻撃を仕掛ける。目標は滑走路、燃料貯蔵施設、指揮統制施設。完全破壊ではなく「24〜48時間の機能停止」を狙う。
その間に、人民解放軍は台湾海峡を渡り、台湾本島への上陸を開始する。自衛隊が出動準備を整え、米軍が反撃体制を立て直す頃には、既に台湾は制圧されている——これが中国のシナリオだ。
シナリオ2:「A2/AD」による米空母の接近阻止
米海軍の空母打撃群が台湾周辺に展開しようとした場合、ロケット軍はDF-21DとDF-26による対艦攻撃を実施する。
空母1隻を撃沈するには何発必要か?
米海軍の試算では「最低10発の命中弾」とされるが、中国は「1隻に50発を集中投射」する計画だと言われる。つまり、圧倒的物量で防御を飽和させる戦術だ。
空母ロナルド・レーガン(横須賀配備)が撃沈されれば、米世論は「もう一隻の空母を失うリスク」を冒してまで介入するだろうか? ロケット軍の存在は、まさにこの「米国の介入意思」を揺さぶるためにある。
シナリオ3:本土攻撃による「戦意喪失」
もし日本が台湾有事に本格介入した場合、中国は通常弾頭ミサイルによる「限定的な本土攻撃」を検討する可能性がある。
目標は、航空自衛隊のレーダーサイト、海上自衛隊の港湾施設、そして——心理的効果を狙った都市部への警告攻撃。
「次は核弾頭かもしれない」という恐怖を植え付け、日本政府に「これ以上の介入は国民の命を危険に晒す」と判断させる。これが中国の「強制外交」だ。
悔しいが、現在の日本には、これを完全に防ぐ手段がない。弾道ミサイル防衛(BMD)システムは存在するが、数百発規模の飽和攻撃には対処しきれないのが現実だ。
日本の対抗策:「盾」から「矛」へ
弾道ミサイル防衛(BMD)の限界
日本は現在、イージス艦搭載の「SM-3」と地上配備の「PAC-3」による二段構えのBMDシステムを運用している。SM-3は大気圏外で迎撃、PAC-3は着弾直前の終末段階で迎撃する——という理屈だ。
だが、このシステムには致命的な欠陥がある。
- 迎撃率は100%ではない(実験では80%程度)
- 同時対処能力に限界(1隻のイージス艦で対処できるのは数発程度)
- 極超音速兵器には無力(軌道予測が困難)
つまり、中国が本気で100発単位の飽和攻撃を仕掛けてきた場合、「何発かは必ず着弾する」のだ。
反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有へ
この絶望的な状況を打破するため、日本政府は2022年、「反撃能力」の保有を閣議決定した。これは事実上の「敵基地攻撃能力」だ。
具体的には、12式地対艦誘導弾の射程延伸型(射程1000km以上)や、トマホーク巡航ミサイルの導入を進めている。これにより、中国沿岸部のミサイル基地を「発射前に叩く」能力を獲得する——というのが狙いだ。
しかし、現実はそう甘くない。
中国のミサイルは移動式であり、地下トンネルに隠匿されている。仮に日本が先制攻撃を成功させても、残存したミサイルによる報復攻撃は避けられない。しかも、国際法上「先制攻撃」は正当化が難しく、米国の支持を得られるかも不透明だ。
本当に必要なのは「抑止の信憑性」
では、どうすればいいのか?
冷静に考えれば、答えは明白だ。中国に「日本を攻撃すれば、自分たちも耐え難い損害を受ける」と思わせること。
そのためには、
- 日米同盟の強化(米国の核抑止力を確実に機能させる)
- 反撃能力の実効性向上(本当に発射前に叩けるのか、実証する)
- 国民保護体制の整備(シェルター、避難計画、備蓄)
の3点が不可欠だ。
特に3点目は、多くの日本人が見て見ぬふりをしている問題だ。スイスやフィンランドのように、国民の大多数が避難できるシェルターを整備しない限り、「ミサイルが飛んでくる」という現実に対処できない。
ロケット軍の「弱点」——見えてきた綻び

2023年の大規模粛清:腐敗と士気の問題
2023年7月、世界は驚愕のニュースを目にした。
ロケット軍司令官の李玉超上将、副司令官の劉光斌中将ら幹部9名が、相次いで失踪・更迭されたのだ。表向きの理由は「腐敗」だが、実際には装備調達における横領、訓練データの改ざん、さらには「ミサイル燃料の水増し販売」という信じがたい疑惑まで浮上している。
あるリークでは、「発射テスト用のミサイルが実は中身が空だった」「地下サイロの建設費が水増しされ、実際には手抜き工事だった」という証言もある。
これが事実なら、ロケット軍の「実戦能力」には深刻な疑問符がつく。少なくとも、習近平はそう判断したからこそ、大規模粛清に踏み切ったのだろう。
技術的課題:極超音速兵器の「未完成」
西側メディアは中国の極超音速兵器を「無敵の超兵器」のように報じるが、実際には技術的課題が山積している。
- 誘導精度の問題(マッハ10で飛行しながら、どうやって移動目標を追尾するのか?)
- 耐熱材の限界(大気圏再突入時の高温に耐えられるか?)
- 量産体制の未確立(実験成功と実戦配備は別問題)
米国防総省の分析では、「DF-17は実験段階であり、実戦配備数は50発以下」とされている。つまり、宣伝映像で見せられる「無敵の兵器」は、まだ完成していない可能性が高い。
ロジスティクスの脆弱性
ロケット軍の最大の弱点は、燃料と部品の供給だ。
液体燃料弾道ミサイルは、発射前に燃料注入が必要であり、この作業に数時間を要する。しかも、燃料は毒性が高く、長期保管ができない。つまり、「常時即応」は不可能なのだ。
また、固体燃料ミサイルも、発射機(TEL)の整備や部品交換が必要であり、これらは中国国内の限られた工場でしか製造できない。仮に日米が中国本土の軍需工場を攻撃した場合、ロケット軍は「撃てるミサイルの数」が急速に減少する。
僕たちはどう備えるべきか——歴史からの教訓
大日本帝国の轍を踏むな
僕たちの祖父や曾祖父の世代は、「敵を過小評価し、自国の力を過信した」結果、無謀な戦争に突入した。
真珠湾攻撃の成功に酔いしれ、「米国は長期戦に耐えられない」と誤判断した。だが、現実は残酷だった。米国の工業力は日本の10倍以上であり、物量で押し潰された。
今、僕たちは同じ過ちを繰り返してはならない。
中国ロケット軍を「張り子の虎」と侮ってはいけない。同時に、「無敵の超兵器」と過大評価してもいけない。冷静に、事実に基づいて、彼らの能力と限界を見極める必要がある。
「知ること」が最初の一歩
この記事を読んでいるあなたは、少なくとも「中国ロケット軍」という存在を知った。それだけで、大多数の日本人よりも一歩先を行っている。
次にすべきことは、この知識を周囲と共有すること。家族に、友人に、職場の同僚に——「実は今、こういう脅威がある」と伝えることだ。
民主主義国家において、世論は政策を動かす。国民の多くが「ミサイル防衛をもっと強化すべきだ」「反撃能力を早く整備しろ」と声を上げれば、政府は動かざるを得ない。
まとめ——見えない槍は、最も恐ろしい
中国ロケット軍。
それは、数千発のミサイルを操る「戦略の槍」であり、米国の介入を躊躇させる「強制外交の道具」であり、そして——僕たち日本人の命を人質に取る「見えない脅威」だ。
悔しいが、認めなければならない。今の日本には、この脅威を完全に無力化する手段はない。
だが、絶望する必要はない。
大日本帝国海軍は、物量では米海軍に劣っていたが、「質」と「戦術」で対抗しようとした。零戦の格闘戦性能、酸素魚雷の射程距離、夜戦訓練の徹底——限られた資源の中で、最大限の工夫を凝らした。
今の僕たちも、同じことができるはずだ。
ミサイル防衛技術の向上、反撃能力の実効性確保、そして国民保護体制の整備。やるべきことは山積している。
そして、何より大切なのは「諦めない心」だ。
祖父たちは、圧倒的劣勢の中でも最後まで戦い抜いた。その精神を、僕たちも受け継がなければならない。
中国ロケット軍は強大だ。だが、無敵ではない。
僕たちには、守るべきものがある。この国を、この島々を、そして——ここで暮らす人々の命を。
だから、知ろう。学ぼう。そして、備えよう。
見えない槍が飛んでくる日が来ないように。そして、もし来たとしても——僕たちが生き延びられるように。
あわせて読みたい関連記事
中国ロケット軍について理解を深めたあなたには、こちらの記事もおすすめだ。
- 中国人民解放軍の軍事力とは?陸海空の主力装備と戦力をわかりやすく解説【2025年版】 – ロケット軍を含む中国軍全体の戦力を俯瞰できる。
- 中国最新空母「福建」とは?電磁カタパルト搭載のモンスター空母をわかりやすく解説 – ロケット軍の「空母キラー」が標的とする、中国の最新空母について。
- 日本が保有するミサイル全種類を完全解説!極超音速ミサイルから弾道ミサイル防衛まで – 日本の対抗手段を知りたいなら、まずはこちら。
- 中国ステルス戦闘機J-20とは?性能・運用コンセプトとF-35との違いを解説 – 空からの脅威も忘れてはいけない。
- 【2025年最新版】世界最強戦闘機ランキングTOP10|徹底比較 – 日中の航空戦力を比較する上で必読。
そして、もしあなたがこの記事を「勉強になった」と感じたなら——次は「形」として残せるものを手に入れてみてはどうだろう?
関連書籍・グッズで「知識」を「所有」へ
中国軍事を深く学ぶならこの一冊
『中国「軍事強国」への夢──習近平の野望と人民解放軍の実像』(阿南友亮 著/新潮選書)
ロケット軍の戦略的位置づけから、習近平の軍改革の全貌まで、学術的かつ読みやすく解説された名著。中国軍を語るなら必読の一冊だ。
『日中最新兵器バトル!どちらが凄いのか?』(別冊宝島)
ロケット軍のDF-21Dと、海上自衛隊のイージス艦——この対決の行方をビジュアル豊富に解説。初心者でも楽しめる入門書として最適。
「もし戦争になったら」をリアルに想像する
『シミュレーション 台湾侵攻戦争』
元米国防総省の専門家が描く、「2025年台湾有事」のシミュレーション。ロケット軍が初動でどう動くかが、恐ろしいほど具体的に描かれている。
万が一に備える——有事対策グッズ
核シェルター級 防災用高性能マスク(N100規格)
ミサイル攻撃による粉塵や、最悪の場合の放射性物質からも身を守る。「そんなもの必要ない」と思うなら、この記事をもう一度読み直してほしい。
非常用長期保存水 5年保存 2リットル×12本
ライフラインが止まった時、最初の72時間を生き延びるための最低限の備え。ロケット軍が本土攻撃を仕掛けた場合、水道は止まる。
最後に——「平和」は祈るものではなく、守るもの
この記事を書きながら、僕は何度も自問した。
「こんなに恐ろしい現実を、読者に伝えるべきなのか?」
だが、答えは明確だ。知らないことこそが、最大の危険だ。
大日本帝国は、米国の国力を正しく認識せず、戦争に突入した。その結果、300万人以上の同胞が命を落とした。
僕たちは、同じ過ちを繰り返してはならない。
中国ロケット軍は存在する。そのミサイルは、今この瞬間も、僕たちに照準を合わせている。
だが——だからこそ、僕たちは知り、学び、備えなければならない。
平和は、祈るものではない。守るものだ。
そして、守るためには、まず「敵を知る」ことから始めなければならない。
この記事が、あなたの「第一歩」になれば、僕にとってこれ以上の喜びはない。


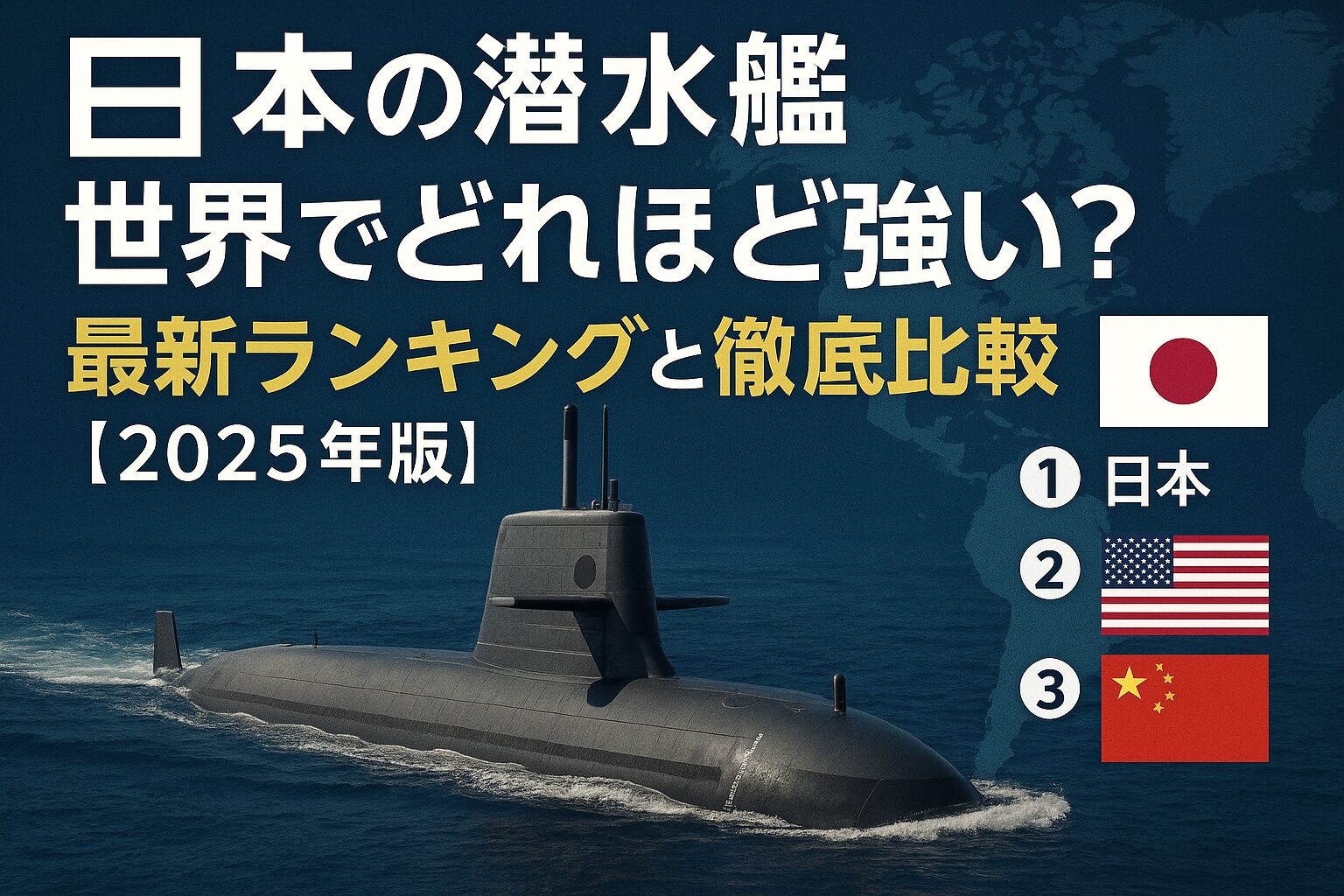















コメント