「三菱電機×防衛」に注目すべき理由
防衛費増額と「見えない戦力」への注目
2025年、日本の防衛費は過去最高の約8兆円を突破しました。この数字が意味するのは、単なる予算の増加だけではありません。ミサイル防衛、サイバーセキュリティ、宇宙監視――現代戦は「見える兵器」だけでは戦えない時代に突入しています。
そんな中、注目を集めているのが三菱電機です。
「え、三菱電機って家電メーカーじゃないの?」
そう思った方も多いでしょう。確かに、私たちの生活では冷蔵庫やエアコンでおなじみです。しかし、防衛分野では全く異なる顔を持っています。レーダー、通信システム、電子戦装備――自衛隊の「目と耳と神経」を支える、まさに“陰の功労者”なのです。
三菱重工が戦闘機や艦艇といった「見える兵器」の主役なら、三菱電機は情報・通信・電子戦という「見えない戦力」の主役。両社は名前こそ似ていますが、実は全く別の企業であり、それぞれが日本の防衛産業で重要な役割を担っています。
ミリタリーファンが押さえるべき視点
ミリタリーファンの皆さんなら、イージス艦のSPY-1レーダーや、F-2戦闘機の電子戦装備に興味があるはず。実は、これらの国産化・改良に三菱電機が深く関わっています。
戦前の軍用無線機から始まり、戦後の自衛隊創設期にレーダー開発で復活。そして現在、PAC-3ミサイル防衛システム、次世代戦闘機GCAPの電子戦システム、宇宙監視レーダーまで――80年以上にわたる技術の蓄積が、今の自衛隊を支えています。
この記事では、三菱電機の防衛事業を歴史から最新技術、業績、国際展開まで徹底解説します。読み終わる頃には、「三菱電機 防衛」で検索したくなること間違いなし。さあ、一緒に「見えない戦場」を覗いてみましょう!
用語ミニ解説:電子戦(Electronic Warfare)
電磁波を使った戦闘のこと。レーダーを妨害したり、敵の通信を傍受したり、逆に味方の電波を守ったり。現代戦では、銃弾が飛び交う前に電子戦で勝負が決まることも。三菱電機は、この分野で日本のトップランナーです。
2. 三菱電機の全体像と防衛事業の位置づけ
三菱電機は、1921年に三菱造船(現・三菱重工)から分離独立した総合電機メーカーです。2025年現在、従業員数は約14万人、売上高は約5兆円規模のグローバル企業。家電から産業機器、インフラ、そして防衛まで、幅広い事業を展開しています。
セグメント構成と防衛事業の割合
三菱電機の事業は、主に以下のセグメントに分かれています:
- 重電システム:発電設備、鉄道システムなど
- 産業メカトロニクス:FAシステム、自動車機器など
- エネルギー・電力システム:電力機器、配電盤など
- 電子システム:防衛・宇宙システムがここに含まれる
- 情報通信システム:通信ネットワーク、セキュリティなど
- 家庭電器:エアコン、冷蔵庫など
2024年度の決算では、全体売上収益が約5兆1,000億円。このうち、電子システムセグメント(防衛・宇宙含む)は約5,000億円で、全体の約10%を占めます。防衛事業単体の正確な売上は非公開ですが、業界推計では2,000億~3,000億円規模とされています。
三菱重工の防衛事業が約1兆円規模であるのに対し、三菱電機は規模では劣りますが、利益率の高さが特徴。レーダーや電子機器は高付加価値製品であり、営業利益率は15~20%に達すると言われています。
主要プロダクト領域
三菱電機の防衛事業は、以下の領域に集中しています:
- レーダーシステム
- 地上配備型防空レーダー(FPS-3、FPS-7など)
- 艦載レーダー(OPS-24、OPS-50など)
- 航空機搭載レーダー(F-2戦闘機のJ/APG-2など)
- 通信・指揮統制システム
- 自衛隊の統合指揮システム
- データリンクシステム(Link 16など)
- 衛星通信装置
- 電子戦装備
- 電波妨害装置(ジャマー)
- 電子支援装置(ESM:Electronic Support Measures)
- 赤外線対策装置
- ミサイル防衛システム
- PAC-3ミサイルの射撃管制装置
- イージス艦のレーダー国産化支援
- 宇宙監視システム
- 宇宙状況監視(SSA)レーダー
- 衛星搭載機器
これらの領域で、三菱電機は自衛隊の電子装備の約40%を担っていると推定されます。特にレーダー分野では、ほぼ独占的な地位を築いています。
三菱重工との違い
「三菱」つながりで混同されがちですが、三菱電機と三菱重工は完全に別の会社です。歴史的には同じルーツを持ちますが、1921年に分離して以来、独立した企業として発展してきました。
三菱重工は「プラットフォーム」(戦闘機、艦艇、戦車など)を作り、三菱電機はその「頭脳と神経」(レーダー、通信、電子戦装備)を作る――こう理解すると分かりやすいでしょう。
もちろん、両社は密接に協力しています。例えば、三菱重工が建造する護衛艦には、三菱電機製のレーダーや通信システムが搭載されます。F-2戦闘機の機体は三菱重工、レーダーと電子戦装備は三菱電機――このように役割分担が明確なのです。
次のセクションでは、この技術力のルーツを歴史から紐解いていきましょう。
3. 歴史で読み解く:三菱電機と日本の防衛電子技術の系譜
三菱電機の防衛事業を語る上で、歴史を振り返ることは欠かせません。戦前の軍用無線機開発から、戦後の復活、そして現代の最先端レーダーまで――80年以上にわたる技術の系譜が、今の自衛隊を支えています。
戦前:軍用無線機とレーダーの黎明期
三菱電機の軍事技術の原点は、1920年代の軍用無線機開発にあります。1921年の独立直後から、陸海軍向けの無線通信機器を製造。当時の日本軍は、日露戦争で無線通信の重要性を痛感しており、国産化を急いでいました。
1930年代に入ると、三菱電機はレーダー技術の研究にも着手します。第二次世界大戦中、日本は連合国に比べてレーダー開発で遅れを取っていましたが、三菱電機は海軍と協力し、艦載レーダーや対空レーダーの試作を進めました。実戦配備は限定的でしたが、この時期の経験が戦後の技術基盤となります。
また、戦時中は真空管や電子部品の製造も手がけ、軍需生産の一翼を担いました。名古屋や神戸の工場では、通信機器や計測装置が大量生産され、前線に送られました。
戦後の復活:自衛隊とともに歩んだレーダー開発
敗戦後、GHQの軍需禁止令により、三菱電機の軍事部門は一時休眠を余儀なくされます。しかし、1950年代の朝鮮戦争と自衛隊創設が転機となりました。
1954年、自衛隊が正式発足すると、防空レーダーの需要が急増します。三菱電機は、米国から技術導入しつつ、国産レーダーの開発に着手。1960年代には、国産防空レーダー「J/FPS-2」を完成させ、全国の航空自衛隊基地に配備されました。これが、現代に続くレーダー事業の出発点です。
1970年代には、艦載レーダーOPS-14シリーズを開発。海上自衛隊の護衛艦に搭載され、対空・対水上監視能力を大幅に向上させました。この時期、三菱電機は「レーダーの三菱」としての地位を確立します。
冷戦期の技術革新:イージスとPAC-3
冷戦期、日本は米国との同盟強化の中で、最新の防衛技術を導入していきます。三菱電機もその恩恵を受け、イージスシステムやPAC-3ミサイル防衛に参画しました。
イージスシステムは、米国が開発した艦載統合戦闘システム。SPY-1レーダーと高速コンピュータで、多数の目標を同時追尾・迎撃します。1980年代、海上自衛隊がイージス艦「こんごう」型を導入する際、三菱電機はレーダーの国産化改良や戦闘指揮システムの統合を担当しました。
PAC-3(パトリオット・ミサイル)は、弾道ミサイル迎撃用の地対空ミサイルシステム。三菱電機は、射撃管制装置やレーダー改良を手がけ、2000年代に航空自衛隊へ配備。北朝鮮の弾道ミサイル脅威に対応する要となっています。
現代:宇宙監視と次世代戦闘機へ
2020年代に入り、三菱電機の防衛事業は新たなフェーズに突入しました。宇宙領域と次世代戦闘機です。
宇宙状況監視(SSA)レーダーは、人工衛星やスペースデブリ(宇宙ゴミ)を追跡するシステム。2023年、防衛省は三菱電機にSSAレーダーの開発・運用を委託し、岡山県に配備しました。これにより、自衛隊は独自の宇宙監視能力を獲得しています。
次世代戦闘機GCAP(Global Combat Air Programme)は、日本・英国・イタリアが共同開発する第6世代戦闘機。三菱電機は、電子戦システムと統合センサーの開発を担当。2030年代の初飛行を目指し、最先端技術の実証を進めています。
タイムライン:三菱電機×日本の防衛史(主なマイルストーン)
- 1921年:三菱造船から独立。軍用無線機開発開始。
- 1930年代:レーダー研究着手。海軍と協力。
- 1945年:終戦。軍需禁止令下で民需転換。
- 1954年:自衛隊発足。防空レーダー開発再開。
- 1960年代:国産レーダーJ/FPS-2完成。全国配備。
- 1980年代:イージスシステム参画。SPY-1レーダー国産化。
- 2000年代:PAC-3導入。弾道ミサイル防衛の要に。
- 2023年:SSAレーダー運用開始。宇宙監視能力獲得。
- 2025年:GCAP電子戦システム開発加速。
この歴史が、三菱電機を「防衛電子技術の顔」たらしめています。次は、現在の自衛隊装備で具体的にどんな役割を果たしているのか見ていきましょう。
4. 自衛隊装備との関係:三菱電機が担う”見えない戦力”
三菱電機は、自衛隊の電子装備で圧倒的なシェアを誇ります。レーダー、通信、電子戦――これらは戦闘の「目と耳と神経」。敵を見つけ、情報を伝え、敵の電波を妨害する。三菱電機なくして、現代の自衛隊は成り立ちません。
レーダーシステム:空・海・陸を見通す”目”

航空自衛隊の防空レーダー
航空自衛隊の防空網を支えるのが、三菱電機製の固定式警戒管制レーダーです。
FPS-3改は、全国28カ所に配備された3次元レーダー。探知距離約450km、同時に数百の目標を追尾できます。北朝鮮の弾道ミサイルや中国機の領空接近を即座に探知し、戦闘機のスクランブル発進を指示します。
FPS-7は、さらに高性能な次世代レーダー。フェーズドアレイ方式で、電子ビームを瞬時に切り替え、複数方向を同時監視。2020年代から順次配備が進んでいます。
移動式警戒管制レーダーJ/TPS-102は、車載型で展開可能。災害時や有事の際、迅速に展開して空域を監視します。
海上自衛隊の艦載レーダー
海自の護衛艦には、三菱電機製レーダーが標準装備されています。
OPS-24は、対空・対水上両用の3次元レーダー。「あさひ」型護衛艦に搭載され、ステルス性の高い目標も探知可能。電子走査式で、機械的な回転が不要なため、故障が少なく信頼性抜群です。
OPS-50は、最新の「もがみ」型護衛艦(FFM)に搭載。多機能レーダーとして、対空・対水上・対潜水艦の全てをカバー。コンパクトながら高性能で、省人化された新型艦にぴったりです。
イージス艦「まや」型には、米国製SPY-1Dレーダーが搭載されていますが、三菱電機は国産化改良と戦闘システム統合を担当。将来的には、国産イージスレーダーの開発も視野に入れています。
航空機搭載レーダー
F-2戦闘機には、三菱電機製のJ/APG-2火器管制レーダーが搭載されています。アクティブ・フェーズドアレイ方式で、対空・対艦両用。特に対艦モードでは、海面すれすれを飛ぶ対艦ミサイルを探知する能力に優れています。
次世代戦闘機GCAPでは、さらに進化した統合RFセンサーを開発中。レーダー、電子戦、通信を一体化し、ステルス性を保ちながら全方位を監視します。
通信・指揮統制システム:情報を伝える”神経”
現代戦は、情報戦です。どれだけ早く正確に情報を共有できるかが、勝敗を分けます。三菱電機は、自衛隊の統合指揮システムとデータリンクを支えています。
統合指揮システムは、陸海空の情報を一元管理し、リアルタイムで共有するネットワーク。三菱電機は、防衛省の中央指揮システムや各自衛隊の作戦指揮所システムを構築。サイバー攻撃に強い暗号化通信で、安全性を確保しています。
Link 16データリンクは、NATO標準の戦術データ通信システム。航空機、艦艇、地上部隊が戦術情報を共有します。三菱電機は、Link 16端末の国産化を進め、自衛隊の相互運用性を高めています。
衛星通信装置も重要です。離島防衛や災害派遣では、地上回線が使えないことも。三菱電機製の衛星通信端末は、小型・軽量で展開が容易。2024年、陸上自衛隊の離島訓練で、医薬品輸送の指揮に使われました。
電子戦装備:敵を欺き、味方を守る”盾と矛”
電子戦は、現代戦の隠れた主役。三菱電機は、電子支援(ESM)、電子攻撃(EA)、電子防護(EP)の全領域で装備を提供しています。
電子支援装置(ESM)は、敵のレーダーや通信を傍受・分析します。F-2戦闘機のJ/ALQ-6電波探知装置は、敵レーダーの位置と種類を特定し、パイロットに警告。回避行動や攻撃の判断材料を提供します。
電子攻撃装置(ジャマー)は、敵のレーダーや通信を妨害します。三菱電機製の地上設置型ジャマーは、特定周波数の電波を強力に発信し、敵の探知を無効化。護衛艦にも艦載型ジャマーが搭載され、対艦ミサイルの誘導を妨害します。
赤外線対策装置(IRCM)は、赤外線誘導ミサイルから航空機を守ります。三菱電機は、陸自のヘリコプターや輸送機にフレア発射装置や指向性赤外線ジャマーを供給。敵ミサイルを欺瞞し、生存性を高めています。
ミサイル防衛:弾道ミサイルを迎撃する”盾”
北朝鮮の弾道ミサイル脅威に対し、日本はPAC-3とイージスBMDの二段構えで対応しています。三菱電機は、両システムで重要な役割を果たしています。
PAC-3(ペトリオット)は、航空自衛隊が運用する地対空ミサイルシステム。三菱電機は、AN/MPQ-65レーダーの改良と射撃管制装置を担当。2017年、北朝鮮のミサイル発射時には、首都圏に展開して警戒しました。
イージスBMDは、海上自衛隊のイージス艦が弾道ミサイルを大気圏外で迎撃するシステム。三菱電機は、SPY-1レーダーのBMDモード追加と戦闘システム改修を支援。SM-3ミサイルの発射指揮を行います。
将来的には、イージス・アショア代替艦への参画も予定されており、ミサイル防衛の要としての地位はさらに強まるでしょう。
宇宙監視:新たな戦場を見守る”目”
宇宙は、21世紀の新たな戦場です。人工衛星は通信・測位・偵察に不可欠ですが、攻撃や妨害のリスクも増しています。三菱電機の宇宙状況監視(SSA)レーダーは、この新領域で自衛隊を支えます。
2023年、岡山県に配備されたSSAレーダーは、高度数万kmの静止軌道まで監視可能。数千個の衛星とデブリを追跡し、衝突リスクを予測します。防衛省は、このデータを米国宇宙軍と共有し、宇宙の安全保障に貢献しています。
三菱電機は、衛星搭載機器も手がけており、自衛隊の偵察衛星や通信衛星に部品を供給。宇宙から地上まで、一貫した監視・通信網を構築しています。
5. 防衛装備庁との連携のリアル
三菱電機の防衛事業を語る上で、防衛装備庁との関係は避けて通れません。防衛装備庁は、防衛省の外局として2015年に発足した組織で、装備品の研究開発・調達・国際協力を一元管理しています。三菱電機は、この装備庁と密接に連携し、最先端技術の実用化を進めています。
契約実績:どれだけの規模で受注しているのか
防衛装備庁が公表する契約実績によれば、三菱電機は毎年トップ10に入る主要企業です。2023年度の防衛関連契約額は推定で約2,500億円規模。これは三菱重工、川崎重工に次ぐ第3位クラスの数字です。
契約の内訳を見ると、以下のような特徴があります:
- レーダーシステム関連:約40%(FPS-7配備、艦載レーダー改修など)
- 通信・指揮統制システム:約30%(統合指揮システム更新、データリンク整備)
- 電子戦装備:約15%(ジャマー、ESM装置の納入・改良)
- ミサイル防衛関連:約10%(PAC-3改修、イージスBMD支援)
- その他:約5%(宇宙監視、研究開発など)
特筆すべきは、随意契約の割合が高いこと。レーダーや電子戦装備は高度な技術と実績が求められるため、競争入札ではなく随意契約(特定企業との直接契約)になるケースが多いのです。これは三菱電機の技術的優位性と信頼性の証明と言えます。
共同研究開発プロジェクト
防衛装備庁は、民間企業との共同研究に積極的です。三菱電機も多数のプロジェクトに参画しており、その一部をご紹介します。
次世代レーダー技術
GaN(窒化ガリウム)半導体を用いた高出力レーダーの研究開発が進行中です。GaN素子は、従来のガリウム砒素(GaAs)に比べて高出力・高効率で、探知距離を大幅に延ばせます。三菱電機は、装備庁の委託を受けて試作機を開発し、2024年に実証試験を実施しました。この技術は、将来のFPS-8レーダーや艦載レーダーに応用される見込みです。
AI活用型電子戦システム
電子戦では、瞬時に敵の電波を分析し、最適な妨害手段を選ぶ必要があります。三菱電機は、機械学習AIを組み込んだ電子戦システムを研究中。膨大な電波データをAIが学習し、未知の脅威にも自動対応できる仕組みです。2025年には、地上試験で有効性が確認されました。
宇宙監視の高度化
SSAレーダーの性能向上も進んでいます。現在は数十センチ以上の物体を追跡できますが、将来的には数センチレベルの小型デブリまで探知する計画。三菱電機は、高感度センサーと高速信号処理技術を開発中です。
技術移転と国産化支援
自衛隊の装備には、米国製システムが多く導入されています。しかし、全てを輸入に頼ると、整備・改修で米国に依存し、コストも高騰します。そこで重要なのがライセンス生産と国産化です。
三菱電機は、米国から技術導入した装備を国内で生産・改良する役割を担っています。例えば:
- PAC-3レーダー:米レイセオン社から技術移転を受け、国内生産。日本の地形や気候に合わせた改良を実施。
- Link 16端末:米国規格に準拠しつつ、自衛隊の既存システムと統合する独自仕様を開発。
- イージスレーダー:SPY-1Dの運用データを蓄積し、将来の国産イージスレーダー開発に活用。
これらの取り組みにより、日本は技術的自立度を高め、有事の際にも装備を自力で維持できる体制を築いています。
防衛装備移転三原則と輸出への対応
2014年、日本は「武器輸出三原則」を緩和し、防衛装備移転三原則を制定しました。これにより、一定の条件下で防衛装備の輸出が可能になりました。三菱電機も、この流れに対応しつつあります。
ただし、三菱重工が潜水艦や戦闘機のような「プラットフォーム」の輸出を模索しているのに対し、三菱電機はレーダーや通信システムといった「コンポーネント」の輸出を重視。東南アジア諸国への防空レーダー供与や、米国との共同開発品の第三国輸出などが検討されています。
詳細は第3回の「輸出と国際協力」セクションで掘り下げます。
防衛産業基盤強化への貢献
防衛装備庁は、日本の防衛産業基盤の維持・強化を重要課題としています。三菱電機は、以下の形で貢献しています:
- サプライチェーンの維持
レーダーや電子機器には、数千点の部品が使われます。三菱電機は、国内中小企業と協力し、特殊部品の供給網を維持。景気変動で防衛需要が減っても、技術が途絶えないよう支援しています。 - 人材育成
防衛電子技術者の育成にも力を入れています。社内研修はもちろん、大学との共同研究や、防衛装備庁の技術者育成プログラムにも協力。次世代の技術者を育てることで、長期的な技術基盤を確保しています。 - 技術標準化
自衛隊の装備は、陸海空で規格がバラバラになりがち。三菱電機は、通信プロトコルやインターフェースの標準化を推進し、異なる装備間の相互運用性を向上させています。
6. 主要製品・技術の深掘り
ここでは、三菱電機の代表的な防衛製品を、技術的特徴と実戦での役割に焦点を当てて深掘りします。
FPS-7レーダー:次世代防空網の要
FPS-7は、航空自衛隊の警戒管制レーダーの最新型です。従来のFPS-3改を置き換える形で、2020年代から配備が進んでいます。
技術的特徴
- アクティブ・フェーズドアレイ方式:機械的に回転する従来型と異なり、電子的にビームを操作。複数方向を同時に監視でき、探知速度が飛躍的に向上。
- L/Sバンドデュアル周波数:異なる周波数を使い分け、ステルス機や小型ドローンにも対応。
- 高速信号処理:最新のデジタル信号処理技術で、ノイズを除去しつつ微弱な信号を検出。巡航ミサイルのような低空飛行目標も捕捉可能。
実戦での役割
FPS-7は、日本の防空識別圏(ADIZ)監視の中核を担います。中国軍機の領空接近や、北朝鮮の弾道ミサイル発射を即座に探知し、戦闘機のスクランブルやPAC-3の警戒態勢を指示。24時間365日、休みなく日本の空を見守っています。
2024年、尖閣諸島周辺で中国海警局の船舶が活動した際、FPS-7が上空を飛行する中国軍機を探知し、空自のF-15が緊急発進。領空侵犯を未然に防ぎました。
将来の発展
現在、FPS-7のさらなる高性能化が検討されています。特に注目されるのが極超音速兵器(HGV)対応。マッハ5以上で飛行するHGVは、従来レーダーでは追尾が困難。三菱電機は、高速目標追尾アルゴリズムの開発を進めており、次期FPS-8での実装を目指しています。
OPS-50多機能レーダー:コンパクトな万能選手
OPS-50は、最新鋭護衛艦「もがみ」型(FFM)に搭載される多機能レーダー。従来は対空・対水上で別々のレーダーを使っていましたが、OPS-50は一台で全てをカバーします。
技術的特徴
- X/Cバンド統合:対空用Xバンドと対水上用Cバンドを統合。一つのアンテナで両方の機能を実現。
- 省電力設計:FFMは少人数で運用するため、電力消費を抑える必要があります。OPS-50は、GaN半導体の採用で高出力かつ省電力を実現。
- モジュラー構成:故障時には故障部品だけを交換できる設計。整備性が高く、稼働率が向上。
実戦での役割
「もがみ」型は、離島防衛や海上交通路警護を主任務とします。OPS-50は、低空飛行する対艦ミサイルや、小型高速艇を探知。さらに、対潜ヘリコプターの管制や、対空ミサイルの射撃管制も担います。
2025年の南西諸島周辺訓練では、OPS-50が複数の模擬目標を同時追尾し、対空ミサイル「ESSM」の模擬射撃を成功させました。
J/APG-2火器管制レーダー:F-2の”目”

F-2戦闘機は、対艦攻撃を主任務とする支援戦闘機です。その心臓部が、三菱電機製のJ/APG-2レーダー。
技術的特徴
- アクティブ・フェーズドアレイ(AESA):世界初の戦闘機搭載AESAレーダーの一つ。電子走査で高速探知。
- 対艦モード:海面のクラッターを除去し、水上艦を精密に探知。対艦ミサイルの照準に不可欠。
- 合成開口レーダー(SAR)モード:地上の静止目標を高解像度で撮影。爆撃精度を向上。
実戦での役割
F-2は、有事の際に敵艦隊を攻撃する切り札です。J/APG-2は、100km以上離れた艦艇を探知し、ASM-2対艦ミサイルを誘導。海上自衛隊との連携で、日本周辺の制海権を守ります。
訓練では、悪天候下でも目標を正確に捕捉する能力が実証されています。
Link 16データリンク端末:情報共有の要
Link 16は、NATO標準の戦術データ通信システム。航空機、艦艇、地上部隊が暗号化された戦術情報を共有します。三菱電機は、自衛隊向けのLink 16端末を国産化し、独自の改良を加えています。
技術的特徴
- 高速データ伝送:秒間数千メッセージを送受信。敵機の位置や味方の状況をリアルタイム共有。
- 耐ジャミング性:周波数ホッピング技術で、敵の妨害に強い。
- 多層暗号化:NSA(米国家安全保障局)基準の暗号で、傍受・解読を防止。
実戦での役割
Link 16により、自衛隊は米軍や同盟国と情報を共有できます。例えば、航空自衛隊のE-2D早期警戒機が探知した敵機情報を、Link 16経由で海自のイージス艦や空自のF-35戦闘機に送信。統合的な防空網を構築します。
2024年の日米共同訓練では、Link 16を通じて自衛隊と米軍が情報を共有し、模擬敵を迎撃する演習が成功しました。
電子戦装置:見えない戦いの主役
三菱電機の電子戦装置は、多岐にわたります。代表例をいくつか紹介します。
J/ALQ-6電波探知装置(F-2搭載)
敵レーダーの電波を探知し、種類と方位を特定。パイロットに警告を発し、回避行動や電子妨害の判断材料を提供します。
地上設置型ジャマー
特定周波数の電波を強力に発信し、敵レーダーを無効化。陸上自衛隊が離島防衛で使用を想定。敵の上陸作戦を妨害します。
赤外線対策装置(IRCM)
赤外線誘導ミサイルから航空機を守ります。フレア(熱源おとり)を射出したり、指向性赤外線で敵ミサイルのセンサーを欺瞞。陸自のCH-47輸送ヘリや、UH-60多用途ヘリに搭載されています。
7. 競合との比較:東芝・NEC・OKIとの違い
日本の防衛電子産業は、三菱電機の独壇場ではありません。東芝、NEC、OKIといった企業も重要な役割を果たしています。それぞれの特徴と、三菱電機との違いを見てみましょう。
東芝:潜水艦ソナーと指揮統制の雄
東芝は、特に対潜戦(ASW)システムで強みを持ちます。海上自衛隊の潜水艦に搭載されるソナー(音響探知機)や、護衛艦の戦術情報処理装置を手がけています。
三菱電機がレーダー中心なのに対し、東芝は音響技術と情報処理が得意。両社は競合しつつも、護衛艦では三菱電機がレーダー、東芝がソナーと指揮装置――という形で棲み分けています。
ただし、東芝は2017年の経営危機以降、防衛事業を縮小気味。三菱電機が市場シェアを拡大する傾向にあります。
NEC:通信とサイバーセキュリティの専門家
NECは、通信ネットワークとサイバーセキュリティに強みを持ちます。自衛隊の衛星通信システムや情報セキュリティ基盤を構築。また、指紋認証や顔認証などの生体認証技術を防衛施設のセキュリティに提供しています。
三菱電機が「戦術レベルの通信(Link 16など)」を担うのに対し、NECは「戦略レベルの通信インフラ」を担当。役割が異なるため、直接的な競合は少なめです。
また、NECは宇宙分野でも強く、偵察衛星の開発で実績があります。三菱電機と共同でプロジェクトを進めることも多いです。
OKI:戦術通信機器のニッチプレイヤー
OKI(沖電気工業)は、戦術無線機や野戦通信装置を得意とします。陸上自衛隊の部隊間通信で使われる携帯無線機や、車載無線装置を供給。小型・軽量・頑丈な設計が評価されています。
三菱電機が大型レーダーや艦載システムといった「大物」を扱うのに対し、OKIは「小型戦術機器」に特化。市場規模は小さいですが、ニッチ市場で確固たる地位を築いています。
三菱電機の優位性まとめ
三菱電機が他社と比較して優れている点は、以下の通りです:
- レーダー技術の圧倒的実績:60年以上の開発・運用経験。競合他社を大きく引き離しています。
- 統合システム構築力:レーダー、通信、電子戦を一貫して手がけられるため、システム全体の最適化が可能。
- 民生技術との相乗効果:家電や産業機器で培った電子技術・生産技術を防衛に応用。コスト削減と品質向上を実現。
- 国際協力の実績:米国やNATO諸国との共同開発経験が豊富。次世代技術へのアクセスが容易。
一方で、弱点もあります。後述の「課題とリスク」セクションで詳しく触れます。
8. 防衛事業の業績と今後の展望
三菱電機の防衛事業は、収益性が高く、安定した成長を続けています。ここでは、財務データと市場環境から今後を展望します。
業績推移と収益構造
前述の通り、三菱電機の防衛事業売上は推定で年間2,000億~3,000億円。全社売上の約5~6%を占めます。規模は大きくありませんが、営業利益率が15~20%と非常に高いのが特徴です。
これは、以下の理由によります:
- 高付加価値製品:レーダーや電子戦装備は技術難易度が高く、価格競争になりにくい。
- 長期契約と保守収益:一度納入した装備は、数十年にわたって保守・改修が発生。継続的な収益源となります。
- 随意契約の多さ:競争入札が少ないため、適正利益を確保しやすい。
2020年代前半の業績を見ると、防衛事業は堅調に推移しています。特に、以下の要因が成長を後押ししています:
- 防衛費増額:日本政府は2027年度までに防衛費をGDP比2%に引き上げる方針。レーダーや通信システムへの投資が増加。
- 装備の老朽化更新:冷戦期に配備された装備が更新時期を迎えており、需要が旺盛。
- 新領域対応:宇宙、サイバー、電磁波といった新領域での装備開発に予算が投入されている。
今後の成長要素
三菱電機の防衛事業が今後成長するカギは、以下の4つです。
1. 次世代戦闘機GCAP
日英伊共同開発の次世代戦闘機GCAPは、総事業費数兆円規模のビッグプロジェクト。三菱電機は、電子戦システムと統合RFセンサーを担当します。これらは戦闘機の「頭脳」にあたる部分で、開発費だけで数百億円、生産・保守まで含めれば数千億円の収益が見込まれます。
2030年代の量産開始後は、輸出も視野に入れており、長期的な収益源となるでしょう。
2. ミサイル防衛の強化
北朝鮮の核・ミサイル開発、中国の軍事力増強を背景に、ミサイル防衛の強化は待ったなしです。政府は、イージス・アショア代替艦の建造や、統合防空ミサイル防衛(IAMD)システムの構築を進めています。
三菱電機は、これらのプロジェクトでレーダーや指揮統制システムを供給する見込み。2020年代後半から2030年代にかけて、大型受注が期待されます。
3. 宇宙監視・宇宙防衛
宇宙は、21世紀の新たな戦場です。日本政府は、宇宙作戦隊を創設し、SSA能力を強化しています。三菱電機は、既存のSSAレーダーの増強に加え、宇宙配備型センサーや衛星通信システムの開発も視野に入れています。
宇宙関連予算は今後急増する見込みで、三菱電機にとって大きなチャンスです。
4. 輸出とライセンス生産
防衛装備移転三原則の下、日本の防衛装備輸出が徐々に進んでいます。三菱電機は、東南アジア諸国への防空レーダー輸出や、米国との共同開発品の第三国供与を模索中。
特に、フィリピンやベトナムといった南シナ海沿岸国は、中国の海洋進出に対抗するため防空能力強化を急いでいます。三菱電機のレーダーは、性能・信頼性・価格のバランスが良く、輸出競争力があります。
2030年の姿を予測する
これらの成長要因が実現すれば、2030年の三菱電機防衛事業は以下のような姿になるでしょう:
- 売上規模:年間4,000億~5,000億円(現在の約1.5~2倍)
- 営業利益率:20%前後(高付加価値化により維持・向上)
- 主力製品:GCAP電子戦システム、次世代イージスレーダー、宇宙監視システム
- 輸出比率:10~15%(現在はほぼゼロ)
もちろん、これは楽観的なシナリオです。次のセクションで触れる課題やリスクもあり、実現には困難が伴います。
9. 輸出と国際協力の可能性
三菱電機の防衛事業は、長らく国内市場に特化してきました。しかし、防衛装備移転三原則の制定と、国際的な安全保障環境の変化により、輸出と国際協力が新たな成長ドライバーとして注目されています。
防衛装備移転三原則と三菱電機の対応
2014年、日本政府は「武器輸出三原則」を見直し、防衛装備移転三原則を制定しました。これにより、以下の条件下で防衛装備の輸出が可能になりました:
- 平和貢献・国際協力の積極的推進
- 日本の安全保障に資する場合
- 透明性の確保
三菱電機は、この新方針を受けて輸出戦略を本格化させています。ただし、三菱重工のような「完成装備品(戦闘機や潜水艦)」の輸出ではなく、レーダーや通信システムといったコンポーネントに焦点を当てています。
東南アジア市場:フィリピンへのレーダー輸出
三菱電機の防衛輸出で最も注目されるのが、フィリピンへの防空レーダー供与です。
2020年、日本政府はフィリピンに警戒管制レーダー4基を無償供与することを決定。このレーダーは、三菱電機が開発したFPS-3ME(輸出仕様)で、移動式で展開が容易、対空・対水上両用という特徴があります。
フィリピンは、南シナ海で中国と領有権問題を抱えており、防空能力の強化が急務でした。日本としても、同盟国・友好国の防衛力向上は、地域の安定と自国の安全保障に直結します。三菱電機のレーダーは、この戦略的ニーズにぴったりでした。
2024年、第1号機がフィリピン空軍に引き渡され、ルソン島に配備されました。現地では高く評価されており、追加調達の可能性も報じられています。
ベトナム・インドネシアへの展開可能性
ベトナムとインドネシアも、中国の海洋進出に対抗するため、防空・海洋監視能力の強化を急いでいます。両国とも日本との関係が良好で、防衛協力が進んでいます。
ベトナムは、沿岸監視レーダーの整備を計画中。三菱電機は、日本政府の支援の下、レーダー供与の可能性を探っています。ベトナムは旧ソ連製装備が中心ですが、近代化の一環として西側装備の導入を進めており、日本製レーダーの導入は象徴的意味も持ちます。
インドネシアは、広大な海域を持つ島嶼国家。海洋監視と防空が課題です。2023年、日本とインドネシアは防衛装備協力の覚書を締結。三菱電機のレーダーや通信システムが候補に挙がっています。
米国との共同開発と第三国供与
三菱電機は、米国企業との共同開発にも積極的です。特に、レイセオン・テクノロジーズ(旧レイセオン社)とは長年の協力関係があります。
例えば、PAC-3ミサイルシステムでは、レイセオンが主契約者、三菱電機がレーダー改良と射撃管制装置を担当。この協力関係を活かし、第三国へのPAC-3輸出における日本製コンポーネントの供給が検討されています。
また、次世代戦闘機GCAPでも、米国企業との協力が進行中。電子戦システムの一部は、米国の同盟国(オーストラリア、韓国など)への輸出も視野に入れています。
欧州市場:NATOとの相互運用性
三菱電機は、NATO標準の通信システム(Link 16など)を手がけており、欧州市場への参入余地があります。
特に、ポーランドやバルト三国など、ロシアの脅威に直面する東欧諸国は、防空システムの強化を急いでいます。日本製レーダーは、性能・信頼性・価格のバランスが良く、欧州市場でも競争力があります。
2025年、三菱電機はポーランドの防衛展示会に出展し、FPS-7レーダーのデモンストレーションを実施。現地の反応は上々で、今後の商談が期待されています。
輸出の課題と障壁
もちろん、輸出には課題もあります。
価格競争
欧米や韓国のメーカーは、大量生産でコストを下げています。日本は少量生産が中心で、価格面で不利です。三菱電機は、性能と信頼性で差別化を図っていますが、価格に敏感な途上国市場では苦戦する可能性があります。
政府間交渉の複雑さ
防衛装備の輸出は、企業間の商談だけでは完結しません。政府間の合意、技術移転の範囲、メンテナンス体制の構築など、複雑な交渉が必要です。日本は輸出経験が浅く、ノウハウの蓄積が課題です。
技術流出リスク
最先端技術が第三国に流出し、さらに敵対国に渡るリスクもあります。三菱電機は、輸出仕様では機密性の高い部分をブラックボックス化するなど、対策を講じています。
国内世論
「武器輸出」に対する国内の反発も根強く残っています。三菱電機は、「平和貢献」「地域の安定」という大義名分を前面に出し、慎重に進める姿勢です。
2030年の輸出展望
これらの課題を踏まえつつ、三菱電機の輸出は着実に拡大するでしょう。2030年には、以下のような姿が予想されます:
- 輸出比率:防衛事業売上の10~15%(現在はほぼゼロ)
- 主要輸出先:東南アジア(フィリピン、ベトナム、インドネシア)、東欧(ポーランド)、中東(UAE、サウジアラビア)
- 主力製品:警戒管制レーダー、沿岸監視レーダー、衛星通信装置
- 協力形態:政府間無償供与、商業ベースの直接販売、米欧企業との共同提案
輸出は、単なる収益源ではありません。国際的な存在感の向上、同盟国・友好国との関係強化、技術の国際標準化――これらを通じて、日本の安全保障にも貢献するのです。
10. 課題とリスク
三菱電機の防衛事業は順風満帆に見えますが、いくつかの課題とリスクも抱えています。
人材不足と技術継承
防衛電子技術は、高度な専門知識と長年の経験が必要です。しかし、少子高齢化により、技術者の確保が困難になっています。
三菱電機は、2020年代に入り、防衛部門の採用を強化。新卒採用だけでなく、中途採用や他部門からの配置転換も進めています。また、ベテラン技術者の定年延長や、OBによる技術指導制度も導入。技術の継承に全力を挙げています。
それでも、レーダー設計や電子戦アルゴリズムといった特殊技能は、一朝一夕には習得できません。10年後、20年後を見据えた計画的な人材育成が不可欠です。
サプライチェーンの脆弱性
防衛装備には、数千点の部品が使われます。その多くは、中小企業が供給しています。しかし、防衛需要は変動が大きく、採算が取りにくいため、撤退する企業が増えています。
三菱電機は、サプライヤーとの長期契約や、技術支援を通じて、供給網の維持に努めています。また、部品の共通化・標準化を進め、調達先を複数確保する「マルチソース化」も推進中です。
さらに、半導体不足も深刻です。レーダーや通信機器には、高性能な半導体が不可欠。世界的な半導体不足が続く中、安定調達が課題となっています。三菱電機は、国内半導体メーカー(ルネサス、ソニーなど)との連携を強化し、優先供給を受ける体制を構築しています。
サイバーセキュリティ脅威
防衛システムは、サイバー攻撃の標的になりやすい分野です。敵国が、レーダーや通信システムにマルウェアを仕込み、有事の際に無力化する――こんなシナリオは、もはやSFではありません。
三菱電機は、2020年に大規模なサイバー攻撃を受け、防衛関連情報が流出する事件がありました。この教訓を踏まえ、セキュリティ体制を抜本的に強化。以下の対策を実施しています:
- ネットワーク分離:防衛システムと民生システムを物理的に分離。
- 多層防御:ファイアウォール、侵入検知システム、暗号化を多層化。
- ゼロトラスト:「内部も信用しない」前提で、全てのアクセスを検証。
- 定期監査:外部専門家による脆弱性診断を定期実施。
それでも、サイバー攻撃は日々進化しており、完全な防御は困難です。継続的な投資と警戒が求められます。
予算変動リスク
防衛費は、政治・経済情勢に左右されます。現在は増額傾向ですが、将来的に財政悪化や政権交代で削減される可能性もあります。
三菱電機は、防衛依存度を下げるため、民生技術との相乗効果を重視しています。例えば、レーダー技術は気象観測や自動運転にも応用可能。通信技術は5G/6Gネットワークに活かせます。防衛と民生の技術を相互に活用することで、リスクを分散しています。
国際競争の激化
防衛市場は、グローバル化が進んでいます。米国のロッキード・マーティンやレイセオン、欧州のタレス、韓国のハンファシステムなど、強力なライバルがひしめいています。
三菱電機の強みは、高い技術力と日本市場での実績。しかし、輸出市場では新参者です。価格、納期、アフターサービスで競争力を高める必要があります。
特に、韓国企業の追い上げは脅威です。韓国は、政府が輸出を強力に後押しし、ポーランドやオーストラリアで大型契約を獲得しています。三菱電機も、政府との連携を強化し、「オールジャパン」で戦う体制を築く必要があります。
11. ミリタリーファンが知っておくべきポイント
ここまで、三菱電機の防衛事業を多角的に解説してきました。最後に、ミリタリーファンの皆さんが押さえておくべきポイントをまとめます。
三菱電機製装備を見分ける方法
自衛隊の基地祭や観艦式で、三菱電機製の装備を見分けるコツをご紹介します。
レーダーの特徴
- 固定式警戒管制レーダー:巨大な四角いアンテナが特徴。FPS-3改は回転式、FPS-7は固定式(電子走査)。
- 艦載レーダー:護衛艦のマストに設置された八角形のアンテナ。OPS-24は大型、OPS-50は小型でスリム。
- 移動式レーダー:トレーラーに搭載された展開式アンテナ。J/TPS-102は、約30分で展開可能。
通信・電子戦装備
- Link 16端末:航空機や艦艇の操縦席・艦橋に設置された専用ディスプレイ。地図上に味方・敵の位置がリアルタイム表示されます。
- 電子戦ポッド:F-2戦闘機の翼下に吊り下げられた細長いポッド。J/ALQ-6電波探知装置やジャマーが内蔵されています。
関連施設・展示
三菱電機の防衛技術に触れられる場所をご紹介します。
三菱電機鎌倉製作所
神奈川県鎌倉市にある鎌倉製作所は、防衛・宇宙システムの主力拠点。一般公開はされていませんが、年に数回、地域イベントで施設の一部が公開されることがあります。事前に公式サイトをチェックしましょう。
航空自衛隊 基地祭
全国の航空自衛隊基地で開催される基地祭では、FPS-7レーダーやPAC-3システムが展示されることがあります。特に、入間基地(埼玉)、浜松基地(静岡)、築城基地(福岡)は規模が大きく、見応えがあります。
海上自衛隊 観艦式
数年に一度開催される観艦式では、最新鋭の護衛艦が勢揃い。OPS-24やOPS-50レーダーを搭載した艦艇を間近で見られます。次回は2026年開催予定(2025年現在)。
防衛技術博物館(構想中)
防衛省は、過去の装備品を展示する博物館の設立を検討中。実現すれば、三菱電機の歴代レーダーや通信機器も展示されるでしょう。続報を待ちましょう。
おすすめ書籍・資料
三菱電機の防衛事業をもっと知りたい方におすすめの資料です。
書籍
- 『日本の防衛産業』(東洋経済新報社)日本の防衛産業全体を俯瞰する入門書。三菱電機の位置づけも詳しく解説されています。
- 『レーダー技術の基礎と応用』(オーム社)
レーダーの仕組みを技術的に解説。三菱電機のレーダーがどう動いているのか理解できます。 - 『自衛隊装備年鑑』(朝雲新聞社、毎年刊行)
自衛隊の全装備を網羅。三菱電機製装備のスペックや配備状況が詳細に記載されています。
ウェブサイト
- 三菱電機 公式サイト 防衛・宇宙システム事業
製品情報やニュースリリースが掲載されています。ただし、機密性の高い情報は限定的。 - 防衛装備庁 公式サイト
契約実績や研究開発プロジェクトが公開されています。三菱電機の受注状況も確認できます。 - Jane’s Defence Weekly(英語)
世界的な防衛専門誌。日本の防衛産業に関する記事も豊富です。
プラモデル・ゲームで楽しむ
三菱電機の装備は、プラモデルやゲームでも楽しめます。
プラモデル
- 1/700 護衛艦「まや」(ピットロード)
イージス艦「まや」のプラモデル。SPY-1レーダー(三菱電機が国産化支援)が精密に再現されています。 - 1/700 護衛艦「もがみ」(アオシマ)
最新鋭FFM「もがみ」のキット。OPS-50レーダーのディテールが見事です。
ゲーム
- 『War Thunder』
リアル志向の戦闘機・戦車ゲーム。F-2戦闘機が登場し、J/APG-2レーダーの性能も再現されています。 - 『艦これ(艦隊これくしょん)』
大人気の艦船擬人化ゲーム。護衛艦「まや」「もがみ」が実装されており、レーダー装備の重要性が描かれています。
12. まとめ:三菱電機が描く防衛の未来
ここまで、三菱電機の防衛事業を歴史、技術、業績、国際展開、課題まで徹底的に解説してきました。最後に、三菱電機が描く防衛の未来を展望し、記事を締めくくります。
「見えない戦力」の重要性はさらに高まる
現代戦は、もはや「戦車や戦闘機の数」だけでは決まりません。情報優越、電子戦、サイバー戦――「見えない戦力」が勝敗を分ける時代です。
三菱電機が得意とするレーダー、通信、電子戦は、まさにこの領域の中核。今後、AI、量子技術、極超音速兵器といった新技術が登場しても、情報を集め、伝え、敵を欺くという基本原理は変わりません。三菱電機の役割は、ますます重要になるでしょう。
宇宙・サイバー・電磁波――新領域での挑戦
防衛省は、宇宙・サイバー・電磁波を重視する方針を打ち出しています。三菱電機は、この3領域全てで強みを持っています。
- 宇宙:SSAレーダー、衛星搭載機器
- サイバー:暗号化通信、セキュリティシステム
- 電磁波:電子戦装備、高出力マイクロ波兵器
特に、高出力マイクロ波兵器(HPM)は注目技術です。強力な電磁波でドローンや電子機器を無力化する兵器で、三菱電機は実証実験を進めています。2030年代には実用化される見込みです。
国際協力と輸出の拡大
日本の防衛産業は、長らく「国内完結型」でした。しかし、グローバル化と安全保障環境の変化により、国際協力と輸出が不可欠になっています。
三菱電機は、フィリピンへのレーダー輸出を皮切りに、東南アジア、東欧、中東へと市場を広げています。また、GCAPのような多国間共同開発も増えるでしょう。
輸出は、単なるビジネスではありません。同盟国・友好国の防衛力を高めることで、地域の安定を実現し、日本の安全保障にも貢献する――この戦略的意義を忘れてはなりません。
民生技術との融合
三菱電機の強みは、民生技術と防衛技術の相乗効果です。レーダー技術は自動運転や気象観測に、通信技術は5G/6Gに、AI技術は産業ロボットに応用されます。
逆に、民生で培った技術が防衛に還元されることもあります。例えば、スマートフォンの小型高性能チップは、携帯型通信機器に応用可能。家電の省電力技術は、電池駆動の野戦装備に役立ちます。
この「デュアルユース(軍民両用)」戦略は、リスク分散だけでなく、技術革新のスピードアップにもつながります。
次世代を担う技術者へのメッセージ
三菱電機の防衛事業は、日本の安全保障を支える誇り高い仕事です。しかし、技術者不足という課題も抱えています。
もしあなたが、電気・電子・情報工学を学ぶ学生や、キャリアチェンジを考える技術者なら、ぜひ防衛産業に目を向けてみてください。最先端技術に触れ、国の安全に貢献できるやりがいのある分野です。
三菱電機は、新卒・中途採用を強化しており、研修制度も充実しています。興味のある方は、公式採用サイトをチェックしてみてください。
最後に:「陰の功労者」に敬意を
三菱電機の防衛事業は、華々しいスポットライトを浴びることは少ないかもしれません。戦闘機や戦車のように、一目で分かる「かっこよさ」もないかもしれません。
しかし、レーダーが敵機を探知し、通信が情報を伝え、電子戦が敵を欺く――これらがなければ、どんな強力な兵器も役に立ちません。三菱電機は、まさに「陰の功労者」なのです。
私たちが安心して暮らせるのは、こうした「見えない戦力」が24時間365日、日本を守り続けているから。その技術と努力に、心から敬意を表します。
【関連記事へのリンク】
- 日本の防衛産業・軍事企業一覧【2025年最新】三菱電機以外の防衛企業も網羅。日本の防衛産業全体を理解できます。
- 【2025年解説】三菱重工の防衛産業
「三菱つながり」で混同されがちな三菱重工の防衛事業を詳しく解説。両社の違いが明確に分かります。 - 【2025年最新】川崎重工の防衛事業を徹底解説
潜水艦やヘリで有名な川崎重工。三菱電機との協力関係も紹介されています。 - 【2025年最新版】海上自衛隊の艦艇完全ガイド
三菱電機のレーダーが搭載された護衛艦の詳細情報が満載。 - 【2025年最新版】日本の戦闘機一覧
F-2戦闘機のJ/APG-2レーダーなど、三菱電機製装備が活躍する戦闘機を網羅。
【おすすめ商品】
三菱電機の防衛技術をもっと深く知りたい方、ミリタリー模型で楽しみたい方におすすめの商品をご紹介します。
書籍
- 『日本の防衛産業』(東洋経済新報社)
Amazonで見る
日本の防衛産業全体を俯瞰する決定版。三菱電機の位置づけも詳しく解説されています。 - 『自衛隊装備年鑑 2025』(朝雲新聞社)
Amazonで見る
自衛隊の全装備を網羅。三菱電機製レーダーや通信機器のスペックが詳細に記載されています。 - 『レーダー技術入門』(オーム社)
Amazonで見る
レーダーの仕組みを基礎から学べる技術書。三菱電機のレーダーがどう動いているのか理解できます。
プラモデル
- 1/700 海上自衛隊 イージス護衛艦 DDG-179まや(ピットロード)
Amazonで見る
最新鋭イージス艦「まや」のプラモデル。SPY-1レーダー(三菱電機が国産化支援)が精密に再現されています。 - 1/700 海上自衛隊 護衛艦 FFM-1 もがみ(アオシマ)
Amazonで見る
最新鋭FFM「もがみ」のキット。OPS-50レーダーのディテールが見事です。 - 1/72 航空自衛隊 F-2A 戦闘機(ハセガワ)
Amazonで見る
F-2戦闘機の精密モデル。J/APG-2レーダーや電子戦ポッドも再現されています。
DVD・ブルーレイ
- 『自衛隊 最前線の記録』(NHKエンタープライズ)
Amazonで見る
自衛隊の訓練や装備を記録したドキュメンタリー。三菱電機製レーダーの運用シーンも登場します。 - 『沈黙の艦隊 北極海大海戦』(Blu-ray)
Amazonで見る
人気漫画の実写映画化。イージス艦のレーダーシステムがリアルに描かれています。
【締め】
三菱電機の防衛事業は、華やかさこそないものの、日本の安全保障を根底で支える「縁の下の力持ち」です。レーダー、通信、電子戦――これらの「見えない戦力」なくして、現代の自衛隊は成り立ちません。
80年以上にわたる技術の蓄積、民生技術との相乗効果、そして国際協力への挑戦。三菱電機は、日本の防衛の未来を切り開いています。
ミリタリーファンの皆さん、次に自衛隊の装備を見る時は、ぜひ「三菱電機製かな?」と想像してみてください。そのレーダーが、今この瞬間も日本の空と海を見守っているのです。





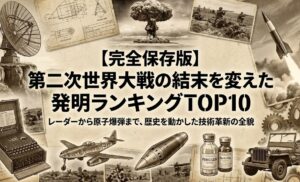




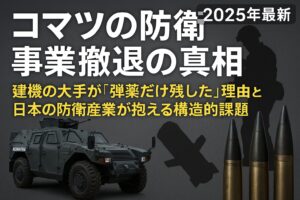

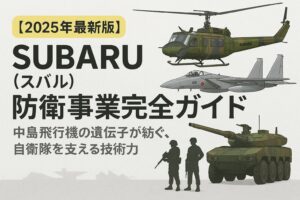
コメント