1944年冬、ベルギーの濃霧に現れた「王虎」

1944年12月16日早朝、ベルギー・アルデンヌの森。
夜明け前の濃霧の中、地響きとともに巨大な影が姿を現した。全長10メートル超、重量70トン近い鋼鉄の塊――ティーガーII、通称「キングタイガー(王虎)」だ。
その傾斜装甲の前面は150mm。実質的に200mm以上の防御力を持つ。砲塔前面に至っては185mmの均質圧延装甲。そして、6メートルを超える長砲身から放たれる88mm砲弾は、2,000m先の敵戦車を一撃で粉砕する。
米軍第7機甲師団の戦車兵たちは、この「怪物」を目の当たりにして凍りついた。
「まるで城が動いているようだった」 「我々のシャーマンの砲弾は、すべて跳ね返された」 「正面から撃破するなど、不可能だ」
――米軍第3機甲師団 戦闘報告書より
ティーガーIIは、第二次世界大戦でドイツが生み出した「究極の重戦車」だった。わずか489輌しか生産されなかったこの戦車は、戦局を変えることはできなかった。しかし、その圧倒的な性能は、連合軍兵士たちに深い恐怖を刻み込んだ。
僕自身、子どもの頃に戦車のプラモデルカタログでティーガーIIを見た時、その威圧感に心を奪われた。あの長い砲身、傾斜した装甲、そして「王虎」という名前――すべてが「最強」を象徴していた。
日本とドイツ。僕たちは同じ枢軸国として、そして敗戦国として、複雑な歴史を共有している。ティーガーIIは、技術の粋を極めながらも、戦争という巨大なシステムの前に敗れ去った「悲劇の傑作」だ。
今回は、このティーガーII――「絶対防御」を纏った最強重戦車の全貌を、開発から実戦、弱点、そして現代での楽しみ方まで、徹底的に解説していく。
関連記事:【完全保存版】第二次世界大戦ドイツ最強戦車ランキングTOP10|ティーガーから幻の超重戦車まで徹底解説
ティーガーII(キングタイガー)とは何か?
基本概要
ティーガーII(Panzerkampfwagen Tiger II)は、ドイツが第二次世界大戦末期に開発・生産した重戦車だ。正式名称は「VI号戦車B型(Panzerkampfwagen VI Ausführung B)」。
愛称の「キングタイガー(Königstiger)」は、英語圏での呼称だ。ドイツ語の「Königstiger」は本来「ベンガルトラ」を意味するが、英語圏では「King Tiger(王虎)」と訳され、この名前が世界中に広まった。
ティーガーIIは、先代のティーガーIをあらゆる面で上回る性能を目指して開発された。特に注目すべきは:
- 圧倒的な装甲防御力: 前面150mm(傾斜50度)、砲塔前面185mm
- 強力な主砲: 88mm KwK 43 L/71長砲身砲
- 傾斜装甲の採用: ソ連のT-34とパンターから学んだ設計思想
連合軍兵士たちは、この戦車を「無敵」と恐れた。実際、正面から撃破されたティーガーIIは極めて少ない。
基本スペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全長 | 10.286m(砲身含む)、車体7.38m |
| 全幅 | 3.755m |
| 全高 | 3.09m |
| 重量 | 約69.8トン |
| 乗員 | 5名(車長、砲手、装填手、操縦手、無線手) |
| 主砲 | 88mm KwK 43 L/71(71口径長) |
| 副武装 | 7.92mm MG34機関銃×2 |
| エンジン | マイバッハ HL230 P30 V型12気筒ガソリンエンジン(700馬力) |
| 最高速度 | 路上41.5km/h、不整地15〜20km/h |
| 航続距離 | 約170km(路上)、約120km(不整地) |
| 装甲厚 | 前面150mm(傾斜50度)、側面80mm、砲塔前面185mm |
| 生産期間 | 1944年1月〜1945年3月 |
| 生産台数 | 約489輌 |
この数字を見るだけでも、ティーガーIIの「規格外」ぶりがわかる。重量70トン近く、装甲150mm以上――これは、もはや戦車ではなく「移動要塞」と呼ぶべき存在だった。
ティーガーIIが生まれた背景――「もっと強い戦車を」
ティーガーIの成功と限界
1942年、ドイツ軍に配備されたティーガーI(Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf. E)は、圧倒的な性能で連合軍を震撼させた。
- 88mm砲による強力な火力
- 100mmの装甲による高い防御力
- 連合軍戦車に対する圧倒的優位
しかし、1943年に入ると、ティーガーIにも限界が見え始めた。
- ソ連のT-34/85とIS-2重戦車の登場
ソ連は、T-34に85mm砲を搭載したT-34/85を投入。さらに、122mm砲を搭載したIS-2重戦車も登場した。これらの戦車は、ティーガーIの側面装甲を貫通できる火力を持っていた。
- 西部戦線でのシャーマン・ファイアフライ
イギリス軍は、シャーマン戦車に17ポンド砲(76.2mm)を搭載した「ファイアフライ」を投入。この砲は、1,000m以内でティーガーIの前面装甲を貫通できる性能を持っていた。
- 増加装甲による重量増加
ティーガーIは、実戦での経験から増加装甲を追加されることが多くなった。これにより、重量が増加し、機動性が低下していた。
ドイツ軍首脳部は、決断を下した。
「ティーガーIを超える、絶対的な重戦車を開発せよ」
ヒトラーの要求――「無敵の戦車」

1943年初頭、ヒトラーはポルシェ博士とヘンシェル社に対し、次世代重戦車の開発を命じた。
ヒトラーの要求は明確だった:
- ティーガーIの88mm砲より強力な主砲
- 100mmを超える装甲厚
- パンターの傾斜装甲を採用
- 連合軍のあらゆる戦車に対して絶対的優位を確保
この要求に応えるため、2つの設計案が提出された。
- ポルシェ案(VK 4502 P)
フェルディナント・ポルシェ博士が設計。電気式トランスミッション(ガソリンエンジンで発電→電気モーターで駆動)を採用。砲塔はポルシェ砲塔と呼ばれる曲面を多用したデザイン。
- ヘンシェル案(VK 4503 H)
ヘンシェル社が設計。従来型の機械式トランスミッションを採用。砲塔はヘンシェル砲塔と呼ばれる傾斜装甲を多用したデザイン。
1943年10月、試作車の比較テストが行われた。結果、ヘンシェル案が採用された。
理由は明確だった:
- 機械式トランスミッションの方が信頼性が高い
- 電気式は銅などの希少資源を大量に消費する
- 生産性が高い
こうして、ティーガーII(ヘンシェル砲塔型)が誕生した。
しかし、興味深いことに、初期の50輌はポルシェ砲塔を搭載して生産された。これは、ヘンシェル案が採用される前に、ポルシェ博士がすでに砲塔を50基発注していたためだ。
現在、ポルシェ砲塔型とヘンシェル砲塔型の2種類が存在するのは、この経緯による。
パンターとの関係――「傾斜装甲」という革命
ティーガーIIの設計には、パンターV型戦車から学んだ要素が色濃く反映されている。
関連記事:パンターV型戦車完全ガイド
特に傾斜装甲の採用だ。
パンターは、ソ連のT-34から学んだ傾斜装甲を採用し、80mmの装甲厚を実質140mm相当の防御力に高めていた。ティーガーIIも、この思想を受け継いだ。
- 前面装甲150mmを50度傾斜 → 実質200mm以上の防御力
- 砲塔前面185mmの傾斜装甲 → 実質220mm以上の防御力
この設計により、ティーガーIIは「正面から撃破不可能」な戦車となった。
ティーガーIIの詳細スペックと技術的特徴

主砲――88mm KwK 43 L/71という「絶対火力」
ティーガーIIの主砲は、88mm KwK 43 L/71(71口径長、砲身長6.248m)だ。
この砲は、ティーガーI(56口径長)よりはるかに強力で、事実上「対戦車砲の最終形態」と言える性能を持っていた。
貫徹力
| 距離 | 装甲貫徹力(垂直装甲) |
|---|---|
| 500m | 274mm |
| 1,000m | 237mm |
| 1,500m | 219mm |
| 2,000m | 202mm |
| 3,000m | 173mm |
この数字が何を意味するか?
- シャーマン戦車(前面装甲51mm): 3,000m以上の距離から一撃で撃破可能
- T-34/85(前面装甲45mm傾斜): 2,500m以上の距離から撃破可能
- IS-2重戦車(前面装甲120mm): 1,500m以内で撃破可能
ティーガーIIの88mm砲は、連合軍のあらゆる戦車を、安全な距離から一方的に撃破できたのだ。
砲弾の種類
ティーガーIIの88mm砲は、以下の砲弾を使用できた:
- PzGr 39/43 徹甲弾(APCBC-HE)
- 重量10.4kg
- 初速1,000m/秒
- 最も一般的な対戦車砲弾
- PzGr 40/43 硬芯徹甲弾(APCR)
- 重量7.3kg
- 初速1,130m/秒
- タングステン芯を使用、貫徹力最大
- 希少資源のため、使用は限定的
- Sprgr 43 榴弾(HE)
- 重量7.65kg
- 対歩兵・対陣地用
照準装置
ティーガーIIには、ツァイス製TZF 9d/1照準器が搭載されていた。
この照準器は、2.5倍の拡大率を持ち、距離測定用の目盛りが刻まれていた。熟練した砲手であれば、2,000m以上の距離でも高精度の射撃が可能だった。
実戦記録を見ると、驚くべき報告がある:
「SS第501重戦車大隊のティーガーIIが、3,500m以上の距離からシャーマン戦車を撃破した」 ――1944年8月、フランス・ノルマンディー戦線
3.5km――これは、肉眼ではほとんど見えない距離だ。ティーガーIIの射撃精度がいかに高かったかがわかる。
装甲――「絶対防御」の真実

ティーガーIIの装甲は、第二次世界大戦のドイツ戦車の中でも最強クラスだった。
装甲配置
| 部位 | 装甲厚 | 傾斜角 | 実質防御力 |
|---|---|---|---|
| 前面上部(車体) | 150mm | 50度 | 約200mm以上 |
| 前面下部(車体) | 100mm | 50度 | 約140mm |
| 側面(車体) | 80mm | 垂直 | 80mm |
| 後面(車体) | 80mm | 垂直 | 80mm |
| 砲塔前面 | 185mm | 傾斜 | 約220mm以上 |
| 砲塔側面 | 80mm | 傾斜 | 約100mm |
| 上面(車体) | 40mm | – | 40mm |
連合軍の対戦車砲との比較
連合軍の主要対戦車砲で、ティーガーIIの前面装甲を貫通できるものは、ほとんどなかった。
| 兵器 | 貫徹力(1,000m) | ティーガーII前面貫通 |
|---|---|---|
| シャーマン75mm砲 | 約60mm | 不可能 |
| T-34/85 85mm砲 | 約100mm | 不可能 |
| シャーマン・ファイアフライ 17ポンド砲 | 約140mm | 至近距離でも厳しい |
| IS-2 122mm砲 | 約160mm | 500m以内なら可能 |
| M26パーシング 90mm砲 | 約120mm | 不可能 |
実戦記録を見ると:
「ティーガーIIの前面装甲に、シャーマンの75mm砲が10発以上命中したが、すべて跳弾した。乗員は無傷で、そのまま反撃して敵戦車4輌を撃破した」 ――SS第501重戦車大隊の戦闘報告書
ただし、側面・後面は別だ。
側面80mm、後面80mmは、連合軍の対戦車砲で貫通可能な厚さだった。このため、連合軍は「側面攻撃」を重視する戦術を開発した。
エンジンと機動性――700馬力の苦闘
ティーガーIIのエンジンは、マイバッハ HL230 P30 V型12気筒ガソリンエンジン(700馬力)だ。
実は、このエンジンはパンターV型戦車と同じものだ。
- パンターの重量: 約44.8トン
- ティーガーIIの重量: 約69.8トン
パンターより25トンも重いティーガーIIに、同じエンジンを搭載した――これが、後に深刻な問題を引き起こす。
パワーウェイトレシオ
パワーウェイトレシオ(馬力÷重量)は、戦車の機動性を示す重要な指標だ。
| 戦車 | 重量 | 馬力 | パワーウェイトレシオ |
|---|---|---|---|
| ティーガーII | 69.8トン | 700馬力 | 10.0 hp/t |
| ティーガーI | 57トン | 700馬力 | 12.3 hp/t |
| パンター | 44.8トン | 700馬力 | 15.6 hp/t |
| シャーマン | 30.3トン | 400馬力 | 13.2 hp/t |
| T-34/85 | 32トン | 500馬力 | 15.6 hp/t |
ティーガーIIのパワーウェイトレシオは、わずか10.0 hp/t。これは、主要戦車の中でも最低クラスだ。
実際の最高速度も:
- 路上: 41.5km/h(理論値)、実際は35km/h程度
- 不整地: 15〜20km/h
シャーマン(路上48km/h)やT-34/85(路上55km/h)と比べると、圧倒的に遅い。
トランスミッションの悲鳴
ティーガーIIのトランスミッション(変速機)は、マイバッハOLVAR OG 40 12 16 B(プレセレクト式8速)だ。
このトランスミッションは、本来50トンクラスの戦車用に設計されたものだった。それを70トンのティーガーIIに搭載した結果、頻繁に故障した。
戦場からの報告には、こうある:
「トランスミッションの破損により、行軍中に脱落する車両が続出している。整備兵は昼夜を問わず修理に追われているが、追いつかない」 ――第503重戦車大隊 整備班報告書(1944年12月)
特に、アルデンヌ攻勢では、多くのティーガーIIがトランスミッション故障で放棄された。
燃費と航続距離――「動かない要塞」
ティーガーIIの最大の弱点は、燃費の悪さだった。
- 燃料タンク容量: 860リットル
- 燃費(路上): 約4.8リットル/km
- 燃費(不整地): 約7〜10リットル/km
航続距離は:
- 路上: 約170km
- 不整地: 約120km
これがどれだけ短いか、他の戦車と比較してみよう。
| 戦車 | 航続距離(路上) |
|---|---|
| ティーガーII | 170km |
| ティーガーI | 140km |
| パンター | 200km |
| シャーマン | 190km |
| T-34/85 | 360km |
T-34/85の半分以下だ。
1944年以降、ドイツは深刻な燃料不足に陥っていた。ルーマニアの油田がソ連に占領され、連合軍の戦略爆撃で合成燃料工場が破壊されていたためだ。
この状況下で、ティーガーIIは「動く要塞」ではなく「動かない要塞」になってしまうことが多かった。
アルデンヌ攻勢では、多くのティーガーIIが燃料切れで放棄された。ある報告では、SS第501重戦車大隊の約30輌のうち、15輌以上がガス欠で放棄されたとされている。
ティーガーIIの生産と配備
生産工場と生産数
ティーガーIIは、ヘンシェル社のカッセル工場で生産された。
生産期間: 1944年1月〜1945年3月
総生産台数: 約489輌
月別生産数を見ると:
| 時期 | 月産台数 |
|---|---|
| 1944年1〜3月 | 約3〜5輌(試作段階) |
| 1944年4〜6月 | 約20〜30輌 |
| 1944年7〜9月 | 約40〜50輌(ピーク) |
| 1944年10〜12月 | 約30〜40輌 |
| 1945年1〜3月 | 約10〜20輌 |
1944年夏がピークで、月産50輌近くに達した。しかし、連合軍の戦略爆撃により、工場が損傷を受け、生産数は徐々に減少していった。
比較として:
- ティーガーI: 約1,347輌
- パンターV型: 約6,000輌
- IV号戦車: 約8,500輌
- シャーマン戦車: 約50,000輌
- T-34全系列: 約84,000輌
ティーガーIIの生産数は、圧倒的に少ない。
生産コストと時間
ティーガーIIの生産には、莫大なコストと時間がかかった。
- 生産コスト: 約32万ライヒスマルク(IV号戦車の約2.5倍)
- 生産時間: 約15,000〜18,000工数(IV号戦車の約2倍以上)
1輌のティーガーIIを作る間に、IV号戦車なら2〜3輌、シャーマンなら3〜4輌を作れた。
1944年のドイツは、もはや「質より量」を選ぶ余裕がなかった。しかし、「量」でも連合軍に勝てず、「質」でも戦局を変えられなかった――これが、ドイツの悲劇だった。
配備部隊――「エリート」たちの戦車
ティーガーIIは、ドイツ軍の「エリート部隊」にのみ配備された。
主な配備部隊:
武装親衛隊(Waffen-SS)重戦車大隊
- SS第501重戦車大隊: 西部戦線(ノルマンディー、アルデンヌ)
- SS第502重戦車大隊: 東部戦線(ハンガリー、オーストリア)
- SS第503重戦車大隊: 東部戦線(ポーランド、ドイツ本土)
国防軍(Wehrmacht)重戦車大隊
- 第503重戦車大隊: 東部戦線(ポーランド、ハンガリー)
- 第505重戦車大隊: 東部戦線(東プロイセン、ポーランド)
- 第506重戦車大隊: 東部戦線(ハンガリー、オーストリア)
これらの部隊は、通常30〜45輌のティーガーIIで編成されていた(定数。実際の配備数はこれより少ないことが多かった)。
重戦車大隊は、機甲師団や装甲軍団の直轄部隊として、「切り札」的に投入された。激戦地に送り込まれ、局地的な優勢を確保する任務を担った。
実戦での活躍――戦線別エピソード
東部戦線――ソ連軍との死闘
ティーガーIIの初陣は、1944年5月、東部戦線だった。
ポーランド戦線(1944年夏)
1944年夏、ソ連軍は「バグラチオン作戦」で大攻勢を開始した。ドイツ軍は、防衛線の崩壊を食い止めるため、ティーガーIIを投入した。
第501重戦車大隊の記録:
「1944年7月、ポーランド東部。我々のティーガーIIは、ソ連のT-34/85部隊と交戦した。我々は待ち伏せ戦術を用い、1,500m以上の距離からT-34を次々と撃破した。T-34の85mm砲は、我々の前面装甲を貫通できなかった」
しかし、ソ連軍は数で圧倒してきた。1輌のティーガーIIが10輌のT-34を撃破しても、ソ連軍はさらに20輌を補充できた。
ハンガリー戦線(1945年初頭)
1945年1月、ソ連軍はハンガリーの首都ブダペストを包囲した。ドイツ軍は、「コンラート作戦」を発動し、ブダペスト救出を試みた。
この作戦に、SS第503重戦車大隊のティーガーIIが投入された。
「1945年1月、ハンガリー・バラトン湖周辺。泥濘の中、ティーガーIIは進撃した。しかし、重量70トンの車体は、泥に沈んだ。多くの車両が立ち往生し、放棄された」
泥濘――これは、ティーガーIIにとって最悪の敵だった。幅広の履帯を装備していたが、それでも重量には勝てなかった。
東プロイセン防衛戦(1945年初頭)
1945年1月、ソ連軍は東プロイセア(現在のポーランド北部)に侵攻した。ドイツ軍は、第505重戦車大隊のティーガーIIで防衛線を構築した。
「東プロイセアの町々で、ティーガーIIは移動要塞として運用された。町の中心部に陣取り、進撃してくるソ連戦車を、1,500m以上の距離から撃破した。1輌のティーガーIIが、1日で15輌以上のT-34とIS-2を撃破した記録もある」
しかし、ソ連軍は包囲戦術を用いた。ティーガーIIの側面・後面に回り込み、近距離から攻撃した。また、対戦車砲や航空攻撃も併用した。
結局、多くのティーガーIIが、燃料切れや弾薬不足で放棄された。
西部戦線――連合軍との対決
ノルマンディー戦線(1944年夏)
1944年6月6日、連合軍がノルマンディー上陸作戦を開始した。
7月、SS第501重戦車大隊のティーガーIIがノルマンディーに到着した。これが、西部戦線でのティーガーIIの初陣だった。
有名な戦例が、**ヴィレル=ボカージュ近郊の戦い(1944年7月)**だ。
ティーガーIIは、丘の上から、進撃してくるイギリス軍戦車部隊を待ち伏せた。
「我々のティーガーIIは、1,800m以上の距離から、イギリスのクロムウェル戦車とシャーマン戦車を次々と撃破した。イギリス軍は、どこから撃たれているのかすらわからず、混乱していた」 ――SS第501重戦車大隊 戦闘報告書
しかし、ノルマンディーの地形――狭い道路、生け垣(ボカージュ)、丘陵――は、ティーガーIIにとって不利だった。
狭い道路では、重量70トンのティーガーIIは取り回しが悪く、待ち伏せされやすかった。連合軍は、ティーガーIIの側面を狙う戦術を徹底した。
また、連合軍の圧倒的な航空優位も、ティーガーIIを苦しめた。P-47サンダーボルトやタイフーンといった対地攻撃機が、ロケット弾や爆弾でティーガーIIを攻撃した。
アルデンヌ攻勢(バルジの戦い、1944年12月)
1944年12月16日、ドイツ軍は最後の大反攻「アルデンヌ攻勢(ラインの守り作戦)」を発動した。
この作戦に、SS第501、第502重戦車大隊のティーガーIIが投入された。
関連記事:バルジの戦い(アルデンヌ攻勢)を徹底解説|ヒトラー最後の大反攻
作戦初日、濃霧の中、ティーガーIIは米軍戦車部隊を次々と撃破した。
「濃霧のおかげで、連合軍の航空機は飛べなかった。我々のティーガーIIは、米軍のシャーマン戦車を、まるで標的射撃のように撃破した。1個大隊(約30輌)で、米軍戦車100輌以上を撃破した」 ――SS第501重戦車大隊 戦果報告書
有名なエピソードが、ヨアヒム・パイパーSS中佐の戦闘群だ。
パイパー戦闘群には、ティーガーIIが配備されていた。彼らは、米軍の後方深く突進し、補給基地を襲撃した。しかし、燃料不足に直面した。
「燃料が尽きた。我々のティーガーIIは、道路脇に放棄するしかなかった。乗員たちは、涙を流して愛車を破壊した」 ――パイパー戦闘群の記録
アルデンヌ攻勢は、最終的に失敗に終わった。ドイツ軍は、多くのティーガーIIを失った。その多くは、戦闘ではなく、燃料切れや故障で放棄されたものだった。
ルール包囲戦(1945年3〜4月)
1945年3月、連合軍はドイツ最後の工業地帯「ルール地方」を包囲した。
ドイツ軍は、残存するティーガーIIで、町々を防衛した。
「ティーガーIIは、町の中心部に陣取り、進撃してくる米軍戦車を撃破した。しかし、米軍は包囲戦術を用い、ティーガーIIを孤立させた。弾薬と燃料が尽き、多くのティーガーIIが放棄された」 ――第506重戦車大隊の記録
1945年4月、ルール地方のドイツ軍は降伏した。残存するティーガーIIも、連合軍に接収された。
イタリア戦線――限定的な投入
ティーガーIIは、イタリア戦線にも少数が投入された。
第504重戦車大隊(国防軍)が、ティーガーIとティーガーIIの混成部隊として、イタリア北部で戦った。
しかし、イタリアの山岳地形は、重戦車に不向きだった。狭い山道では、ティーガーIIの機動性の低さが致命的だった。
戦術と運用――「待ち伏せの王」
ティーガーIIの理想的な戦術は、**待ち伏せ(ambush)**だった。
基本戦術
- 陣地の選定
- 丘の上、森の陰、建物の物陰など、視界が良く、隠れられる場所を選ぶ
- 敵戦車の進撃路を見渡せる位置
- 待ち伏せ
- エンジンを停止し、静かに待つ
- 敵戦車が射程内(1,500〜2,000m)に入るのを待つ
- 射撃開始
- 長距離から、一方的に敵戦車を撃破
- 88mm砲の高精度を活かす
- 撤退
- 敵の反撃が来る前に、ゆっくりと後退
- 次の陣地へ移動
この戦術で、ティーガーIIは驚異的な戦果を上げた。
しかし、この戦術には弱点もあった:
- 機動性が低いため、包囲されやすい
- 燃料消費が激しく、長距離移動が困難
- 航空攻撃に脆弱
連合軍は、この弱点を突く戦術を開発した。
連合軍の対ティーガーII戦術
連合軍は、ティーガーIIを「正面から戦ってはいけない」と学んだ。
1. 側面攻撃
ティーガーIIの側面装甲80mmは、連合軍の対戦車砲で貫通可能だった。
米軍、イギリス軍は、複数の戦車で協力し、ティーガーIIを包囲する戦術を用いた。
- 正面から1〜2輌が陽動(ティーガーIIの注意を引く)
- 側面から3〜4輌が回り込み、側面を攻撃
2. 航空攻撃
連合軍は、圧倒的な航空優位を活かした。
P-47サンダーボルト、タイフーン、IL-2シュトゥルモヴィクといった対地攻撃機が、ロケット弾や爆弾でティーガーIIを攻撃した。
ティーガーIIの上面装甲40mmは、航空爆弾には耐えられなかった。
3. 砲兵砲撃
米軍は、大口径榴弾砲(155mm、203mm)でティーガーIIを砲撃した。
直撃弾は、ティーガーIIの装甲を貫通できなかったが、履帯やエンジンを損傷させ、行動不能にすることができた。
4. 歩兵による近接攻撃
ソ連軍、米軍の歩兵は、夜間や近距離で、ティーガーIIに接近し、火炎瓶や対戦車地雷で攻撃した。
ティーガーIIは、車体上部の機関銃(MG34)で対歩兵戦闘ができたが、夜間や市街戦では限界があった。
連合軍の評価と恐怖――「ティーガーII恐怖症」
連合軍兵士たちは、ティーガーIIに対して、ティーガーIと同様の「恐怖症」を抱いた。
米軍の評価
米陸軍の報告書には、こうある:
「ティーガーIIは、我々のあらゆる戦車を、1,500m以上の距離から撃破できる。我々のシャーマンの75mm砲は、ティーガーIIの前面装甲を貫通できない。ティーガーIIを撃破するには、側面攻撃、航空攻撃、または包囲戦術が必要だ」 ――米陸軍第3機甲師団 戦術報告書(1945年1月)
米軍戦車兵の証言:
「ティーガーIIを見た瞬間、死を覚悟した。我々のシャーマンでは、正面から戦っても勝ち目はない。生き延びるには、側面に回り込むしかない――しかし、その前に撃破される可能性が高い」
イギリス軍の評価
イギリス軍の報告書:
「ティーガーIIは、戦場で最も恐ろしい敵だ。我々のクロムウェル戦車、チャーチル戦車では、太刀打ちできない。シャーマン・ファイアフライ(17ポンド砲搭載)でも、1,000m以内に接近しなければ、前面装甲を貫通できない」
イギリス軍戦車兵の証言:
「ティーガーIIを撃破するには、最低5輌のシャーマンが必要だ。しかし、最初の4輌は撃破されることを覚悟しなければならない」
この言葉は、ティーガーIの時と同じだ。ティーガーIIも、同様の「伝説」を作った。
ソ連軍の評価
ソ連軍も、ティーガーIIを「最も危険な敵」と評価した。
「ドイツのティーガーIIは、我々のT-34/85、IS-2でも、正面から戦うのは困難だ。我々は、数的優位と包囲戦術で対抗するしかない」 ――ソ連軍第1ウクライナ戦線 戦術報告書
ソ連軍戦車兵の証言:
「ティーガーIIは、まるで動く要塞だった。我々のT-34は、ティーガーIIの射程外から一方的に撃破された。ティーガーIIを見たら、すぐに側面に回り込むか、煙幕を張って逃げるしかなかった」
ティーガーIIの弱点と限界――「無敵」の代償
ティーガーIIは、多くの弱点を抱えていた。
1. 機動性の低さ
重量70トン、パワーウェイトレシオ10.0 hp/t――これは、主要戦車の中で最低クラスだ。
- 最高速度が遅い(路上35km/h程度)
- 不整地での機動性が極めて低い(15〜20km/h)
- 急旋回が困難
この低機動性は、包囲戦術に脆弱だった。連合軍は、この弱点を徹底的に突いた。
2. 燃費の悪さと航続距離の短さ
燃費約4.8リットル/km(路上)、航続距離約170km――これは、作戦行動を大きく制限した。
1944年以降のドイツの燃料不足により、ティーガーIIは「動かない要塞」になることが多かった。
アルデンヌ攻勢、ハンガリー戦線、東プロイセア戦線――あらゆる戦線で、ティーガーIIは燃料切れで放棄された。
3. トランスミッションの故障
マイバッハOLVAR OG 40 12 16 Bトランスミッションは、70トンの重量に耐えられず、頻繁に故障した。
整備記録を見ると:
「行軍中、約30%の車両がトランスミッション故障で脱落した。整備班は、昼夜を問わず修理に追われたが、部品不足で対応できないことも多かった」 ――第503重戦車大隊 整備記録
4. 生産数の少なさ
総生産台数約489輌――これは、戦局を変えるには圧倒的に少なかった。
比較:
- シャーマン戦車: 約50,000輌
- T-34全系列: 約84,000輌
ドイツが489輌のティーガーIIを生産する間に、米ソは10万輌以上の戦車を生産していた。
「質」で勝っても、「量」で負ければ、戦争には勝てない――これが、ティーガーIIが教えてくれた教訓だ。
5. 橋を渡れない
重量70トン――これは、ヨーロッパのほとんどの橋の耐荷重(50トン以下)を超えていた。
ティーガーIIは、橋を渡ることができず、迂回するか、渡河装置を使う必要があった。これは、作戦の柔軟性を大きく制限した。
6. 上面装甲の薄さ
上面装甲40mm――これは、航空爆弾や砲兵の榴弾に対して脆弱だった。
連合軍は、この弱点を突き、航空攻撃や砲兵砲撃でティーガーIIを攻撃した。
7. 整備性の悪さ
ティーガーIIは、複雑な機構を持っており、整備に高度な技術と時間が必要だった。
- エンジン交換: 約8〜12時間
- トランスミッション交換: 約12〜20時間
- 履帯交換: 約4〜6時間
戦場での急速な修理は困難だった。故障した車両は、放棄されることが多かった。
ティーガーIIの派生型・バリエーション
ティーガーIIには、いくつかの派生型が存在する(計画のみのものも含む)。
ポルシェ砲塔型 vs ヘンシェル砲塔型
前述の通り、ティーガーIIには2種類の砲塔が存在する。
ポルシェ砲塔型(初期50輌)
- 曲面を多用したデザイン
- 前面装甲100mm(曲面)
- 防盾(砲の周囲の装甲)が突出しており、「ショットトラップ(跳弾が車体上部に当たる)」の弱点があった
ヘンシェル砲塔型(残り約439輌)
- 傾斜装甲を多用したデザイン
- 前面装甲185mm(傾斜)
- 防盾の突出を改善し、ショットトラップの問題を解決
現在、博物館に展示されているティーガーIIの多くは、ヘンシェル砲塔型だ。
ヤークトティーガー(Jagdtiger)
ティーガーIIの車体をベースに、128mm砲を搭載した駆逐戦車。
- 重量: 約71.7トン
- 主砲: 128mm PaK 44 L/55
- 前面装甲: 250mm
第二次世界大戦で実戦投入された最大口径の対戦車砲を搭載した駆逐戦車だ。約79輌が生産された。
E-75(計画のみ)
ティーガーIIの後継として計画された重戦車。
- 重量: 約75〜80トン
- 主砲: 88mm KwK 43 L/71または105mm砲
- 装甲: ティーガーIIより強化
「E」シリーズ(Entwicklung = 開発)の一環として計画されたが、実際に生産されることはなかった。
日本への影響――「虎の遺伝子」は海を越えたか?
大日本帝国陸軍は、ティーガーIIの存在を知っていたのだろうか?
答えは、知っていた。
日独技術交流
第二次世界大戦中、日本とドイツは、潜水艦や交換船を使って、技術情報を交換していた。
1944年、ドイツから日本に、ティーガーIIを含む最新兵器の技術資料が提供された。
日本の技術者たちは、これを見て衝撃を受けた。
「装甲150mm、主砲88mm、重量70トン――これは、もはや戦車ではない。陸上戦艦だ」 ――陸軍技術本部の報告書(1944年)
しかし、日本にはティーガーIIを生産する工業基盤がなかった。
- 日本最大の戦車: 四式中戦車チト(30トン)
- エンジン出力: 最大でも400馬力程度
- 装甲圧延技術: 50mm程度が限界
関連記事:【完全保存版】第二次世界大戦時の日本の戦車一覧:日本軍の戦車は弱かった?
何より、太平洋の島嶼戦では、重戦車は不要だった。狭いジャングル、泥濘、橋のない川――ティーガーIIは、太平洋戦線では使い物にならなかっただろう。
戦後への影響――「傾斜装甲」という遺産
しかし、ティーガーIIの技術思想は、戦後の日本戦車開発に影響を与えた。
関連記事:【2025年最新版】陸上自衛隊の日本戦車一覧|敗戦国が生んだ世界屈指の技術力
特に、61式戦車(1961年制式化)の開発では:
- 傾斜装甲の採用(パンター、ティーガーIIの影響)
- 90mm砲の搭載(ドイツ戦車の「大口径砲」思想の継承)
- 高度な照準装置(ツァイス光学技術の研究)
そして現在、陸上自衛隊の10式戦車は、世界最高水準の戦車として評価されている。
- 120mm滑腔砲
- 複合装甲
- 高度な射撃統制装置(FCS)
- 世界最軽量(44トン)の第3世代戦車
ティーガーIIの「遺伝子」は、確かに日本にも受け継がれているのだ。
ティーガーIIを「今」楽しむ方法
プラモデル――手のひらの上の「王虎」

ティーガーIIのプラモデルは、世界中のメーカーから発売されている。
初心者におすすめ
タミヤ 1/35 ドイツ重戦車 キングタイガー(ヘンシェル砲塔)
- 組みやすさ: ★★★★★
- ディテール: ★★★★☆
- 価格: 約3,000〜4,000円
タミヤのキットは、組みやすく、初心者に最適だ。説明書もわかりやすい。
タミヤ 1/35 ドイツ重戦車 キングタイガー(ポルシェ砲塔)
- 初期型のポルシェ砲塔を再現したキット
中級者におすすめ
ドラゴン 1/35 ティーガーII ヘンシェル砲塔 後期生産型
- 組みやすさ: ★★★☆☆
- ディテール: ★★★★★
- 価格: 約5,000〜6,000円
ドラゴンのキットは、ディテールが非常に精密だが、やや組みにくい。中級者向け。
上級者におすすめ
ライフィールドモデル 1/35 ティーガーII ヘンシェル砲塔
- 組みやすさ: ★★☆☆☆
- ディテール: ★★★★★
- 価格: 約8,000〜10,000円
最新の金型を使用した、超精密キット。エンジンルーム、サスペンションまで再現されている。上級者向け。
塗装のポイント
ティーガーIIの塗装は、ウェザリング(汚し塗装)が醍醐味だ。
- 基本塗装: ダークイエロー(Dunkelgelb)、オリーブグリーン、レッドブラウンの迷彩
- ウェザリング:
- 泥汚れ: ダークブラウン、ダークアースをドライブラシ
- 錆: オレンジ、レッドブラウンをドライブラシ
- 排気煙汚れ: ブラックをエアブラシで軽く吹く
- チッピング(塗装剥がれ): シルバーをスポンジで軽く叩く
ゲーム――仮想戦場で「王虎」を操る
War Thunder(PC/PS4/PS5/Xbox)
リアル系戦車戦ゲームの決定版。ティーガーIIが、複数のバリエーションで登場する。
- ティーガーII(P)(ポルシェ砲塔型)
- ティーガーII(H)(ヘンシェル砲塔型)
リアルな物理演算で、装甲厚、傾斜角、砲弾の種類が戦果に影響する。ティーガーIIの「正面無敵」感を、存分に味わえる。
無料プレイ可能。
World of Tanks(PC/PS4/Xbox)
カジュアルな戦車戦ゲーム。ティーガーIIが登場する。
- ティーガーII(Tier 7重戦車)
アーケード的な爽快感があり、チーム戦が楽しい。
無料プレイ可能。
Enlisted(PC/PS5/Xbox Series X|S)
第二次世界大戦FPSゲーム。歩兵視点で、ティーガーIIと戦ったり、操縦したりできる。
臨場感のあるグラフィックで、ティーガーIIの「恐怖」を体験できる。
無料プレイ可能。
映画――スクリーンの中の「王虎」
『フューリー』(Fury, 2014年)
ブラッド・ピット主演。1945年4月、ドイツ本土でのシャーマン戦車部隊の戦いを描いた作品。
劇中に、ティーガーIが登場するが、ティーガーIIは登場しない。ただし、ティーガーI vs シャーマンの戦闘シーンは圧巻で、ティーガーIIの「恐怖」を想像するのに役立つ。
『バルジ大作戦』(Battle of the Bulge, 1965年)
アルデンヌ攻勢を描いた古典的戦争映画。劇中に登場する「ドイツ戦車」は、実際にはM47パットン戦車を改造したものだが、ティーガーIIを想定している。
博物館――「本物」に会いに行く

世界中の博物館に、ティーガーIIの実物が展示されている。
クビンカ戦車博物館(ロシア)
ロシア・モスクワ郊外にある世界最大の戦車博物館。
- ティーガーII(ヘンシェル砲塔型)が展示されている
- ソ連軍が鹵獲した車両
ボービントン戦車博物館(The Tank Museum, イギリス)
イギリス・ドーセット州にある戦車博物館。
- ティーガーII(ヘンシェル砲塔型)が展示されている
- イギリス軍が鹵獲した車両
ソミュール戦車博物館(フランス)
フランス・ソミュールにある戦車博物館。
- ティーガーII(ポルシェ砲塔型)が展示されている
- 初期型のポルシェ砲塔を見られる貴重な機会
ドイツ戦車博物館(Deutsches Panzermuseum Munster, ドイツ)
ドイツ・ムンスターにある戦車博物館。
- ティーガーII(ヘンシェル砲塔型)が展示されている
- エンジンや内部構造も見学可能
アバディーン性能試験場(米国、現在は閉鎖)
かつて米国メリーランド州にあった試験場。現在は閉鎖されているが、収蔵品の一部は他の博物館に移されている。
米軍が鹵獲したティーガーIIが保管されていた。
まとめ――「絶対防御」が教えてくれたこと
ティーガーII(キングタイガー)は、「絶対防御」を纏った最強重戦車だった。
- 前面装甲150mm(実質200mm以上)
- 砲塔前面185mm
- 88mm KwK 43 L/71長砲身砲
- 連合軍のあらゆる戦車を、2,000m以上の距離から撃破できる火力
正面から撃破することは、ほぼ不可能だった。
しかし、ティーガーIIは戦局を変えられなかった。
なぜか?
「質」だけでは勝てない
生産台数わずか489輌。シャーマン約50,000輌、T-34約84,000輌と比べると、圧倒的に少ない。
1輌のティーガーIIが10輌の敵戦車を撃破しても、敵は100輌を補充できた。
機動性と燃費の問題
重量70トン、航続距離170km、燃費4.8リットル/km――これは、作戦行動を大きく制限した。
多くのティーガーIIが、戦闘ではなく、燃料切れや故障で放棄された。
連合軍の適応
連合軍は、ティーガーIIの弱点――側面装甲、上面装甲、機動性の低さ――を突く戦術を開発した。
側面攻撃、航空攻撃、包囲戦術――これらの戦術で、ティーガーIIは「無敵」ではなくなった。
それでも「伝説」は残った
ティーガーIIは、戦局を変えることはできなかった。
しかし、連合軍兵士たちに深い恐怖を刻み込んだ。
「ティーガーIIを見たら、死を覚悟しろ」
この言葉は、ティーガーIIの「伝説」を物語っている。
そして、その技術と思想は、戦後の戦車開発に受け継がれた。
- 傾斜装甲
- 大口径砲
- 高精度照準装置
ティーガーIIの「遺伝子」は、今も世界中の戦車に生き続けている。
日本人として、僕たちが学ぶべきこと
大日本帝国は、ティーガーIIのような重戦車を作れなかった。
しかし、だからといって「劣っていた」わけではない。
戦略思想、戦場環境、工業基盤――これらすべてが異なっていた。
そして、戦後の日本は、ドイツの技術を学び、独自の発展を遂げた。
10式戦車――世界最軽量(44トン)の第3世代戦車――は、日本の技術力の結晶だ。
ティーガーIIは、「技術の極限」を追求した戦車だった。
その挑戦は失敗に終わったかもしれない。しかし、その「夢」は、今も生き続けている。
鋼鉄の「王虎」は、もう咆哮しない。
しかし、その「魂」は、永遠に不滅だ。
関連記事・さらに深く知るために
ドイツ戦車を知る
日本の戦車を知る
世界の最強戦車を知る
第二次世界大戦を知る
- 【第二次世界大戦】欧州戦線・激戦地ランキングTOP15|同盟国ドイツが戦った”もうひとつの大戦”を徹底解説
- バルジの戦い(アルデンヌ攻勢)を徹底解説|ヒトラー最後の大反攻
- ノルマンディー上陸作戦を徹底解説
日本の防衛産業を知る
おすすめプラモデル・書籍
プラモデル
ティーガーII
- タミヤ 1/35 ドイツ重戦車 キングタイガー(ヘンシェル砲塔): 組みやすさ◎、初心者におすすめ
- タミヤ 1/35 ドイツ重戦車 キングタイガー(ポルシェ砲塔): 初期型を再現
- ドラゴン 1/35 ティーガーII ヘンシェル砲塔 後期生産型: ディテール◎、中級者向け
- ライフィールドモデル 1/35 ティーガーII ヘンシェル砲塔: 超精密、上級者向け
書籍
- 『ドイツ戦車大全』(学研): 写真・図解豊富、初心者におすすめ
- 『ティーガー戦車隊戦闘記録』(大日本絵画): 実戦記録、読み応え◎
- 『キングタイガー重戦車 1942-1945』(大日本絵画): 技術解説詳細
最後まで読んでくれてありがとう。読者の皆さんが、ティーガーIIの「強さ」と「悲劇」を感じ取ってくれたなら、これ以上の喜びはない。
「王虎」の咆哮は、もう聞こえない。しかし、その「魂」は、今も僕たちの心に生き続けている。
ありがとう。そして、また次の記事で会おう!





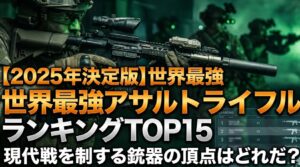







コメント