1939年9月1日、夜明け前のポーランド国境——電撃戦の幕開け
1939年9月1日、午前4時45分。
ポーランド国境地帯に、轟音が響き渡った。
数百輌のドイツ戦車が、国境線を越えて進撃を開始する。先頭を走るのは、灰色に塗装されたIII号戦車だった。砲塔に描かれた白い十字マークが、夜明け前の薄闇の中で鈍く光る。
37mm砲を搭載した中戦車——それがIII号戦車だ。
この戦車こそが、ドイツ国防軍の電撃戦(Blitzkrieg)を支えた「働き者」であり、後のティーガーやパンターへと続く、ドイツ戦車設計思想の基礎を築いた名車なのだ。
今回は、このIII号戦車について、スペックから実戦での活躍、そして日本戦車との比較まで、徹底的に解説していく。プラモデルやゲームでIII号戦車に興味を持った人、War Thunderで操縦している人、そしてドイツ戦車の「原点」を知りたい人——ぜひ最後まで読んでほしい。
III号戦車とは?——ドイツ電撃戦を支えた中戦車の全貌

基本スペック一覧
まず、III号戦車の基本スペックを確認しておこう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全長 | 6.41m(車体)、砲身含む全長は型により異なる |
| 全幅 | 2.95m |
| 全高 | 2.50m |
| 重量 | 約23トン(後期型) |
| 乗員 | 5名(車長、砲手、装填手、操縦手、無線手) |
| 主砲 | 初期:37mm KwK 36<br>中期:50mm KwK 38<br>後期:50mm KwK 39 L/60 |
| 副武装 | 7.92mm MG34機関銃×2〜3 |
| エンジン | マイバッハ HL120TRM V型12気筒ガソリンエンジン(300馬力) |
| 最高速度 | 路上40km/h |
| 航続距離 | 約165km |
| 装甲厚 | 前面:最大50mm+増加装甲、側面:30mm |
| 生産期間 | 1939年〜1943年 |
| 生産台数 | 約5,700輌 |
スペックだけ見ると、決して「最強」ではない。ティーガーIのような圧倒的な火力も装甲もない。しかし、III号戦車には、別の「強さ」があった。
それは、「実用性」だ。
ヴェルサイユ条約の制約を越えて——III号戦車開発の背景

「戦車禁止」という屈辱
1919年6月28日、ヴェルサイユ宮殿。
第一次世界大戦に敗れたドイツ帝国は、連合国に屈辱的な講和条約を押しつけられた。ヴェルサイユ条約だ。
この条約で、ドイツ軍は事実上の武装解除を強いられる。
- 陸軍兵力:10万人以下に制限
- 戦車・装甲車の保有禁止
- 航空機の保有禁止
- 海軍艦艇の大幅削減
特に、戦車の保有・開発が完全に禁止されたことは、ドイツ陸軍にとって致命的だった。第一次世界大戦で、連合国の戦車(イギリスのマークI型など)がドイツ軍の塹壕線を蹂躙したことを、ドイツ軍首脳部は痛感していたからだ。
「戦車なくして、次の戦争は戦えない」
しかし、条約がある限り、表向きは戦車開発はできない。
秘密の開発——「農業用トラクター」という偽装
ドイツ軍参謀本部は、諦めなかった。
彼らは、ヴェルサイユ条約の監視の目をかいくぐり、密かに戦車開発を継続したのだ。
1920年代、ドイツはソ連と秘密協定を結ぶ。ソ連領内に戦車訓練学校を設置し、そこでドイツ軍士官たちが戦車戦術を研究した。表向きは「農業機械の共同研究」とされていたが、実際には戦車の試作と訓練が行われていた。
そして1933年、アドルフ・ヒトラーが政権を掌握すると、ドイツは公然と再軍備を開始する。
ヴェルサイユ条約?——もう守る気はない。
こうして、ドイツ戦車開発が本格化した。
「敵戦車と戦える中戦車」というコンセプト
1930年代半ば、ドイツ陸軍は新型戦車の開発計画を策定した。
当時のドイツ戦車は、I号戦車(7.5トン、機関銃のみ)とII号戦車(9.5トン、20mm機関砲)しかなかった。これらは訓練用・偵察用としては有用だが、敵戦車と正面から戦うには力不足だった。
そこで、ドイツ陸軍が求めたのは:
- 敵戦車(フランスやソ連の軽・中戦車)と正面から戦える火力
- 十分な装甲防御力
- 高い機動性と信頼性
- 5名の乗員で効率的に運用可能
こうして開発されたのが、III号戦車だ。
当初の主砲は37mm KwK 36砲。これは、当時のフランス軽戦車(ルノーR35、ホチキスH35など)やソ連軽戦車(T-26、BT-7など)に対しては十分な火力だった。
しかし、この判断が後に「甘すぎた」ことが判明する。それがT-34ショックだ——が、それは後で詳しく語ろう。
電撃戦(Blitzkrieg)の立役者——ポーランドとフランスでの圧倒的勝利
1939年9月、ポーランド侵攻——III号戦車の実戦デビュー
1939年9月1日、ドイツ軍はポーランドに侵攻した。
この作戦で、III号戦車は実戦デビューを果たす。
当時のドイツ機甲師団は、以下の戦車で構成されていた:
- I号戦車:機関銃のみ、偵察・歩兵支援用
- II号戦車:20mm機関砲、軽装甲車両・歩兵への制圧
- III号戦車:37mm砲、対戦車戦闘担当
- IV号戦車:75mm短砲身榴弾砲、陣地・トーチカ破壊
III号戦車は、「敵戦車と戦う」という明確な役割を与えられていた。
ポーランド軍の主力戦車は、7TP軽戦車(37mm砲搭載)とTKS豆戦車(機関銃のみ)。III号戦車の37mm砲は、これらのポーランド戦車を容易に撃破できた。
結果、ポーランドはわずか1ヶ月で降伏。
ドイツ軍の新戦術「電撃戦(Blitzkrieg)」は、世界を震撼させた。
電撃戦とは何か?——航空支援と機甲部隊の連携
電撃戦とは、航空支援と機甲部隊の高速機動を組み合わせた戦術だ。
従来の戦争では、歩兵が主役だった。戦車は「歩兵の随伴」として使われ、歩兵の速度に合わせて進撃していた。
しかし、グデーリアンらドイツ軍の戦車指揮官たちは、まったく逆の発想を持っていた。
「戦車が主役だ。歩兵は後からついてくればいい」
電撃戦の基本的な流れは、こうだ:
- 航空攻撃:シュツーカ急降下爆撃機が敵の防衛線を爆撃
- 機甲部隊突破:戦車部隊が一点集中で敵の防衛線を突破
- 後方浸透:戦車部隊が敵の後方に侵入し、指揮系統・補給線を遮断
- 包囲殲滅:後続の歩兵部隊が包囲網を完成させる
III号戦車は、この「機甲部隊突破」の中核を担った。
37mm砲で敵戦車を撃破しながら、時速40kmで進撃する。敵が反撃態勢を整える前に、次の目標へと移動する。
この「スピード」こそが、電撃戦の本質だった。
1940年5月、フランス侵攻——マジノ線を迂回した奇襲
1940年5月10日、ドイツ軍は西方に進撃を開始した。
目標は、フランスとイギリス。
フランス軍は、第一次世界大戦の教訓から、ドイツ国境沿いに巨大な要塞線「マジノ線」を構築していた。コンクリートと鋼鉄で固められた要塞群は、ドイツ軍の侵攻を阻むはずだった。
しかし、グデーリアンは、マジノ線を正面から攻撃しなかった。
彼は、アルデンヌの森を突破する計画を立てた。
アルデンヌの森は、起伏が激しく森林が密集しており、「戦車の通過は不可能」とフランス軍は判断していた。だからこそ、防備が手薄だった。
グデーリアンは、この「不可能」を可能にした。
- 5月10日深夜、ドイツ機甲師団はアルデンヌに突入。III号戦車を含む数百輌の戦車が、森林地帯を突破した。
- 5月13日、ドイツ軍はセダンでフランス軍の防衛線を突破。
- 5月20日、ドイツ軍は英仏海峡に到達し、連合軍を南北に分断。
- 6月14日、ドイツ軍はパリを無血占領。
- 6月22日、フランスは降伏。
わずか6週間で、フランスは陥落した。
この勝利の立役者の一つが、III号戦車だった。
T-34ショック——ドイツ戦車開発の転換点

1941年6月22日、バルバロッサ作戦——ソ連侵攻の開始
フランスを降伏させたヒトラーは、次の目標を東に定めた。
ソビエト連邦だ。
1941年6月22日午前3時15分、ドイツ軍は独ソ不可侵条約を一方的に破棄し、ソ連に侵攻した。作戦名「バルバロッサ作戦」——人類史上最大の陸上侵攻作戦の開始だ。
関連記事:ヒトラーの野望・バルバロッサ作戦とは──”人類史上最大の侵攻作戦”と、冬将軍に砕かれた野望
III号戦車を含むドイツ機甲師団は、ソ連領内に怒涛の進撃を開始した。
当初、ソ連軍の抵抗は混乱していた。スターリンの大粛清で将校団が弱体化していたこと、ドイツ軍の奇襲が成功したことが原因だった。
III号戦車は、ソ連の軽戦車T-26やBT-7を次々と撃破した。37mm砲でも、これらの軽戦車には十分対抗できたのだ。
ドイツ軍兵士たちは、「モスクワまであと数週間だ」と楽観していた。
しかし——。
1941年夏、T-34の出現——「我々の砲弾が跳ね返された」
1941年7月、ドイツ軍第4装甲師団がウクライナ地方で進撃中、奇妙な報告が司令部に届いた。
「未知の敵戦車と遭遇。我々の37mm砲、50mm砲が通用しない」
その「未知の戦車」こそ、T-34中戦車だった。
T-34は、ドイツ軍にとって悪夢だった。
T-34の何が恐ろしかったのか?
- 傾斜装甲:前面装甲45mmを60度傾斜させており、III号戦車の37mm砲では貫通不可能
- 76.2mm砲:III号戦車を1,500m以上の距離から一撃で撃破
- 幅広履帯:ロシアの泥濘地でも高い機動性を発揮
- 圧倒的な生産台数:ソ連の工業力で大量生産
ドイツ戦車兵の証言が、当時の絶望を物語っている。
「我々の砲弾は、T-34に当たっても跳ね返された。まるで石を投げているようだった。一方、T-34の76.2mm砲は、我々の戦車を1,000m以上の距離から貫通した。これは技術的敗北だ」 ——第4装甲師団戦車兵の証言
この衝撃を、「T-34ショック」という。
緊急対応——50mm砲への換装
ドイツ軍首脳部は、すぐに対応を決断した。
III号戦車の主砲を、50mm KwK 39 L/60長砲身砲に換装することを決定したのだ。
50mm L/60砲の性能:
- 貫徹力:1,000mで60mm、500mで77mmの装甲を貫通
- 砲弾初速:835m/秒
- 有効射程:約1,500m
この改良により、III号戦車はT-34と「ある程度」戦えるようになった。
しかし、根本的な解決にはならなかった。
T-34の傾斜装甲は、50mm砲でも正面から貫通するのは困難だった。III号戦車の乗員たちは、T-34の側面や後面を狙うしかなかった。
そして、ドイツ軍首脳部は決断した。
「III号戦車では不十分だ。もっと強力な戦車が必要だ」
こうして、ティーガーI、パンターV型の開発が加速する。
III号戦車の改良と各型式の変遷
A型〜E型(初期型):37mm砲搭載型
III号戦車の開発は、1934年に始まった。
最初の試作型は1936年に完成し、その後、量産型が次々と開発された。
初期型(A型〜E型)の特徴:
主砲:37mm KwK 36 L/45
装甲厚:前面15mm、側面15mm(A〜D型)、前面30mm(E型)
重量:約15〜19トン
生産台数:合計約300輌
初期型は、ポーランド侵攻とフランス侵攻で使用された。しかし、装甲が薄く、フランス軍の対戦車砲に対して脆弱だったため、すぐに改良が必要になった。
F型〜G型(中期型):装甲強化と50mm砲の導入
1940年以降、III号戦車は装甲が強化された。
F型以降の特徴:
装甲厚:前面30mm→50mm、側面30mm
主砲:初期は37mm、後に50mm KwK 38 L/42
重量:約19.5〜20トン
生産台数:F型約435輌、G型約600輌
特にG型からは、50mm KwK 38 L/42砲が標準装備となった。これにより、対戦車能力が向上した。
H型〜M型(後期型):50mm長砲身砲とT-34への対応
1941年のT-34ショック後、III号戦車は再び大幅な改良を受けた。
後期型(H型〜M型)の特徴:
主砲:50mm KwK 39 L/60長砲身砲
装甲厚:前面50mm+20mm増加装甲(合計70mm)、側面30mm
重量:約21〜23トン
生産台数:H型約308輌、J型約1,549輌、L型約653輌、M型約250輌
特にJ型は、最も生産台数が多い型式となった。
しかし、それでもT-34やソ連の新型重戦車KV-1には対抗できなかった。
N型:最終進化型、75mm短砲身砲搭載
1942年、III号戦車の最終型であるN型が登場した。
N型の特徴:
主砲:75mm KwK 37 L/24短砲身砲(IV号戦車初期型と同じ)
用途:歩兵支援、対陣地攻撃
装甲厚:前面50mm+増加装甲、側面30mm
生産台数:約660輌
N型は、対戦車戦闘ではなく、歩兵支援任務に特化していた。75mm榴弾で敵の陣地やトーチカを破壊する役割だ。
しかし、1943年以降、III号戦車は前線から徐々に退いていく。
代わりに登場したのが、「III号突撃砲(StuG III)」だ。
III号突撃砲(StuG III)——砲塔なき「最高の戦車駆逐車」

「砲塔を外せば、もっと強力な砲を搭載できる」
III号戦車の車体は、優秀だった。
信頼性の高いエンジン
整備しやすい機構
バランスの取れた機動性
しかし、砲塔に搭載できる砲の大きさには限界があった。
そこでドイツ軍が考えたのが、「砲塔を外して、固定式の大口径砲を搭載する」という発想だった。
こうして誕生したのが、III号突撃砲(Sturmgeschütz III、略称StuG III)だ。
StuG IIIの特徴
主砲:初期75mm L/24、後期75mm L/48長砲身砲
装甲:前面50〜80mm
車高:2.16m(III号戦車より約30cm低い)
用途:歩兵支援、対戦車戦闘
生産台数:約10,500輌(ドイツ装甲戦闘車両で最多)
StuG IIIは、砲塔がないため、車高が低く、隠密性が高かった。待ち伏せ戦術に最適だったのだ。
そして、75mm L/48長砲身砲を搭載した後期型は、T-34やシャーマンを1,500m以上の距離から撃破できた。
実際、StuG IIIの撃破数は、III号戦車を大きく上回った。
「もしStuG IIIがなければ、東部戦線は崩壊していた」
ドイツ軍の戦車兵団長グデーリアンは、後にこう語っている。
「StuG IIIは、ドイツ装甲部隊の救世主だった。ティーガーやパンターよりも多く生産され、戦線を支え続けた」
StuG IIIは、III号戦車の車体を使った「最高の進化形」だったのだ。
関連記事:【完全保存版】第二次世界大戦ドイツ最強戦車ランキングTOP10
実戦での評価と戦果——III号戦車は「弱かった」のか?
撃破比(キルレシオ)から見るIII号戦車の実力

III号戦車は、ティーガーIやパンターのような「伝説」を持たない。
しかし、実戦での戦果は決して低くない。
- ポーランド戦(1939年):ポーランド軍戦車を圧倒
- フランス戦(1940年):フランス軍戦車を撃破
- 北アフリカ戦線(1941〜1943年):イギリス軍のクルセイダー戦車やマチルダII戦車と交戦
- 東部戦線(1941〜1943年):T-34には苦戦したが、側面攻撃で多数撃破
特に、北アフリカ戦線でのロンメル将軍の「アフリカ軍団」では、III号戦車が主力として活躍した。
エルヴィン・ロンメル将軍は、III号戦車の機動性を活かした戦術を得意とした。
砂漠の広大な地形を活かし、側面から敵を攻撃
88mm対空砲を水平射撃で使用し、遠距離から敵戦車を撃破
III号戦車は、このロンメル戦術の中核を担った。
関連記事:エル・アラメインの戦いを徹底解説|「砂漠の狐」ロンメルが敗れた日
「III号戦車は実用的だった」——整備性と信頼性
III号戦車の最大の美点は、信頼性と整備性だ。
ティーガーIは強力だったが、故障が多く、整備に時間がかかった。パンターも初期型は故障が頻発した。
しかし、III号戦車は違った。
マイバッハHL120エンジンは、信頼性が高かった
トランスミッションも比較的単純で、整備しやすかった
部品供給が安定しており、補給体制が整っていた
実戦では、「動かない最強戦車」よりも、「動く普通の戦車」の方が価値がある。
III号戦車は、まさに「動く実用戦車」だった。
日本の戦車と比較する——III号戦車は日本にとって「夢」だったのか
日本の戦車——チハ、チヌ、チト
大日本帝国陸軍の主力戦車は、九七式中戦車「チハ」だった。
チハのスペック:
- 重量:約15トン
- 主砲:57mm戦車砲(初期)、後に47mm戦車砲に換装
- 装甲:前面25mm、側面25mm
- 最高速度:38km/h
乗員:4名
チハは、III号戦車と比較すると、明らかに劣っていた。
- 火力:57mm砲はIII号戦車の50mm砲より劣る
- 装甲:25mmでは、III号戦車の50mmに遠く及ばない
しかし、それは日本が「劣っていた」わけではない。
日本とドイツでは、戦場が違ったのだ。
関連記事:【完全保存版】第二次世界大戦時の日本の戦車一覧:日本軍の戦車は弱かった?
太平洋の島嶼戦 vs ヨーロッパ大陸戦
ドイツ軍は、広大なヨーロッパ大陸で戦った。
- 平原での機甲戦
- 敵は重装甲のT-34やKV-1
だからこそ、大型で重装甲の戦車が必要だった。
一方、日本軍は、太平洋の島嶼戦とジャングル戦が主戦場だった。
- 狭い島での戦闘
- ジャングルや山岳地帯での戦闘
- 敵の主力は歩兵と軽装甲車両
だからこそ、日本軍は軽量で機動性の高い戦車を開発したのだ。
もし日本がIII号戦車を持っていたら?——おそらく、ペリリューやサイパンの島嶼戦では、重すぎて使いづらかっただろう。
それでも、III号戦車から学べることはあった
戦後、日本の防衛産業は、ドイツ戦車の技術を徹底的に研究した。
- 傾斜装甲の重要性(パンターから学んだ)
- 高精度照準装置(ツァイス光学技術)
- 無線機による部隊連携
これらの技術は、戦後の日本戦車——61式戦車、74式戦車、90式戦車、そして現在の10式戦車——に受け継がれている。
関連記事:【2025年最新版】陸上自衛隊の日本戦車一覧|敗戦国が生んだ世界屈指の技術力
III号戦車は、日本にとって「直接的な脅威」ではなかった。しかし、「学ぶべき先輩」だったのだ。
III号戦車を今楽しむ方法——プラモデル・ゲーム・博物館

プラモデル——手のひらの上のIII号戦車
III号戦車のプラモデルは、世界中のメーカーから発売されている。
初心者におすすめ:
- タミヤ 1/35 ドイツIII号戦車L型:組みやすさ抜群、初心者に最適
- タミヤ 1/35 ドイツIII号戦車M型:後期型の決定版
- タミヤ 1/48 ドイツIII号突撃砲G型初期生産車:小型で場所を取らない
中級者以上におすすめ:
- ドラゴン 1/35 III号戦車N型:ディテール重視、やや難易度高
- トランペッター 1/35 III号戦車J型:精密パーツ多数
ゲーム——War ThunderとWorld of Tanksで操縦する
III号戦車は、多くのミリタリーゲームに登場している。
War Thunder(PC/PS4/PS5/Xbox)
リアル系戦車戦ゲームの決定版
III号戦車のすべての型式(E型、F型、J型、L型、M型、N型)が登場
装甲厚、砲弾の種類、エンジン性能など、細かく再現されている
無料プレイ可能
World of Tanks(PC/PS4/Xbox)
カジュアルな戦車戦ゲーム
III号戦車は、ドイツ戦車ツリーのTier3〜4に配置
初心者でも扱いやすい
無料プレイ可能
Enlisted(PC/PS5/Xbox)
第二次世界大戦FPSゲーム
歩兵視点で、III号戦車と戦ったり、操縦したりできる
臨場感のあるグラフィック
無料プレイ可能
これらのゲームで、III号戦車を操縦すれば、「なぜドイツ軍がこの戦車を主力にしたのか」がよく分かるはずだ。
博物館——本物のIII号戦車に会いに行く
世界には、実物のIII号戦車が展示されている博物館がいくつかある。
ドイツ戦車博物館(Deutsches Panzermuseum Munster, ドイツ)
III号戦車の各型式が展示されている
エンジンや内部構造も見学可能
ドイツ戦車ファンの聖地
クビンカ戦車博物館(ロシア)
鹵獲されたドイツ戦車が多数展示
III号戦車も複数展示されている
ボービントン戦車博物館(The Tank Museum, イギリス)
世界最大級の戦車博物館
III号戦車も展示されている
もし海外旅行の機会があれば、ぜひ訪れてみてほしい。プラモデルやゲームとは違う、本物の「重さ」「大きさ」を感じられるはずだ。
まとめ——III号戦車が教えてくれる「実用性という強さ」
III号戦車は、ティーガーIのような「伝説」を持たない。
パンターのような「最高傑作」とも呼ばれない。
しかし、III号戦車には、別の「強さ」があった。
それは、実用性だ。
信頼性が高く、整備しやすく、量産しやすい。
電撃戦の成功を支え、1943年まで前線で戦い続けた。
そして、その車体はIII号突撃砲として生まれ変わり、終戦まで戦い抜いた。
「最強」でなくても、「最も役に立つ」ことができる。
それが、III号戦車が僕たちに教えてくれることだ。
僕たち日本人も、同じだ。
大日本帝国の戦車は、ドイツ戦車に劣っていた。しかし、太平洋の島嶼戦という「自分たちの戦場」で、最善を尽くした。
そして戦後、日本は技術を磨き続け、今や世界最高水準の10式戦車を作り上げた。
「最強」を目指すのもいい。しかし、「実用的」であることの価値を忘れてはいけない。
III号戦車は、そんなことを教えてくれる戦車なのだ。





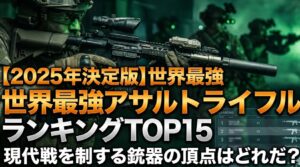







コメント