天安門広場を行進する中国人民解放軍の戦車部隊――その隊列は年々、明らかに変わってきている。
僕が10年前に見た映像と、2024年の建国75周年パレードを見比べてみると、その変化は一目瞭然だ。かつての主力だった旧式の59式戦車はほぼ姿を消し、代わりに楔形の増加装甲を纏った99A式や、デジタル迷彩を施された96式が隊列の中心を占めている。そして何より印象的なのは、軽戦車の区分に突如として現れた15式の存在だ。
「中国の戦車なんて、所詮ソ連のコピーでしょ?」――そんなイメージを持っている人は多いかもしれない。確かに中国戦車開発の出発点は、1950年代にソ連から供与されたT-54のライセンス生産だった。だが現在の中国は、独自の戦車開発技術を確立し、用途に応じて使い分ける多彩なラインナップを整備している。
本記事では、中国人民解放軍が保有する戦車を世代ごとに徹底解説する。最新の第3世代主力戦車から、いまだ一部で運用される第1世代戦車、そして台湾侵攻を想定した水陸両用戦車まで――中国の「陸の戦力」の全貌を、日本の戦車との比較も交えながら紐解いていこう。
中国戦車開発の歴史――ソ連コピーから独自開発へ

中国の戦車開発史を語る上で避けて通れないのが、建国直後の「ゼロからのスタート」である。
1949年の中華人民共和国建国時、人民解放軍が保有していた戦車は約375両。その内訳は旧日本軍の95式軽戦車や97式中戦車、国共内戦で国民政府軍から鹵獲したアメリカ製M4シャーマンやM3軽戦車など、まさに「寄せ集め」だった。中華民国時代を通じて戦車の国産化は一度も行われておらず、すべてを外国からの輸入に頼っていた状況である。
この状況を打開したのが、ソ連からの技術支援だった。1956年、中国はソ連からT-54A戦車のライセンス生産権を獲得し、内モンゴル自治区の包頭市に建設された第617工場で生産を開始する。これが後に「59式戦車」として制式化され、すべての中国戦車の始祖となった。
しかし、1960年代に入ると中ソ対立が深刻化し、ソ連からの技術供与は途絶える。1969年のウスリー川中州・ダマンスキー島(珍宝島)での軍事衝突では、中国軍はT-62戦車を鹵獲し、その技術を徹底的に研究した。こうして得られた技術を59式に盛り込んだのが69式戦車であり、ここから中国独自の戦車開発が本格的に始まることになる。
1980年代に入ると、改革開放政策によって西側諸国との技術交流が可能になった。イギリス製の105mmライフル砲L7のライセンス生産、西ドイツ製ディーゼルエンジン、イスラエル製射撃統制システムなど、積極的に西側技術を導入したのが80式、88式といった第2世代戦車である。
そして1990年代、湾岸戦争でイラク軍の中国製戦車がM1エイブラムスに一方的に撃破される光景を目の当たりにした中国は、第3世代戦車の開発を急ピッチで進めた。その成果が98式(後の99式)戦車であり、欧州の技術を大胆に取り入れつつ、独自のレーザー防御システムなどを組み込んだ「中国オリジナル」の戦車として完成したのである。
現在、中国は第3世代主力戦車の99式と96式を主力に据えつつ、山岳・高原地帯向けの15式軽戦車、台湾侵攻を想定した05式水陸両用戦車など、用途に応じた多彩なラインナップを整備している。総保有数は約5,000両とも言われ、その規模は日本の陸上自衛隊(約300両)を大きく上回る。
では、具体的にどのような戦車が配備されているのか。世代ごとに見ていこう。
第3世代主力戦車――中国機甲部隊の中核
99式戦車/99A式戦車――中国最強のフラッグシップMBT

中国機甲部隊の「顔」と言えるのが、この99式戦車である。
1999年の建国50周年軍事パレードで初めてその姿を現した99式は、実は98式戦車の改称版だ。98式は軍事パレードの時点ではまだ完全な実用段階に達しておらず、射撃管制装置や照準装置に不具合があったとされる。それでも「建国50周年」という記念すべき年に公開されたことを記念して、99式と改名された。つまり実質的には、98式が99式のプロトタイプといえる。
99式の最大の特徴は、従来の中国戦車とは一線を画す「脱ソ連型」の設計思想である。
砲塔には、ドイツのレオパルト2A6を思わせる楔形の増加装甲が取り付けられている。これは爆発反応装甲と複合装甲を組み合わせたもので、前面装甲の防御力は対APFSDS弾(装弾筒付翼安定徹甲弾)で1,000mm以上のRHA(均質圧延鋼装甲)相当とされる。
主砲は125mm滑腔砲で、2,000m先の800~900mmのRHA装甲を貫通できる性能を持つ。また、車両間情報システム(IVIS)を搭載し、戦車部隊全体で敵車両および味方部隊の位置・行動データをリアルタイムで共有できる。これは西側のM1A2エイブラムスやフランスのルクレールなどで既に導入されていた技術だが、中国戦車としては画期的な進化だった。
さらに特筆すべきは、独自開発のレーザー検知式アクティブ防護システムとレーザー誘導兵器である。敵のレーザー照準を感知し、逆照射で無力化する――まるでSF映画のような装備だが、実戦配備されている。
2007年、アメリカ軍のピーター・ペース海兵隊大将(当時)が中国軍基地を訪れた際、99式戦車の行進間射撃を見学した。その時99式は、APFSDS弾6発すべてを1,400m先の目標に命中させたという。この精度の高さは、西側の軍事関係者を驚かせた。
そして2012年頃から配備が始まったのが、99式の改良型である99A式戦車だ。
99A式は車体が90-II式戦車(輸出用戦車)の設計を参考に再設計され、車体長が99式の7.3mから6.487mへと約0.8m短縮された。これは横置き式のウクライナ製6TDディーゼルエンジンを参考に、新型国産エンジン(1,500馬力)と新型自動変速機CH-1000を搭載したことで実現した。従来の中国製戦車は機械式変速装置で超信地旋回が不可能だったが、99A式はこれを可能にした。
砲塔前面の楔形装甲はより急角度になり、砲塔側面の籠状ラックは砲塔後部まで延長され、装着された爆発反応装甲の数も増加している。まさに「重武装・重装甲」を追求した戦車である。
現在、99式と99A式を合わせて約1,200両が生産されている。配備先は北京軍区や瀋陽軍区など、中国の最精鋭部隊だ。もし台湾有事が発生すれば、上陸後の地上戦でこの99式が主力を担うことになるだろう。
日本の10式戦車と比較すると、99式は重量54トン(10式は48トン)とやや重く、機動性ではやや劣る可能性がある。しかし火力と装甲では互角以上と見られ、もし対峙することがあれば、決して侮れない相手である。
詳しくは、中国最新主力戦車99式戦車とは?日本の10式戦車との違いと実力を徹底比較を読んでみてほしい。
96式戦車/96A式戦車――「数」で支える実質的主力

もし「中国機甲部隊の真の主力は?」と問われたら、答えは99式ではなくこの96式戦車かもしれない。
96式は1996年に制式採用された第2世代主力戦車である。そう、世代区分としては「第2世代」なのだ。にもかかわらず、2020年時点で96式(初期型)が約1,000両、96A式(改良型)が約1,500両保有されており、合計約2,500両――これは99式の約2倍に相当する。
なぜこれほど大量に配備されているのか。理由は簡単で、96式は99式に比べて「安い」のである。
96式の開発背景はこうだ。第3世代戦車である98式(後の99式)の開発は1980年代後半から進められていたが、その生産コストの高さから全面的な配備は困難と予想された。そこで、既存の88式戦車をベースに、輸出向けに開発した85-IIM/85-IIAP式戦車の技術を取り入れ、比較的低コストの戦車として開発されたのが96式である。
つまり96式は、99式が揃うまでの「つなぎ」として開発された戦車だった。ところが、99式の生産が思ったほど進まず、結果として96式が「数的な主力」となってしまったのである。
96式の主砲は125mm滑腔砲(ZPT-98)で、自動装填装置を備える。これはソ連のT-72を参考にした設計だ。エンジンは当初730馬力の12150ZLBW水冷ディーゼルエンジンだったが、G型からは1,000馬力の150型V型12気筒水冷ディーゼルエンジンに強化された。最高速度も57km/hから65km/hへと向上している。
そして2005年頃から配備が始まったのが、96A式戦車である。
96A式は99式戦車の技術をフィードバックした改良型で、砲塔前面には楔形の増加装甲が追加され、FY-4爆発反応装甲も装着されている。射撃統制システムも改良され、火力・防御力ともに大幅に向上した。もはや「第2.5世代」と呼んでもいい性能である。
96式は中国の戦車開発史において、ある意味で「現実的な選択」の象徴である。最高性能を追求した99式と、コストパフォーマンスを重視した96式――この2本立てで中国は機甲戦力を整備してきた。
ちなみに、中国は2014年から毎年ロシアで開催される「戦車バイアスロン」国際大会に参加しているが、中国チームが使用するのは96式のカスタム版(96A1、96B)である。他国がT-72B3を使う中、中国だけが自国産戦車を持ち込んでいる。結果は、ロシアに次ぐ2位や3位を記録することが多い。これは96式の実力を示す一つの証拠と言えるだろう。
新世代軽戦車――15式軽戦車「高原の虎」

中国戦車開発史の中で、ひときわ異彩を放つのがこの15式軽戦車である。
2018年12月、中国国防部が公式に存在を発表した15式は、重量33~36トンという軽量級の戦車だ。99式(54トン)や96式(41トン)に比べて圧倒的に軽い。
「なぜ今さら軽戦車なのか?」――そう疑問に思う人もいるだろう。実際、第二次世界大戦後、世界的に軽戦車は廃れていった。軽戦車が担っていた偵察や支援の役割は、主力戦車やその他の装甲車が受け継いだからだ。
だが中国には、15式を必要とする明確な理由があった。それは「地理的制約」である。
中国は広大な国土を持つが、その全域で50トン級の主力戦車を運用できるわけではない。例えば中国南部の水郷地帯では、水田や湿地が多く、重い戦車は地盤が支えきれない。チベット高原などの高山帯では、標高4,000m以上の高地でエンジンが十分な出力を発揮できず、重い戦車の機動が困難になる。
こうした地域には、長らく旧式の62式軽戦車(1962年制式採用、重量21トン)が配備されていた。しかし62式はあまりに旧式で、現代戦には対応できない。現場の部隊からも新型戦車を求める強い要求が出ていた。
そこで開発されたのが15式である。開発コードネームは「高原猛虎」。まさにチベット高原での運用を想定した名称だ。
15式の主砲は105mmライフル砲で、ロイヤル・オードナンス105mm戦車砲L7のライセンス生産版を改良したものである。自動装填装置を備え、中国規格の砲弾に加えてNATO標準規格の弾薬も使用できる。
「105mm砲では火力不足では?」と思うかもしれない。確かに、125mm滑腔砲を搭載する99式や96式に比べれば火力は劣る。しかし15式の想定任務は、敵の最新主力戦車との正面対決ではない。山岳地帯や高原で敵の機動戦力や固定施設、歩兵部隊と交戦し、味方歩兵に機動火力を提供することが主な役割である。
そしてこの戦車の真の強みは、火力よりも「情報化」にある。
15式にはセンサー類が多数装備されており、その情報処理能力は99式と同等かそれ以上とされる。他のユニットからの情報を基に間接射撃も可能で、まさに「高度に情報化された」戦車である。山岳地帯で敵が侵入できない地形を機動し、ネットワーク化された火力支援を提供できれば、中国軍は圧倒的に優位に立てる。
開発は難航した。冷却水管の破裂、エンジン火災、油気圧パワーアシスト破損、射撃不良など、あらゆる面で問題が発生し、完成までに8年を要したという。しかし2019年10月の建国70周年軍事パレードで初めて公開された15式の姿は、まさに「新世代」を感じさせるものだった。
輸出型はVT-5の名称で販売されており、既にタイ王国海兵隊やベネズエラ海兵隊が採用している。
日本の視点から見ると、この15式は興味深い存在である。日本にも16式機動戦闘車という軽量の火力支援車両があるが、15式とはコンセプトが異なる。16式は装輪式で道路機動を重視するのに対し、15式は装軌式で不整地踏破性を重視している。もし将来、山岳地帯で日中が対峙することがあれば、この15式が相手になるかもしれない。
第2世代戦車――西側技術導入の産物
88式戦車――短命だが技術向上に貢献
88式戦車は、1988年に正式採用された第2世代戦車である。
80式戦車の開発着手後に入手した西側技術を反映させるため、80式と平行する形で開発が進められた。80式が輸出仕様だったのに対し、88式は主に国内仕様として位置づけられた。
88式の特徴は、NATO規格の83式105mmライフル砲(オーストリア製L7のライセンス版)、イギリス製の射撃統制システム、西ドイツ製のエンジンなど、積極的に西側技術を導入した点である。車体・砲塔は80式と基本的に同じだが、砲塔部には複合装甲も取り付け可能になった。
しかし88式には、生まれた時代が悪かったという不運がある。
1988年といえば、世界の主力戦車は既に第3世代MBTへと移りつつあった時期だ。M1A1エイブラムス、レオパルト2A4、T-80Uなど、複合装甲と高性能な射撃統制システムを備えた戦車が続々と登場していた。そんな中で登場した88式は、いわゆる「第2世代」であり、登場した時点で既に旧式という立場に置かれてしまった。
さらに決定打となったのが、1991年の湾岸戦争である。
この戦争でイラク軍が保有していた中国製の59式、69式戦車が、西側の第3世代戦車であるM1エイブラムスになすすべなく撃破される光景が世界中に報道された。世界における中国製戦車のブランドイメージは失墜し、88式の輸出も振るわなかった。
中国自身も、西側に対抗できる新たな戦車開発の必要性を痛感した。その結果、88式の生産は1995年に約500両をもって終了した。主力戦車としては短命だった。
しかし88式は、中国の戦車開発技術の向上に大きく貢献した。西側技術を実際に導入し、運用することで得られた知見は、後の96式、99式の開発に活かされている。その意味で、88式は中国戦車開発史における「橋渡し役」だったと言えるだろう。
80式戦車――輸出に失敗した第2世代戦車
80式戦車は、79式戦車の車体をベースに開発された中国初の第2世代主力戦車である。
それまでのソ連戦車のコピー品だった59式や69式と異なり、80式はNATO規格の105mmライフル砲、イギリス製の射撃統制システム、西ドイツ製のエンジンなど、積極的に西側の戦車技術を取り込んで自国開発を目指した戦車だった。
車体は79式をベースに大型化し、転輪も大型転輪5個から上部支持輪を持つ小型転輪6個へ変更された。砲塔は、ソ連軍戦車独特の避弾経始を重視したお椀型デザインを引き継ぎつつ、西側のNATO規格105mmライフル砲を採用するという、東西のハイブリッド設計である。微光増幅式暗視装置、アナログ式弾道コンピュータ、レーザー測定器なども導入された。
しかし80式には致命的な問題があった。それは「輸出に失敗した」ことである。
80式は主に輸出向けとして開発されたが、販売が全く振るわず、本格的な生産は行われなかった。原因は複数ある。第一に、当時の中国製戦車に対する国際的な評価が低かったこと。第二に、同時期に開発された88式(国内仕様)との競合。そして第三に、価格面で他国の中古戦車に対抗できなかったことだ。
結局80式は試作段階で終わり、そのノウハウは88式、さらには96式の開発に受け継がれることになった。80式自体は歴史の表舞台に立つことはなかったが、その技術的蓄積は決して無駄ではなかった。
第1世代戦車の系譜――中国戦車開発の源流

59式戦車――すべての始まり
59式戦車――この戦車なくして、中国の戦車開発史は語れない。
1959年にソ連のT-54をライセンス生産した59式は、全ての中国戦車の「始祖」である。1963年から本格的な生産が始まり、1980年代半ばまでに10,000両以上が生産された。うち6,000両が中国人民解放軍陸軍に配備され、残りは世界各国に輸出された。
59式はT-54Aとほぼ同一の性能を持つ。車体は溶接鋼板、砲塔は鋳造鋼板で製造され、主砲は100mm滑腔砲D-10T(59式砲)。重量は36トン、乗員は4名で、最高速度は50km/hである。
当初は部品をソ連から輸入して組み立てるノックダウン生産だったが、1961年までに砲塔・装甲板・戦車砲・弾薬も国産化できるようになった。ただし、照準装置や夜間暗視装置などの精密機器は、中ソ関係が悪化する1964年頃まではソ連からの輸入に頼っていた。
59式は世界各地の紛争に投入された。1965年の第二次印パ戦争、1979年の中越戦争、1980年のイラン・イラク戦争、そして1991年の湾岸戦争――しかしその多くで、59式は期待された性能を発揮できなかった。
特に湾岸戦争では、イラク軍の59式がM1エイブラムスに一方的に撃破される光景が世界中に報道された。第1世代戦車と第3世代戦車の性能差を、59式は身をもって示すことになったのである。
現在、中国国内では後継の96式や99式が配備され、59式は退役が進んでいる。しかしパキスタン、北朝鮮、ベトナムなど一部の国では、改良を加えられつつも今なお現役で使用されている。その意味で、59式は21世紀の今も「生き続けている」戦車なのである。
69式戦車/79式戦車――独自開発への第一歩
69式戦車は、59式戦車をベースに開発された中国初の「国産」主力戦車である。
1969年の中ソ国境紛争時に鹵獲したT-62戦車の技術も盛り込み、独自に発展させたのが69式だ。開発は内モンゴル自治区にある617工場が担当した。
69式の主砲は当初100mm滑腔砲を搭載する予定だったが、命中精度の問題から100mmライフル砲に換装された。標準型となった69-II式戦車は、TSFC2射撃統制システムを装備し、59式に比べて射撃精度が向上した。
特に69-II式戦車は2,000両以上が輸出に成功し、1980年代の紛争地域で頻繁にその姿を現した。パキスタン、イラン、イラク、タイなど多くの国が採用している。
そして西側の戦車技術を取り込んで開発されたのが、69-III式戦車、後の79式戦車である。
79式は69式をベースに、イギリス製L7系105mmライフル砲のライセンス生産版を搭載した改良型だ。1986年に制式採用され、500両余りが中国国内に配備された。主砲のライセンス契約の関係で輸出は禁止されたため、国内配備のみに終わった。
69式/79式は、中国が「ソ連のコピー」から脱却し、独自の戦車開発技術を確立していく過程を象徴する戦車である。その技術的蓄積は、後の80式、88式、そして96式へと受け継がれていった。
62式軽戦車――中国初の純国産戦車
62式軽戦車は、中国初の純国産設計の戦車である。
59式戦車をスケールダウンさせた軽戦車として、1958年から設計が始まり、1963年から生産が開始された。山岳、水田、河川の多い地域での運用を目的に開発され、1989年までに1,500両以上が生産された。
車体の基本設計は59式を一回り小型化したもので、重量は21トンと59式(36トン)より15トン軽量化されている。装甲の厚さは車体前面で35mm、砲塔前面で45mmとかなり薄い。主砲は85mm砲で、59式の100mm砲よりも小口径だ。
62式は主にチベットや内モンゴルなどの山岳地域、華南の低地など道路条件の悪い地域で重宝された。また積極的な輸出も行われ、北ベトナム(200両)、北朝鮮、バングラデシュ、スーダンなど多くの国に輸出された。
しかし1979年の中越戦争で実戦投入された際、装甲の薄さによる脆弱性を露呈した。特に携帯火器であるRPGによる攻撃で数多くの車両が撃破された。これを教訓に、1980年には装甲を中心に改良が施された62式改軽戦車が開発された。
その後も改良が続けられ、2000年には105mm低反動砲の搭載やERA(爆発反応装甲)装着など延命措置が施されたが、2011年には全車退役となった。後継車両として開発されたのが、前述の15式軽戦車である。
62式は性能面では決して優秀な戦車ではなかった。しかし「中国初の純国産設計」という点で、中国戦車開発史において重要な位置を占めている。
水陸両用戦車――台湾侵攻を見据えた特殊兵器

05式水陸両用戦車――世界最強クラスの水陸両用戦力
中国が台湾侵攻を想定して開発した兵器の中で、最も注目すべきものの一つが05式水陸両用戦車である。
05式は、05式水陸両用歩兵戦闘車(ZBD-05)の派生型として開発された火力支援車両で、63A式水陸両用戦車の後継として配備されている。制式名称はZTD-05。開発は湖南江麓機械集団が担当した。
05式の最大の特徴は、その圧倒的な水上速度である。
従来の63A式が水上で時速14km程度だったのに対し、05式は時速30~40kmと約3倍の速度を誇る。これは揚陸艦から発進して海岸に到達するまでの時間を劇的に短縮する。敵の対艦ミサイルや砲撃に晒される時間が短いほど、上陸作戦の成功率は高まる。
この高速水上航行を実現しているのが、車体後部に装備されたウォータージェット推進装置である。陸上では通常の履帯走行、水上ではウォータージェットに切り替わる。まさに「陸海両用」の戦闘車両だ。
主砲は低反動化された105mmライフル砲で、砲安定化装置により行進間射撃も可能である。副武装として30mm機関砲、紅箭73C対戦車ミサイル発射機2基、7.62mm同軸機銃を装備する。
装甲は軽量化のため薄めだが、敵の重装備と正面から交戦することは想定していない。05式の任務は、上陸部隊の歩兵を支援し、海岸の防御陣地を制圧することである。歩兵や主力戦車とともに橋頭堡を構築し、敵の装甲部隊による反撃を食い止めて揚陸部隊第2陣の到着まで上陸地点を確保する――これが05式に期待される役割だ。
2005年に行われた中露合同演習では、上陸作戦の演習中に旧式の63A式が2両水没し8名の死者を出す事故が発生した。この教訓も05式の開発に活かされている。
05式は「世界最強の水陸両用戦車」と評されることもある。確かに水上速度や火力支援能力では、アメリカ海兵隊のAAV7や日本の水陸機動団が使用するAAV7を上回る性能を持つ。
輸出型はVN-16の名称で販売されており、タイ王国海兵隊とベネズエラ海兵隊が採用している。
もし台湾有事が発生すれば、この05式が上陸作戦の第一波を担うことになるだろう。日本にとっても、決して対岸の火事ではない。
63式水陸両用戦車――ソ連PT-76の発展型
63式水陸両用戦車は、ソ連製PT-76水陸両用戦車をコピー生産した60式水陸両用戦車の車体に、62式軽戦車の85mm砲塔を搭載して開発された戦車である。
PT-76が76.2mm砲だったのに比べ、85mm砲を搭載した63式は火力が向上している。製造は中国北方工業公司(NORINCO)が担当した。
63式は主に中国人民解放軍海軍の海軍陸戦隊に配備され、アルバニア、パキスタン、北朝鮮、ベトナム、ミャンマーなどに輸出された。ベトナム戦争や中越戦争でも実戦投入されている。
1990年代に入ると、63式の近代化改修が実施された。主砲を従来の85mm砲から105mm低圧砲に換装した型が63A式水陸両用戦車である。1997年より配備が始まった。
しかし前述の通り、2005年の中露合同演習で63A式の2両が水没事故を起こした。車体に比して大型の砲を搭載したため重量バランスに問題が生じていたとされる。
この事故を受けて開発が急がれたのが、前述の05式水陸両用戦車である。現在、63A式は05式に更新されつつあるが、一部では今なお現役で使用されている。
中国戦車の総合評価と日本への示唆

ここまで中国の戦車ラインナップを見てきて、どのような印象を持っただろうか。
率直に言って、中国の戦車開発技術は着実に向上している。
1950年代の「ソ連のコピー」から始まった中国戦車は、半世紀以上の開発を経て、今や独自の技術と設計思想を持つに至っている。99A式の楔形増加装甲、15式の高度な情報化、05式の高速水上航行能力――これらはすべて、中国が独自に開発した技術である。
もちろん、すべてが完璧というわけではない。エンジンの耐久性や射撃統制システムの精度など、西側の最新鋭戦車に比べればまだ改善の余地はある。99式のエンジンMTBF(平均故障周期)は500時間とされ、欧米のエンジン(1,000時間程度)に比べて信頼性が低い。また、戦車バイアスロン大会では車輪が外れたりエンジンが停止したりといったトラブルも報告されている。
しかし重要なのは、中国がこれらの課題を認識し、着実に改善を進めている点である。99式から99A式への改良、96式から96A式への改良――それぞれの世代で確実に性能向上を図っている。そして何より、中国は「数」で圧倒できる生産能力を持っている。
日本の視点から見ると、中国の戦車戦力は明らかな「脅威」である。
陸上自衛隊が保有する戦車は約300両(10式戦車、90式戦車、74式戦車の合計)。対する中国は約5,000両。数の差は歴然としている。もちろん、すべての戦車が対日戦に投入されるわけではないし、海を越えて日本本土に上陸させるのは容易ではない。しかし台湾有事や尖閣諸島有事を想定した場合、中国の水陸両用戦力は無視できない存在である。
では、日本はどう対応すべきか。
第一に、質で優位を保つことだ。日本の10式戦車は、C4Iシステム(指揮・統制・通信・コンピュータ・情報)の統合、優れた射撃統制システム、高い機動性など、世界トップクラスの性能を持つ。この技術的優位を維持し続けることが重要である。
第二に、水陸両用戦力への対処能力を強化することだ。中国の05式水陸両用戦車に対抗するため、日本も水陸機動団の装備を充実させ、南西諸島の防衛態勢を強化する必要がある。
第三に、日米同盟の重要性を再認識することだ。数で劣る日本が中国の機甲戦力に対抗するには、アメリカ軍の支援が不可欠である。日米共同訓練を通じて相互運用性を高めておくことが、抑止力の強化につながる。
中国の戦車開発は今後も続く。次世代主力戦車の開発、無人戦車の研究、AI搭載戦車の実験――中国は軍事技術の最先端を追い求めている。
私たちにできることは、中国の軍事力を冷静に分析し、適切に対処することだ。過小評価も過大評価もせず、事実に基づいて判断する。それが、この複雑な時代を生き抜くために必要な姿勢だと、僕は思う。
中国戦車の全貌、少しでも理解していただけただろうか。この記事が、あなたの「知りたい」という好奇心に応えられたなら幸いである。
※本記事で紹介した中国戦車について、さらに詳しく知りたい方は、日本の戦車との比較記事もぜひご覧いただきたい。日本が誇る10式戦車の技術力についても、別記事で詳しく解説している。




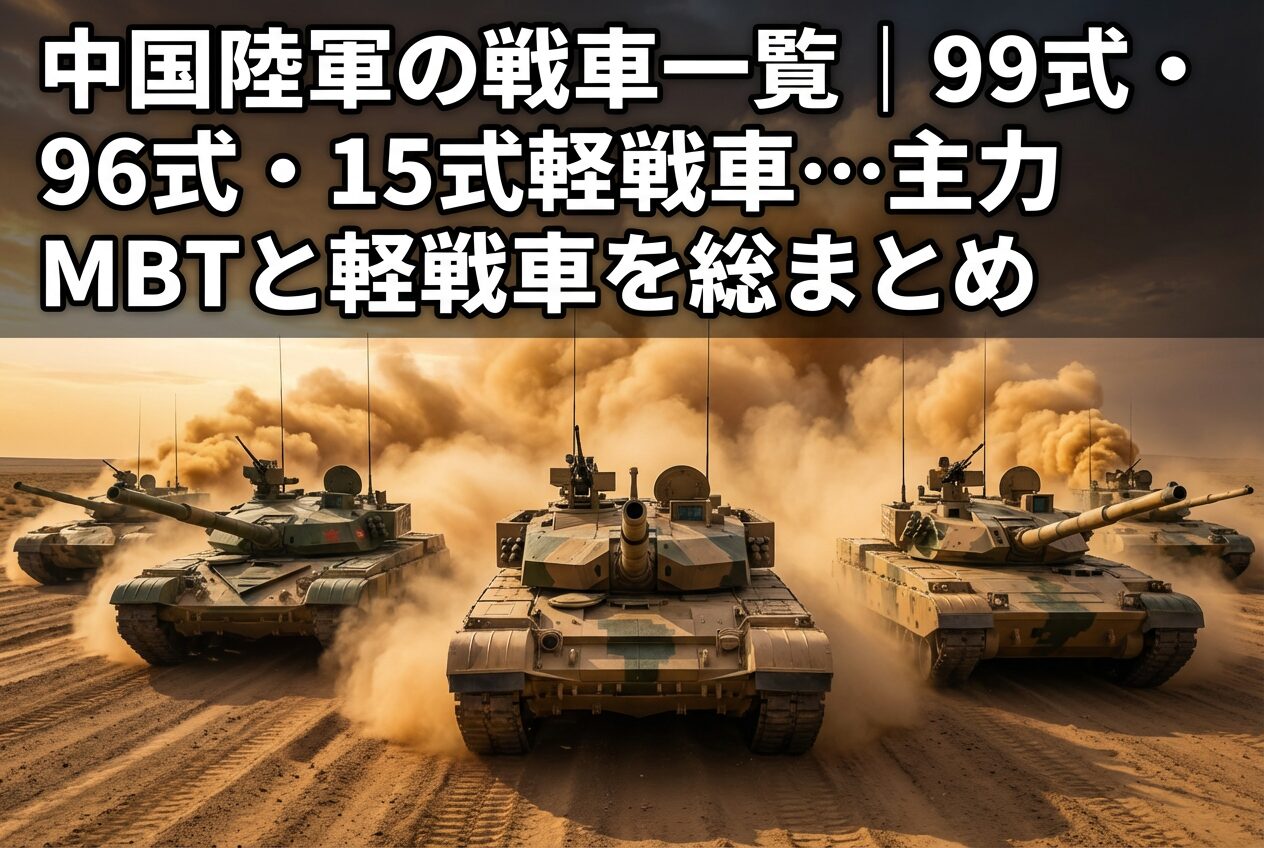
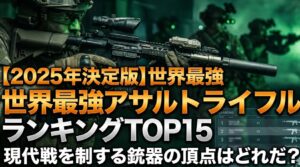







コメント