「スプートニク・ショックに極めて近い」──米軍トップが漏らした本音
2021年10月、アメリカ軍制服組トップのマーク・ミリー統合参謀本部議長が、記者の前で珍しく動揺を隠さなかった。
「中国の極超音速ミサイル実験は、”スプートニク・ショック”に極めて近いものだった」
スプートニク・ショックとは、1957年にソ連が世界初の人工衛星を打ち上げた際、アメリカが受けた衝撃のことだ。それまで技術的に優位だと信じていた超大国が、突如として後塵を拝する立場に追い込まれた瞬間だった。
あれから60年以上が経った現代、中国の極超音速兵器がアメリカに同等の衝撃を与えている。そして、その脅威の矛先は、日本にも向けられているのだ。
今回の記事では、「極超音速兵器って結局何がすごいの?」「本当に迎撃できないの?」「日本はどう対応しているの?」といった疑問に、できるだけわかりやすく答えていこうと思う。
そもそも極超音速兵器とは何か?

まず基本から押さえておこう。
「極超音速」とは、音速の5倍(マッハ5)以上の速度を指す。音速が秒速約340メートルなので、マッハ5だと秒速約1,700メートル。東京から大阪までの約500キロを、わずか5分足らずで到達できる計算になる。
「いや、弾道ミサイルだって再突入時にはマッハ20とか出るでしょ?」と思った方、鋭い。実はその通りで、速度だけなら従来の弾道ミサイルも極超音速で飛んでいる。
では、なぜ「極超音速兵器」が新たな脅威として注目されているのか。それは「速さ」だけでなく、「軌道の変則性」にある。
従来の弾道ミサイルは、その名の通り「弾道」を描いて飛ぶ。発射されると大気圏外に飛び出し、放物線を描いて落ちてくる。軌道が予測しやすいため、発射を探知すれば着弾点を計算でき、迎撃のタイミングを計ることができた。
ところが極超音速兵器は違う。マッハ5以上の速度を維持しながら、大気圏内の低高度を飛行し、しかも軌道を変えることができる。レーダーで捕捉しにくく、どこに向かっているのか予測が難しく、迎撃のチャンスが極めて限られる。
これが「ゲームチェンジャー」と呼ばれる所以だ。
極超音速兵器の2つのタイプ

極超音速兵器は大きく2種類に分けられる。
HGV(極超音速滑空体)
HGV(Hypersonic Glide Vehicle)は、弾道ミサイルのロケットブースターで打ち上げられた後、大気圏内で切り離されて「滑空」する兵器だ。
イメージとしては、紙飛行機を山の頂上から投げるようなもの。最初はロケットの力で高く上がり、その後は自身の翼で空気の力を使いながら滑空して目標に向かう。推進装置を持たないため「グライダー」のような存在だが、その速度はマッハ5から10に達する。
HGVの最大の特徴は、滑空中に軌道を変えられること。上下左右に機動しながら目標に向かうため、従来の弾道ミサイル防衛システムでは捕捉・迎撃が非常に難しい。
HCM(極超音速巡航ミサイル)
HCM(Hypersonic Cruise Missile)は、「スクラムジェットエンジン」という特殊なエンジンで自ら推進力を得ながら極超音速で飛行するミサイルだ。
通常の巡航ミサイル(例えばトマホーク)が地表すれすれを亜音速で這うように飛ぶのに対し、HCMは高高度を極超音速で突っ走る。エンジンを持っているため、飛行中も加速・減速が可能で、軌道変更の自由度も高い。
日本の防衛装備庁も、このスクラムジェットエンジンを使った極超音速誘導弾の開発を進めており、2022年7月にはJAXAとの共同で燃焼試験に成功している。
中国の極超音速兵器ラインナップ

では、中国が実際に配備・開発している極超音速兵器を見ていこう。
DF-17(東風17号)──世界初の実戦配備型HGV
中国の極超音速兵器の「顔」といえば、やはりDF-17だろう。
2019年10月1日、中国建国70周年を祝う軍事パレードで、16台の自走発射機に搭載されたDF-17が世界に初めてお披露目された。これは、実戦配備された極超音速滑空兵器として世界初とされている。
DF-17の基本スペックを整理すると以下のようになる。
射程:1,800〜2,500キロメートル 速度:マッハ5〜10 弾頭:通常弾頭または核弾頭搭載可能 発射方式:道路移動式(TEL車両搭載) 運用開始:2020年
DF-17は、固体燃料のロケットブースター(DF-16を転用したとされる)で打ち上げられ、DF-ZF(米国側呼称:WU-14)と呼ばれる極超音速滑空体を分離して目標に向かわせる。
射程2,500キロメートルというのは、中国の福建省あたりから発射しても、日本の東北地方南部まで届く距離だ。つまり、東京は完全に射程圏内に入っている。
さらに注目すべきは、米戦略コマンドがDF-17を「戦略核システム」の一つに分類していることだ。核弾頭搭載可能ということは、戦術核兵器としての使用も想定されている可能性がある。
DF-21D/DF-26──「空母キラー」の異名
DF-17ほど話題にならないが、対艦攻撃という点で日本にとって脅威なのがDF-21DとDF-26だ。
DF-21Dは「空母キラー」の異名を持つ対艦弾道ミサイル。射程約1,500キロメートルで、西太平洋を航行する空母打撃群を攻撃できるとされる。DF-26は射程約4,000キロメートルで、「グアムキラー」とも呼ばれている。
これらは厳密には「極超音速滑空体」ではなく変則軌道を取る弾道ミサイルだが、再突入段階で機動できるとされ、従来のミサイル防衛では迎撃が困難という点では同様の脅威を持つ。
台湾有事の際、これらのミサイルが在日米軍基地や介入しようとする米空母機動部隊に向けられる可能性は十分にある。
星空2号(Xingkong-2)──スクラムジェット巡航ミサイル
DF-17がHGV(滑空型)の代表なら、星空2号はHCM(巡航型)の代表だ。
2018年に中国航天科技集団第十一研究院が飛行試験に成功したと発表されており、マッハ6での飛行が可能とされる。スクラムジェットエンジンを搭載し、大気圏内を極超音速で巡航しながら目標を攻撃する。
現時点では実戦配備には至っていないとみられるが、中国が着実に技術を蓄積していることを示す重要な存在だ。
部分軌道爆撃システム(FOBS)──宇宙を経由する悪夢
2021年7月、中国は米軍関係者を最も震撼させた実験を行った。
長征ロケットを使って極超音速滑空体を一度宇宙に打ち上げ、地球を周回させた後に目標に向けて落下させるというものだ。これは「部分軌道爆撃システム(FOBS:Fractional Orbital Bombardment System)」と呼ばれる技術で、冷戦時代にソ連が開発したシステムの発展型とされる。
従来の弾道ミサイルは北極上空を経由してアメリカに向かうため、米国の早期警戒システムはその方向を重点的に監視している。ところがFOBSは南極方向から地球を周回してくるため、既存の監視網をすり抜けることができる。
さらに驚くべきことに、この実験では極超音速滑空体が滑空中に南シナ海上空でさらにミサイルを発射したとされている。極超音速で飛行しながら別の飛翔体を発射する技術は、他国では実現例がなく、米国防総省の専門家たちに大きな衝撃を与えた。
なぜ日本にとって脅威なのか

ここまで読んで、「中国とアメリカの話でしょ?」と思った方もいるかもしれない。しかし、これは日本にとっても切実な問題だ。
東京が射程圏内という現実
先ほど触れたように、DF-17の射程は1,800〜2,500キロメートル。中国沿岸部から発射すれば、日本列島のほぼ全域が射程に入る。
しかも、DF-17は道路移動式の発射機に搭載されている。固定式のミサイルサイロと違い、発射前に位置を特定することが非常に難しい。発射の兆候を察知して先制攻撃することも、発射後に発射地点を攻撃して残りのミサイルを無力化することも困難だ。
既存の防衛システムでは迎撃が難しい
現在の日本のミサイル防衛は、基本的に2段構えになっている。
第1段階:イージス艦搭載のSM-3で大気圏外での迎撃 第2段階:地上配備のPAC-3で大気圏内での迎撃
この体制は「弾道飛行」する従来のミサイルを想定したものだ。弾道ミサイルは予測可能な軌道を描くため、着弾点を計算し、最適なタイミングで迎撃ミサイルを撃ち込むことができる。
ところが、極超音速滑空体の場合、事情が異なる。
DF-17のHGV部分(DF-ZF)の滑空高度は60キロメートル以下とされる。これは、SM-3ブロックIIAの推定最低迎撃高度70キロメートルを下回っている。つまり、SM-3では届かない高度を飛んでくる可能性がある。
かといって、PAC-3で迎撃しようにも、マッハ5〜10で飛来し、しかも軌道を変えながら突っ込んでくる目標を捉えるのは至難の業だ。
これが「極超音速兵器は迎撃不可能」と言われる所以である。
台湾有事との連動リスク
もう一つ忘れてはならないのが、台湾有事との関連だ。
高市早苗首相が「台湾有事は存立危機事態になり得る」と発言したことで日中関係は緊張を高めているが、台湾に対する武力行使が現実になった場合、日本が巻き込まれる可能性は極めて高い。
在日米軍基地は台湾支援の拠点となる。中国としては、米軍の介入を阻止するために、これらの基地を無力化したいと考えるだろう。極超音速兵器は、その「接近阻止・領域拒否(A2/AD)」戦略の中核をなす存在だ。
DF-17やDF-21D、DF-26といったミサイルが、嘉手納、横須賀、三沢といった基地に向けられる可能性は、決して絵空事ではない。
本当に迎撃は不可能なのか?

ここまで脅威を強調してきたが、では本当に打つ手はないのだろうか。
結論から言えば、「現時点では難しいが、対策は進んでいる」というのが正確なところだ。
日米共同開発のGPI(滑空段階迎撃用誘導弾)
最も期待されているのが、日米共同で開発を進めている「GPI(Glide Phase Interceptor)」だ。
2023年8月の日米首脳会談で共同開発が合意され、2024年11月には防衛省が三菱重工業と約560億円の契約を締結したことを発表している。
GPIの特徴は、極超音速滑空体が「滑空している段階」で迎撃を狙うこと。従来の迎撃ミサイルが大気圏外(SM-3)または着弾直前(PAC-3)で対処するのに対し、GPIはその間の段階での迎撃を担う。
日本は第2段ロケットモーターやキルビークル(破壊飛翔体)の推進装置などを担当し、2030年代の開発完了を目指している。これが実現すれば、世界初の極超音速兵器迎撃ミサイルとなる。
日本のミサイル技術については、関連記事「日本が保有するミサイル全種類を完全解説」も参考にしてほしい。
衛星コンステレーションによる探知能力強化
迎撃の前提として、まず相手のミサイルを探知・追尾できなければならない。
極超音速兵器は低高度を飛行するため、地上や海上のレーダーでは遠方から捕捉しにくい。そこで期待されているのが、多数の低軌道衛星で構成する「衛星コンステレーション」だ。
宇宙から監視することで、地上レーダーでは捉えられない低高度飛行中の目標も追跡できるようになる。日本もIHIなどが実証事業を受注しており、日米連携でこの能力の構築を進めている。
防衛産業全体の動向については、「日本の防衛産業・軍事企業一覧」や「三菱重工の防衛産業」も併せてご覧いただきたい。
レールガン(電磁砲)の可能性

もう一つ注目されているのが、レールガン(電磁砲)だ。
レールガンは火薬ではなく電磁力で砲弾を発射する兵器で、従来のミサイルでは追いつけない極超音速目標に対しても、弾丸自体を高速化できる可能性がある。しかも、1発あたりのコストが安く、連射も可能。
日本の防衛省は1980年代からレールガンの研究を続けており、実は世界でも先端を走っている。米国が2021年に開発を中止した一方で、日本は2030年までの実用化を目指して研究を継続している。
2024年の防衛装備庁シンポジウムでも、極超音速兵器の迎撃を念頭に置いたレールガンの進捗状況が報告されている。
「ゴールデン・ドーム」構想
2025年5月、トランプ大統領は次世代ミサイル防衛システム「ゴールデン・ドーム」の計画を発表した。
これは陸・海・宇宙に展開される統合的なミサイル防衛システムで、「地球の反対側や宇宙から発射されたミサイルでも迎撃できる」という野心的な構想だ。日本もこの計画に協力する形で、極超音速兵器への対処能力を高めていくことになる。
「攻撃は最大の防御」──反撃能力の整備
迎撃だけでなく、「撃たせない」ための抑止力も重要だ。
2022年に閣議決定された「国家安全保障戦略」では、相手領域内のミサイル発射基地などを攻撃できる「反撃能力」の保有が明記された。
長射程の巡航ミサイルや、将来的には日本独自の極超音速誘導弾の開発も進んでいる。「撃てば必ず報復を受ける」という状況を作ることで、そもそも撃たせないという発想だ。
もちろん、これは専守防衛との整合性や、エスカレーションのリスクなど、慎重に議論すべき問題を含んでいる。だが、極超音速兵器という新たな脅威に対し、日本が本気で対応策を検討し始めていることは間違いない。
僕たちにできること
ここまで読んで、「じゃあ一般市民として何かできることはあるの?」と思った方もいるだろう。
正直なところ、極超音速ミサイルに対して個人で備えられることは限られている。発射から着弾まで数分しかない状況で、一般の防空壕では意味をなさない可能性が高い。
ただ、以下のことは心がけておいても損はないだろう。
まず、正確な情報を得ること。SNSでは過度に不安を煽る情報も、逆に「日本の技術は世界一だから大丈夫」といった根拠のない楽観論も飛び交っている。防衛白書や信頼できる専門家の発信を参考にしたい。
次に、基本的な防災準備。直接的なミサイル対策にはならなくても、緊急事態における最低限の備えは、他の災害対策にも共通して役立つ。
そして、この問題について関心を持ち続けること。民主主義国家において、国防政策は最終的に国民の意思によって決まる。無関心であることは、この重要な問題を他人任せにすることを意味する。
まとめ:脅威は現実、しかし対策も進む
中国の極超音速兵器は、すでに東京を射程に収める段階まで来ている。従来のミサイル防衛システムでは対処が難しく、日本にとって深刻な脅威であることは間違いない。
しかし、日本も手をこまねいているわけではない。日米共同開発のGPI、衛星コンステレーションの構築、レールガンの研究、そして反撃能力の整備と、複層的な対策が進められている。
極超音速兵器の開発競争は、米中露だけでなく、北朝鮮やインド、そして日本も含めた世界規模の現象になっている。この軍拡競争がどこへ向かうのか、そして日本がどのような選択をしていくのか、私たちは注視し続ける必要がある。
かつて、帝国海軍は「量より質」で列強に対抗しようとした。零戦の性能で数の劣勢を補おうとした歴史がある。現代においても、日本は限られたリソースの中で最大限の防衛能力を追求している。
その努力が実を結ぶことを、僕は心から願っている。


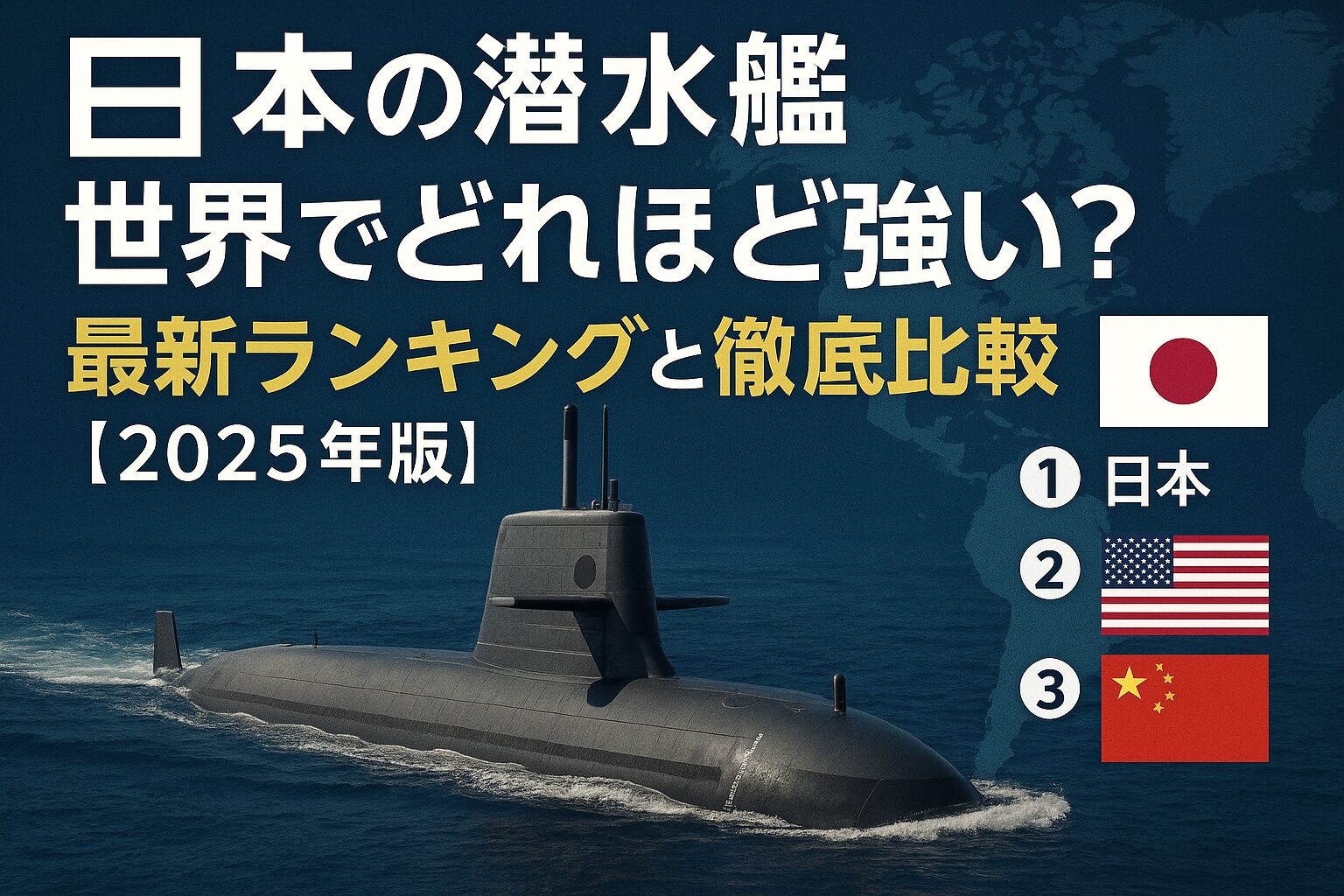










コメント