2025年初頭、尖閣諸島周辺で中国公船の活動がさらに活発化し、台湾海峡では連日のように中国軍機が中間線を越えている。日本のニュースでは「中国の軍事的圧力が高まっている」と報じられるが、実際のところ、中国人民解放軍はどれほどの実力を持っているのだろうか?
僕たちが子供の頃、中国は「人数は多いけど装備は古い」というイメージだった。しかし今、その認識は完全に時代遅れだ。中国は過去30年間で驚異的な経済成長を遂げ、その資金を惜しみなく軍事力の近代化に注ぎ込んできた。結果として、2025年現在、中国は米国に次ぐ世界第2位の軍事大国へと変貌を遂げている。
空母3隻体制を確立し、ステルス戦闘機J-20を実戦配備し、弾道ミサイルで空母を狙える「空母キラー」を開発し、極超音速兵器の実験に成功している。僕たちの祖父や父親の時代に戦った「あの中国」とは、もはや別の国と言っていいほどの変化だ。
この記事では、中国人民解放軍(PLA)の現在の実力を、陸海空それぞれの軍種ごとに徹底解説していく。「中国軍って実際どれくらい強いの?」「日本の自衛隊と比べてどうなの?」という素朴な疑問に、できるだけわかりやすく答えていきたい。
中国人民解放軍(PLA)とは?——5つの軍種からなる巨大組織

中国人民解放軍、通称PLA(People’s Liberation Army)は、中国共産党が指揮する軍事組織だ。ここが重要なポイントで、多くの国では軍隊は「国」に属するが、中国では「党」に属している。つまり、PLAは中国共産党の「私兵」という側面を持つ。
2015年の軍制改革以降、PLAは以下の5つの軍種で構成されている。
陸軍(PLA Ground Force)
伝統的な地上戦力。現役兵力だけで約97万人を擁し、世界最大規模の陸軍だ。かつては「人海戦術」のイメージが強かったが、現在は機械化・情報化が急速に進んでいる。
海軍(PLA Navy)
正式名称は「中国人民解放軍海軍」(PLAN)。艦艇数では既に米海軍を上回り、世界最大の海軍となった。空母3隻を保有し、第4、第5空母も建造中とされる。
空軍(PLA Air Force)
約40万人の人員を擁し、戦闘機約1,900機を保有する巨大な航空戦力。第5世代ステルス戦闘機J-20の実戦配備も進んでいる。
ロケット軍(PLA Rocket Force)
旧称「第二砲兵」。弾道ミサイルと巡航ミサイルを専門に扱う戦略部隊だ。核弾頭を搭載可能な大陸間弾道ミサイル(ICBM)から、対艦弾道ミサイル「DF-21D」「DF-26」といった「空母キラー」まで、多様なミサイル戦力を保有している。
戦略支援部隊(Strategic Support Force)
サイバー戦、電子戦、宇宙戦を担当する新しい軍種。2015年に新設された。現代戦では情報の優位が勝敗を左右するため、この部隊の重要性は増している。
これら5軍種を統括するのが中央軍事委員会で、その主席は習近平国家主席が務めている。総兵力は現役約200万人、予備役を含めると300万人を超えると推定される。
参考までに、日本の自衛隊は陸海空合わせて現役約24万人、予備役を含めても約31万人だ。単純な人数比較では、中国は日本の10倍近い規模を持っていることになる。
陸軍——97万人の地上戦力と最新装備

世界最大規模の常備陸軍
中国陸軍の現役兵力は約97万人。これは米陸軍(約48万人)の約2倍、陸上自衛隊(約15万人)の約6.5倍という圧倒的な規模だ。
かつての中国陸軍は「兵隊の数は多いが装備は旧式」というイメージだった。確かに1990年代までの中国陸軍は、朝鮮戦争時代の装備を引きずっていた部分も多かった。しかし2000年代以降の近代化は目覚ましく、今や世界トップクラスの装備を誇る機械化部隊へと変貌している。
主力戦車:99式と96式
中国陸軍の主力戦車は「99式主力戦車」と「96式主力戦車」の2系統だ。
99式は中国最新鋭の第3世代主力戦車で、西側の評価では「ロシアのT-90やドイツのレオパルト2に匹敵する性能」とされる。主砲は125mm滑腔砲で、対戦車ミサイルも発射可能。複合装甲と爆発反応装甲を組み合わせた防御力、1,500馬力のエンジンによる機動力を持つ。最新型の99A式では、射撃統制システムも大幅に向上している。
96式は99式より一回り小型・軽量で、数的主力を担う戦車だ。125mm滑腔砲を装備し、基本性能は十分に高い。コストパフォーマンスに優れており、大量配備が可能な点が強みだ。
これらに加えて、山岳地帯や島嶼作戦を想定した「15式軽戦車」も配備が進んでいる。重量わずか33トンという軽量さで、空輸や水陸両用作戦にも対応できる。チベット高原や台湾侵攻を意識した装備と言われている。
戦車の保有数は99式が約600両、96式が約2,500両、旧式の59式・79式などを含めると総数5,000両以上と推定される。陸上自衛隊の戦車が約300両(10式戦車、90式戦車など)であることを考えると、その差は歴然だ。
ちなみに、日本の10式戦車は「世界最高峰の射撃統制システム」と「狭い日本の地形に最適化された機動性」が売りだ。単純なスペック比較では99式と互角以上とも言われるが、中国は「数で圧倒する」戦略を取れる点で有利だ。
(内部リンク:【2025年最新版】陸上自衛隊の日本戦車一覧|敗戦国が生んだ世界屈指の技術力 戦前から最新10式まで)
歩兵戦闘車・装甲車
中国陸軍は機械化歩兵部隊の整備にも力を入れている。主力歩兵戦闘車は「ZBD-04」系列で、30mm機関砲と対戦車ミサイルを装備し、兵員8名を輸送できる。水陸両用能力も持ち、渡河作戦や島嶼上陸作戦にも対応可能だ。
また、8輪装甲車「ZBL-08」ファミリーは、指揮車、偵察車、対戦車車、自走迫撃砲など多様なバリエーションを持つ。舗装路では時速100kmで走行でき、戦略機動性に優れる。
自走砲・ロケット砲
火力支援では、155mm自走榴弾砲「PLZ-05」が主力だ。射程30km以上を誇り、GPS誘導砲弾も使用可能とされる。また、多連装ロケット砲「PHL-03」は射程130km以上の長距離ロケット弾を発射でき、広範囲を制圧できる。
これらの火砲は、かつての日本軍が太平洋戦争で苦しんだ米軍の「圧倒的な火力支援」を彷彿とさせる。もし地上戦になれば、この砲撃の雨が最大の脅威となるだろう。
陸軍航空隊
中国陸軍は独自の航空部隊も持っている。攻撃ヘリコプター「Z-10」「Z-19」、輸送ヘリコプター「Z-8」「Z-20」などを約900機保有している。
Z-10は中国が独自開発した攻撃ヘリで、対戦車ミサイルや30mm機関砲を装備。米国のAH-64アパッチに匹敵する性能を目指して設計された。実戦配備は2010年代からで、まだ実戦経験は少ないが、訓練では高い命中率を示しているという。
陸軍の弱点
ただし、中国陸軍にも弱点はある。最大の課題は「実戦経験の不足」だ。中国が最後に大規模な地上戦を経験したのは1979年の中越戦争で、もう45年以上前のことだ。それ以降、中国陸軍は実戦をほとんど経験していない。
装備は最新でも、それを扱う兵士や指揮官が実戦でどう動くかは未知数だ。対照的に、米軍は湾岸戦争、イラク戦争、アフガニスタン戦争と実戦を重ね、戦術・戦技を磨いてきた。自衛隊も平和維持活動や災害派遣で「現場対応力」を鍛えている。
また、一人っ子政策の影響で、中国の若者は「小皇帝」と呼ばれるほど大切に育てられており、厳しい軍隊生活に適応できるのかという懸念もある。士気や練度では、まだ課題が残るかもしれない。
海軍——777隻の艦艇と空母3隻体制

世界最大の海軍艦艇数
中国海軍(PLAN)の艦艇数は、2023年の米国防総省報告で777隻とされている。これは米海軍の約300隻を大きく上回り、「艦艇数では世界最大」の海軍だ。
ただし、「数が多い=強い」とは限らない。中国海軍の艦艇には小型の沿岸警備艇も多く含まれており、遠洋作戦能力を持つ大型艦は限られている。とはいえ、この10年で大型艦の建造ペースは驚異的で、駆逐艦やフリゲート艦の近代化は急速に進んでいる。
空母:遼寧、山東、福建
中国海軍の象徴は、何と言っても空母だ。現在、「遼寧」「山東」「福建」の3隻を保有し、さらに2隻が建造中とされる。
「遼寧」は、ウクライナから購入したソ連製空母「ワリャーグ」を改修したもので、2012年に就役した。全長約305m、満載排水量約6万トン。スキージャンプ式の発艦方式を採用し、J-15艦載戦闘機を約24機搭載できる。遼寧は主に訓練空母として使われており、艦載機パイロットの育成や艦隊運用のノウハウ蓄積に貢献している。
「山東」は中国初の国産空母で、2019年に就役した。遼寧をベースに改良が加えられ、艦載機の搭載数が増えている。外見は遼寧と似ているが、艦橋の位置や内部レイアウトが最適化されている。
そして2024年に就役した最新空母「福建」は、中国海軍の「ゲームチェンジャー」と呼ばれている。全長約320m、満載排水量約8万トンという巨体で、中国初の「電磁カタパルト」を搭載している。
電磁カタパルトとは、電磁力で航空機を射出する最新技術だ。従来のスキージャンプ式では、艦載機は自力で離陸する必要があり、燃料や武装を満載できなかった。しかし電磁カタパルトなら、重量のある状態でも強制的に射出できるため、作戦半径や攻撃力が大幅に向上する。現在この技術を実用化しているのは米海軍の空母「ジェラルド・R・フォード」だけで、福建は世界で2番目の電磁カタパルト空母となった。
福建の就役により、中国海軍は「第1列島線(日本列島~台湾~フィリピン)の内側だけでなく、第2列島線(小笠原諸島~グアム~パラオ)の外まで影響力を及ぼす」能力を持つことになる。台湾有事や南シナ海での作戦において、空母打撃群を展開できる体制が整いつつあるのだ。
日本の「いずも型」護衛艦も空母化改修が進んでいるが、満載排水量約2.7万トン、F-35Bを最大12機程度搭載という規模だ。福建とは役割も規模も全く異なる。いずも型は「島嶼防衛のための軽空母」であり、福建は「遠洋作戦のための正規空母」だ。
(内部リンク:【2025年最新版】海上自衛隊の艦艇完全ガイド|護衛艦から潜水艦まで全艦種を徹底解説)
駆逐艦・フリゲート艦
中国海軍の水上戦闘艦も急速に近代化している。主力は「055型駆逐艦」と「052D型駆逐艦」だ。
055型は満載排水量約1.3万トンという巨大な駆逐艦で、イージス艦に匹敵する防空能力を持つとされる。112セルの垂直発射システム(VLS)を装備し、対空ミサイル、対艦ミサイル、対地攻撃ミサイル、対潜ミサイルを多数搭載できる。米海軍のアーレイ・バーク級駆逐艦(VLS 96セル)を上回る火力だ。既に8隻が就役し、さらに建造が続いている。
052D型は満載排水量約7,500トン、VLS 64セルを持つ汎用駆逐艦で、2025年現在で約25隻が就役している。中国海軍の「数的主力」を担う存在だ。
フリゲート艦では「054A型」が主力で、約40隻が就役している。満載排水量約4,000トン、VLS 32セルを持ち、対潜・対空・対艦のバランスが良い艦だ。海上自衛隊の護衛艦「あさひ型」「もがみ型」に相当する役割を担っている。
これらの艦艇建造ペースは「キャベツ式」(剥いても剥いても次の層が出てくる)と揶揄されるほど速い。中国の造船業は世界最大規模で、軍艦も商船も大量生産できる体制が整っている。
潜水艦戦力
中国海軍は約60隻の潜水艦を保有している。内訳は、弾道ミサイル潜水艦(SSBN)6隻、攻撃型原子力潜水艦(SSN)6隻、通常動力潜水艦(SSK)約48隻とされる。
最新鋭の093型SSNや095型SSNは、静粛性が向上したと言われるが、それでも米海軍や海上自衛隊の潜水艦に比べると騒音レベルは高いとされる。中国は潜水艦技術でやや遅れを取っているが、急速にキャッチアップしている。
一方、海上自衛隊の潜水艦は世界トップクラスの静粛性を誇る。「そうりゅう型」「たいげい型」は、AIP(非大気依存推進)やリチウムイオン電池を搭載し、長時間の潜航が可能だ。数では中国に劣るが(海自は22隻体制)、質では優位を保っている。
(内部リンク:【2025年最新】世界の潜水艦ランキング!日本の「たいげい」は何位?海自が誇る静粛性の秘密と各国潜水艦を徹底比較)
海軍の課題
中国海軍の最大の課題も「実戦経験の不足」だ。近代的な海戦を経験したことがなく、空母打撃群の運用ノウハウもまだ蓄積途上だ。
また、遠洋作戦を支える「補給艦隊」の整備もこれからだ。米海軍は世界中に基地を持ち、同盟国からの支援も受けられるが、中国海軍が遠洋で長期作戦を維持するのは容易ではない。ジブチに初の海外基地を持ったが、まだ1ヶ所だけだ。
それでも、「第1列島線の内側」では中国海軍の優位が確立しつつある。台湾海峡や南シナ海で局地的な海戦が起きれば、中国側が有利に戦える態勢が整っている。
空軍——1,900機の航空戦力とステルス戦闘機J-20

アジア最大級の空軍戦力
中国空軍(PLAAF)は、戦闘機・攻撃機約1,900機、輸送機約450機、早期警戒機・電子戦機約50機を保有する巨大な航空戦力だ。人員は約40万人で、これは米空軍に次ぐ規模となっている。
かつての中国空軍は、ソ連製MiG-21のコピー機「殲-7」が主力で、「数は多いが旧式」というイメージだった。しかし2000年代以降、ロシアから最新鋭のSu-27、Su-30を導入し、さらにそれらを国産化・改良した「殲-11」「殲-16」を大量生産。そして2010年代には独自開発の第5世代ステルス戦闘機「殲-20」の実戦配備を開始した。
第5世代ステルス戦闘機:J-20(殲-20)
J-20は、中国空軍の「切り札」と呼ばれるステルス戦闘機だ。全長約20m、最大速度マッハ2以上、戦闘行動半径約1,200kmとされる。外見は米国のF-22に似ているが、機体はやや大型で、長距離迎撃任務を重視した設計だ。
J-20の最大の特徴は「ステルス性」だ。機体形状や塗装により、敵レーダーに映りにくい。また、機内兵器倉に空対空ミサイル「PL-15」を搭載し、レーダー反射を増やさずに武装できる。PL-15は射程約200kmとも言われ、米軍のAIM-120(射程約100km)を上回る可能性がある。
ただし、J-20にも弱点はある。最大の課題はエンジンだ。当初はロシア製エンジンAL-31Fを搭載していたが、現在は国産エンジンWS-10Cに切り替わりつつある。しかし、推力や信頼性ではまだ米国のF-22やF-35に搭載されるエンジンに及ばないとされる。特に「超音速巡航」(アフターバーナーを使わずに超音速飛行)ができるかどうかは疑問視されている。
それでも、J-20は既に約200機以上が配備され、東部戦区(台湾方面)や南部戦区(南シナ海方面)に重点配備されている。台湾有事では、J-20が台湾空軍のF-16やF-CK-1を圧倒する可能性がある。
日本の航空自衛隊はF-35A(42機配備済み、最終的に105機予定)とF-35B(42機配備予定)でこれに対抗する構えだ。F-35はステルス性、センサー融合能力、電子戦能力で世界最高峰とされるが、数で劣る点が懸念される。
(内部リンク:【2025年最新版】日本の戦闘機一覧|航空自衛隊が誇る空の守護者たち。最強は?)
主力戦闘機:J-10、J-11、J-16
J-10は、中国が独自開発した軽量戦闘機だ。デルタ翼とカナード(前翼)を持つ独特の形状で、機動性に優れる。エンジンは単発だが、推力偏向ノズルを装備した改良型J-10Cは、高い格闘戦能力を持つ。約400機が配備されている。
J-11は、ロシアのSu-27をライセンス生産し、改良したもの。大型で航続距離が長く、空対空ミサイルを多数搭載できる。最新型のJ-11Bは、国産レーダーとアビオニクスを搭載し、性能が向上している。
J-16は、Su-30をベースにした多用途戦闘機で、「中国のF-15E」とも呼ばれる。空対空戦闘だけでなく、対地・対艦攻撃もこなせる万能機だ。強力なAESA(アクティブ電子走査アレイ)レーダーを搭載し、多目標同時攻撃能力を持つ。約200機が配備され、中国空軍の「主力打撃機」として活躍している。
爆撃機・攻撃機
中国空軍は戦略爆撃機「H-6」を約170機保有している。H-6は、ソ連のTu-16を基にした双発ジェット爆撃機だが、何度も近代化改修が施されている。最新型のH-6Kは、巡航ミサイル「CJ-10」(射程1,500km以上)を6発搭載でき、日本全土を射程に収める「スタンドオフ攻撃」が可能だ。
また、次世代ステルス爆撃機「H-20」の開発も進んでいるとされる。米国のB-2に匹敵する全翼機で、ステルス性と長距離攻撃能力を兼ね備えた戦略爆撃機になると予想されている。もし実戦配備されれば、第2列島線の外まで爆撃できる能力を持つことになる。
空中給油機・早期警戒機
近代的な空軍には、「支援機」の充実が不可欠だ。中国空軍は空中給油機「Y-20U」や「H-6U」を約10機保有し、戦闘機の作戦半径を延ばしている。ただし数はまだ少なく、米空軍の約500機には遠く及ばない。
早期警戒管制機(AEW&C)では「KJ-500」「KJ-2000」を約15機保有している。これらは米国のE-3やE-2Dに相当する機体で、広範囲の空域を監視し、味方戦闘機を指揮できる。台湾海峡や南シナ海では、これらの早期警戒機が常時飛行しており、空域管制を行っている。
空軍の弱点
中国空軍の弱点も、やはり「実戦経験の不足」だ。1990年代以降、中国空軍は実戦を経験していない。一方、米空軍は湾岸戦争以降、ほぼ継続的に実戦を経験し、戦術を磨いてきた。航空自衛隊も、冷戦期から続くスクランブル対応で、実際の空中戦を想定した訓練を積み重ねている。
また、パイロットの飛行時間も課題だ。中国空軍パイロットの年間飛行時間は約100~150時間とされ、米空軍(約200時間)や航空自衛隊(約150時間)と比べてやや少ない。ただし、シミュレーター訓練の充実で補っているとも言われる。
ロケット軍——「空母キラー」を持つミサイル戦力

中国の戦略兵器を一手に担う
中国人民解放軍ロケット軍(旧・第二砲兵)は、弾道ミサイルと巡航ミサイルを専門に扱う戦略部隊だ。核弾頭を搭載可能な大陸間弾道ミサイル(ICBM)から、通常弾頭の中距離弾道ミサイル、対艦弾道ミサイルまで、多様なミサイル戦力を保有している。
ロケット軍の存在は、中国の「接近阻止・領域拒否(A2/AD)」戦略の核心だ。A2/ADとは、敵(主に米軍)が中国近海に接近するのを阻止し、仮に接近しても自由な作戦行動をさせない戦略を指す。その主役がミサイルだ。
大陸間弾道ミサイル(ICBM)
中国は核保有国として、約350発の核弾頭を保有している(2024年推定)。さらに、2030年までに1,000発に増やすとの予測もある。これらの核弾頭を運搬するのがICBMだ。
主力は「DF-5」(射程約13,000km)、「DF-31」(射程約11,000km)、最新鋭の「DF-41」(射程約14,000km、複数弾頭搭載可能)などだ。DF-41は移動式発射台を使用し、探知・攻撃が困難とされる。これらのICBMは、米本土全域を射程に収めている。
また、弾道ミサイル搭載原子力潜水艦(SSBN)も保有しており、「JL-3」潜水艦発射弾道ミサイル(射程約10,000km)を搭載している。「核の三本柱」(陸上・海上・空中)の構築を目指している段階だ。
中距離弾道ミサイル(IRBM)と中距離巡航ミサイル
中国は、米ロが冷戦後に廃棄した「中距離ミサイル」を大量に保有している点が特徴だ。米国とロシアは1987年の中距離核戦力(INF)全廃条約で射程500~5,500kmのミサイルを廃棄したが、中国は条約に縛られず、この分野で圧倒的な優位を築いた。
主力は「DF-21」(射程約1,700km)と「DF-26」(射程約4,000km)だ。これらは通常弾頭・核弾頭の両方を搭載可能で、日本全土、グアム、フィリピンを射程に収めている。特にDF-21DとDF-26は「対艦弾道ミサイル」として、動く空母を狙える能力を持つとされる。
対艦弾道ミサイルは「空母キラー」とも呼ばれ、米海軍空母打撃群にとって最大の脅威だ。弾道ミサイルは高速で落下してくるため、迎撃が極めて困難とされる。ただし、移動する空母を正確に追尾・攻撃できるかは未実証で、実際の効果には疑問も残る。
極超音速兵器
近年注目されているのが「極超音速兵器」だ。中国は「DF-17」という極超音速滑空体(HGV)搭載弾道ミサイルを実戦配備している。極超音速兵器はマッハ5以上で飛行し、弾道が予測しづらく、現在のミサイル防衛システムでは迎撃が困難とされる。
また、2021年には極超音速兵器の実験で「地球を一周してから目標に着弾する」という驚異的な能力を示したと報じられた(中国はこれを否定)。もし事実なら、従来のミサイル防衛網を完全に無効化できる可能性がある。
日本への脅威
中国のミサイル戦力は、日本にとって直接的な脅威だ。在日米軍基地(横田、横須賀、嘉手納など)は、DF-21やDF-26の射程内にある。台湾有事では、これらの基地がミサイル攻撃を受ける可能性が高い。
日本はイージス艦のSM-3や地上配備のPAC-3でミサイル防衛体制を整備しているが、飽和攻撃(大量のミサイルを同時発射して防衛網を飽和させる)には対応しきれない可能性がある。現在、日本政府は「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有を進めており、長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾の改良型」(射程1,000km以上)の配備を計画している。
(内部リンク:日本が保有するミサイル全種類を完全解説!極超音速ミサイルから弾道ミサイル防衛まで)
戦略支援部隊——目に見えない戦場で戦う

現代戦の新たな主役
2015年に新設された戦略支援部隊は、サイバー戦、電子戦、宇宙戦、心理戦を担当する。これは中国が「情報化戦争」を重視している証だ。
現代の戦争では、銃弾やミサイルだけでなく、「情報」そのものが武器になる。敵の通信を妨害し、レーダーを無効化し、衛星を破壊し、サイバー攻撃で指揮系統を麻痺させる——こうした「見えない戦場」での戦いが、勝敗を左右する。
サイバー戦
中国は世界最大級のサイバー戦力を持つとされる。人民解放軍第61398部隊は、米国や日本の企業・政府機関へのサイバー攻撃を行っているとされ、機密情報の窃取や重要インフラへの侵入を試みている。
もし日中間で軍事衝突が起きれば、開戦と同時に電力網、通信網、金融システムへのサイバー攻撃が行われる可能性が高い。自衛隊の指揮系統や米軍基地の通信も標的になるだろう。
電子戦
電子戦とは、電波を使った攻防戦だ。敵のレーダーや通信を妨害する「電子攻撃」、味方の電波を守る「電子防護」、敵の電波を傍受・分析する「電子戦支援」がある。
中国は電子戦機や電子戦システムの開発に力を入れており、J-16には電子戦型の「J-16D」が存在する。これは米海軍のEA-18Gグラウラーに相当する電子戦機で、敵のレーダーや防空システムを無力化できる。
宇宙戦
中国は宇宙分野でも急速に力をつけている。独自の衛星測位システム「北斗」を完成させ、GPS に依存しない測位能力を持つ。また、偵察衛星や通信衛星も多数打ち上げており、宇宙からの監視・指揮能力を高めている。
さらに、対衛星兵器(ASAT)の開発も進めている。2007年には自国の気象衛星を弾道ミサイルで破壊する実験に成功し、世界に衝撃を与えた。もし戦争になれば、敵の軍事衛星を破壊して「目を潰す」作戦が考えられる。
米軍も自衛隊も、衛星による測位・通信・偵察に大きく依存している。もし衛星が使えなくなれば、精密誘導兵器は使えず、部隊間の連絡も困難になる。宇宙戦は、今や戦争の勝敗を左右する重要な領域なのだ。
中国軍の強み——圧倒的な物量と急速な近代化
ここまで見てきたように、中国軍には明確な強みがある。
1. 圧倒的な物量
人員、装備、予算、すべてにおいて中国は「数」で圧倒できる。戦車5,000両、艦艇777隻、戦闘機1,900機という規模は、日本やその他のアジア諸国を大きく上回る。
戦争では「質より量」の局面も多い。いくら高性能な兵器でも、多方面から同時攻撃されれば対応しきれない。中国はその「飽和攻撃」が可能な規模を持っている。
2. 急速な近代化
中国の軍事技術は、この20年で飛躍的に向上した。ステルス戦闘機、空母、イージス艦、極超音速兵器——これらを短期間で実用化する技術力と資金力は驚異的だ。
かつては「コピー品ばかり」と言われた中国の兵器だが、今や独自開発の最新兵器が次々と登場している。J-20、055型駆逐艦、福建空母などは、世界トップクラスの性能を持つ。
3. 統合作戦能力の向上
2015年の軍制改革以降、中国軍は「統合作戦」(陸海空ロケット戦略支援を統合した作戦)を重視している。かつては各軍種がバラバラに動いていたが、今は中央軍事委員会が一元的に指揮する体制が整いつつある。
また、5つの「戦区」(東部・南部・西部・北部・中部)を設定し、地域ごとに陸海空を統合した指揮系統を構築している。東部戦区は台湾・日本方面、南部戦区は南シナ海方面を担当し、それぞれの地域で迅速に対応できる体制だ。
4. 国内の造船・航空産業の巨大さ
中国の造船業と航空産業は世界最大規模だ。軍艦も航空機も、驚異的なスピードで量産できる。米国ですら、造船所の数や生産能力で中国に劣る状況だ。
もし長期戦になれば、この「生産力」が決定的な差になる。太平洋戦争で日本が敗れた一因は、米国の圧倒的な生産力に対抗できなかったことだった。中国は今、かつての米国と同じ立場にある。
中国軍の弱み——実戦経験の不足と構造的課題
一方で、中国軍には明確な弱点もある。
1. 実戦経験の不足
何度も述べたが、これが最大の弱点だ。装備が最新でも、実戦で使ったことがなければ、どう機能するかわからない。訓練と実戦は全く違う。
米軍は30年間、ほぼ継続的に実戦を経験してきた。その中で戦術を磨き、装備を改良し、兵士を鍛えてきた。自衛隊も、災害派遣やPKO活動で「現場対応力」を養っている。中国軍にはこれが欠けている。
2. 兵士の士気と練度
一人っ子政策の影響で、中国の若者は家族に大切に育てられており、厳しい軍隊生活に適応できるかという懸念がある。また、徴兵制ではなく志願制に移行したが、農村部出身の若者が多く、教育水準や体力面で課題があるとも言われる。
対照的に、自衛隊は志願制で競争率も高く、選抜された優秀な若者が入隊している。訓練も厳格で、規律と団結力は世界トップクラスだ。
3. 腐敗と汚職
中国軍内部には、腐敗と汚職の問題が根深く存在する。習近平政権は「反腐敗運動」で多くの高級将校を処罰したが、問題は完全には解決していない。
装備調達での不正、訓練のごまかし、昇進のための賄賂——こうした問題が、実際の戦闘能力にどう影響するかは未知数だ。
4. 補給・兵站の脆弱さ
中国軍は「前線での戦闘」には強いが、「後方支援」には弱いとされる。燃料、弾薬、食料、医療——これらを継続的に前線に届ける「兵站」の体制が、まだ十分に整備されていない。
太平洋戦争で日本軍が苦しんだのも、兵站の軽視だった。ガダルカナル島やニューギニアで、多くの日本兵が餓死したのは、補給が途絶えたからだ。中国軍も同じ轍を踏む可能性がある。
(内部リンク:ガダルカナル島の戦いとは?「餓島」で2万人が散った太平洋戦争の転換点を徹底解説)
5. 同盟国の不在
米国は世界中に同盟国を持ち、基地を提供され、後方支援を受けられる。日本も日米同盟という強固なバックアップがある。
しかし中国には、真の意味での「同盟国」がほとんどいない。ロシアや北朝鮮と友好関係にあるが、それも利害の一致に基づく関係で、戦争になった時に本当に助けてくれるかは不透明だ。
孤立した中国が、米国+日本+同盟国連合と戦うのは、たとえ装備が優れていても厳しい戦いになるだろう。
日本への影響と課題——僕たちはどう備えるべきか
中国の軍事的台頭は、日本にとって直接的な脅威だ。尖閣諸島、台湾海峡、南シナ海——いずれの地域でも、中国の軍事的圧力が高まっている。
台湾有事のリスク
中国が台湾に侵攻すれば、日本も無関係ではいられない。在日米軍基地からの出撃支援、自衛隊の後方支援、さらには存立危機事態として自衛隊の直接参加もあり得る。
米国のシンクタンクが行ったシミュレーションでは、「中国の台湾侵攻は、米軍と日本の支援があれば阻止できるが、双方に甚大な被害が出る」との結果が出ている。日本の南西諸島の基地や艦艇が攻撃され、多数の犠牲者が出る可能性が高い。
(内部リンク:沖縄戦をわかりやすく解説|日本軍最後の大規模地上戦の全貌【映画・アニメファン向け完全ガイド】)
防衛力の強化
日本政府は2023年に「防衛力強化計画」を策定し、防衛費を5年で43兆円(対GDP比2%)へと倍増させる方針を打ち出した。長射程ミサイルの配備、イージス・システム搭載艦の建造、サイバー・宇宙領域の能力強化などが進められている。
しかし、中国の軍拡ペースは日本を上回る。中国の国防予算は公表ベースで年間約2,250億ドル(約33兆円)だが、実際にはその1.5倍以上とも言われる。日本が防衛力を強化しても、中国との差は開く一方だ。
日米同盟の重要性
だからこそ、日米同盟が決定的に重要になる。日本単独では中国に対抗できないが、米軍と一体となれば抑止力を維持できる。
米国にとっても、日本は「不沈空母」だ。嘉手納基地、横須賀基地、岩国基地——これらの前方展開基地があるからこそ、米軍は西太平洋で迅速に行動できる。日米は運命共同体なのだ。
歴史の教訓
僕たちの祖父や曾祖父の世代は、大日本帝国として米国と戦い、敗れた。あの戦争から学ぶべき教訓は多い。
物量で劣る側が、精神論だけで勝てるほど戦争は甘くない。補給を軽視すれば、前線の兵士は餓死する。同盟国なき孤立した戦いは、最終的には敗北する。
今の日本は、かつての日本と同じ轍を踏んではならない。米国との同盟を堅持し、技術力と練度で優位を保ち、そして何より「戦争をしない」ための外交努力を続けることが重要だ。
まとめ——巨龍は本当に強いのか?
中国人民解放軍は、確かに強大だ。200万の兵力、777隻の艦艇、1,900機の戦闘機、そして核兵器——これだけの戦力を持つ国は、米国を除いて他にない。
しかし、「強大な軍隊」と「実戦で勝てる軍隊」はイコールではない。中国軍は装備では世界トップクラスだが、実戦経験、兵站、士気、同盟国——これらの面では米軍や自衛隊に劣る部分も多い。
もし本当に戦争になれば、どちらが勝つかは誰にもわからない。ただ一つ確実なのは、「どちらが勝っても、双方に甚大な被害が出る」ということだ。
だからこそ、僕たちは「戦わない」ための努力を続けなければならない。抑止力を高め、外交を重視し、対話のチャネルを保つ。それが、先人たちの犠牲の上に立つ僕たちの責任だ。
中国軍の実力を正しく理解すること——それは、「恐れる」ためではなく、「備える」ためだ。この記事が、その一助になれば幸いだ。
関連記事
もっと詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。










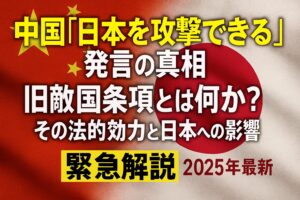
コメント